
娘とアール・ブリュットをみに。
ポケモンからアール・ブリュット展
いかん。
このままではゴールデン・ウィークが、
バイオレット・ウィークになってしまう。
正確には、ポケットモンスター・バイオレット・ウィークに。
なんならすでに半分なっちゃってる。
娘は憑かれたように画面を見つめ、ボタン一つでピカチュウを戦闘に送り込む。何度も何度も。
待て。生物多様性をキミの代理戦争に利用するな。乱獲はやめろ。それは無用の殺生というものだ。
かくして私は娘をお出かけに誘ってみた。
「お父さん、行きたいトコあんだけど、付き合ってくんない?」
「ヤダ」
こちらをチラとも振り返ってくれない6歳児。
「サーティワンとゲーセンとヴィレヴァンにも行きましょうよ」
「しょうがないな。どこいくの」
モンスタボールよろしく、小一娘をゲットだぜ。
連れ出した先は、東京都渋谷公園通りギャラリー。「アール・ブリュット ゼン&ナウ Vol.3ただよう記憶の世界」なる展覧会だった。
国内外のアール・ブリュットシーンで活躍する作家、とりわけ何らかの障害をもつ作家たちの作品が紹介されていた。
ギャラリーは渋谷区立勤労福祉会館の1階にあった。名前からしてオカタイ。床のくたびれ具合から築の年季が伝わる。廊下も狭い。
渋谷区のサイトによれば「勤労者が気軽にスポーツやサークル活動を行うことができる施設です」なのだそうです。渋い。建った当時は、子どもの訪問など想定していなかったのだろう。
そんなビルの奥深くを目指して、いきなり娘がダッシュした。
だだだだだっ。子どもの足音が場違いに響く。展示入口の作品に飛びついたのだった。そこには「なんだありゃ」が壁に飾られていた。
色が聴こえる。色に流される
大ぶりな座布団サイズの作品が2枚。
遠くから見て、どちらもザラザラした手触りを予感させた。ノイズを描き起こしたかのような。しかも極彩色。いったい何色使われているのか。
昔のファミコンって、よくあんな感じで画面がバグったっけ。
作品の前で、娘の背中もフリーズしている。
しかし、一歩また一歩と近づくにつれ印象は変わり、フリーズどころではなく、躍動を感じるようになった。
そして、作品の正体も。
「プチプチ?」
そう。プチプチ。割れ物とかを包む緩衝材のプチプチ。
「え。まじで」
その作品は、プチプチが一つずつ塗り潰され、何百となり、点描画を成していた。
「さわっちゃダメ!」
娘がビクッと指をひっこめた。思わず声が大きくなってしまった。
しかし、気持ちはわかる。とってもわかる。ただでさえプチプチなのだ。ツンツン、プニプニ。できればプチッと。むしろそっちのほうが正しい使い方とも言える。
囚人のように両手をガッチリ後ろに組み、寄り目で観察する6歳と43歳。私が作品だったら「口くせえよ」と言いたくなるほど、「とくに43歳のほう」と付け加えたくなるほどの至近距離。
「何が見える?」
「ここにKがある。ここにも」「こっちはY」
「三角がたくさんあるね」
私と娘とでも、見えてくるものが違う。絵には特定のモチーフがあるわけではなく、幾何学模様でもない。
1プチ1プチ塗りつぶしているうちに線ができ、面が生まれ、図形になる。それが隣の線や面の展開につながり、いつの間にかタペストリーになっていた。のではないか。
規則性はない。かといって、完全なランダムでもない。自分にしか見えていないものを描いている。それが一瞬で伝わる、圧倒的なオリジナリティ。
なによりも、間違いなく美しい。もしプチッとやったら。聴こえてくるのは、きっと色の弾ける音だろう。
美しいだけでなく、見ていて心地よかった。不思議な感覚だった。
「これずっと見てられるわ」
呆けて見惚れる私に、娘がささやいた。
「おとうさん、あっち」
ようやく出番を得た娘の人差し指。私はその先に目をやった。
滝。
「おい。嘘だろ」
ろ がため息で霞んだことに自分でも気づいた。そこにあったのは、ドットの滝だった。
近づくのも躊躇するほどの迫力。瀑布を訪れたときの畏敬を思い出した。
いま対峙していた作品とは桁違いの大きさ。幅は6歳児が腕を広げたくらい、およそ1m強。長さ、というか高さは、私が見上げるくらいなので2m以上、いやもっと。
それだけではない。滝の頭と壺にロールが太く巻かれている。つまり、広げていない部分のほうがずっと長い。
「ねぇ、これどのくらいの長さがあると思う?」
「んーわかんない。100メートルくらい?」
「さすがにそれは」
「じゃ10メートル」
「じゃ、ってなんだよ」
アホ丸出しでヤマカン合戦を繰り広げる私たちを見かねたのか、いやウルサかっただけかもしれないが、スタッフの方が話しかけてくれた。
「それは20mあるんです」
「えー!」
私たちのユニゾンが、ギャラリーの壁に反響した。
「20mだってよ」
「20メートルってどのくらい?」
「きみの学校のプールくらい」
「ふーん」
そこはピンとこいよ。
滝。あるいは、この世のプログラム・コード。混沌さえ組み込まれた秩序が、止めどなく流れ落ちているを感じる。動かない絵からスピードを感じたのは初めてだった。
死んだら魂はこんな次元をたゆたい、次を待つのかもしれない。
「ちなみに。こっちは40mあります」
スタッフさんの頭越し。まったくちなみきれていないものが、そこにあった。
「川。波、いや、竜、ですか」
とうてい視界におさまりきらないスケール。作品というには、展示空間とのバランスがおかしなことになっていた。これが作品なら、天井や階段も作品だろう。
「・・・なるほど」
6歳児と大差ないリアクションしか出ない43歳。人間ほんとうに驚いた時は、眼前の出来事に鈍感になることを実感した。私が驚ける能力を軽々と超えていた。脳の過呼吸と防衛本能。蒸発した父親が16年ぶりに姿を現したときも、ここまで驚かなかったはずだ。
娘の手をきゅっと握った。そして、自分たちを飲み込みそうな作品を仰いでいた。
いっそ飲み込まれたかった。色に流されるままに、どこかへ行ってしまいたかった。
しばらく動く気になれなかった。
満腹画と名付けたい
もうお腹いっぱい。
最初の作品で早くもグッタリした私たちを待っていたのは、食事メニューの絵たちだった。
食事メニューの絵って何よ、と。それはもう食事メニューの絵としか言いようがない。
焼き鯖弁当。幕の内弁当。鰻弁当。カツ丼。親子丼。寿司の折詰。チャーハン。きんぴらごぼう。豚の味噌焼き。カレーうどん。の、絵。
しかも、衝撃的な精密画だった。
「食品サンプルかよ」
食品サンプルではない。念のため。
メインのおかずはもとより、麺の一本一本、米の一粒一粒まで、丁寧に描きこまれている。味や食感、香りまで再現しようとしてるんじゃないか。
料理の盛り付けが皿や丼の中で片寄っている様までリアルで、しどけなくも微笑ましい日常がそこに記されているのを感じた。
舐めるように、いや食べるようにジッと見ていて、気になることがあった。
なんだか妙に色っぽいのだ。なまめかしいというか。
スタッフの方から解説を聞いて、その理由がわかった。と同時に、作品の見方がガラリと変わった。
作品は写実ではなかった。
作者は書き溜めたメモ書きを見返して、食べた日の記憶を呼び起こしながら描いていた。
つまり「あの日のごはん、美味しかったなぁ」を絵にしていた、ということ。
美味しそうな絵ではない。美味しかった絵。
明るい追憶が、食材の色やカタチ、テカり具合、皿の配置や箸の傾きにいたるまで、隅々に宿っていた。鮮やかに。
おそらく目の前の食事を写実しただけでは、この色気は表現できないだろう。
満腹の多幸感。愉悦と言ってもいいかもしれない。
はー食った食ったと腹をポンポンする。あの瞬間が描かれていた。
見ていて腹が空く絵というのはある。映画も音楽もあるだろう。しかし、見ていて満腹になる絵というのは、初めて出会った。
「これみて!すごくない?」
娘に声をかけたものの、リアクションは
「ふーん」
またですか。娘、食い付かず。リアルすぎてフツーに見えたらしい。
そういえば。私が小学校の頃は、遠足の後日には決まって絵を描かされた。テーマは「遠足の思い出」。クラスには必ず弁当の絵を描くヤツがいて。食い意地が張ってるだの、だからデブッチョなんだ、だのと友だちにツッコまれながらも、なんだかんだ力作に仕上がったものだった。私だ。
もしかすると作者は、あんな気分で描いていたのかもしれない。だとすれば、その時間もまた味なものだろうな。
「すばらしかったですおかげでさまでたのしめました」
その他にも目を奪う、いや、視線をカツアゲしてくる作品が展示されていたのだが、6歳児の集中力がそれほど長く続くわけもなく。お口のチャックが限界を迎えたところで、アンケートを書いておいとますることに。
娘にとっては人生初アンケート。
「どこにチェック?」「書くのここ?」
と私に確認をとりながら、ときおり息を止めるようにして文章をしたためていた。小学校の宿題、早くも成果を発揮。
”すばらしかったですおかげでさまでたのしめました”
おかげで、の物言いが不遜であると、子どもながらに気付いたのか。さまで、を書き加えていた。句読点はまだ習ってないらしい。
アンケートに書くことがあるということは、この展覧会が充実していたということだ。
清き一票でも投じるように、娘はうやうやしくアンケートを投函箱に入れた。
帰り道。サーティーワンのアイスを食べながら、私は展覧会の作者たちについて補足した。
「さっきの作品は、ぜんぶ障害のある人が作ったんだって」
「・・・」
「障害ってきいたことある?」
「・・・」
「ほら、きみのお友だちにもOくんとかKちゃ」
と言いかけて、私は言葉を飲み込んだ。何かとんでもない一線を引いてしまいそうだったからだ。
というかもう、娘は私の話を聞いてない。スプーンでオレンジシャーベットをオールバックに撫でながら、愛しそうに食べている。アイス”クリーム”のお店なんだし、もっとクリーミーで甘くてコクのあるアイス食べればいいのに。
アイスの好みはさておき、アートの見方や感想はひとそれぞれ。
作者を知らずに、自分の目だけを信じて鑑賞する方法。作者を知り、興味に導かれて鑑賞する方法。両方アリ。
「アートに障害なんて関係ないよね」も、「障害があるのにすごい」も、「障害者だからこその作風だね」も、アリ。
でも。そこにとどまっていては、面白くないんじゃないか。
アートに障害は関係ない、は本当か?
作者に障害がなかったら、私はこの展覧会に来ただろうか。
障害があるのにすごい?あるからすごい?
いや。この日出会った作品は、そんなの関係なかった。いかなる前置きも寄せ付けない、圧倒的な存在感だった。直感的に興奮できた。
そもそも。障害者なのに。障害者だから。その観点で作品を丸かじりできるのか。
たしかに彼らと私たちは、違うところがある。同じと言ってのけてしまうのは、障害を軽んじているように感じる。
では。私たち同士の違いと、どう質が異なるのか。いや、私たち同士って誰のことなのか。問いはそのまま、彼らとは、人間とは、といった次の問いにつながり、彼我の違いは捉えどころがなくなっていく。
じゃあ障害者アートって何だ?
ややもすれば、あちら側とこちら側を分けるような違和感のあるカテゴリ。
現代アートとはいうが、現代人アートとはいわない。西洋芸術とはいうが、西洋人芸術とはいわない。
しかし障害者アートは、しばしば呼び習わされる。本当はそのカテゴライズの危うさを疑い、世界の広さや深さに出会うことに醍醐味があると思うのだが。
娘はどう感じているのか。
とっくに空になったカップを啜りながら、私のアイスをジッと見つめる彼女に、疑問をぶつけてみた。
「今日、どうだった?」
「おもしろかった。ママもくればよかったのに」
ママ。お母さんではなく、ママ。娘は本気で欲しがる時、無意識かつ戦略的に”ママ”を行使する。
作品を見て、誰か好きな人を誘いたくなったら最高だ。その鑑賞体験は素晴らしいものだ。それ以上の何が必要だというのか。
その一言で、私はようやく深呼吸できた気がした。
それまでの私は仕事の人間関係でストレスをかかえ、不眠と過呼吸に悩まされていた。不眠は薬でなんとかなったが、過呼吸がやっかいだった。
夜は溺れる夢をみる。苦しくて目が覚める。よかった。夢か。あれ。まだ息ができない。目覚めても続く悪夢。
やがて日中でも息ができなくないことが増え、その時間も長くなった。
会社や取引先といった、閉じられていて、均質で、不自由なルールに窒息していた私は、すっかり忘れていた。
世の中は広く、いろんな人がいて、想像もつかないルールで生きていることを。そしてそこには、大切な人を誘いたくなるほど素敵な出会いがあることを。
つまり、世界はまんざらでもない、ということを。
娘にお礼を言った。
「今日は付き合ってくれてありがとう」
「わたしのほうこそつきあってくれてありがとう」
「付き合ってもらったのは俺の方だよ」
「またみにきたい」
「まだ見てないやつあったしね」
私は、まだ溶けてない自分のアイスを差し出した。
「ゲーセンとヴィレヴァン、わすれてないよね?」
胸のすくようなチョコミントを口に運びながら、娘が言った。
〈おわり〉
Photos
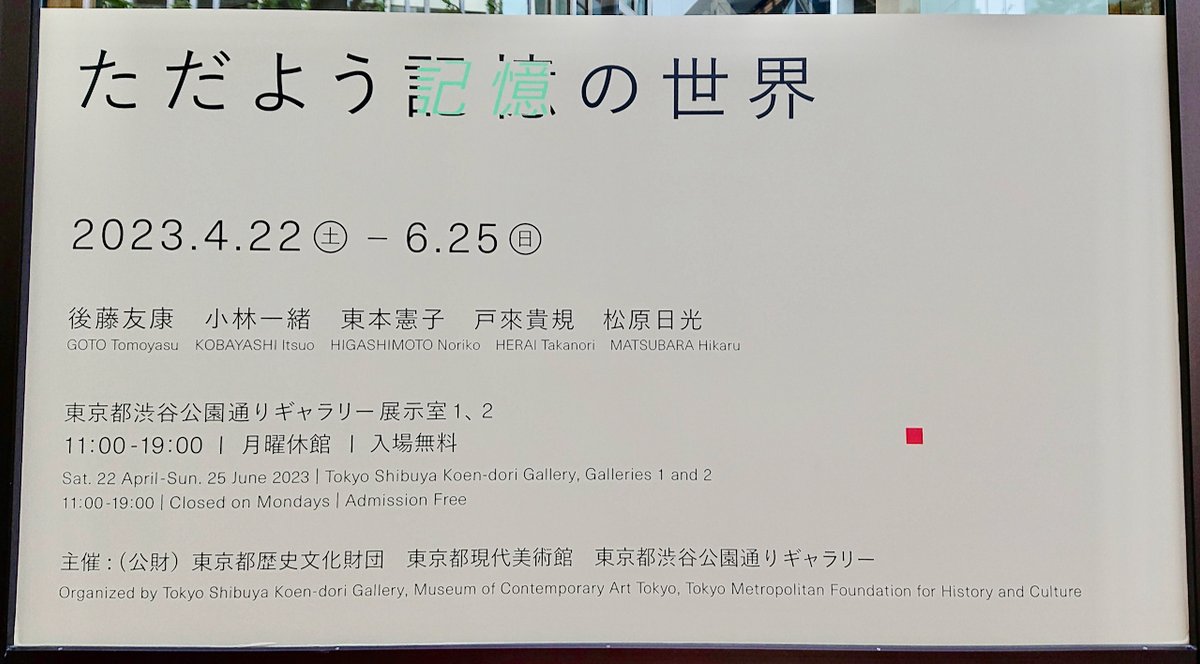


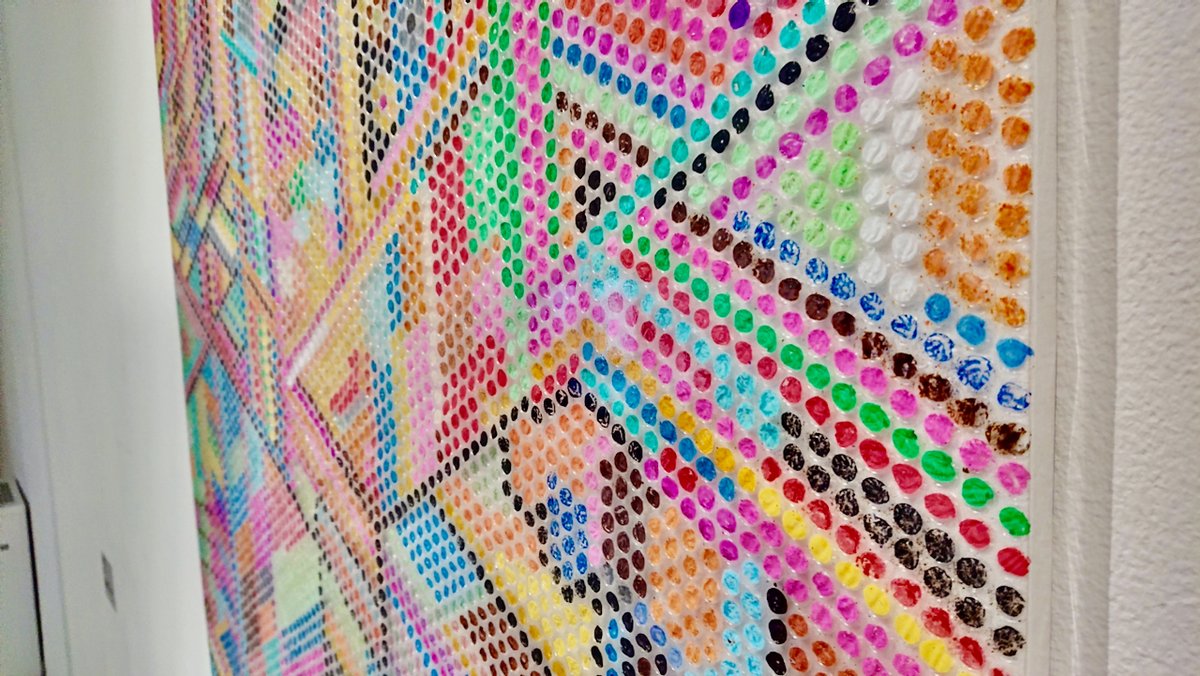





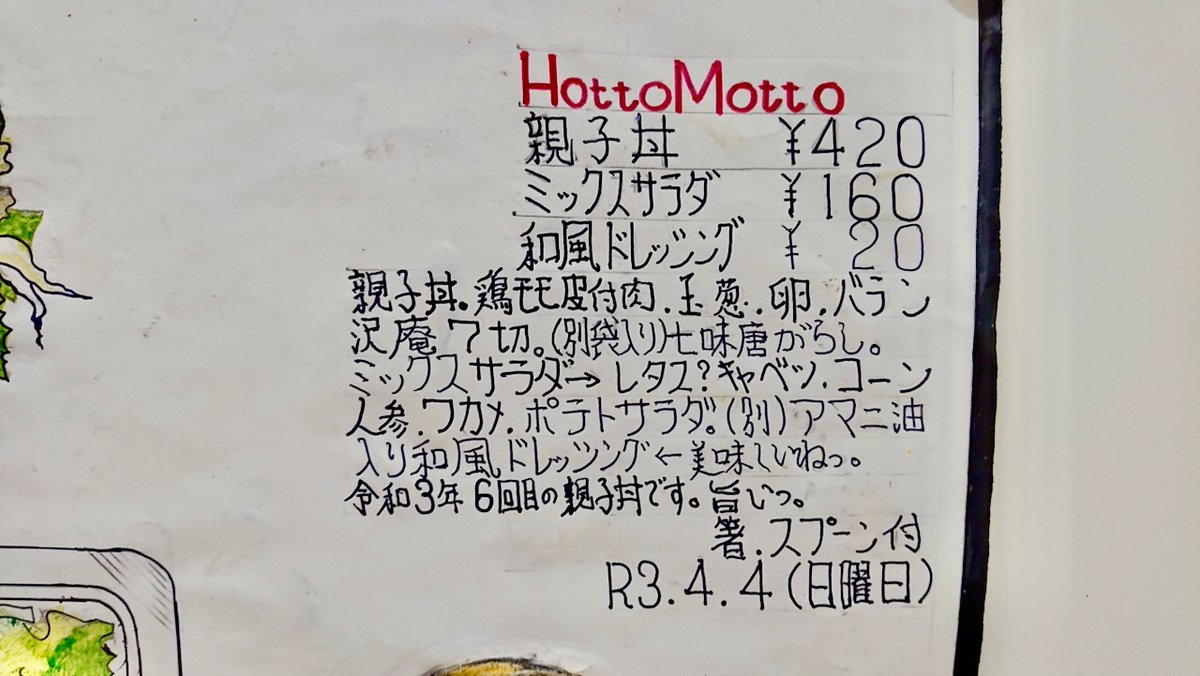
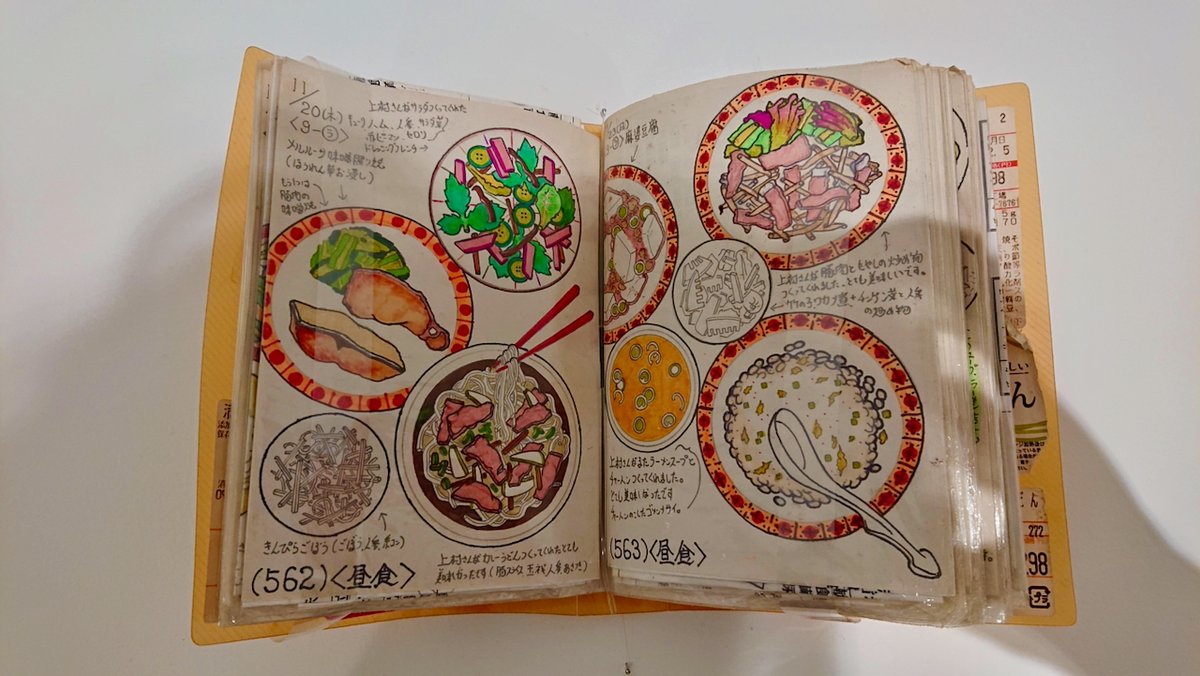




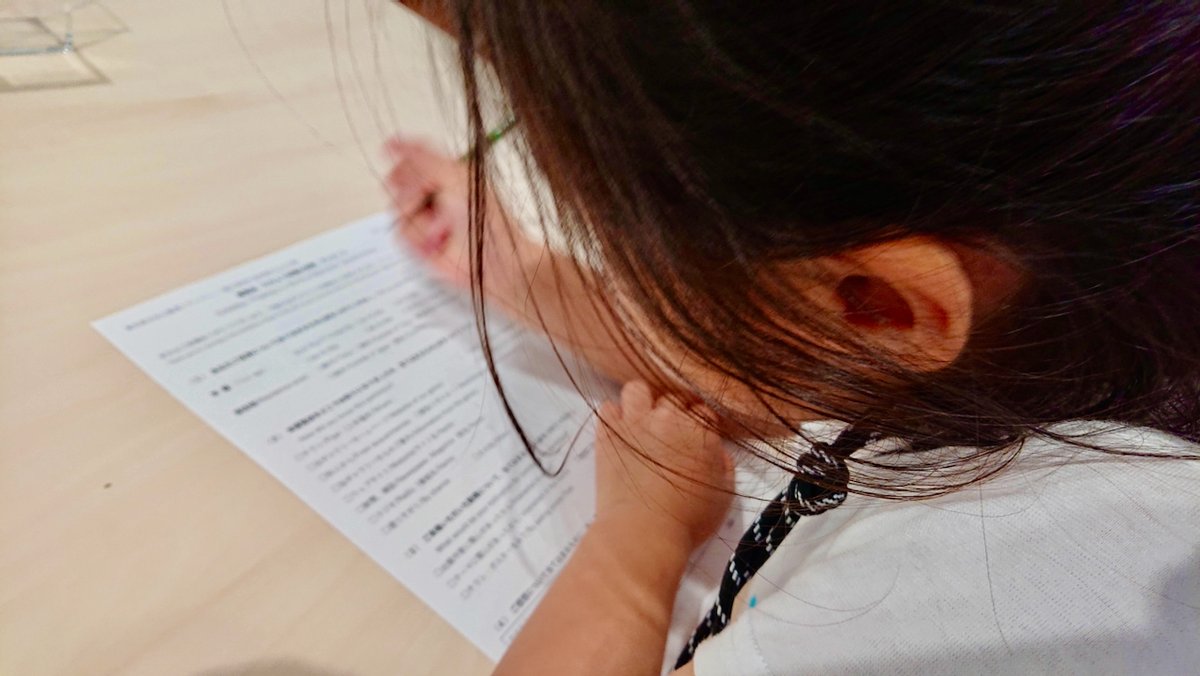
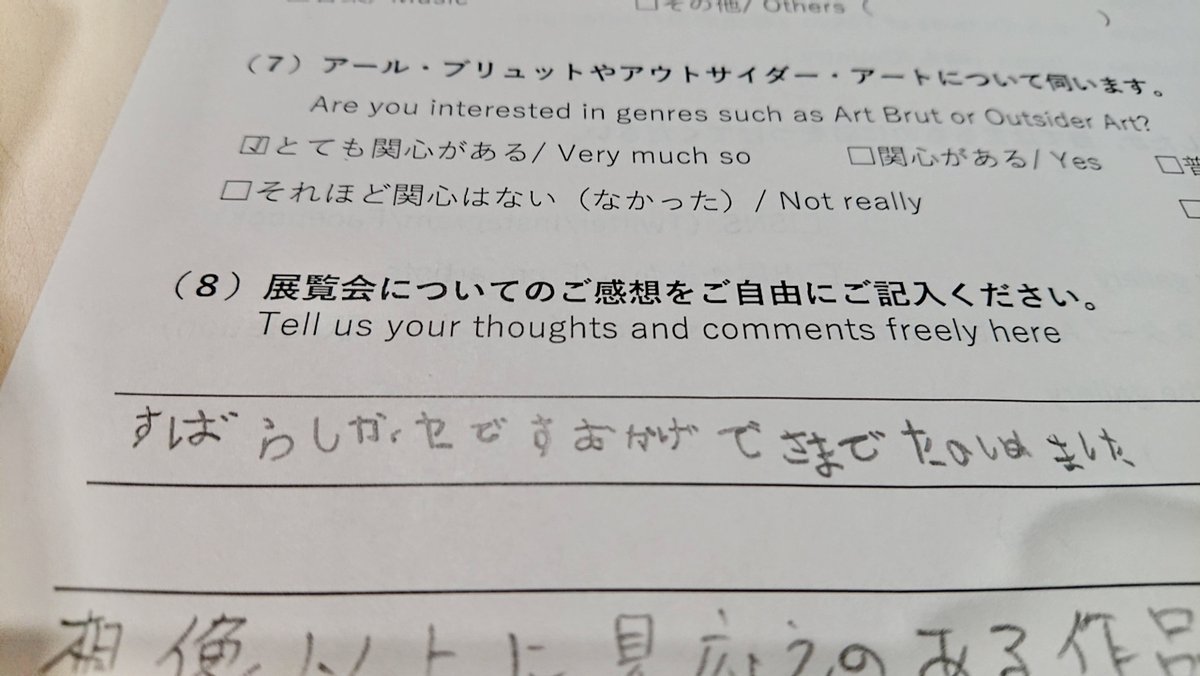
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
