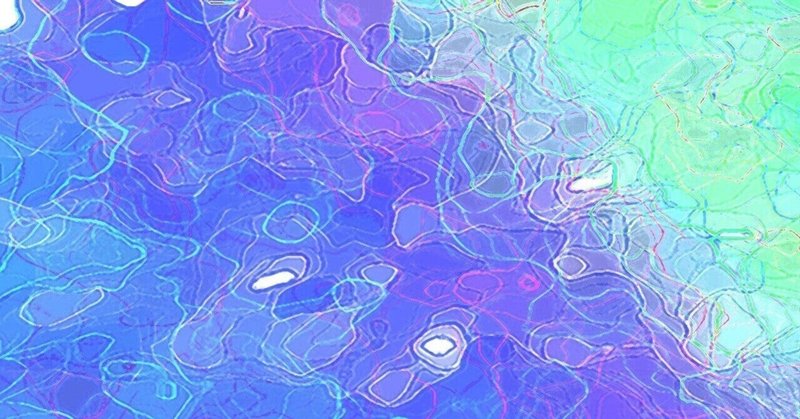
短編小説 『風待ち月』
「六月」の別名は、水無月、水月、田無月、そして風待ち月。田んぼの稲が青々と育って、そろそろ花が咲くという頃。いい風が吹いて、稲がよく実りますように。そんな風が吹くのを待つ月──
「お姉さん、そんなとこから乗り出してたら、落っこちて死んじゃいますよ」
突然、背後からさわやかな声が聞こえた。
平日、真昼の東尋坊。とはいえ、一応観光地なのだから、それなりに人がいるのだろうと思いきや、時間のせいもあってか、あたりには誰もいない。
聞こえるのは、砕ける波音と海鳥の声だけ。
その静かな雰囲気に、私はついつい気を大きくして、崖の際に近づいていた。自殺の名所として、何人もの命を奪ったはずの、目もくらむようなその断崖に。
初夏の日差しを受けた海面は宝石のようなコバルトブルーで、岩にしぶく波の白さが目にまぶしかった。その美しさに引き寄せられるように、もう少し、あと少し、私はふらふらと立ち入り禁止の柵を乗り越え、両手を地面につき、切り立った崖の淵から海を覗き込んだ。声がかけられたのは、そのときだった。
どうせ誰もいないだろう、そう安心しきっていた私は、恥ずかしいような後ろめたいような気持ちに顔を赤くして、後ろを振り向いた。
そこに立っていたのは、私よりもずっと若い、高校生くらいの男の子だった。声と同じさわやかな笑みを浮かべて、こちらを見ている。細面で色白の、なかなかのイケメンだ。
「そっち、立ち入り禁止だよ。危ないから」
「ごめんなさい。海があんまり綺麗だったから、もっと近くで見たくなっちゃって」
笑顔を作って謝りながら、私は手の乾いた土を払った。
梅雨の明けた空は晴れ渡り、太陽がじりじりと照りつけている。けれど、汗ばむような陽気だというのに、私の手は冷たく乾き切っていた。暑がりの会社の先輩がいつも冷房を効かせ過ぎるせいで、万年冷え性なのだ。
「うん、本当に綺麗ですよね」
私の台詞に、男の子はぱっと嬉しそうな笑顔を作った。
まぶしいな、私は反射的に目を細めた。イケメンの笑顔ってなぜかすごくまぶしく感じる──というのもあるけれど、そのときの私は、その無邪気な若さを直視することができなかったのだった。
だって、大学卒業後、社会人になって二年目の私はもうおばさんだ。ううん、これは決して年齢の話じゃない。そうじゃなくて、私の若さはこの一年でぼろぼろにすり切れて、もう誰からも見向きされなくなってしまったのだった。
私が黙っていると、男の子はひょいと柵を乗り越えた。ふとすると風に煽られ、バランスを崩して青い海に真っ逆さま──そんな危険な場所だというのに、私のように四つん這いになることもなしにすいすいと歩いてくる。そして、まるで曲芸師のように私の隣まで来ると、そこでやっとかがみ込み、再びにこっと笑った。
「……立ち入り禁止なんじゃないの?」
「お姉さんが怖くて動けなくなってるんじゃないかと思って」
違う? とでもいうように、首をかしげる。まだ少年のくせに、私より大きな手のひらを差し出す。
「優しいのね」
その手から目をそらすと、私は言った。我ながら嫌な言い方だった。けれど、若さも無邪気さもすり切らしてしまった私には、そんな言い方しかできなかった。
一年前の私だったら、その手を素直に取っていただろうに。どこか他人事のように、私は思った。それからふと思い直した。いや、それより前に、一年前の私だったら、こんな場所に一人で来るだなんて、そんなこと絶対にしなかっただろう、と。
宙ぶらりんになった手を、男の子はしばらくしてから困ったように引っ込めた。
ごめんね、おばさん余裕ないのよ、だからどうかこれに懲りて私を放っておいてくれる? 言葉に出さずにつぶやくと、私は視線を海に戻した。
青い青い青い海。白く砕ける波しぶき。水平線の向こうには、まだずーっと青い海が広がっている。
昔の人は、どうしてあんな青の向こうに、誰かの住む大陸があるだなんて思ったのだろう。何の確証もない夢みたいなものを信じて、命をかけてこぎ出せたのだろう。
もし、それがなかったら──信じたものがなかったら、だなんて少しも考えなかったんだろうか。大陸がなければ、自分の人生は無駄で、とんでもない失敗で、まったく意味のないものになってしまう、とは思わなかったのか。なぜそれが怖いと思わなかったのか。
──結奈、ずっと一緒にいよう。
そのとき、耳元であの人の声が聞こえた。ふとした折に聞こえるその声は幻聴で、あの人が私の隣にいるはずがないということは、何度も経験して分かっていることだった。
だというのに、その人を探して私ははっと振り返った。その瞬間、目が合った男の子が、驚いたようにまばたきをした。
海の音が聞こえた。私はしばらく惚けたように、男の子の瞳を見つめていた。ややあって、彼が口を開いた。
「……お姉さん、泣いてるの?」
「え?」
頬に手を当てると、確かにそこには涙のような滴が流れていた。
「……うん……そうみたい」
私は答えた。すると、いい加減枯れ果てたと思っていた涙がさらにぼろぼろとこぼれてきた。
「ごめんなさい、私……ごめんなさい……」
誰に何を謝っているのか分からないまま、私はそう繰り返し、泣き崩れた。会ったばかりの、名前も知らない男の子は、最初はおずおずと、それから優しく、私の背中を撫でてくれた。
*
あの人は会社の先輩で、名前を都築優介といった。社内でも優秀な営業マンで、みんなが彼を尊敬していた。仕事ができる男の人ってかっこいいよね、女の子たちはそう囁きあって、彼が営業所に顔を出すと、ぱっと雰囲気が明るくなるのだった。
一方、私は経理担当の事務員でも日陰の存在で、おしゃべりの輪にも加わることができないような、引っ込み思案を絵に描いたような性格をしていた。
思えば、学生時代からそうだった。
私がいるところはどこであっても日陰のように暗い、ぽつんと一人だけの空間だった。例え、仲間の輪に入ろうと努力してもそれは同じで、私はいつのまにかまた一人で、楽しそうなおしゃべりの輪は遠く離れた別の場所にあるのだった。
それは、誰かが意図的に私を仲間はずれにしたり、いじめているというわけではなかった。そうではなく、私はなぜかいつも集団の中からぽんと飛び出してしまうような性質を持っているらしい。まるで、磁石のN極とN極が反発し合うように、気付くと私は一人なのだ。
それがどうしてなのか、もちろん私は幼いころから悩んできた。一人でいることは苦ではなかったが、友達には憧れがあった。おそろいの筆箱を持ったり、好きな人を告白し合ったり、親には言えない秘密を共有したり。
けれど、それはことごとく憧れに終わった。そして、大学に入った頃には、私は一種、そんな自分自身を達観していた。ここでも私に友達はできないだろう。例えば挨拶を交わしたり、講義教室の変更を尋ねることができるくらいの、そんな最低限の良い関係を築くくらいが、私にできる精一杯のことなのだ、と。
友達でその調子なのだから、恋人などいわずもがなだった。
私の恋愛観は、中学生レベル──いや、小学生くらいで止まったままだった。つまり、クラスの人気者を遠く離れた場所から眺めて、かっこいいなあ、素敵だなあ、と一人で思っているくらいの。
当然のことながら、告白したい、付き合いたいなどと大それたことは思わない。それどころか、話したい、近くに行きたい、そんな感情すら起こらない。
本当にただ眺めているだけで、幸せ。それ以上のことは望むべくもない。他の女の子たちが順調に恋をし、手を繋いだ、キスをした、その先に進んだ、そう騒いでいるというのに、私はそんな幼い精神のまま、大学を卒業してしまった。そして、彼に出会ってしまったのだ。
*
「……少し、落ち着きました?」
男の子はそう言って、私の顔を覗き込んだ。
一応、ウォータープルーフの化粧品を使ってきたけれど、この涙の前にはぐちゃぐちゃだろう。
「これ、使います?」
どこから取り出したのか、ティッシュを取り出す。今時の男の子はこんなものも常備してるのかしら、妙なところに感心しながら、私はそれをありがたくもらうと顔に押し当てた。
「ごめんなさい。もう大丈夫だから、行ってちょうだい。たぶん……」
お母さんが心配してる? 学校の先生が探してる?
そう考えて、私は首をかしげた。男の子の横顔をまじまじと見つめる。
平日、真っ昼間の東尋坊。そんな場所に、この子は一体どこから来たのだろう。もちろん、彼は迷子になったというような年齢ではない。それに近くに学校など見当たらなかったし、あったとしてもサボりに来るには、ここは年頃の男の子には退屈で、不穏当な場所だ。
私の胸中に気付いたのか、男の子は例のまぶしい笑みを浮かべた。
「俺、学校とか行ってないから」
「行ってないって……不登校とか?」
聞いてから、失礼な問いだったかと慌てる。しかし、彼は困ったように笑っただけだった。
「うーん、っていうか、まあ不登校っちゃあ不登校っていうか……」
視線が着ている服を見るように、ふと下がる。つられて、私も彼の服を眺めた。そして、次の瞬間、いままでそれに気づかなかった自分に驚いた。
薄い長袖の縞シャツと、同じ柄をしたズボン。靴下もはかない足元はいわゆる便所サンダルで、消えかかった薄いマジックペンで「坂井総合病院」と書かれている。
「病院って……」
同じ柄の上下──つまり、パジャマを着ている彼の姿を、私は目を丸くして見つめた。
言われてみれば、何となく顔が青白いような気もする。入院患者だと言われれば、納得できるようなひょろっとした感じも受ける。けど、それにしたってどうして病人がこんなところに? まさか、病人は病人でも、頭の病院から抜け出した患者じゃ……?
「やだなあ、そんな変な目で見ないで下さいよ」
男の子は照れたように頭をかいた。
「まあ、言っても信じてもらえないかもしれないけど、精神病院から脱走した患者とかじゃないから」
「あ、別にそんなこと……」
考えをずばりと読まれて、私は顔を赤くした。
けれど、それなら彼はどんな病気なのだろう。怪我をしている様子はないし、パジャマのまま出歩ける病気なんて、そんなにあるとは思えない。
「今日は何だか調子がいいんだ」
すると、男の子は空を見上げるように顔を上げた。潮の匂いに満ちた海風が、少し長めの髪をさらう。気持ちよさそうなその表情に、私も思わず空を見上げた。
まるで南国みたいに真っ青な空。こんなに青い空を見るのは、もしかしたら初めてかもしれない。
「ね、天気もいいから、気分もいいでしょ?」
男の子は大きく伸びをすると、その何気ない調子のままで続けた。
「だから、こんな日に自殺なんて、もったいないよ、お姉さん」
そして、やっぱり困ったような笑みを浮かべた。
*
「……どうして私が自殺するんだって思ったの?」
真上にあった太陽がその位置を少し傾けるまで、しばらく私たちは黙りこくって空を見上げていた。
その間、私は何を考えていたのか。いや、何も考えていなかったんだろう。そうでなければ、やっとのことで口に出した質問があんなに馬鹿げたものになるはずがない。
この自殺の名所、東尋坊の崖っぷちにいながら、どうして自殺しようとしているとわかったのか、だなんて。
「ううん、えっとそうじゃなくて、その……やっぱりここで自殺する人ってそんなに多いの?」
我ながら間の抜けた質問だ。けど、男の子はそんなことは気にしないとでも言うように、首を振った。
「うーん、多分多いとは思うけど、詳しいことはよくわかんないです。俺もこんなとこまで来たのは初めてだし」
自殺しようとしてる人に会ったのも初めて、と小さな声で付け加える。
「にしては、堂々と声をかけてきたじゃない」
「あー、それは何でだろう。ちょっと違うけど、火事場の馬鹿力みたいな感じかな」
「そう? 慣れてる感じだったけど」
「いやいや。普段は知らない人に声かけたりしないですから」
「うそでしょう。ナンパとか、得意なんじゃない?」
「そんなことないですって。信じて下さいよ」
「どうしようかなあ……」
「いやいや。お願いしますって」
顔の前で手を合わせる仕草に、私は笑った。同時に、笑っている自分に驚いた。さっきまでボロボロに泣いて死のうと思ってた人間が、よくも年下の男の子との会話を楽しんでるもんだな、って。
また少し落ち込んだような雰囲気を感じさせてしまったのか、男の子が私の顔を覗き込む。けれど、今度は何も言わずに、そのままじっと私を見つめる。
「……そんなにひどい顔してる?」
「ひどい顔っていうか……これ、言ってもいいのかわかんないけど」
「なに?」
「まつげが、取れてます」
「うそ、やだ」
あいにく、鏡は持ち合わせていない。というか、お財布も手帳も、何もかもホテルに置いたまま出てきてしまった。死んでしまえば、そんなものは関係ないと思ったのだ。
私は手の感覚だけでつけまつげをつまむと、それをぺりぺりと引き剥がした。自然に見えるようにとわざわざ買っている、本物の人毛まつげ。当然、ポリエステル製なんかよりずっとお高いやつだ。
「それ、面白いですね」
感心したように男の子が言う。
「そうやってまつげを長くするんだ。いや、俺の周りって同年代の女子とかいないんで、そもそもそういうのを見たことがないっていう……」
「そうか、入院してる人が、お化粧なんてしないだろうしね」
どうせなら、ともう片方のまつげも剥がし、私はつぶやく。それから、ふと小さな声で告白をした。
「……まあ、私もこんなことを覚えたの、最近なんだけどね」
「そうなんですか?」
男の子が不思議そうに聞き返す。うん、私はうなずいて、剥がれたまつげを手のひらに乗せた。
──君って、化粧をしたら引き立つ顔だと思うけどな。
そう言ったのは、あの人だった。そして、あの人は覚えていないだろうけど、それが私たちが交わした最初の言葉だった。
輪から外れることに慣れ切って、いつものように日陰で事務処理をしていた私は、初め、それが自分にかけられた言葉だとはわからず、顔を上げることもしなかった。
日陰の私は、透明人間。誰にも見えない、声も聞こえない、ただひっそりと出社して、黙々と仕事を続ける、陰気な事務員。そんな人間に声をかけるような好き者がいるだなんて、私には思いもよらないことだったのだ。
──ねえ、無視しないでよ。聞こえてるんでしょ? 君だよ、君。佐原結奈さん。
まさか、この会社内に自分のフルネームを知ってる人間がいるだなんて。私は驚いて目を上げた。そして、そこにいたあの人の顔をまじまじと見つめた。
都築さん。女の子たちがいつも騒いでる、営業部の都築優介さん。
もちろん、私はその人のことを知っていた。けれど、その逆なんてあり得ない。会社でも中心の、きらきらと輝く太陽の下にいるその人が、どうして日陰の私を知っているの?
──知ってるよ、だって君、いつも真面目に仕事をしてるだろ? いい子だなーってずっと思ってたんだよ。
自分の仕事が、誰かの目に止まっていた。それだけで私は天まで舞い上がるような心地だったというのに、それがあの都築さんに認められていた、そんなことは自分の人生に起こっていい幸運ではないような気がした。
──そんなに自分を卑下するなよ。君は十分魅力的だし、仕事だってできる。……そうだ、このあとご飯なんてどう? もちろん、俺がおごるからさ。
私は真っ赤になってうなずいた。そして、それからの一ヶ月で、いままで聞いたことしかなかったような体験をすべてした。それは夢のような時間だった。
その夢の中で、私はお化粧を覚え、洋服のブランドを覚え、アクセサリーやネイルを覚えていった。
けれど、それは無駄だった。すべて、無駄だったのだ。
*
「私、好きな人がいたの。けど、その人、既婚者だったの」
十代の男の子には重すぎる告白を、私は吐き出すように口にした。
「周りの人はみんなそれを知ってて、私が浮かれてるのを笑ってたの。知らないのは、私だけだったの。本当に、私だけ……」
つぶやいた言葉は波の音にかき消され、風がその痕跡さえも消していった。けれど、その優しい自然は、頭の中の忌まわしい記憶までは消してくれなかった。いや、私がこの身を海に投げ出せば、跡形もなく消してくれるのだろうが。
「……それで、自殺しようとしたの?」
しばらくの沈黙の後、男の子はつぶやいた。自意識過剰だろうか、その言葉に批判が含まれているような気がして、私は皮肉っぽく返した。
「男にだまされただけじゃ、死ぬ理由にはならない?」
「そんなこと、言ってないですよ」
「ううん、でもそう思ってるでしょ? それくらいでって。失恋くらいで死んでちゃ、世界中から人間は消えてるものね」
「だから、そんなこと言ってないですって」
「でも、私にとっては初めての恋だったのよ」
彼の言葉など聞かず、私は叫ぶように言った。
「初めてだったの。何もかも、よ。こんなに人を好きになったのも、その人のために自分を変えたいって思ったことも、何もかも。それなのに、こんなのって……」
ひとりぼっちの、何にも知らないような女に近づき、モノにする。それが彼の得意技だと知ったのは、既婚者だと知ってすぐのことだった。
その仕事ぶりなんて見たこともない。名前なんて、当然知らない。けど、名前なんか机の名刺を見るなり、誰かに聞いておけばわかることだし、仕事も真面目にしている、だなんて適当に褒めておけばいい。化粧も知らないような女なら、それですぐに引っかかる。舞い上がって、手っ取り早く遊べる人形になる。
だから、これは恋なんかじゃなかったのだ。あの人は私じゃなくても、退屈しのぎになれば誰でもよかったのだ。
考え出すと再び涙が溢れてきて、青い空が海底から見上げたようにゆらゆらと揺れた。
私の隣で、男の子はじっと口をつぐんでいた。けれど、さあっと吹き抜けた風に顔を上げると、ふとこんなことを言った。
「……お姉さん。昔は六月のことを、何て言ったか知ってます?」
「……水無月とか、そういうこと?」
何を言われたかわからず、戸惑いながら私は答える。すると、男の子は少し笑った。
「うん、水無月。けど、ほかにもいっぱいあるんですよ。水月とか、田無月とか──風待ち月とか」
「風待ち月?」
「うん。風を待つ月」
海の風が吹いている。そのずっと向こう、水平線を見つめるように、彼は言った。
「田んぼの稲が青々と育って、そろそろ花が咲くって頃に、いい風が吹いて、稲がよく実りますようにって。そんな風が吹くのを待つ月」
何て返したらいいのか分からず、私は黙った。すると、男の子はきゅっとくちびるを横に引いた。何かを決意したような表情だった。
「……俺、ホントはお姉さんと同じなんです」
「同じって?」
「自殺しようと思ってここに来たってこと」
ちらり、笑うような目が私を見る。どうして、聞くより先に、彼は答えた。
「俺、実は今日、手術の日だったんですよね。ちょっと、頭ん中に居候がいるらしくて、そいつに退去してもらう手術」
「居候……?」
繰り返してから、それが脳腫瘍のようなものかもしれない、と思い当たる。
「そう、居候。これが俺の人生をいろいろ引っかき回してくれるんですよ」
軽く言いながらも、そっと頭に手を当てる。
脳の手術。事情など知らなくても、それが危険をはらむものだということは、私にも分かる。
「それって……大丈夫なの?」
私はどうしてこんなに頭が悪いんだろう。大丈夫だなんて、そんなはずがあるわけないのに。
けれど、男の子はやっぱり笑った。
「どうだろ。なんか危険な位置にあるらしいってことしか、俺もわかんないんだけど」
「危険な位置って……」
「なんかね」
男の子はやっぱり笑っていたが、私はもしかしたらそれは笑顔なんかじゃないのかもしれないと思った。笑顔じゃなく、一種の仮面。周囲を安心させるための。
「なんか、それを取っちまったら、俺が俺じゃなくなるかもしれないんですって。なんていうか、いままでの俺じゃなくなるっていうか、ほら、脳っていろいろヤバいでしょ? だから……」
私たちは再び黙った。沈黙の後、口を開いたのは、今度は私だった。
「……風待ち月、ね」
その言葉を彼はどこで知ったのだろう。私は知らない。けれど、なぜ彼がそんなことを言い出したのかは、少しだけ分かった気がした。
「うん。風待ち月」
彼が答える。
風は凪ぐことなく吹いている。この風は、果たして私たちの待っていた風なのだろうか。いや、私たちの風はまだ吹かない。いつ吹くのかも分からない。永遠に吹かないこともあるのかもしれない。
けれど、私たちにできることは、ただこうして風を待つことだけなのだ──彼はそう言いたかったんじゃないだろうか。
実らないからと、まだ青い稲を刈ってしまうのではなく、ただ信じて待つこと。いつかは風が吹き、黄金色の稲穂を実らせる、その風景を思い描いて、いまは待つこと。それが、いま私たちがすべきことなのかもしれない、と。
私は彼方の水平線を眺めた。なぜ昔の人はその先にあるものを信じることができたのだろう、ついさっきそう考えたことを思い返す。
「……ねえ、手術、受ける?」
その真っ直ぐな線から目を離さず、私は聞く。
「……お姉さんはどうします?」
同じように、水平線を見つめたまま、男の子が聞き返す。
「……思ったんだけど」
それには答えず、私は言った。
「世界とか何にも知らない状態で、この海のずっとずっと向こうにアメリカがあるって言われたら、どうする? 信じる?」
「……どうだろう。信じないかも」
「でもいまは? 学校でも習って、テレビにもアメリカ人が映って、飛行機で行くこともできて、その状態では信じる?」
「……うん。まあ」
何が言いたいのだろうという顔で、男の子が首をかしげる。
「私は──」
ゆっくりと噛み締めるように、私は言った。
「さっきまで忘れてたけど、どんなに傷ついても、いつかは過去になるって知ってる。笑い話になるって信じる。だから、もう死のうなんて思わない」
さっきまで泣きじゃくってた私の変わり身の早さに呆れただろうか、男の子がくすりと笑う。けれど、彼はすぐにその笑みを消すと、私と同じようにゆっくりと言った。
「じゃ、俺も手術は成功するって信じます。失敗したって死ぬわけじゃないし、もし俺が俺じゃなくなっても、そこから新しい人生が始まるって信じます。だから……」
もう死のうなんて思わない。彼はそう言って、おもむろに立ち上がると海に向かって同じ言葉を叫んだ。若いな、私がそう思って思わず笑うと、彼は最初会ったときと同じように、その大きな手のひらを差し出した。
「ほら、笑ってないで、お姉さんも一緒に」
「ええ? 私も? 私は……」
「いいから、ほら」
促され、私はその手を握り、立ち上がった。あんなやつのためには死なないぞ、そう叫ぶ。隣で男の子が、その調子、と笑う。それからびっくりするくらい大声で、死ぬもんか、と叫ぶ。そうして私たちは顔を見合わせて大笑いした。
「こら! そこは立ち入り禁止だぞ! 死にたいのか!」
私たちの声に気付いたのか、どこからかおじさんが走ってくる。
私たちはもう一度顔を見合わせると、その人に向かってこう叫んだ。
「絶対に死にません!」
その息はぴったりで、まるで事前に示し合わせたかのようだった。
風待ち月の風が、ようやく私たちにも吹き始めたようだった。
【風待ち月──完】
読んでいただき、ありがとうございました🙏
その他の小説はこちらのサイトマップから、ご覧いただけます😃
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
