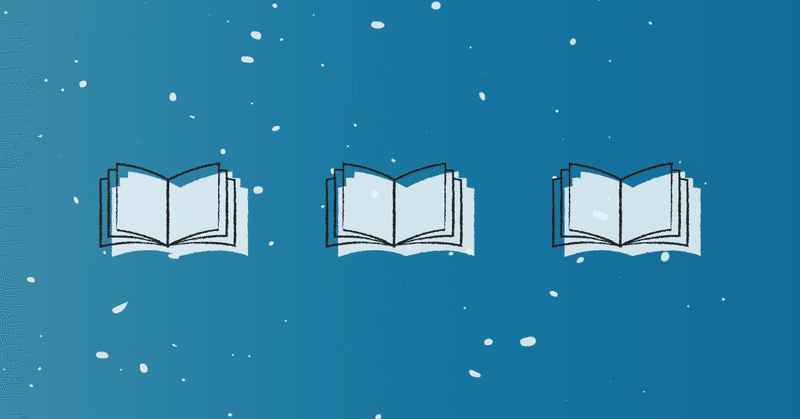
自学自習について
現在受け持っているクラスで、4月から続けている取り組みが「自学自習」と呼んでいるものだ。すごくシンプルに言えば、「子どもが授業をする授業」
自分の中にあるのは、一斉授業への違和感。「個別最適な学び」とはどういうもので、現在の授業の在り方をどうやって変えていけばいいのか。一年くらい前からずっとそのことを考えていて、まず自分のクラスレベルでできることと言えば、これだと思った。
準備
大きく三つあって、一つは単元の中でどの時間を自学自習をするのかを決めること。これは、単元の途中であることがほとんどだった。導入など、その学習を初めてやる時には、あまりむかない。先が見えている教師が、きちんときめるべきところだし、思い付きで決めてはいけない。
もう一つは、自学自習を担当する子どもとの打ち合わせ。このときには、教師用指導書など、普段の教材研究で使うものはすべてコピーして渡す。徹底した情報公開が最低条件。
指導書のコピーを渡すことに抵抗もあったが、よくよく考えてみたら、今やちょっと検索すれば指導案が出てくるし、NHK for Schoolでは、学習するためのワークシートまで出ている。というか、教科書の答えを教えることが授業ではないというのなら、こちらの手の内を隠す必要は、本来はないはずだった。本時目標や発問の計画を、一緒に立てていく。感覚としては、教員同士でやっている教材研究にちかい。
最後のひとつは、板書計画づくり。これは、個人的なこだわりかもしれない。どこに何を書くのかを、だいたい決めておくと、授業の形が見えてくる。
授業実践~授業後
子どもたちの授業が始まったら、口を挟まないように気を付ける。なんだか、うまくいかない感じがするときも、ぐっとがまん。そうすると、不思議と子どもたちは自力で何とかしてしまう。あとやることと言えば、写真を撮ったり、子どもたちの話に耳を傾けたりと、目の前の子どもたちの姿をただひたすら受け取ること。
終わったら、必ず教師が話すようにしている。授業者のよかったところ、この時間での学び、次回への改善点などが主である。
ここまでやってきて気付いたこと
(1)自分の授業の癖がわかる
子どもたちの授業の流れは、基本的には自分のマネなので、一斉授業における自分の癖や、欠点が浮き彫りになる。例えば、自分の場合は授業の導入では活発に発言をさせるが、まとめのあたりになると、引っぱってまとめていることが多いことがわかった。
(2)子どもたちは「学びたい」と思っているということ
それと、子どもたちが想像以上に自力で学ぶ力をもっているということに気づかされる。「教えてあげないとわからない」「支援してあげないとできない」と大人が手厚くすればするほど、子どもの力を奪っているのかもしれない。休み時間がとられるし、緊張するしで、大変な自学自習だけど、子どもたちはけっこうこの時間が好きだ。「自分たちでできる」というのがうれしいらしい。先日、子どもたちから「丸一日自学自習で過ごしてみたい」という要望があったくらいだ。単元の進み具合の調整が大変そうだが、できる限り実現したいと、自分も思っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
