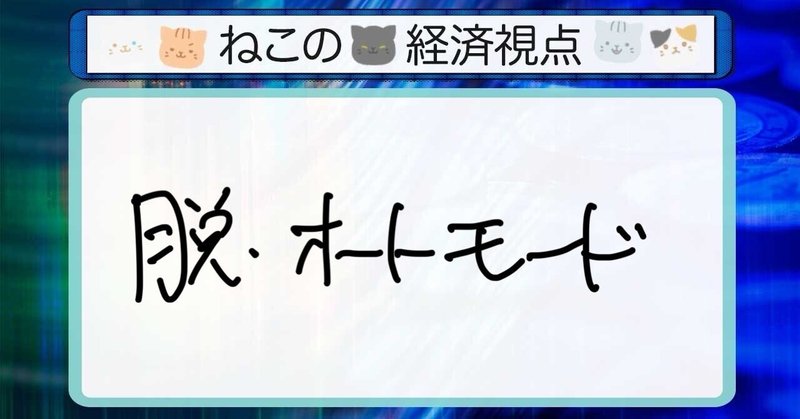
オートモードから成長戦略へ

① 日本株に業績予想の壁
もう一つの要因が、23年以降の株高局面で、日本株を新たに買い始めた海外投資家が多かったことだ。日本企業の保守的な情報開示姿勢に慣れておらず、「減益予想」が失望売りを招きやすかったとみられる。ゴールドマン・サックス証券の石橋隆行ヴァイス・プレジデントは日欧株の成績格差は「日本企業の慎重な計画と、それに慣れていない投資家層による売り反応で説明できる」と話す。
(中略)
日本経済新聞の集計では、東証プライム上場企業のうち前期と比較可能な約1070社が25年3月期の純利益を前期比4%減と5年ぶりの減益予想をする。野村証券の北岡智哉チーフ・エクイティ・ストラテジストは「日経平均が再び4万円台を目指すには四半期ごとの決算発表時点の上方修正を経て、今期の増益率が10%近くに高まる必要がある」とみる。
ここ最近の日本株が軟調な理由のひとつに、新規で入ってきた外国人投資家が日本の保守的な業績見通しに慣れてにゃいからー 実際にそうにゃんだろうけど、日本の慎重さにじゃっかん引いてる外国人投資家の表情を想像するとおかしくてしょうがにゃいにゃ😹
ひとつ論点として確かにゃのは、オートモードでじゃんじゃん外国から日本株に資金が流入するフェーズは終わって、ガチガチに守りを固めた業績予想を着実に上回っていけるか? 個別の成長戦略の可能性が見極められる展開ににゃってきましたにゃ☝️
② 【スクランブル】「自社株買い」後、続かぬ株高
持続的な株価の上昇には、中長期目線の投資家が将来の利益成長を確信できる材料が欠かせない。みずほ証券の菊地正俊チーフ株式ストラテジストは「自社株買いによる株式需給の引き締まり、1株あたり利益(EPS)の押し上げといった効果は一時的。単に自社株買いをするだけではだめだ」と指摘する。
(中略)
ソニーGは潤沢なキャッシュ創出力を武器に、自社株買いと成長投資の両立を図る。コモンズ投信の伊井哲朗社長は「資本コストを意識した経営を徹底している」と高く評価する。
積極的な株主還元が常識となる中、選別の目はいっそう厳しさを増している。
これも同じ話で、これまでは自社株買いをすればオートモードで株価も上がってったけど、これからは成長投資にも振り向けられるかが大事に☝️ 確かに、発表直後は大きく株価を上げてもその勢いは続いていかにゃい銘柄が多い印象でしたにゃ。それでも株価水準を上げている銘柄はあるから、その中から成長余力のありそうなものを探していくといいかにゃ? 相場全体がヨコヨコで推移してる今のうちに見つけておきたいですにゃ☝️
③ 物価を考える 試される持続力(4)「公助」で賃上げ、残る不安
おきぎん経済研究所(那覇市)のまとめによると県内観光客は3月まで28カ月連続、ホテル客室単価も14カ月連続で前年同月を上回った。3月の消費者物価指数は生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.5%上昇し、全国10地方で最も高かった。
地方でも需要増が先導し、物価や賃金の上昇に至るサイクルが回り出した。観光と並ぶけん引役が半導体だ。2023年の生鮮食品を除く総合指数上昇率は半導体投資が盛んな北海道で3.4%、東北で3.5%と全国(3.1%)を上回る。九州も23年10月以降は単月で全国を上回る。
これもオートモードで上昇し続けてきた物価。半導体やらインバウンドやらで九州・沖縄、北海道あたりが強いのはにゃんとにゃく想像できるけど、東北も意外と強いんですにゃ💪 記事では補助金も使って賃上げを促して物価との好循環を作り出そうと躍起ににゃってると紹介されてたけど、ここから各企業の成長力で維持していけるかどうか、引き続き賃上げ余力があって成長性も期待できるところは強いかにゃ?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
