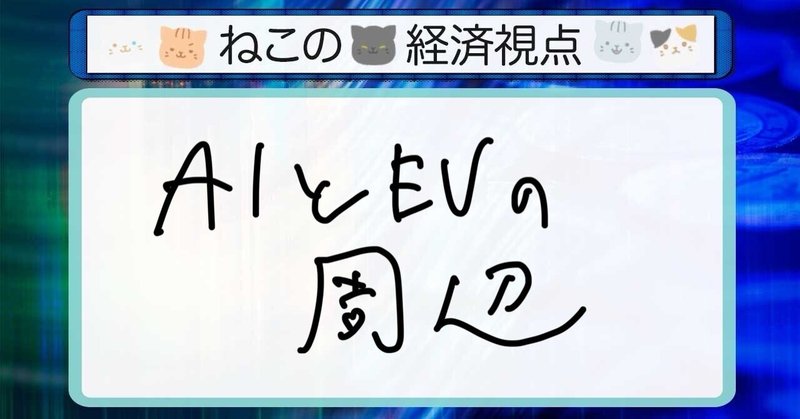
AIとEVの周辺に眠るチャンス

① AI関連株投資、裾野広く 世界の電力会社に資金
株式市場では物色の対象が周辺機器にも及ぶ。電力供給設備やサーバー向けの冷却装置を製造する米バーティブ・ホールディングスの株価は23年末の2.1倍になった。DC向けの電力システムや非常用電源を手掛ける米イートンは40%高い。
DC向け冷却設備を手掛ける米モディーン・マニュファクチャリングは23年末比で62%上昇。ニデックも4月に米サーバー大手のスーパー・マイクロ・コンピューターと開発した水冷機器の生産能力を引き上げると発表、翌日の株価は約半年ぶりの高値をつけた。
送電線の世界最大手、イタリアのプリズミアンの株価は年初から右肩上がりが続く。東海東京インテリジェンス・ラボ外国企業調査部の小暮大樹アナリストは「風力や太陽光発電所の普及で発電設備が分散しており、より多くの送電線が必要になることで恩恵が期待できる」とみる。
日本市場でもデータセンター関連、冷却技術、再生可能エネルギーの普及による送電インフラの需要増加に注目すると良いかにゃ? これらの分野に強みを持つ企業を地道に物色していくことはまだまだ有効と言えますにゃ😸 特に冷却装置とかは着目したことがにゃかったから、関連領域を広げればどんどん大きくなっていきそうですにゃ。国内外の市場動向を踏まえつつ、長期的な視点でこれらの分野への投資を検討したいですにゃ。
② 中国EV電池「10分で充電」 国軒、年末に量産開始
中国汽車工業協会によると、新車販売(輸出含む)に占めるEVやPHVなど新エネルギー車の比率は足元で32%で、EVだけだと20%だ。新エネ車の保有台数が増えたことで、連休期間中には高速道路のサービスエリアで充電を待つ列が長くなっていることなどが問題となっている。
こうした課題を受けて、中国ではEVを高電圧の充電に対応させることで充電時間を短縮しようとする動きが出ている。これまでは400ボルトの充電に対応できるEVプラットホーム(車台)を使うことが主流だったが、800ボルトに対応する車載電池の開発競争が激しくなっている。
車載電池世界最大手の寧徳時代新能源科技(CATL)は、4月下旬に開かれた北京国際自動車ショーで、LFP電池の新商品「神行PLUS電池」を発表。10分間で航続距離600キロメートル分の充電ができ、満充電の状態では1000キロメートルの走行が可能という。
(中略)
既存の充電ステーションで急速充電器を増やすには、送電線の増強が必要となる場合もあり、充電器を整備する側の投資は重くなる傾向にある。急速充電のEVが消費者に行き渡るためには、EVの性能向上とインフラ整備をバランス良く進める必要がある。
米欧ではEV幻滅期に入ったと言われてるけど、中国ではなんのその、加速度的に進化中にゃ💨 長い目で見ればEV化の波には逆らえそうににゃいから、そうにゃるとAIと相まってますます電力の重要性がましそうだから、そういう観点で投資のヒントはにゃいかChat GPTに聞いてみたらこんな答えをくれたにゃ😹
###
送電線および電力供給企業への投資に関する詳細なヒントは以下の通りです。
送電インフラ企業: 高電圧充電の普及に伴い、送電線の増強が必要となるため、送電インフラ企業への投資が有望です。既存の送電網の強化や新しい送電設備の導入を手がける企業を検討しましょう。
電力供給会社: 急速充電に対応するための電力需要が増加するため、電力供給会社への投資も検討に値します。再生可能エネルギーを積極的に導入している企業は特に注目されます。
スマートグリッド技術: 電力網の効率的な管理と運用を可能にするスマートグリッド技術を提供する企業も有望です。これにより、送電の安定性と効率が向上し、EV充電インフラの拡充が加速します。
政府政策と補助金: 各国政府のEV普及政策や補助金の動向を注視し、これに関連する企業への投資を検討することが重要です。政策支援が強い地域の企業は成長が見込まれます。
これらのポイントを踏まえ、送電および電力供給分野の企業への投資戦略を構築することができます。
###
にゃかにゃか簡潔にポイントを整理してくれたのでそのまま載っけとくにゃ😹
③ 【スクランブル】次の「株価2倍」銘柄を探せ
ダブルバガー株には株主還元を強化した銘柄も少なくない。東京証券取引所が資本コストを意識した経営を促す点が背景にある。川崎汽船は配当利回りの高さと継続的な自社株買いが材料視される。丸三証券は前期から5年にわたり特別配当を出すとした。
ただ、三井住友DSアセットマネジメントの木村忠央チーフファンドマネージャーは「中長期で最も重視したいのは、既存事業の収益性の向上だ」と指摘する。木村氏は「株主還元は一時的な上昇効果の場合もあり、成長投資の戦略は説得力に乏しい事例も少なくない」と続ける。
(中略)
ある運用会社のファンドマネジャーは、ワイパーゴムのフコク(同68%高)を評価する。不良品低減といった地道な努力を積み重ね、純利益で連続最高益を見込む。
今年の本決算では大幅な増配を発表して株価が急上昇する銘柄も少なくにゃかったけど、株主還元だけでなく、事業そのものの競争力や成長性を評価する必要があるにゃ☝️ 地道な努力で収益性を高めている企業は持続的な成長が期待できるけど、にゃかにゃかそういうところを見抜くのは難しいから、常々小さな変化を見逃さにゃいように見ていきたいものですにゃ😼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
