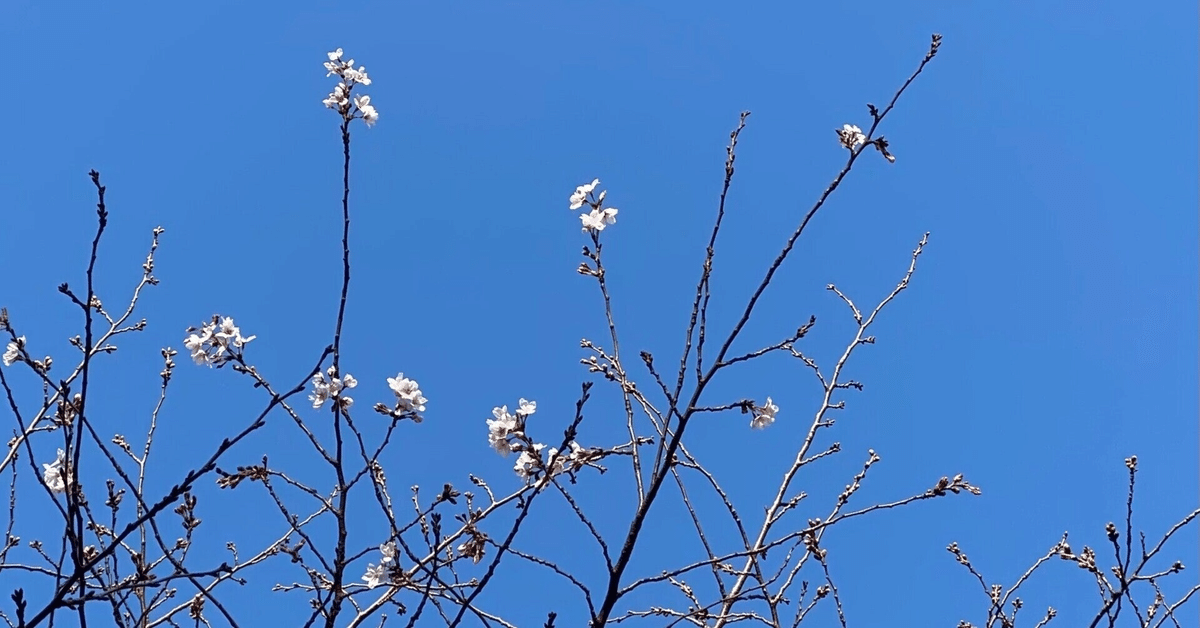
(22-01-05)擬人化された英単語が地球を救う。はあ?【小説】ことだまカンパニー エピローグ(1)~(5)
一
何を言っているのか分からないが、ひそひそ話が交わされている。二、三人の男たちの低い声……。それがごくゆっくりと、意味のありそうな音の連続として意識の城壁の外から呼びかけている。だが、まだその会話の文脈を分析するだけの理性は戻っていない。ただ、聞いている。
「二人とも、息がある……」
「あの……白衣と袴で良ければ、着替え持ってきましょうか」
「恐れ入ります。お言葉に甘えます」
「こちらの女性へは……」
「智哉くん、司庁舎から巫女装束を」
「あ、神谷さん、分かりました」
それからしばらく静かになった。頬に緩く風が当たる感触がある。
「起こしますか」
「あ、ちょっと待ってください」
すると、急にリアルな布の感触が頬と口元から脳に伝わってきて、思わず顔をしかめる。同時に闇がさっと白くなったので、目を閉じたまま、さらにギュッと目の周りの筋肉に力を入れた。
後ろの方でわずかに弾んだ声がする。
「あ、陽が差してきましたね」
聞き覚えのある男がすぐ間近でつぶやいた。
「余計目立つなあ。しょうがないなあ……」
布で口元を強めに拭われる。それが不快でまぶしさに怯えつつ、うっすら目を開けていく。
「お。万三郎、気が付いたか」
一文字に細く目を開けて、光量を絞りながら正面に認めたのは、逆光でまだ表情がよく分からないものの、声からして杏児に違いなかった。万三郎は、何枚かの毛布にくるまれて長椅子の上に横向きに寝かされていることを自覚した。
「どう? 体調は」
まだ意識がクリアにならないので、そのままの視線を保つ。杏児が額に手を置いた。徐々に目が光に慣れてくる。
「うむ、平熱。万三郎、ユキに感謝しろよ」
――ユキ……。あ……。
ユキの顔が心に浮かんだ。それと同時に、フラッシュバックのように、それまでの記憶が一気によみがえってきた。
「お、目に光が戻って来たな」
杏児が嬉しそうに言いながら、視線を万三郎の腹の方に移している。
「杏児……ユキは?」
万三郎がつぶやくように聞くと、一瞬視線を戻した杏児が、「ここだ」と改めて視線で腹の辺りを示した。ああ、そう言われれば、腹の辺りに少し重さを感じる。だが、万三郎は頭をもたげて自分の腹を見る力もまだなかった。
「生きてる?」
「ああ、呼吸はある。でもかわいそうに、服もびしょ濡れだ」
杏児はそう言うと、ユキの身体を揺り動かしているようだ。
「おいユキ、大丈夫か」
万三郎は、その振動が伝わってくる自分の脇腹辺りに手を伸ばしてみた。毛布越しにユキの手が感じられる。さらに手を伸ばすと、万三郎が横たわっている長椅子の中ほど、万三郎の腹のあたりに、ユキの頭の感触があった。ユキは床にぺたりと座って、万三郎の長椅子に上体を預けて力尽きたようだ。
万三郎は意を決して上体を起こした。身体中の筋肉が傷み、思わず顔をゆがめる。両肘を後ろに突いて頭を起こしてみると、ユキが濡れた髪を振り乱してそこに突っ伏していた。
「ユキ」
万三郎が呼びかけ、杏児が肩をつかんでそっと揺らすと、ユキがうーんと言って動いた。
「おお、気がついたようで良かった」
神谷が皺の多い目尻を下げ、しみじみと喜びを口にした。
そこへ、司庁舎から着替えを持って衛士が戻って来る。
二
若い衛士は気が利いていて、三人の足袋や草履まで揃えて持って来てくれていたので、烏帽子や髪飾りこそないものの、しばらくの後、三人は神職の装束をまとって神妙な面持ちで参集殿の椅子に並んで腰かけていた。
濡れた衣服から解放され、万三郎は着替えを手伝ってくれた若い衛士に礼を言った。ユキも、年配の女性職員に手伝ってもらい、別室で着替えた後、濡れてばらけていた髪をきれいに梳かれ、巫女のように束ねられて、うっすら紅まで差してもらったので、やつれた印象が幾分ましになっていた。それでもまだ、杏児ほど元気にはなれず、口数が極端に少ない。
「杏ちゃん、ちづるちゃんは?」
杏児がユキの方に顔を向けて答える。
「夜中にことだま東京に帰った。アポフィスがそれたら、リアル・ワールドで必ず会おうって」
「そう」
杏児の声が若干弾んでいるのを感じ、ユキは微笑んだ。
その時、向こうから神谷と、他に四人の職員が万三郎たちに近寄ってきた。さっきから会っていたのに今になって初めて気付いた。彼らはこのような未曽有の状況にあっても、衛士の制服あるいは神職の装束をきちんと身にまとっている。神谷老衛士を先頭に、五人が、万三郎たちが座っている長椅子の前に進んできた。万三郎たちは何事かと目を見張る。すると五人は万三郎たちに正対して気を付けをして、
「救国官の皆さん、ありがとうございます!」
と言って深々と敬礼したのだ。
「い、いや、ちょっと、待ってください……」
身体は丸太のようだったが、それでも万三郎もユキも杏児も、その場で慌てて起立した。五人はまだ頭を下げている。三人は本当に困惑した。
「こちらこそ、祈りの場所を貸していただいて……。でも、まだ、本当に危険が去ったかどうか……」
万三郎の言葉に答えて、頭を下げた衛士たちの向こうから声が聞こえた。
「危険は去った。地球は救われたよ」
三人ともその声にハッとする。
「石川さん!」
石川は一人でコツコツと歩み寄ってきた。
「アポフィスは、地球をかすめて通り過ぎて行ったよ。台風の被害は大きいが、今は日本海に抜けた。電波障害は……」
石川はスーツの内ポケットからスマホを取り出してリダイヤルボタンを押した。すると、ユキのスマホから山寺和尚さんの着信音が鳴り始めた。
「まだ政府専用回線だけかもしれんが、回復したようだ」
「石川さん、夜中に私にかけましたか」
「お、あのとき着信していたのか? なぜ出ない」
石川の問いにユキは皮肉っぽく笑う。
「気を失っていくところでした」
「そうか。真夜中頃、一時的に電波表示が立っているのを発見してかけてみたのだ。それ以降はまたずっと通じなかった。だが専門家の話だと、電磁波も少しずつ正常値に落ち着いてくるだろうということだ」
ユキが前のめりになって訊く。
「ワーズたちは、ワーズたちはどうなりましたか」
石川は、衛士たちの後ろからユキを目で制した。ことだまワールドの情報について、昨日大泉総理が公表した以上のことは秘密だということらしい。
「ち、ちづるッ!」
杏児が叫んだ。
「颯介さ……杏児さん」
後ろから石川の横をすり抜けて杏児に駆け寄ったのは、まさしく杏児の恋人、小村ちづるだ。杏児はちづるの両手を握った。
「やっぱり、リアルさが全然違う!」
そう言いながら両手をさすり続ける杏児を、同僚や衛士たちが見ているのに気恥ずかしさを覚え、ちづるはそっと手を引く。杏児はちづるの無事を喜びながら訊いた。
「どうしてここに?」
ちづるはちょっと後ろを振り返った。
「石川さんに東京から連れて来ていただいたんです」
「どうやって」
神谷の目配せで衛士たちがその場から立ち退いて、そこへ石川が一歩近づきながら言った。羽田に向かう飛行機の中で杏児の襟首をつかんだ石川とは違って、目に、ほんの微かに笑みを浮かべている。
「国家権力を甘く見るな。これくらいの風なら、ここまで充分ヘリを飛ばせる」
隣りで聞いていた万三郎が小さくつぶやく。
「なんてこったい、国家権力……」
石川はチラリと万三郎を見てから杏児に視線を戻した。
「古都田社長がお前と藤堂の活躍を褒めていたから、その褒美に会わせてやることにした」
「藤堂……?」
ちづるが杏児に答える。
「私のことです」
三
ひと足先に参集殿の外に出ていた神谷たち衛士の誘いで、万三郎たちは外へ出てみた。吹き返しの風は生暖かく、まだ時折り強く吹いたが、雨は完全に止んで、雲間から日が差し込んでいる。ユキの束ねた髪が揺れ、万三郎の袴は風を孕んだ。
杏児とちづるも、その横で並んで立っている。彼らの視線の先には、五十鈴川の対岸にある木立ちがあった。五十鈴川の川面は木々に隠されて見えない。対岸の並木でも、折れた立木の、白く生々しい裂け目が散見されたが、目測三十メートルはあろうかという国旗掲揚塔が、昨夜の暴風をしのいで泰然と立っているのが目に留まる。そして、その先端には、日本国の国旗が力強くはためいていた。神谷も救国官たちに並んで日の丸を見ている。そして静かに口を開いた。
「この通り、あなた方救国官の祈りのおかげで、日本は壊滅を免れました。しかし……」
神谷はいったんそこで言葉を切る。そして、万三郎を振り返って訊くのだった。
「政府のお墨付きであるあなた方の、国を救う祈りとは、いったいどのようなものだったのですか」
円熟した老紳士の目の奥に残っていた好奇心が光を発するのが見えた。万三郎は当惑して口ごもりながら視線をぐるぐる巡らせる。すると石川が、神谷には答えず、全然違うことを中浜に言った。
「ああそうだ中浜、お前、航空自衛隊小牧基地の井関さんから車を借りたのか」
神谷に続き、思いがけない話が石川から出て、万三郎はちょっと混乱する。
「え? あ、は……はい。ピックアップトラックをお借りしました」
「そうか。さっきまで、伊関さんの部下たちのヘリがあそこに着陸していた」
そう言って石川は、対岸の木立の向こうにある駐車場のあたりを指さす。
「神宮周辺の被害状況の調査に来たということだ。ピックアップトラックを見つけて、お前たちの働きを理解したようだ。調査報告のためヘリは、隊員二人だけ残してすぐ帰っていった。その二人はトラックを運転して陸路を帰って行ったよ」
そこで石川は万三郎の方に向き直って、折り畳まれた紙片を差し出した。
「お前たちへ、伊関さんから直筆のメモを預かっている」
差し出されるままに万三郎はその紙片を受け取り、開いた。ユキと杏児も寄ってきて紙片を覗き込んだ。
「昨夜、私は皆と一緒に希望を祈り、今朝、人類は救われました。最後の瞬間まで希望を失わないこと――娘の心は、きっとあの時、救われていたのだと信じます。あなた方が無事であると希望を持って祈っています。台風被害からの復旧作業が落ち着いたら、またお会いしましょう。伊関」
一歩離れた後方から紙片を覗き込もうとする神谷に、石川は言葉をかける。だがそれは先ほどの問いに答えるものではなかった。
「それはそうと衛士さん。ヘリで上空から見たら、五十鈴川の水位は相当高いものの、どうやら決壊は免れたようですね。街の浸水は軽微に見えました。御正殿以下ご社殿は無事だったのですか」
石川は神谷の関心を逸らすことに明らかに成功した。神谷は石川の方に向き直り、それから参道を見やった。
「若い職員たちがチェーンソーとロープを持って様子を見に行っています。あ、あれがその一人です。井出くん!」
速足で参道をこちらに向かってきた、作業着姿の男性を神谷は呼び止めた。
「御正殿は?」
息を弾ませつつ男性は答える。
「無事でした。奇跡です」
「その目で見たのか」
「倒木を乗り越え、切り開いて、この目で見てきました」
「おお! ありがたい」
神谷の目がみるみる潤んでゆく。それを照れくさく感じて隠そうとしたのか、神谷は、井出と呼んでいたその男性を抱擁してその背中をポンポンと叩いた。
「良かった良かった……ありがとう」
「神谷さん、僕はこれから大宮司様への報告と参道回復の応援を頼みにいったん司庁舎へ戻ります。神谷さんは、どうされますか」
「ああ、一緒に行こう。大宮司様にお祝い申し上げたい」
神谷は一行を振り返る。
「よろしいですかな」
石川が頷いた。
若い衛士たちも引き連れ、いそいそと司庁舎に向かう神谷の後ろ姿を見届け、石川は部下たちに言った。
「さあ、東京に帰るぞ」
「は?」
は? と言った杏児を石川はギロリと見た。
「総理から直接指示を受けて迎えに来た。お前たちの口で結果報告しなければならない。ヘリを駐車場に待たせてある」
そう言い捨てると石川はスタスタと歩き始める。
「石川さん、ちょっと待ってください!」
万三郎の呼びかけに石川が振り返る。
「何だ」
「御正殿に参拝してからじゃ、ダメですか」
石川は、身体ごと万三郎に向き直り、その白衣と袴の全身の姿をまじまじと見た。そして隣のユキの巫女姿も。
数秒の沈黙があったが、やがて石川は口を開いた。
「藤堂!」
ちづるは驚いてばね仕掛けのように背筋を伸ばす。
「はいッ!」
「司庁舎へ行って、巫女服をひと揃え借りて来い。お前のサイズでな」
「は……はい、分かりました」
心得てちづるは駆け出した。石川の横をすり抜けた時、石川にさらに呼び止められた。
「藤堂!」
「はいッ!」
「男性用もひと揃え追加だ。サイズはLだ」
万三郎とユキは目を丸くして顔を見合わせた。そしてククッと声に出さずに笑った。
弱々しくも口角の上がったユキの頬に、小さくて白いものが貼り付いている。万三郎が気付いてユキの頬からその淡い色の小片をつまみあげてみると、それは花びらだった。風上を見て、初めて気付いた。倒壊を免れたソメイヨシノの小ぶりな木は、昨日の今頃はおそらく満開の花をつけていたのだろう。夜来の台風にあれほどさらされながら、ほんの僅かに、花が咲き残っている。今さら吹き散らされたこのひとひらは不運だったが、風はこれから次第に弱まっていくだろう。万三郎はユキに花びらを見せてやりながら言った。
「リアル・ワールドでのお花見は来年にお預けになったね」
四
ゴールデンウイーク直前のある日、古都田社長の主催で、KCJ事業部合同の社内祝賀会がリアル・ワールド東京某所の居酒屋「百人座敷」で開かれた。もちろん、世界が滅びなかったことのお祝いだ。
皆が掘りごたつの席につくと、座敷がいっぱいになった。リアル・ワールドでの祝賀会だからワーズやソウルズはいない。ここにいるのはETも含め、皆ヒューマン社員ということになる。見回してみると、万三郎たち三人の長テーブルの上座には、甲斐和月先生や戸井久美子先生、片井文吾郎先生がかたまって席についていたし、身の上は知らなかったが、ことだまワールドで見かけたことのある顔ぶれも座敷のそこここに座っている。万三郎は隣に座っているユキにそっと訊いた。
「KCJって、こんなにたくさんのヒューマン社員がいるんだ。ユキ、知ってたの?」
ユキはかぶりを振る。
「私も初めて知ったわ」
すると、テーブルの向かい側に座っている杏児が二人にそっと答えた。
「あそこに明穂……あ、ちづるが座ってるだろ? 彼女とその回りは中国語事業部だって。で、明穂の隣の人に聞いたんだけど、他は、フランス語事業部、ドイツ語事業部、スペイン語事業部、ロシア語事業部の連中らしい」
そのひそひそ声を聞きつけて、隣のテーブルに座っていた若い女性たちの一人が三人に言う。
「私たち、韓国語事業部よ」
「あ……そうなんだ、どうも、はじめまして」
両グループは会釈を交わした。
万三郎が再び会場を見渡しながら独り言のようにつぶやいた。
「スピアリアーズは……」
そんな万三郎を見て、杏児が黙って首を振る。万三郎は杏児のその素振りを見て、目を伏せた。
「そうか……」
その時、恵美に付き添われて古都田社長が登場した。講師たちに先導されて拍手が広がる。
「なんてこったい、ホーリー・マッカラル……」
古都田の姿を見た三人は、一様に驚きの表情を浮かべた。あまりにひどくやつれていたからだ。
――あれほど矍鑠としていた社長が……。
地球は助かったものの、一連の出来事は、社長には心身ともに相当こたえたのかも、と万三郎は思った。
ことだまカンパニーがやっていることは人体実験に他ならないと憤っていた新渡戸部長は、やはり来ていない。あの日以来、古都田と新渡戸が再び接触したのか、少なくとも三人には知らされていない。
三人にとって、新渡戸は入社当時から一番近くにいた上司ゆえ、親愛の情も少なからずあったから、彼が社長に牙をむいたことは、予想だにしないショッキングなできごとだった。以来そのことは意識的に口にせず、気にもせず、三人の心にそれぞれ澱となって静かに沈殿するに任せていたのだったが、こうして痛ましい古都田社長の姿を見せられると、その記憶が再び激しくかき混ぜられた。
ただ、幸いなことに、羽田へ向かうときに頬に受けた銃創はほぼ目立たなくなっていた。
恵美がスタンドマイクの高さを調整している間に、万三郎が杏児にささやく。
「新渡戸部長、まさか雉島さんの側について完全にソウルズになったりしてないだろうな……」
そんな問いに即座に応じた杏児も、やはり同じことを考えていたのだ。
「リアル・ワールドの肉体を放棄してないかってことだろ? 僕もそれが気になって……」
五
マイクの前に立つと、それでも古都田はにっこり笑みを浮かべた。恵美がすぐ横に控えている。
「KCJヒューマン社員の諸君」
意識的にそうしているのかもしれないが、声には社長らしい張りがあった。
「わが社は今回、内部留保のエネルギーを使い果たしました。これから各事業部のワーズ達にエネルギーを注いで元気を取り戻してもらう必要があります。そのために大いに職務に励んでいただきたい。特に!」
――おお、社長室での古都田社長と同じ語り口だ。
間髪入れず緊張感を醸し出す古都田節は健在だと万三郎は思った。
「業績回復のため、今後はより多くのクライアントにことだまを使ってもらわなければならん。そこで営業部を強化することにした。斎藤くん」
口調が古都田社長らしく偉そうになってきた。万三郎は嬉しく思う。
「はい」
古都田社長に近い席から、細身の男が立ち上がって皆の方を向いた。
「斎藤圭太と申します。私は第一営業課長として、主力商品『KCJお得意様強制パック・ゴールド』の普及に努めていましたが、このたび現場オペレーションを部下の皆さんに任せ、私は、クライアント候補の適性を調査・提案する、営業調査部の部長として本社に召還されることになりました。
「いよっ! 斎藤部長! あんたが大将!」
部下たちであろう男女が拍手とともに冷やかす。会場はちょっとした笑いで和んだ。
斎藤は挑戦的なまなざしになって、座敷の一角に汗をぬぐいながら座っているメタボな男を見ながら言った。
「そこにいる、同期の今神前部長より、いい仕事をやってのける所存です。特に、フラッフィーがサーバーと交信している時に流れるイヤー・ワームの曲目を、最近クライアントが口ずさんだ鼻歌に随時差し替えるつもりです。そうすることで、クライアント個人の妄想も含めた全ての思考情報を、違和感を抱かれることなく盗み出す……いや、吸い上げる新システムの普及にまい進する所存ですので、古都田社長、どうぞご期待ください」
斎藤は古都田に向き直って一礼する。ともかくも会場から温かい拍手が贈られた。
古都田はマイク越しに言う。
「特に君に期待をしておるわけではない。今神くんはこれから、役員のみなさんに向けて、一連のできごとを詳細なレポートにまとめなければならん。多忙で営業調査部長を兼務できなくなるため、仕方のない人事だ。そして、斎藤くんの昇進を進言したのは今神くんだ。斎藤くん、今神くんに感謝したまえ」
「は……?」
席に着いたまま呆気にとられる斎藤。場が一気に凍りつく。古都田社長は彼と部下たちを見下ろすような目つきで付け加えた。
「そして、大将は君ではない。私だ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
