
「私、差別と偏見しないから」と言われた僕は絶望で絶句した
「私、差別と偏見しないから」
この発言を超える差別も偏見も、僕は知らない。
僕は、いったいどんな顔をしていただろう。
大学の教室で、午後で、4人で、ディベートをしていた。授業中にも関わらず、僕はひどくショックを受けていた。
ともかく、瞬間最大絶望ランキングの上位3位に食い込むほど徹底的に絶望したのは確かだ。思い出しただけで心臓のあたりが冷えて温度をなくしていく。家が裁判所に差し押さえられた時のほうがまだマシと思えるレベルで、僕は動揺した。
今日はこの言葉で徹底的に絶望した理由と、その絶望を優しい色で塗り替えてくれた言葉の話をする。

「差別・偏見ない」宣言がなぜ衝撃的だったのか
「私、身体の中って空っぽだと思う! だって内臓なんて見たことないし!」
コレと同じくらいの衝撃だった、といえば、僕の失望と絶望と驚愕がなんとなく伝わるだろうか。
この発言がなされたのが、哲学や倫理の授業なら5,000歩譲ってまだわかる。ものごとの実在について激論を交わす場だというなら、話し合いの余地はある。我々はじぶんが直接目にしたことのない内臓の実在を証明できるのか? すばらしいテーマだ。
だがこれが、生物の授業だったら、どうだろう。生物の授業中に「たばこは肺に対し、影響を及ぼすか否か? 近くの席の人と、話し合ってみましょう!」って時に「内臓なんてないと思う!」をブチかまされたとしたら。
素直に「え、マジで?」と、僕は思った。
例え話から実際の事件に話を戻すと、僕がこの発言を食らったのは「サステナビリティ」について話す授業の中でだった。サステナビリティとは「持続可能性」のことで、簡単に言えば「社会や自然環境をなるべく持続させるために、私たちができることはなんだろう?」ということだ。
授業ではサステナビリティをもうすこし広く捉え、ひとがのびのびと暮らし、健康で豊かに生きていくことや、人権について、また教育についても考える時間があった。人の尊厳を守り、教育を施し、より多くの人がのびのびと生きていけることが、社会の持続性につながる。そんな視点での授業だった。
議題は「学校教育が差別を助長することは、あるか?」僕は即座に「ある。いまの教育はどうしても、いくつかの差別や偏見を助長する側面があると思う」と答えた。それを受けて、おなじグループのメンバーが不思議そうな顔でこう言った。
「差別や偏見なんて無いと思う。私は差別も偏見もしないし、周りでも見たことない」
僕はたぶん、生まれて初めて絶句した。
は? とも、なに? とも、言えなかった。
相手は差別や偏見について、自分の中にあることも知らなければ、周囲のそれに気付こうともしていない。少なくとも、僕はそんなふうに受け取った。ショックだったと気付いたのは、何かが腹の底からせり上がるのを感じたときだ。
ドス黒い、怒りだった。
いったい今まで何を考えて生きてきたらこんなことを口に出せるんだ?
ああ、うらやましい。あなたは差別にも偏見にも晒されず、「自分ごと」として考える必要にも迫られず、自分は弱者に理解のあるすばらしい人間だと思って生きている。すごい。あなたは自分が無自覚に、あるいはあなたの思う「やさしさ」で誰かを加害している可能性など露ほども知らずに生きてきた。ああ、僕はあなたがうらやましい。
悲鳴とも唸り声ともつかない音が喉までせりあがるのを感じた僕はあわてて心のシャッターをガラガラ下ろした。あぶねえ。このまま口を開いちゃいけない。ディベートの場で相手の人格を否定しかねない発言をするなど、断じてあってはならない。何より、あまりにも露骨にルサンチマンが全開だ。僕にも恥の感情くらいはある。
そもそもこの部分、今日の議題の本筋じゃない。僕はあわてて頭の中を整理した。深呼吸をひとつして、彼女に質問してみる。
「じゃあ、たとえばですけど。あなたは日本史の教科書に書いて”いない”ことを、どれだけ知っていますか。教科書に書いていなかったことを見たり聞いたりした時、『教科書に書いてないし間違ってるんじゃない?』って思ったことは、ありませんか」
相手はポカンとしていた。
「僕は『教科書に書いてあること以外にも事実はある』ことと『事実の解釈は時代、人により違うし、伝わりかたも変化する』ことを学校で教えるべきだと思っていますが、どうでしょうか……」
僕は辛抱強く待った。
相手はまだポカンとしている。
「はーい、じゃあディベートおしまいです」
教授の声が朗らかに響いた。
彼女の答えを聞く機会は、永久に失われた。

僕は差別と偏見の塊だ
僕は差別も偏見もメチャクチャする。ありすぎて困るくらいに、差別も偏見も、ガンガンしている。だからみんなどんどん差別・偏見しろなんて意味ではない。まずは自分の中に差別と偏見があると認めることが大事という話だ。そのうえで、可能な限りメンテナンスを実施する。「思い込み」という名の差別や偏見があることに気付いたら、ひとつひとつ精査する。丁寧にみつめて、ほぐせるものから、慎重にほぐしていく。誰かと話して、想いに触れて、ガーンという衝撃とともに一気にぶっ壊されることもある。生きているあいだずっと、自分の中の差別や偏見を見直す必要に迫られる。これはたいへんなことだ。それでもだいじで、必要なことだ。
差別や偏見を、悪だとは思わない。免疫細胞やウイルスバスターのようなものだ。花粉症の人の免疫さんたちが、本来は無害な花粉を過剰に攻撃するように。心の免疫作用だと、僕は考えている。
昔いじめにあっていた人がいじめっ子と再会したとき、怒りが湧いたり恐怖が蘇ったりするのを偏見と呼ぶ人は少ない。でも、僕からすればこれも偏見だ。いじめっ子は改心して心を入れ替えているかもしれない。昔のことを心から悔いて、謝りたくてわざわざ会いにきたのかもしれない。
でも実際には、そんなことは稀だ。駅で偶然ばったり会ったとして、また昔のように尊厳を踏みにじられるのがオチだ。だから相手に気づかれないよう足早に通り過ぎる。これは、自衛を含んだ偏見だ。
「男の人が苦手」「女の人と話したくない……」
僕はそういう人に対して「差別はよくないよ!」「偏見はやめようよ!」とは思わないし、口が裂けても、そんな呪いめいたことは言いたくない。
差別や偏見を心の免疫と表現したのには、もうひとつ理由がある。免疫は全自動で作用する。作動し始めたきっかけもわからず、いま作動しているかどうかも、よく注意しないとわからない。
それもそのはずで、人間は目を覚ましているあいだ、目が回るほど多くの「選択」に迫られる。いちいち手動で確認していたら一瞬で脳のエネルギーが消し飛ぶので、多くの判断や決断を自動化する必要がある。
免疫も差別も偏見も、大部分は「決断の自動化」で生まれた公式のようなものだ。だから多くの人は気づかない。病気になったり花粉症になって初めて免疫や身体のことに思いを馳せるのと同じだ。
自分のなかの差別や偏見に向き合うということは、せっかく自動で動いている防衛機能をいちいち停止させて、見知らぬ存在をじっくり丁寧に観察してから判断するという意味だ。いつも運転している車が急にオートからマニュアルに変わるくらいには大変で厄介なことだが、それでも、僕はやるべきことだと思う。
人間が生きていくうえで、差別も偏見も、免疫くらい日常的に、そして元気に活動している。だからまず、自分の中にある差別や偏見に気が付く必要がある。誰の心にも偏見はある。差別は、ある。「ない」と思っているのだとしたら、残念ながら勘違いだ。人によっては、自衛かもしれない。思い込みかもしれない。もしかしたら、善意や正義という形に姿を変えているかもしれない。
重ねて残念なことに、自分の中に差別や偏見があることを認めるのはとてもむずかしい。「差別や偏見をするのは、とても頭が固くて悪いこと」だとみんなが言うから。そんな人間はひどいやつだと誰かに刷り込まれてしまえば、認めるのは至難の業になる。
誰だって、「頭の固くてひどいやつ」にはなりたくない。
だから、自分の中の差別や偏見をなかったことにする。
けれど残念ながら、世界はゼロかイチかの単純な仕組みで作られてはいない。
あなたのなかにある偏見や差別は、決して悪者ではない。それらを無自覚に、無差別にひとにぶつけて他人を傷つけるのがいけないのだ。ひとつひとつの差別や偏見と向き合うことを放棄した人の行きつく先が「世界からすべての偏見や差別をなくす」というムチャで乱暴なスローガンだ。そうではなくて、自分の中にある差別や偏見に気付いて向き合っていくほうが、よほど大変で、誠実なことだと僕は思う。
誰かの何かを、何とかできるとしたら
僕の偏見の話をひとつ、させてほしい。
僕は他人にあまり期待をしない。特に「変わってくれる」ことは全く期待しない。これは全くいいことではなく矯正すべきものだと思う。何が言いたいかというと、僕が持っていた偏見のひとつが「私、差別も偏見もしないから」な人は一生そのまま変わらない、だった。あの日、僕が少し震えた声で聞いた答えを得られる日なんて来ないと思っていた。そんなとき、あるnoteを読んでいて、僕は頭をドガンと殴られた気がした。
「差別しない」という言葉は、
差別する側とされる側の、境界線を
知っているからこそ言える言葉である。
そのうえ私の使ったその台詞は、
マジョリティだけどマイノリティも
受け入れるよ!という
善意のフリした上から目線にも受け取れる。
今は、誰かも分からない友達へ。
ごめんなさい。
謝ったって傷が癒えるわけじゃないけれど
私はきっとあなたを、沢山傷つけてしまった。
私には、ゲイの友達がいない。
正直、ちょっと涙が出た。ほんとは全文掲載したいがそれだと引用にならないのでこのへんにしておくが、とりあえず読んでほしいというのが本音だ。
これを書いたのは昔、「私には差別も偏見もない」と口に出していた人だ。そのあと、自分の発した言葉の意味を、誰に言われたわけでもなく、気づいて、そして考え直した。「自分が誰かを傷つけていたかもしれない」なんて、誰もが目をそらしたくてたまらない事実に、真正面から向き合える人がいたということだ。
あの日もらえなかった答えがここにあった気がした。
あの日心底絶望した僕も一緒に、救われてしまった。
だから僕はいまこの文章を書いている。「人は変わらない」という偏見すら、こんな風に覆る世界だから。僕の言葉も、誰かの何かをほどくきっかけくらいには、なれるかもしれないと思えた。
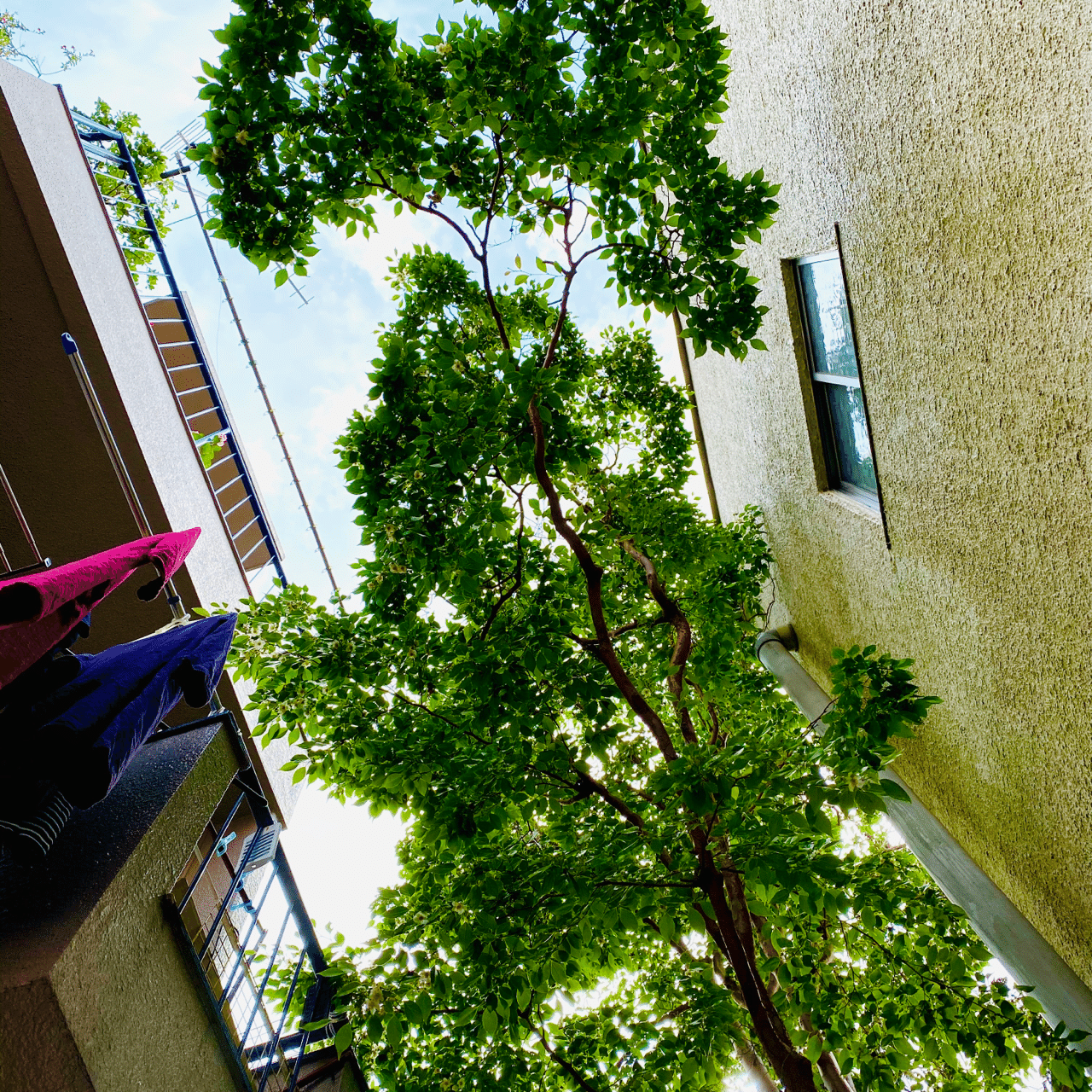
今からあなたに酷いことを言います
ちょっとキツイ話をする。
「私、差別も偏見もしないから!」と言い切れる人は、タチがわるい。ひとは誰しも、僕も含めて、全員が無自覚な加害者になり得る。この世でいちばん厄介な加害は「善意」や「正義」「常識」という言葉に包まれて投げ込まれる爆弾のことだ。そして、差別や偏見をしないと思い込んでいるひとほど、キッツイ威力の爆弾をブン投げてくる。
「親御さんは大事にしなさいね」とか。
「あなたはかわいそうな子ね」だとか。
これは僕が耳にタコ穴式住居ができるレベルで言われ続けていたことだ。彼らは、僕が軽く育児放棄されていたことを知らない。中高6年間、家でまともに声を出すことを禁じられていたことを知らない。他人に「かわいそう」と言われるたびに、死ぬほど屈辱を味わっていたことも、きっと知らなかった。
相手は善意のつもりで差し出してきた、とても小さな爆弾。一日一発くらいなら、我慢はできる。でも確実にじくっと痛くて、心のどこかに傷をつけていく。受け取る側が傷を負わないためには、目の前の相手を加害する以外に方法がない、というのもシンドイところだ。
「いまのは酷い」「その言い方やめて」
自分を守るために、そんな言葉を口に出すほかない。
しかも「なぜイヤなのか」納得してもらうには、こちらの古傷を晒す必要がある。
相手の善意を加害で返すか、思い出したくもない過去の出来事を口に出すしかない。無自覚な偏見と差別を前にしたとき心がやられる理由がこれだ。特に相手の善意のようなものがチラっとでも見えてしまうと、こっちは簡単に引き金を引けない。ためらっている間に、ブン投げられた爆弾をモロに食らって痛い思いをする。
僕はいまあなたに銃口を突きつけ、引き金に指をかけている。あなたの善意を認めた上で、あなたを銃弾で傷つけようとしている。この文章群は「自分は差別も偏見もしない、したことがない」と考えている人の心臓を、どんな弾丸よりも深くえぐってしまうかもしれない、とわかっていながらそれを撃とうとしている。
そうだとしたら、謝罪はしない。
どうか思う存分傷ついて欲しい。
もう一度言う。
「私は差別も偏見もしない」と言い切る人は、差別や偏見について深く考えていない。知ってはいるのかもしれない。でも、浅い。それはまだ、人を傷つけるレベルの浅知恵だ。少なくとも僕は、そんなことを臆面もなく口に出せる人間を一切信用しないし、関わりたいとも思わない。
自分の思う勝手な正義を押し付ける権利は世界のどこの誰にもない。だからほんとうは、僕にこんなことを言われたからといって、あなたに傷つく義務などない。僕は僕がした加害について、せめて責任はとりてぇなと、自分勝手に思っている。だから加害者であることを途中で放棄しないつもりだ。これだって僕が勝手に決めたことだから、まあ、聞き流してもらってもまったく問題ない。
撃ち込まれた弾丸をどう使うか、自分の中の差別や偏見をどう処理するかはあなたが好きに決めて欲しい。
僕が言いたいのはそれだけだ。

いつも応援ありがとうございます! サポートいただいたぶんは主に僕の摂取する水分になります。
