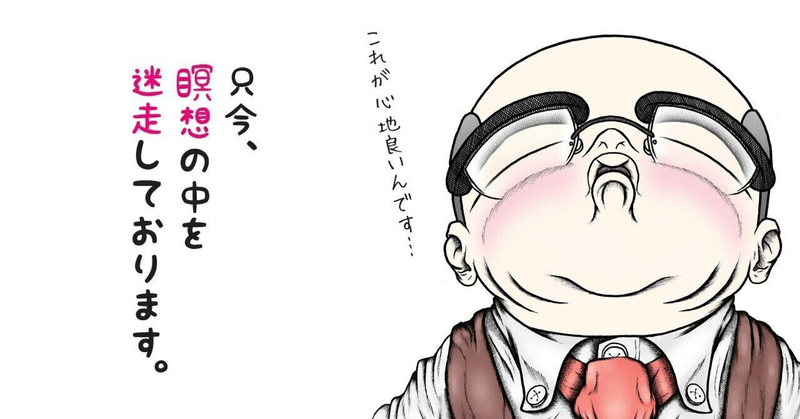
瞑想・メディテーションを考える
今日は1日、たまっている考え事が必要なお仕事をしようDayでした。
形のある物を、異なる形に変えていく。
形があるんだけど、それとは違う意味合いの組み合わせに持っていく。
相手の意図を汲み取って、相手が想像している以上のものを提案する。
なかなか手ごわいものばかり。
頭回らん、、、って思ったりもしますが、ふと思い浮かんだときに考えて、寝かせて、また考えて、話して、考えて、振り絞って、寝かして、、、としていると、そのうちまとまってきたりします。
大体が初めにイメージしたところに戻ったりしますが、行ったり来たりすることが大事なのではないかと思っています。
そんな1日の終わりに、ふとDr. Andrew Hurbermanのyoutubeでも聞きながら料理でもするか、、、と、選んだのが「How Meditation Works & Science-Based Effective Meditations」(瞑想がどのように働くのか、科学的効果実証メディテーション)。
瞑想をしないわけではないのですが、様々な瞑想について書かれた本を読んでも、なんとなく納得していない自分がいました。
その方法に疑問だったのか、その説明に疑問だったのか、おそらく少しずつ両方の何かが引っかかっていたのですが、このDr. Hubermanの説明を聞いていて、その答えが少し見つかった気がしました。
Dr. Hubermanの話すスピードはある種「今、ここ」にいないとキャッチできないくらい早口で、0.75倍で聞いても、普通の人のちょい早口くらいなのですが、通常スピードで聞かないと彼の良さが伝わらないので、耳を100%にして、触覚を100%にして聞く感じです。
そんな中で、色々と面白いなぁと思ったことがあったので、ざっくりとまとめてみます。あくまでも私のアンテナに引っかかった言葉たちなので、すべてではないことはご理解の上、読み進めてください。かつ、私の解釈が間違っている可能性もあるので、、、。
メディテーション・瞑想は、脳内の3つのエリアが大きく関係している。
① Left Dorsal Lateral Prefrontal Cortex:dl-PFC
(左 背外側前頭前皮質)
② Anterior Singular Cortex:ACC(前帯状皮質)
③ Insula(島皮質)
左背外側前頭前皮質は、体の感覚をコントロールして、それが一体なんなのか、感情と体の感覚を解釈する場所。この場所が活性されているとき、今体で感じている感覚は、快か不快かなど適切な判断をすることができる。
そしてこれが②のACCと直接にコミュニケーションをとっていて、ACCは例えば呼吸の速さとか、心拍数などの変化を感じ取り、それが実際の環境や状況に適しているのかどうかを解釈する。つまりACCは自分の体の中、表層で何が起こっているのかを感じる脳。そしてACCはある情報が脳内に入ったときに、過去に刻み込まれている情報とずれていたり、おかしいと感じたり、新しい情報だったりすると活性化する。つまりは「脳に何かがおかしい」と違和感を抱かせるのがACCの役割。dl-PFCは、ACCで何が起こっているのかを受け取り、今のこの状況と環境下で一体何が起こっているのかを、過去の経験から類推して解釈・判断をする。
例えば、走っている状態であれば心拍数が早くなっても不思議ではないが、もしただ座っているだけなのに心拍数が早くなったらそれは適さない反応であるから、dl-PFCが適切に働いていれば、快か不快かという解釈をするという関係。
その働きの中では、感情や記憶の中枢であり大脳辺縁系の一部である、Amygdala(扁桃体)もかかわってくる。
そして3つ目の島皮質は、脳と体で何が起こっているのかを解釈する。痛みや虫刺されの感覚とか、体の外で何が起こっているのかもキャッチして、①,②,③のエリアがともに情報を処理しながら、「今感じているこの感覚は、この状況・環境に適しているのか?」ということを確認している。
ま、この辺りはよく説明でも聞くところですが、私の中で、瞑想というものがこういったエリアと関係あるのであれば、目を閉じて瞑想することの意味は一体どう説明するのだろうか?という疑問があった。
もちろん、ヨガのアーサナは動く瞑想ともいわれ、目を開けた状態で動きをするので、それも瞑想なのだが、一般的にきちんと瞑想をするというと、座って目を閉じて呼吸に耳を傾けて、、、みたいな話になる。
でも、同時に、精神疾患の人はあまり自分の内に入り過ぎるとよくないから、あまり瞑想を勧めないか、目を開けたままで瞑想をしたほうがいい、、、なんてことも聞く。
個人的には、目を開けても、目を閉じても、それぞれの利点があるとは思っているけど、それを説明するためのいい情報がまとまっておらず、なんとなく自分の理解と納得が宙ぶらりんになっていたというのが本音。
なので、自分の感覚として、今はこうしたほうがいい、、、という方法で自分は瞑想をしていたし、クラスの中でもクラスの全体の様子を見て、今回は目を閉じて、今回は目を開けて、、、と少しずつ変化をさせていた。それを何を基準にやっているのか?と聞かれても、「そう感じたから、、、」というのがまず最初の答えで、それ以上言葉にするとなると、無理やり解釈を付けるような説明になるので、そこで止まる。
で、その答えがこの後のDr. Hubermanの会話の中にあったなぁ、、、と。
Dr. Hubermanの瞑想を行う目的のスタンスは、「神経ネットワークの再構築、または新しいネットワークの構築」にある。つまりは、どの方法で行うことが、神経系のネットワークの構築に有効かということが話の帰着点となる。
その中で、一つの研究論文を考えのスタートとして取り上げていて、その研究論文は、「Mind Wandering:今行っていることから注意がそれている、思考がさまよっている)」とHappiness(幸福感)を題材としていて、研究者の結論としては、「Mind wanderingをする人は幸福感が低い」というもの。つまりは、「今、ここに:Be present」でない人のほうが、幸福感が低かったという結果がある、、、と。(Matthew A. Killingsworth* and Daniel T. Gilbert)
うぉ~なのですが、その時浮かんだのが、Mind Wanderingは人間のクリエイティブには重要、それを良しとする考え方があったなぁ、、、ということ。
クリエイティブな状態を作り出すうえで、Mind Wanderingは大切だけど、幸福感は低くなる、、、なかなか興味深いなぁ、、、と。
話を戻すと、Mind Wanderingは脳にとってどういう状態かというと、Default Mode Network(DMN)の状態で、DMNとは、人間が無意識に近い状態の時に作動する脳のネットワークで、いわゆる「ぼーーーっ」としている状態。
で、一般的にDMNが働くことで、脳はタスクネガティブ(なにか課題に取り組んでいる状態の脳:トップダウンの状態ではない)で、自分の内側にある情報を処理している状態であると言われている。そしてDMNそのものがクリエイティブを生むわけではないが、それがクリエイティビティのスタート(種)であると言われている。
話を戻すと、神経ネットワークを構築する目的での瞑想においては、このDMNの状態は望ましくない、、、と。Dr. Hubermanの解釈によると、なぜなら、DMNは通常の自分の記憶の内部に自分を置くことになり、つまりは自分にとってやりやすい、平常の脳の状態で活動している状態であり、それは新しい神経ネットワークの構築には至らない。瞑想において新しい神経系のネットワークを作り出すためには、DMNに入らない状態で行うことが重要である、、、と。
つまりは、今の自分の状態が、内的な意識を快・楽と感じるのか、それとも外的な意識を快・楽と感じるのかを見定めること。
そのうえで、今、より自分が難しいと感じる状態を選択して瞑想をすることを勧める、と。
目を閉じて、視覚情報をキャンセルすると、外受容感覚がシャットダウンされる。そうすると自然と内受容感覚(呼吸や心拍、からだでおこっているかんかくなど)に意識が向く。自分の体への意識が高いか、それとも外への意識が高いか、そのどちらが今のこのタイミングで容易ではないかの状態で瞑想をすることがいい、、、と。
例えば自然と呼吸に意識が向くのであれば、目を開けた状態で外への意識を持って瞑想をする。
意識が外に向いているのであれば(自分の体の感覚の意識が分かりづらく、外の音とか周りの気配とかが気になる)のであれば、自分の内側に意識を向けるために目を閉じて瞑想をする。
その意図は、自分の現在持っていない神経ネットワークを強化するために、より難しいと感じる方法でやることに意味がある、、、と。実際にその方法で行うほうが、瞑想における利点がみられた、とも言っていた。
約2時間半のポッドキャスト・Youtubeなので、もっとたくさんの内容について話していたのですが、ひとまず今日はここまで。
参照
A Wandering Mind Is an Unhappy Mind: https://bit.ly/3sMP64B
Brain Driven 青砥瑞人著 Discover
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
