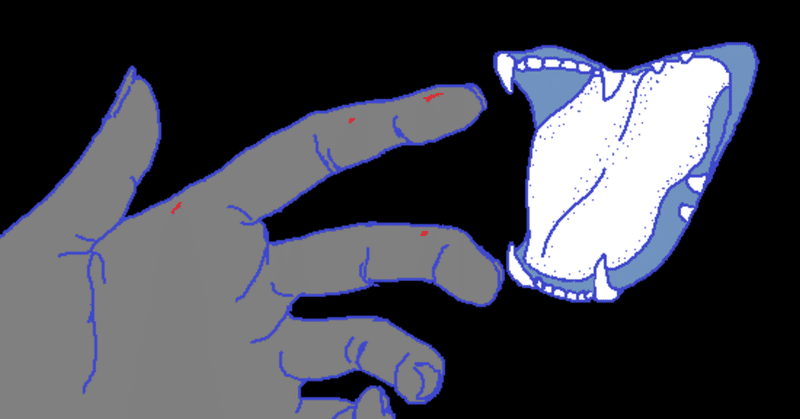
爪と牙②
「ちょっとツッチー先輩! 正気!?」
「当たり前だろノブタ。もうふざけてる時間はない」
「だとしたらバカだよバカ! ノブタが一区で俺が二区って、じゃあ往路は誰が監督車に乗るのさ!?」
「バカはお前だユメタ。レースより裏方を優先するチームなんかあってたまるか」
言われてみればそれはもっともな話だが、とは言えツッコミどころはまだまだある。
昨日ユメタ主務が言っていたとおり、なんとなくの共通認識として上級生の区間配置はだいたい決まっていたようなものだった。──が。そんな予想はことごとく裏切られた。少なくとも、重陽の予想は一区のノブタ主将以外すべてはずれという有様である。
「……まあ、確かにちょっとだけ奇をてらった節はある。けど『奇襲作戦』と言って欲しいな。俺だって勝算がなかったらこんな作戦は取らないさ。このオーダーがハマれば、俺たちはシードを取れる」
四年の二人にがるがると詰め寄られても、土田コーチは強気の姿勢を崩さなかった。重陽にはまだその勝算とやらが見えて来ないのだが、彼にはよほどの自信があるらしい。
「まず一区。ノブタ。このオーダーはシンプルに集団走の力だな。ノブタには集団について行くだけじゃなく、飛び出して引っ張ってく時の思い切りとフットワークの軽さが良い。今の下級生も一万メートルまでならイケると思うけど、二十一キロ続けなきゃなんないとなると全然話は変わってくるから。一区でタレると絶望的だし、ここはスタミナもあるノブタで決まりだ」
手放しに褒められたノブタ主将は照れ臭そうにしているが、これには誰からも異論は出なかった。土田コーチの言うとおり、ここ数年の箱根駅伝では一区の出遅れを取り戻せたチームはいない。
「次に二区。ユメタ。……の前に、監督車問題を解決しておこう。監督車には、二日も三日も松本に乗ってもらうことにした」
土田コーチはこともなげに言ったが、部室は再び十一人の絶叫に包まれた。
「コーチ! アタマでも打ったとですか!? どれだけ時間かかってもいいですけん! 考え直してくんしゃい!」
「心配してくれてありがとう綿貫。でも俺はどこもぶつけちゃいない」
「だとしたら寝不足ですって! ちょっと一晩だけ時間空けて考え直しましょ! ね!?」
「濱田も、心配かけてごめんな。でも俺はこのオーダーを変える気はない」
土田コーチがあくまで強気姿勢なのもそうだが、有希がそっと自分のロッカーからタブレット端末を出してきたのを見て、重陽は「ああ、本当なんだ……」となんだか胸が締め付けられるような思いがした。
「実を言うと、松本には監督車の件について先に話してたんだ。……っていうのもこいつは走力もすごいが、それ以上にレース情報の分析力がえぐい。もちろんそれだけのことなら俺だってレースで活躍してもらうことを優先するけど、知っての通りこいつはまだメンタル面にハンデを抱えてる。それを込みで考えたら、監督車の後部座席でサポートに専念してもらった方がチームにも松本自身にもメリットは大きいと思うんだ」
「でっ、でも! 有希のメンタル面のハンデって『話せない』ってとこじゃないすか! そりゃ助手席と後部座席で筆談って手もあると思いますけど、一分一秒が惜しいってなりません!?」
自分で口にしておきながらなんだが、重陽にも対処法は数秒で片手の指から溢れる程度には思い浮かんでいた。それでも言わずにいられなかったのはひとえに、有希と一緒に同じ襷を繋ぎたかったからだ。高校時代に繋いでもらい自分が運びきることのできなかった襷を──ようやくその罪を濯ぐことができると思っていた。その機会を、重陽はずっと待ち侘びていた。
「……そうだな。喜久井がそう言いたくなるのもわかる。だから、松本には俺がタブレットを持たせた。安物だけど、読み上げ機能が聞きやすいのを一緒に選んだよ」
しかしそんな重陽の思惑など完全に看破されていて、いっそ恥ずかしいほど穏やかな声で諭されてしまい消えてなくなりたくなった。そんな重陽の様を受けてか有希は少し居心地が悪そうに肩を竦めたが、目線を下げタブレットに文字を打ち込んでいく。
「ほんとうにかねがないからたすかった。あとでぐるーぷらいんにもいれてほしい」
有希の抱えているタブレットは、無機質で少したどたどしい声を発する。けれどそのぎこちなさはどこか有希の振る舞いとマッチしていて、誰からともなく「おおー」という感嘆の声とともに拍手が起こった。
「な? 結構良い感じだろ。……ちなみに松本の仕事はアナリストだけじゃない。こいつは一万メートルで二七分台、ハーフは一時間一分台で数字を上げて来てるバケモンだ。──御科。この間撮ったオンライン記録会用の動画アップしたやつ、再生回数は?」
「十万に届くか届かないかっすね。ま、埒外ってやつっすわ」
「そういうことだ」
土田コーチはメンバーの顔を見渡し、にやりと笑う。
「そんな埒外のバケモンがいるんだぜ? よそは絶対にこいつのエントリーを疑わないはずだ。補欠に入っていれば、当たり前に変更があるものとして対策してくる。……だからその裏をかく。これが第一の奇襲だ。区間エントリーで罠を張る。松本には、その仕掛け人になってもらう」
「──なるほど。クソバカ大バクチだけど、考えたじゃんツッチー先輩」
と応えたのは、二区を任されたユメタ主務だ。
「隠し球を隠したまま使わないなんて、フツーはありえないもんね」
「そのとおり。で、二区のユメタだが。走力で言えば順当な配置だろう」
「えー? かえって順当すぎない? そこまで大見得切って奇襲作戦って言うなら、伸び盛りの二年にすればいいじゃん」
土田コーチをして「順当な配置」と言わしめたユメタ主務は、まんざらでもなさそうにしながら口を尖らせる。
「主務としちゃ、監督車に乗るのだって結構楽しみにしてたのに。せめて復路で乗せてくんない?」
「それについては悪かったよ。でも往路の序盤は四年で固めておきたかったし、復路では二人に給水を頼みたいんだ。監督車は、いつか気が向いたら監督として乗ってくれ」
ユメタ主務はまだ口を尖らせながら「ふうん」と顎を上げ、有希の方を見た。
「つーワケなんだよ松本。本当なら、監督車に乗れんのは主務の特権なんだかんな! シートの座り心地、そのケツにしっかり刻んどけ!」
「もとよりこころえている」
先輩に強い口調で檄を飛ばされた有希は、けれど力強く頷きながら、真新しいタブレットで不遜にも古めかしい言葉で応えた。
二区のユメタ主務に続く三区と四区には、それこそ〝伸び盛り〟の二年生が配置されている。二人ともこのコースの沿道に親戚の家があり、思い入れも強いようで目の色が変わっていた。
五区の配置ではまた物議を醸した。指名を受けたのが「激坂最速王」の御科ではなく、一年の如月だったからだ。
「……無理です。コーチ。無理ですっていうか、無理があります!」
区間配置を見せられてからずっと白い顔で小さくなっていた如月は、震えながら細い声を上げた。
「なんで『激坂最速王』の御科さんを差し置いて俺が五区なんですか!?」
「如月がうちで一番平地と登りのタイム差が小さくて、コース取りのセンスがあるから」
そんな如月に対し、土田コーチはあくまで平静を崩さずに答える。
「五区と六区は専門職だ。特に登りの五区は経験とセンスが物を言う。──俺は、経験はともかく如月には山の職人としてのセンスとポテンシャルがあると思ってる。体が軽いからタフなコースに向いてるし、予選会でもロスの少ないコースを取れてた」
「それってつまり、出られるかどうかも分からない再来年とかその次とかのために、御科さんの脚を殺すってことですか」
如月は歯を食いしばり、表情全部で土田コーチに食い下がった。土田コーチはそんな如月の言葉を聞いて、初めて少しだけ眉間に皺を寄せた。
「御科さんはいいんですか!? 山であんなすごい記録出したのに! こんなの、なんのために頑張って来たのか分かんないじゃないですか!」
「……俺は別に。五区のためにターンパイク出たわけでも、箱根のために走って来たわけでもないから」
御科はあろうことか自分のスマホをいじりながら、顔を上げずに言う。
「土田さんが『このオーダーなら勝てる』っつってんだから、勝てんじゃない? 知らんけど。俺は決められたとおり九区を走るよ。……ま、そんなに走りたくないなら補欠に回された綿貫に土下座でもして代走頼めば?」
珍しく少しも茶化したところのない声色なので、彼が怒っているのが分かった。ちょうど重陽にカシオミニを投げて寄越して「分かってたまるかよ」と言った時と同じトーンだ。
如月は、当の御科にそう言い返されてもまだ納得いっていないようだった。目に涙を溜めて俯き、真っ赤になるまで唇を噛み締めている。
「如月。今のはお前が悪か」
そんな彼を、同室で寝起きしている先輩の綿貫が窘めた。
「御科さんはどこでん立派に走れるけん、山ば登らんからって『脚が殺される』っちゅうんは失礼ばい。それから──そがん情けなかこつばほざいとる後輩の控えに回された俺の身にもなれ」
他ならぬ綿貫にそう諭され、如月は鼻をすすり目元を擦って「すみませんでした」と蚊の鳴くような声で発する。如月が負った震えるようなプレッシャーの大きさ。綿貫が必死で押し殺したいじけと悔しさ。どちらも手に取るように分かるので見ていて辛い。
「……いいかお前たち。──特に一、二年。勘違いするなよ。俺は『このオーダーがハマればシードを取れる』って言ったけど、それは『だから任せろ』ってことじゃない。ハマればっていうのはつまり、補欠に回った松本と綿貫も含めた十二人全員が、誰一人として、なに一つのミスもなく、かつ運が良ければ。の話だ」
土田コーチは眉間に皺を寄せたまま、鬼気迫る様子で目に力を込め、ひとつひとつの言葉を噛み砕いて吐き出すように言った。
「予選会はそれができてた。あのレースは、みんながみんな、自分の役割を果たせてたから勝てたんだ。……でも箱根はそんな甘いレースじゃない。単に役割をミスなくこなすってだけじゃ、タスキをゴールまで運びきれたら万々歳ってくらいのもんだろう。……分かるな?」
そう言われて固唾を飲んだのは二年生だった。彼らは良くも悪くもバカではないのだ。勝ちたい気持ちで必死になれる熱さはあっても、上から「勝てる」と言われてそれを鵜呑みにできるほど能天気ではない。
「ミスなく完璧に走る。それは最低限のことだ。それ以上の結果を叩き出すためにじゃあ何をしたらいいかって、ギャンブル以外に何がある? 少なくとも俺には、お前たちのポテンシャルを信じて今まで見てきたことの全部を賭けるってことしか思いつかなかったよ!」
土田コーチがテーブルに拳を打ちつけたあとには、古い蛍光灯がじりじりと鳴る音だけが降り注いでいた。彼の強い覚悟ともどかしさが、沈黙と一緒に痛いほど耳を突く。
「……大きな音をたてて悪かった。でも、箱根でシードを取るには常識を引っ掻き回してこっちのペースに持ち込まなきゃダメだ。俺たちはチャレンジャーの立場だけど、バカ正直に相手の土俵に上がっちゃいけない。相手を俺たちの土俵に引き摺り下ろして戦うんだ。──だから五区は如月、六区は濱田でいく」
名前を出された濱田は神妙に頷き、はい。とよく通る声で返事をした。
「濱田は言ってみればポスト喜久井だ。ロケットスタートで序盤を駆け上がって、下りにそのまま突っ込んでくれ。ただし! コイツの土壇場で変に計算高いところまで真似しなくていいからな。最後まで攻めの姿勢で、ドカっと脚を使い切れ」
「ううっ、痛いところをピンポイントで串刺しにされた……っ!」
重陽が自分のジャージの胸を掴むとノブタ主将とユメタ主務が笑い、張り詰めていた空気がにわかに緩む。しかし、当の濱田は不安のためか顔を強張らせたままだ。
「大丈夫だよハマー。お前ならやれる。万が一失敗したって、御科氏やおれが帳尻合わせればいいだけの話だからさ。再来年のおれたちににタスキ、繋ごうぜ」
テーブルを挟んでちょうど対面にいる濱田へ拳を突き出すと、彼はようやく少し緊張を解き、拳を重ねて重陽を見る。
「……やっぱ、喜久井さんには敵わないですね。こんな時、俺にはまだ『任せてください』なんて言えない」
「ははっ! そりゃ当たり前だ」
不安の中に少しの悔しさを混ぜている濱田の顔が、なんだか怪我で走れなかった頃の自分に重なって見えた。もしおれに後ろをくっついて走ってくる弟がいたらこんな感じかな。と頭を過ぎり、思わずそんな彼の頭を手のひらで強く撫でる。
「こっちは伊達にお前より長くここで走ってないんだ。そう簡単に追いつかれちゃ困るよ。でも本当に大丈夫。ハマーならやれる。お前の足は強いから」
そんな重陽の言葉に、濱田はどこか覚悟を決めたように頷いてから「ありがとうございます」と応えた。
実際、同じ大型のランナーとしてのフィジカルは重陽よりも濱田の方が強靭だ。彼はこれまでの競技生活で大きな故障をしたことがないし、だからこそノーブレーキの思い切った走りができている。怪我のリスクを度外視するなら重陽の方がタイムは稼げるだろうが、土田コーチが「未来」を見据えて配置を決めたのなら濱田の六区抜擢は妥当だ。
そんな濱田に続き、七区と八区のオーダーも一年生が続く。やはり二人とも控えに回った綿貫のことを気にしている様子は明らかだったが、当の綿貫が
「バイトばせんで走りに打ち込めるのも、持って生まれた才能の内ばい!」と一喝されてそれぞれの区間を受け入れる。
「三区や四区と同じように、その裏にあたる七区と八区も世間じゃ『ダレ場』って言われてる箱根のエアポケットだ。けど、今回のシード権争いに関して言えばそうはならないと思え」
土田コーチはそれぞれの区間に配置された下級生たちを見回し、また少し大きな声を発した。
「俺がシードを争う他校の監督なら、この内のどこかに松本が入ってくると見て対策する。特に復路だ。世間だってそれを期待するだろう。……だが、さっき説明したとおり俺たちはそれをしない。エース級の選手をダレ場に釣ってペースをかき乱す。これが第二の奇襲──つまり、一、二年のお前たち全員がこの作戦の仕掛け人ってわけだ」
煽るように言われ、下級生たちが固唾を飲む。その音さえ聞こえてきそうなほどの強い気迫を感じ、重陽は「行ける。勝てる!」という叫び出したいほどの興奮を覚えた。
「──で、だ。九区の御科と十区の喜久井。これはもう場数と距離適性だな。両方とも二十三キロ超えの長丁場で、山の中ほどじゃないがアップダウンも多い。御科はまあ……いつもどおり図太くロングスパートかけてくれ」
「ういーす」
昔からそうだが、こういう時のクールな振る舞いが様になるところが御科はかっこいい。まるでラノベの主人公のようで、思えば三浦ハウスで初めて会った時からある意味で彼は重陽の憧れそのものだった。
「最後にアンカー喜久井! このオーダーはある意味いっっちばんの大バクチだ」
「は、はいっ!」
言葉を溜めに溜められ、今度は重陽が固唾を飲む。
「正直、十区をユメタで行くか喜久井で行くかは最後まで迷った。駆け引きのスキルで言えばユメタが一枚上手だけど、序盤でがっつりタイムの貯金を作ろうと思ったら喜久井って手も固いからな。……けど俺は、十区でコイツの二段ロケット──いや、三段目のロケットが炸裂する方に賭けることにした。なんでだか分かるか?」
「三段目のロケット……つまり、そういう脚を残しておくペース配分──ってことですかね」
こういう場面でビシッと自信持って答えられないところが本当におれはダメ! と内心で頭を抱えながら、重陽はそれでも間を開けずに返した。
──が。彼と首を横に振り、重陽の目を見て言う。
「それもあるけど、そうじゃない。……喜久井はこのメンバーの中で一番、人からの応援を力にできるランナーだ」
大真面目な顔でそう言われ、重陽は思わず眉間に皺を寄せ首を前に突き出した。けれどどうしたことか、御科も、ノブタ主将もユメタ主務も、後輩たちもみんな、それぞれに「ああー」と声を上げてはしきりに頷き合っている。
「え、ま、待ってください。応援を力にって……それ、わりと当たり前のことじゃないです? だって、沿道とかスタジアムから『頑張れーっ!』とか『ファイトーッ!』とか声かけてもらったら誰だって多少は元気出るでしょ。それが家族とか友達なら尚更──」
「確かにそうだよ。そうだけど、喜久井はそれが並外れてる。……もしかして自覚ないのか? お前が今までベスト更新したのって全部、お袋さんかタマっちが応援に来てるレースだぜ?」
と言われてもまだ、重陽には「そんなバカな話あるか!?」としか思えなかった。が、有希がそんな重陽の目の前へ、自分の真新しいタブレットをかざして見せる。
そこには、重陽が走った高二の冬以降のレースの全リザルトが表計算ソフトでまとめられていた。ご丁寧にフルカラーだ。
「……ほ、本当だぁーーっ!!」
数字であからさまに示され、恥ずかしさと動揺のあまり自分の顔が首から耳まで真っ赤に火照るのが分かった。
高二のラストレースになったハーフマラソンに、高三で初めて走ったインターハイ。それに都大路での怪我から復帰したあとの大学デビュー戦、二つ名である「インディゴの不死鳥」を拝した関東インカレに、死力を尽くした予選会──。
確かにどれも、母か夕真が応援に来てくれたレースばかりだ。それも、まるで言い訳なんか利かないくらい露骨なほど大幅に記録を更新している。
「きくいさんはずっと はるきとはまぎゃくだった ひとのためにこそ いちばんちからをだせるひとだった」
ただただ目を丸くしている重陽の前からタブレットを引っ込め、有希は両手の親指で器用に言葉を発する。
「じゅっくでしーどけんまでせーふてぃりーどがなかったとき どたんばでじゅんいをおしあげられるとしたら あなたしかいない」
有希のぎこちなくも率直で雄弁な言葉と、その言葉に頷いてくれる仲間たちの熱い眼差しによって、重陽は確かに腹の底からぐつぐつとマグマのような力が湧き上がってくるのを感じた。
「そういうこと。特に予選会。見てのとおり、給水での御科のファインプレーと十五キロ過ぎでタマっちがシャッター切って以降の喜久井のラップタイムは、まじで凄まじかった。喜久井のあれが十区でも炸裂すれば……正直、今度の箱根は歴史に残るド熱いレースになるぜ」
土田コーチはまた煽るように──というよりは、いっそ愉快そうに言った。
「以上が、俺たち青嵐大の箱根駅伝区間オーダーだ。分かってると思うが、これは十二月二十九日の公式発表までは絶対に誰にも言わないこと! 匂わせもナシだ。特にネットには気をつけろ。あることないこと書かれるだろうが、匿名だろうが記名だろうが否定も肯定も一切禁止だ。基本的に受けていい取材は主催の読売新聞と日本テレビ、それから青スポに限定する!」
まるで映画に出てくる鬼教官がするように命じられ、その場の全員──有希のタブレットも含めて。だ。──で「はい!」と景気良く返事をした。
「よおしいい返事だ。……いいかお前たち。きっと俺たちが今度の箱根でシード権を取るなんて考えてるのは、日本中どこを探したってここにいる俺たち以外にはいない。……だからペテンにかけろ。日本中を騙せ。今までさんざ腐してくれたメディアに手のひらを返させろ。それに乗せられてアホみたいに踊ってきた自称マニアのおっさんどもの口を塞いでやれ! それから──」
そこでようやく重陽は、彼が自分たちを「煽っている」のではないことに気がついた。
この作戦は単なる下見でも、ましてや「未来」への架け橋でもなんでもない。
彼は他ならぬ、彼自身の彼自身による、彼と自分たちのための──あの晩、あの屋根の下で何もかもがめちゃくちゃに変わってしまった運命のための──真っ向から合法な、静かなる「逆襲」の号砲を吠えているのだ。
「──再来年は、正真正銘のヒーローになるぞ」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
