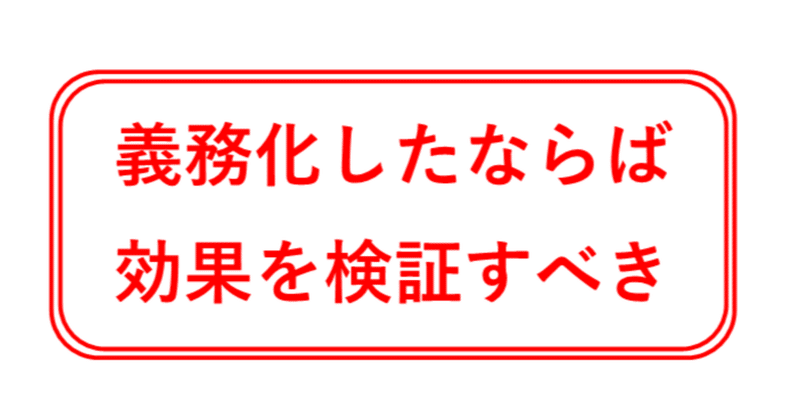
運営要件や義務項目の問題点は、制度化にしてから効果を検証しないところ
■ ケアプラン見直しの重要性
介護サービスは、利用者(高齢者)の要望だけで支援をするわけではない。利用者の状態や生活環境から課題点を分析して、どのようなサービスを提供するかをケアプランにする。
そのケアプランに応じて関係者が役割分担をし、専門分野ごとに介護サービスを提供することで1人の利用者を支援する。
もちろん、サービス後は記録として残す。それは1つの作業報告でもあり、これから先のサービスにつなげるための貴重な情報でもある。
そして、こうしたサービスの実施記録や担当した介護スタッフからの日々の報告を受けて、定期的にケアプランの内容を見直すことになる。
ケアプランの見直すにおいては、基本的に「継続するか」「内容を変えるか」の2つだけだ。内容を変えると言っても、よほど大きな状態変化がなければ大抵は小さな修正や加筆・削除くらいの程度の話である。
それでも、継続であろうが微々たるプラン変更だろうが、1人の利用者の自尊心と生活を支えるためには、サービスという実務だけでなく、その大元となるケアプランの定期的な見直しは重要なのだ。
それは、ケアプランによって提供されている介護サービスが、利用者の生活や身体の維持・向上に寄与しているかを検証するために必要だからだ。
■ 介護サービスは法令に準じて行われている
ケアプランの作成は基本であるとは言え、何も介護業界や各事業所が率先して行っているわけではない。また、「何事においても計画(プラン)は大切」という一般的な観点によるものでもない。
ケアプランを作成する大きな理由は「法令で定められているから」に他ならない。
ケアプランに限らず、介護サービス事業は介護保険制度を始めとした法令によって運営要件が定められている。極論となるが、介護サービスを営んでいる事業所や施設のほとんどは法令で成立していると言っても過言ではない。
国民から徴収している介護保険という、いわば税金によって成立している事業でもあることからも、法令により厳格に運勢が求められるのは当然と言えば当然である。
別に「お上には逆らえない」とは思わないが、提出書類やら調査票など行政からの要請も少なくないことから、介護ビジネスとは言いつつも、少し法令に縛られている感覚が否めないのは本音だ。
■ 義務としての制度がどんどん増えている
法令に縛られている感覚になるのは、やはりそれが「義務」だからだろう。
義務とは「〇〇しなければいけない」ということだ。人間、その内容に妥当性があるとしても、あまりに「〇〇しなければいけない」と言われるとストレスやプレッシャーを抱いてしまう。
介護サービスにおける法令は、事業運営としての基本的な義務と、社会変化にともなって追加となった義務が存在する。
前者はあまり変化はないものの、後者は介護報酬の改定などを経るたびに、どんどん増えてきているのが現状である。
それは感染症のまん延、自然災害、高齢者虐待、身体拘束といった環境や社会問題に由来しているため、仕方ないと言えば仕方がない。
しかし、そのたびに「委員会を設立すること」「定期的に協議すること」「研修を年✕回行うこと」「訓練を年△回行うこと」といったような話がどんどん出てくると、そこにも時間を費やすことになる。
介護業界は人手不足であるということは既知のことなのに、法令としての義務事項がどんどん増えると、支援を必要としている高齢者に差し伸べられる手も引っ込めるしかなくなってしまう恐れがある。
義務となった制度を「必要とない」「撤廃しろ」「緩和しろ」とまでは言わない。単純に「分かるけれど、ちょっとしんどい」と言いたくなるだけだ。
■ 制度の「効果」は検証されない
なぜ「ちょっとしんどい」となるのか?
それは、義務がどんどん追加されるわりに、それら制度の効果が分からないからだ。
つまり、制度の効果の検証性が乏しいので、義務化に妥当性があっても疲弊感が出てしまうのだ。
例えば、身体拘束等の適正化に関する委員会を開催することは、身体拘束を可能な限り実施しないためには啓発としても重要だ。また、実際に身体拘束を行っていたとしても、その妥当性や現状を振り返ることも必要である。
しかし、これだと「やったほうがいい」レベルの話で終ってしまう。「やったほうがいい」と言うことは「やらなくても同じ」という意味でもある。
ここで国から「身体拘束等の適正化に係る委員会の開催を義務化した結果、全国として身体拘束が✕%減りました」という統計があれば分かるが、目に見えてそのような報告はない。
まぁ、身体拘束においてはここ数年において出た義務事項なので今後その効果が出るかもしれない。
しかし、そのような多少なりの効果が出ていないにも関わらず、未実施の場合には介護報酬が減算されるのはいかがだと思う。
そもそも、義務となったわりにその効果が検証されないまま、体制が整備されていないと減算となる要件が多いように伺える。
せめて、義務とした制度に対してしかるべき検証を行い、その効果がそれなりでも立証されてから減算措置を定義するのが筋だと思う。
――― このような話を行政に伝えたところで「制度なので」「義務なので
」「要件に書いているので」と言われえるのがオチである。
この手の根拠を行政に質問したことは幾度かあるが、結局「他事業所ではちゃんとやってますよ」と言われて終わる。こちらとしては「やりたくない」と言っているわけでなく「倫理性だけで義務とするのが国のあり方なの?」と問うているのだ。
環境要因や社会問題に対しても事業継続を求められるのが医療福祉である。しかし、「〇〇しなければいけない」だけでなく「それをしなければ罰則がある」なんて言われるのは腑に落ちない。
モデルケースもなしに、まるで「必要だから制度化しました」と言われるものだから、特にBCP(事業継続計画)などは義務化となった今でも策定できていない事業所があるのだ。
義務化自体は別に構わない。必要だと言うことは分かっている。
しかし、義務にして罰則まで設けるからには、冒頭でお伝えしたようなケアプランと同様、制定した後で検証と効果を提示することが国としての「義務」ではないだろうか?
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
