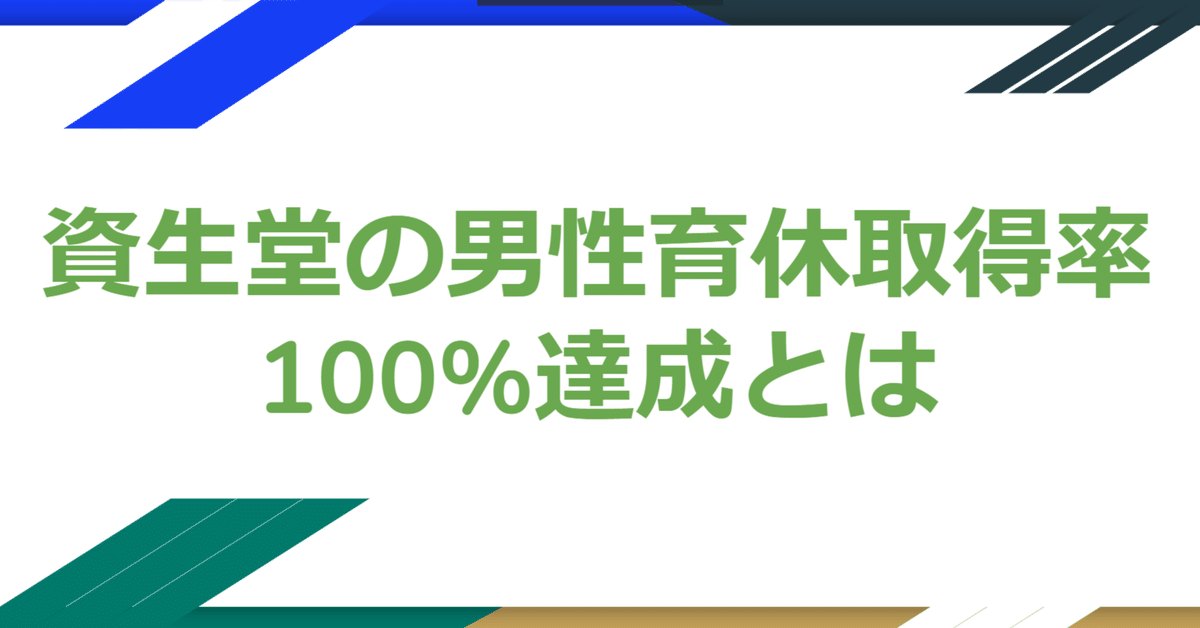
資生堂の男性育休取得率100%達成とは
資生堂が男性育休取得率100% を達成したそうです。
男性育休取得率が少子化低減に貢献するのかどうかなどの議論はあるかと思いますが、これまでとは違う風潮を達成したことでは一つの評価対象ではあると思います。
資生堂は、2023年末に国内資生堂グループ男性社員の育児休業取得率※1 100%を達成しました。
※1 男性社員の育児休業取得率は、「育児休業等の取得を開始した+資生堂独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性社員・契約社員の数」÷「配偶者が出産した男性社員・契約社員の数」×100で算出
※1 とある通り、国の育児休業制度 だけではなく、有給による育児休暇 も併せての100% というのは好感が持てます。個人的には有給推奨派です。
この両者の 割合についても発表して頂きたいです。(後者の割合が高いのではないかと推測します)
資生堂の実施内容
資生堂の PR 内容を要約すると以下のとおりです。
社員のライフスタイル尊重:
フレックスタイム制度や在宅勤務制度、パートタイム勤務オプションを提供。
独自の保育サービスや保育費・教育費補助の提供。
育児休暇(有給)を男女共に導入。
家族とキャリアの両立を支援することを掲げており、奨励することと支援を両立させる方針は非常に理にかなっています。
特に金銭面での支援は分かりやすく、表面上のデメリットを打ち消しやすくなるので100%育休を取ってもらうためには必須となるでしょう。
同性パートナーの扱い:
日本国内では2017年から同性パートナーを異性配偶者と同様に処遇。
事実婚や同性パートナーも支援対象に含む。
同性パートナーへの対応についても Diversity を掲げているからには対応必須です。
これらを踏まえると、資生堂の取組は ワーク・ライフ・バランス の実現が本題であり、男性育休取得率100% はその一つの指標に過ぎないと見受けられます。
男性の育児休業促進:
育休取得率100% を目指し、育休への理解促進を推進。
チーフピープルオフィサーからのメッセージやイクボスセミナーを実施。
KODOMOLOGY株式会社を通じた育児トレーニング提供。
「男性社員の育児休業取得率100%を目標に掲げ」 と ホームページにはあるのですが、中期経営計画 には 社員のワーク・ライフ・バランスについては述べられてないため、いつどこで何のために決まった目標であるのかは 公式資料からは定かではないですが、そういう目標があったのでしょう。
社内の風土を作るために全職位においての教育を実施したのは、DX推進など全ての社内改革のためには必要です。改革に必要なリテラシーというものは取締役から社員において全ての人間が理解してようやく体現できるものだと考えています。
子育て支援サービス:
KODOMOLOGY株式会社による「KANGAROOM+」 サービスを開始。
一時預かりやキッズプログラム、産後訪問サポートを提供。
具体的な支援策があるのは分かりやすくてよいです。
これらの施策が利用者の声を反映してより良いものになる仕組みまであると最高です。
育児休業からの復職サポート:
「ウェルカムバックセミナー」 などを実施し、復職率92.3% を達成。
育児休業からの復職は92.3% ということで、離職してしまうケースは100%を目指すものであるか?と言われると、目指すものではないと思います。
ライフ・ワーク・バランス を掲げるということは個々人の人生を尊重するということであり、育児休業中に考えた人生の選択肢には離職が入っているというのが自然なものであると思います。
会社としての要望からするとコストを掛けて人材向上を行っている以上、復職100%を目指すものであるという意見もあるかもしれませんが、これは100%で無い方が健全であると思います。
企業使命と戦略:
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I) を経営戦略の柱に位置付け。
「PEOPLE FIRST」 の理念のもと、社員が自分らしくキャリアをデザインできる環境を目指す。
今後 日本における人口減少による人材不足、グローバルでの多文化・多人種での ビジネス活動を考えると、どの会社も PEOPLE FIRST を掲げるのは必須にして必然なのであろうと思います。
資生堂の制度
男性育休取得率 100%の PR を見るついでに、資生堂の取組みについても読んでみます。
産前休暇・産後休暇
産前6週間は有給の産前休暇、産後8週間は一部有給の産後休暇を取得できます。無給部分は、積立休暇や年次有給休暇を利用できます。
無給の産休とする場合は、資生堂健康保険組合を通じて出産手当金の給付を請求できます。
この制度は一般的な企業と同等の内容です。あまり特筆すべき内容はないです。
育児休業制度
法定を超えて、資生堂では子どもが満3歳になるまで、通算5年まで育児休業を取得できます。
子どもが1歳未満の場合は、いかなる理由にかかわらず2回まで取得できますが、特別な事情がある場合は2回目以降の申請が可能です。
育児休業中は無給となりますが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
なお、資生堂では女性社員が妊娠中から出産後の職場復帰までのプロセスを上司と確認し合えるようなコミュニケーション体制「チャイルドケアプラン」を整備しています。このプランは、社員の妊娠・出産・育児に対する社員の不安を減らし、上司が交代した際の情報共有に用いることで、スムーズな職場復帰に活用されています。
満3歳になるまで、通算5年というのが資生堂オリジナルということです。
この制度はこの文脈だけではよく分かりません。
一人の子どもが三歳になるまで = 3年間 = 育児休業取得のタイミングの自由度が上がる。
通算5年 = 何の通算? = 子どもが複数いた場合の 通算(合計) が 5年?
「育児休業(育休)」とは、養育する子が満1歳(保育所に入所できない等一定の場合は最長満2歳)の誕生日を迎える前日まで認められている休業です。
と、いう国の制度を考えると、通算5年までの縛りは狭めているように感じます。
「育児休業中は無休となります」の点は国の制度そのままなので、資生堂オリジナルはありません。
チャイルドケアプラン の 男性バージョンももちろん設定されているのでしょう。
出生時育児休業(産後パパ育休)
育児休業制度とは別に子どもの出生後8週間以内に4週間を上限に育児休業を取得できます。なお、初めにまとめて申請すれば、同一子につき分割して2回取得可能です。
育児休業中は無給となりますが、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
出生時育児休業中は労使協定を締結し、社員と会社(上司)が合意した範囲を事前調整したうえで就業することを認めています。
こちらでも「育児休業中は無休となります」とのことですので、国の制度そのままです。
出生時育児休業中は労使協定を締結し、社員と会社(上司)が合意した範囲を事前調整したうえで就業することを認めています。
↑↑ これについては、なぜわざわざ?? という気持ちが出てしまいます。
余計なお世話ですが、男性が育休を取得するのであれば、その期間中は完全に仕事とは決別すべきだと考えます。
休業中の社員に対して仕事をさせる抜け穴を設けるのはお互いのために良くないです。
出産・育児のための特別休暇
社員のパートナー(配偶者など)が出産に際しては、5日以内の特別休暇(有給)が取得できます。
また、子どもが3歳までの期間に、育児を目的とした有給の特別休暇(連続1週間以内(土・日含む)を2回)を取得できます。
この休暇は育児休業の対象外となる勤続1年未満の社員も利用でき、一度に連続2週間の休暇を取得することも可能です。
特別休暇=有給 というのは良いものです。とにかく有給を使う! というのが育休の肝です。収入を減らさないというのは精神的にも経済的にも重要です。
出産特別休暇 はありがたいですが、その使い方は重要です。特に出産日は不確定なので、有給と併せて運用計画をしっかり立てましょう。
育児時間制度
日本の法令では子どもが満3歳になるまでの短時間勤務制度を導入するよう要請されていますが、資生堂では子どもが小学校3年生(9歳の3月末)まで、1日最大2時間の勤務時間を短縮できます。子どもが1歳に達するまでは、短縮した勤務時間のうち1時間分は有給となります。
時短勤務は働く時間の観点からは良いものですが、収入面からはデメリットもあります。
資生堂の場合、良いようには書かれていますが、「子どもが1歳に達するまでは、短縮した勤務時間のうち1時間分は有給」はどういう意図で設定したのかは疑問です。
子どもが1歳に達するまでというのは、センスがないというか、育児への理解がないです。子どもを保育園に預けるのが大体1歳になる前で、子どもが保育園で色々な病気をもらってくるのはここからが本番です。
設定するのであれば、せめて、保育園入園日から XX ヶ月 という設定にしないと実に則してないです。
育児期の店頭販売スタッフへのサポート
店頭でお客さま応対に従事する美容職の社員が育児時間制度を取得して勤務時間を短縮する際に、夕刻以降の店頭の販売業務を支援する代替要員「カンガルースタッフ」を派遣しています。2007年からカンガルースタッフを雇用することで、販売に携わる社員も仕事と育児を両立しやすくなりました。
人員の冗長性の観点からはこの制度は良いです。
事業所内保育所
資生堂掛川工場には保育施設「カンガルーム掛川(静岡県掛川市)」があります。月極めの常時保育と一時保育を運営しており、保護者はリフレッシュ目的で利用することもできます。
この保育所は資生堂社員だけではなく他社に勤める方や地域の住民の方々にも開放しています。
保育新サービス:2023年4月には、資生堂および提携企業社員向け子育ての支援サービス「KANGAROOM+」の提供を開始しています。「多様な働き方に合わせた、柔軟な保育」というコンセプトのもと、地元の保育施設では対応しきれない現在の保育ニーズに合わせ、1対1のベビーシッター事業を中心としたサービス提供を行っています。
ある意味、事業の多角化としての取組でもあると思います。
子育てをしている身からすると、保育園の位置は会社の最寄りよりも家の最寄りであるのがベストだと考えていますので、この取組は最後の砦としてはありがたいですが、選択肢の上位には入らないのかなと思います。
育児期の社員への補助金
国内の資生堂グループの子どもを扶養する社員に対しては、子どもを保育園やベビーシッターに預ける際の保育料や子どもの教育費を補助するための手当を支給しています(カフェテリア制度※の育児・教育費用補助)。
ベビーシッターの補助になるのは非常にありがたい施策です。
授乳のための福利厚生
当社の汐留オフィスと浜松町オフィス、資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)には、授乳や搾乳のためのスペースを設置しています。
(一部の工場ではお客さまの見学コースに授乳室を整備しています。)国内の資生堂グループの子どもを扶養する社員に支給する「育児・教育費用補助」を、搾乳機の購入に充てることも可能です。
1歳未満の子どもを育てる女性従業員が請求すれば、雇用形態に関わらず通常の休憩時間とは別に1日2回各30分以上(労働時間が4時間以内の場合は1日1回30分)の育児時間を付与しており、授乳や搾乳の時間に充てられます。
日本の法令では育児時間中の賃金の取り扱いに関する定めはありませんが、資生堂では育児時間制度を利用すれば、子どもが1歳に達するまでは、短縮した勤務時間のうち1時間分は有給となります。
この様な設備があるのが今後のグローバルスタンダードとなる気がします。
例えばイスラム圏で工事をする際の現場事務所には必ず礼拝所を設け、礼拝の時間は労働時間とは切り離して考えます。その様な文化があるのと同様に育児中の特異性を世間が認識することが出来る世の中が求められていくでしょう。
看護休暇制度
小学校入学前の子どもの病気・ケガの看護や、子どもの健康診断・予防接種のために、1時間単位で取得できる有給休暇です。子どもが一人であれば年間5日(40時間)、二人以上であれば10日(80時間)まで、日本の法定を超えて有給で取得できます。
看護休暇も会社の特別休暇として手厚くなり良いと思います。
一方で、配偶者が資生堂同様の制度がない場合、資生堂社員の方に制度の手厚さに乗っかった家庭での偏りが出そうな気がしますが、この様な制度が夜に広がることで状況も変わるでしょうから、大切な施策です。
育児を目的とした配偶者同行制度
現在までのキャリアが途切れないよう、小学校3年生以下の子どもを持つ社員は、パートナーに国内転勤が発生した際にパートナーの転勤地への同行を希望できます。
個人的には在宅勤務を推し進めているのであれば、パートナーの転勤に同行しても全く問題ないと思います。
一方で、国内の と限定しているのは解せません。
グローバルカンパニーを中計にも掲げているのに、国外への転勤同行を認めていないのは非常にイマイチです。 雇用上・税制上の問題が色々とあるのでしょうが、今後改善されることを期待しています。
育児期にある社員の転居を伴う異動に関する運用ガイドライン
日本の育児・介護休業法では、社員の転勤に際して育児・介護の状況へ配慮するよう事業主へ求めています。資生堂は育児期にある社員の転居を伴う異動に関する運用ガイドラインを定め、育児時間や介護時間を取得中の社員は本人の意向に応じて転居を伴う異動の対象外としています。
これは配慮する 程度で良いと思います。
まとめ
資生堂は ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)を掲げているだけあって、積極的な育休施策を行っていると感じます。
育休以外の ライフ・ワーク・バランス のための 施策も多く実施しているみたいですので、会社の取り組みとしては 日本随一の評価を受けているはずです。
あとは株価が戻ってくるかどうか、注視しておきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
