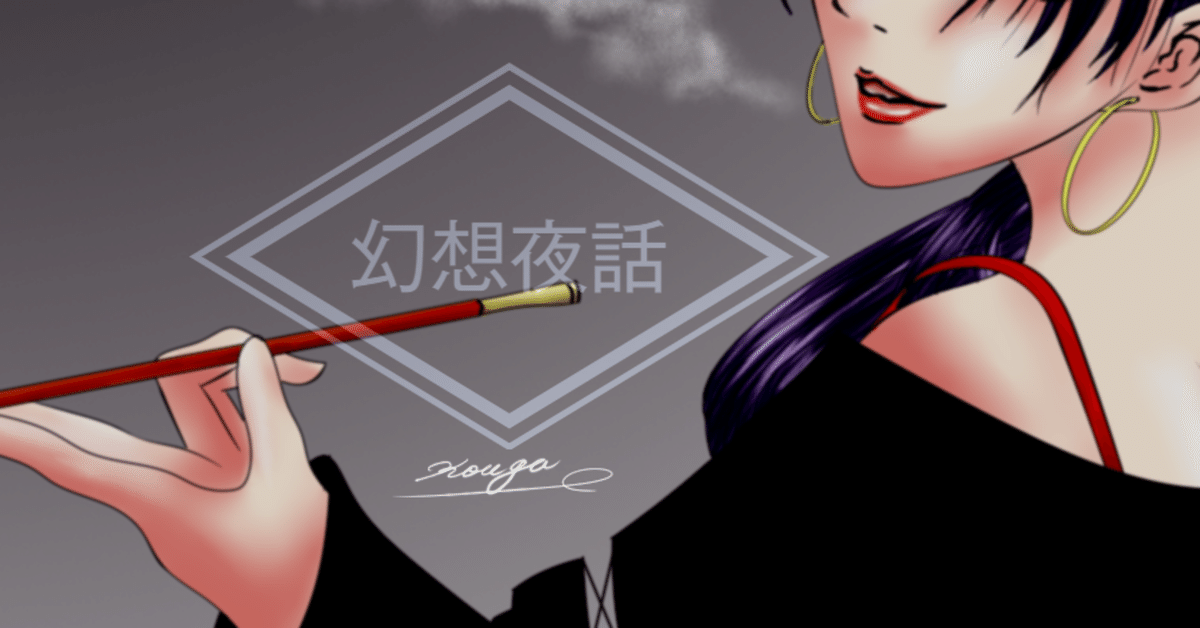
05 幻想夜話
零斗は寂しそうに、しかしどこか嬉しそうな、反する感情を内包した眼差しを湯飲みに落とした。ゆらりと揺れるお茶の水面に、頼りない姿が溶け込んでいく。
胸の奥の痛みを感じ、息を詰まらせたようにして息を吸った。そして泣き出しそうな子供のような表情に、淡い苦笑を滲ませて独白する。
「そうだね。でも師匠の音に焦がれるあまり、俺は自分の音の未熟さに、そして理想とする音から遠ざかっていくことが辛い。どれだけ弾いても、弾けば弾くほど苦しいんだ。師匠の音が頭から離れない。何をしても忘れようとしても記憶から消えないんだ」
湯飲みを受け取りそっと手に乗せる。目を閉じるだけでも師の撥捌きから、あの音の洪水が自分を飲み込もうとする様子に、身震いしてしまう。
津軽生まれの津軽育ち。寡黙で頑固で口下手で、話しかけにくいばかりか、近くにいるだけで威圧感を覚えてしまう。
だが一度その三味線を掻き鳴らせば、誰もが聞き入った。
その力強い旋律。しかし決して雑な音ではなく、しっかりと響かせて聞くものの魂に猛威を振るう音の嵐。
わずらわしいからと弟子を取る事のない人だったが、初めてその音を聞いた零斗は中学一年生の頃からひたすら通い詰めた。
その音に到達したい一心で。
来る日も来る日も通いつめ、北国の雪の吹きすさぶ日も通いつめた。最後に根負けしたのは、師匠のほうだった。
「忘れれば、お兄さん。あんたは今以上の音を出せるのかい?」
あの音を忘れる事ができるわけがない。
師匠の津軽三味線に魂ごと奪われたまま、零斗は今日まで生きてきた。
その音に惚れ込んだからこそ、零斗は津軽三味線の演奏家になろうと思ったのだ。つまり師匠の音を忘れることなどできるわけがない。
それでも師匠の演奏は偉大すぎた。
零斗の理想とする演奏でありすぎて、だからこそ嫉妬する。そこへ近付きたくて努力すればするほど、その理想とする師匠の演奏のとの差に嘆き苦しむ。
自分が今どんな演奏をしているのか、そして今どれだけのものが弾けるのか、それすらも見失っている。
だから師匠の音から遠ざかりたかった。
けれども忘れる事など、一瞬だってなかった。
愛した音だったからこそ。
「わからない。けれど少なくとも忘れることが出来るとすれば、そこに辿り着けない自分に絶望したりはしないよ」
零斗は最後に苦笑し、静かに湯飲みを持ち上げて、お茶を飲んだ。
師匠に出会わなければ、こんな思いに苦しむことなく、ただ津軽三味線を愛し、演奏することにもっと没頭できていたのだろうか?
そんなことを何度か考えた事がある。しかし零斗は木田柳翔樂の津軽三味線に出会ったからこそ、この弦楽器に惚れたのであり、他の演奏家の楽曲では単に「あぁ、三味線だ」と思うばかりで、自分も弾けるようになりたいと願うことはなかったと思う。
再び零斗はお茶で喉を潤す。角がない、するりと喉を滑り降りるお茶は、爽やかな苦味が心地よかった。
ふと自分に影が差し、零斗は顔を上げる。すると煙管を咥えたユメが、床に手をついてこちらに身を乗り出していた。顔と顔との距離があまりに近くて、ぎょっとしてしまう。
「え!」
ユメの意図がわからず、後ろに下がろうとしたら、ユメはにぃっと目を細めて笑った。
そして零斗の顔をめがけて、ふっと紫煙を吹きかけてきた。
思わずぎゅっと目を閉じて顔を背け、上半身を後ろに仰け反らせた。
「ちょっと、何するの!」
一度はそむけた顔をユメに向けると、ユメはもう片方の手を零斗の胸に押し当てた。
紫水晶のような瞳が一瞬きらりと光ったような気がした。
そして次の瞬間。
ズブリと、そう零斗の胸の中に手首まで埋め込んだのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
