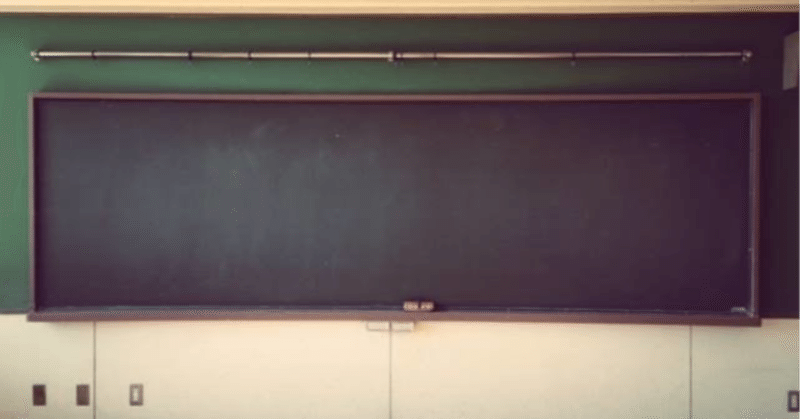
初任、教員一年目に送る ②授業の進め方 #8
続きです。
②授業の進め方
物事は何事も守・破・離が大事。若かれし頃は思いつきのオリジナリティあふれる行き当たりばったりな授業を展開していましたが、現在は、基本的に資質能力を育むために重視すべき理科の学習過程のイメージの型を崩さず授業を進めています。


2021年に新学習指導要領が始まり、自分たちが受けてきたような教室で知識を伝えられる知識獲得重視ではなく、理科の見方・考え方を働かせ探究の過程を通して資質・能力を獲得するように意識しています。
基本的な毎時の授業の流れは
1.オープニング(課題の発見)
2.ボディ(課題の探究)
3.クロージング(課題の解決)
で進めます。
1.オープニング(課題の発見)
事物・現象の紹介します。多くは語りません(5〜10分)。
ここからは生徒の活動の時間です。生徒自身に課題をもたせ、仮説を立てさせます。
2.ボディ(課題の探究)
教科書や資料集、人によっては文献(PC)を用いて、検証方法を調べたり、答えを見つけたり。
理科ですので実際に検証を行い、科学的根拠となるデータを集めます。
3.クロージング(課題の解決)
調べてわかったこと、結果から分かったことを整理し、科学的根拠をもとに結論をまとめます。5〜10分を使って振り返りをします。
生徒の振り返りをフィードバックし、新たな課題や解決できなかった課題について補足解説をしたり、さらなる検証をしていきます。
だいたい1つのテーマにつき2時間で1サイクルです。

その他にも、授業開きでは、オリエンテーション。
単元の頭ではOPPの配布。単元を通した本質的な問いを考えさせ、章の終わりには
学習後にもう一度同じ問いをさせ、自分の変容を感じさせる場面も設けています。
初任、教師一年目に送る 次回予告
③職員室机のポジション
④スケジュール管理法〜Notion~
⑤プロジェクト管理術〜Notion~
4月からの新生活に不安を抱えている人の一助になれば…。
参考になるかどうかわかりませんが、最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
