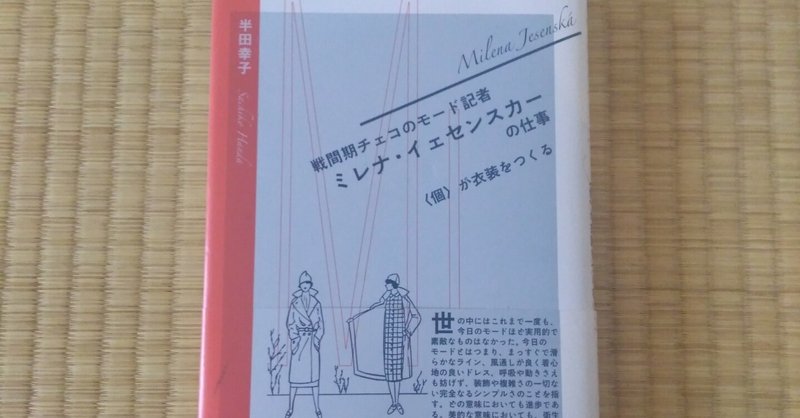
【書評】ミレナからイェセンスカーに[半田幸子『戦間期チェコのモード記者ミレナ・イェセンスカーの仕事 〈個〉が衣装を作る』]
『翻訳文学紀行Ⅳ』でミレナ・イェセンスカーの「浴室、身体、そしてエレガンス」他二編を翻訳された、イェセンスカー研究者の半田幸子さんが、この3月に、これまでの研究をまとめた『戦間期チェコのモード記者ミレナ・イェセンスカーの仕事 〈個〉が衣装を作る(以下『イェセンスカーの仕事』)』を発表されました。
ミレナ・イェセンスカーといえば、日本では(というか世界中で)『変身』等の作品で知られるプラハ出身のドイツ語作家フランツ・カフカの恋人の一人として知られています。あるいは、もう少し踏み込んで調べたことがある方の中には、第二次世界大戦中にユダヤ人保護活動に従事するなど反ナチス的な活動を展開し、ラーフェンスブリュック強制収容所で最期を迎えた正義感に熱くて悲劇的な女性ジャーナリストというイメージを抱いている人もおられると思います。
半田さんの著書『イェセンスカーの仕事』は、これまで大きく取り上げられてこなかったイェセンスカーのモード記者としての活動を詳細に示しだすことで、上に挙げたような「ミレナ神話」を相対化し、彼女の人物像を再構成する非常に意義深いお仕事です。ミレナ・イェセンスカーに関する本は、伝記を始め数多くあり、日本でも紹介されていますが、モード記者としての彼女に焦点を当てた書籍は、おそらくこれが世界で初めてだと思います。
翻訳者イェセンスカー
本書ではまず、イェセンスカーが活動を始める1920年代までのチェコの社会やメディア、女性解放の状況が紹介され、続いてイェセンスカーの執筆活動が紹介されていきます。注目に値するのは、モード記者として活躍したイェセンスカーは、活動初期においては文芸翻訳を多く手掛けていたことです。イェセンスカーが『火夫』をはじめとするカフカの短編作品を翻訳し、新聞に掲載していたのはご存じの方も多いかと思いますが、それだけでなく、ロマン・ロランやゴーリキー、ローザ・ルクセンブルク、スティーヴンソン、エドガー・アラン・ポー、アンデルセンなどヨーロッパ各地の名だたる作家の作品も翻訳・紹介しているのです(末尾に翻訳記事(なんとその数306本!)の目録もついています)。これらはもちろん原文から直接訳されたものばかりではなく、ドイツ語からの重訳も多いと考えられますが、それにしても、イェセンスカーの文学的センスと翻訳者としての能力の高さには思わず嘆息してしまいます。
モードの枠を飛び出す多彩な記事
メインのモード記事についても非常に興味深い議論がなされています。半田さんはイェセンスカーのモード記事を「モード・ライフスタイル論」と言い換えています。彼女の記事は単におしゃれや流行を紹介するにとどまらず、生活様式や、より広くは人生や生き方を問う記事なのだそうです。確かに、『翻訳文学紀行Ⅳ』で紹介してくださった記事は、いずれも単なる服飾の流行の紹介では全くなく、身体の洗い方を細かに指南した健康記事だったり、当時影響力を持っていた心理学に対する個人的な見解を展開するような思想記事だったり、身体と心両方をバランスよく鍛えることを若者に指南する教育的記事だったりと多岐にわたっていました。「モード記事」の枠組みでそこまでしてよいのか?とも思ってしまいますが、このテーマの多様さこそが、イェセンスカーの記事が当時のチェコ人に人気があった理由なのかもしれません。
こうした多岐にわたるイェセンスカーの記事において一貫しているのが、「シンプルさ」を重視する姿勢だと、半田さんは指摘しています。そして、身にまとう物だけでなく、生き方や考え方においてもシンプルさを追求するイェセンスカーの思想は、その背景にある「第一次世界大戦の惨劇や共和国としての独立、戦後の混乱の中での社会構造の転換、大量生産・大量消費社会への突入、科学技術の発達、急速な都市化による人間関係の複雑化(P. 188)」に根ざしていると主張しています。こうした第一次世界大戦後の状況は、パンデミックや戦争が起こり、経済不安が高まっている現在の世界情勢にも通じるところがあります。大きく地殻変動を起こしている社会を生きるのは、不安に満ちたストレスフルなものです。しかし、こうした社会に対する不安やストレスゆえにどこかの偉い人が展開する複雑な思想に振り回されることなく、「自分は自分だ」と言い切って自分を大事にしながら生きていくことが、イェセンスカーの「シンプルさ」なのかなと個人的に思いました。
実は積極的な「フェミニスト」ではなかった?
本書でわたしが最も意外に思ったのは、イェセンスカーのフェミニズムに対する立ち位置です。なんとイェセンスカーは「女性の場所は家庭や子どものそばにあるのであって、国会や公的生活にあるのではない(P. 203)」と主張してすらいるのです。ただ、彼女はこうした自分の考え方がかなり遅れていることも、当時のフェミニストから反発を受けることも重々自覚していたようです。面白いのは、記事によっては批判を受け付けるために記事に在宅時間まで記載していたこと(P.191)。これだけの覚悟を持って発言したからには、彼女にも何らかの強い信念があったのでしょう。この点について半田さんは、イェセンスカーが上記のような主張をしたからといって、働く女性を否定しているわけではなく、むしろ、仕事に適した服紹介するなどして積極的に応援している点を指摘し、「外で職に就き働く女性のことも、家庭に入り、家事や育児に奔走する女性のことも、同等に認め応援していた(P. 205)」と結論付けています。
これは非常に個人的な経験ですが、わたしが知っている何人か専業主婦の女性の中には、家事・育児で十分忙しいにもかかわらず、家の外に出て仕事をしていないことに引け目を感じたり、外に出て働かなくてはというプレッシャーを自分にかけてしまったりすると告白する方が少なくありません。一方、いわゆるキャリアウーマンの友人の中には、家事と育児は大変なのだと頭では分かりながらも、外に出て働かなくてもいいことを思わず羨ましく思ってしまうという人もいます。両者の間には、お互いに対する引け目の壁のようなものがあるのかもしれません。そうしたものはもしかしたら当時にもあって、イェセンスカーはそれを取り払いたかったのかもしれません。
ところでイェセンスカー自身はというと、一人の娘を抱える売れっ子モード作家、今でいうワーママで、彼女の理想の女性像とはかなり落差があったのではないかと思います。実際娘のヤナは、あまり幸せな子ども時代を送ることができなかったようです(以前、チェコのラジオで、娘のヤナが母に対して延々と愚痴を言うラジオドラマを聴いたことがあります)。こうした矛盾に、イェセンスカーはどう向き合っていたのでしょうか? 彼女の心の葛藤に思いを馳せずにはいられませんでした。
ミレナからイェセンスカーに
クララ・シューマンといい、ゼルダ・セイヤーといい、カミーユ・クローデルといい、多くの才能ある女性は長らく、有名な男性芸術家の妻や恋人として理解され、一人の独立した人物としてその作品を純粋に評価されることはありませんでした。それはまさに、彼女たちをファミリーネームではなく、パートナーの男性芸術家の視点からファーストネームで呼ぶという態度に象徴的に現れていると言えるでしょう。
その点で、『イェセンスカーの仕事』は、カフカの恋人ミレナを、同時代のチェコ人のライフスタイルに大きな影響を与えた著述家イェセンスカーとしてとらえなおす、非常に価値のある本だと思います。
『イェセンスカーの仕事』は専門書ではありますが、戦間期の中欧の風習やメディア事情、ヨーロッパ全体のモードをめぐる思想が分かるという点でも面白い本です。また、モード記者の本というだけあって装丁もおしゃれで当時の雑誌や新聞に掲載されていたイラストも多く載せられています。ぜひご一読ください!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
