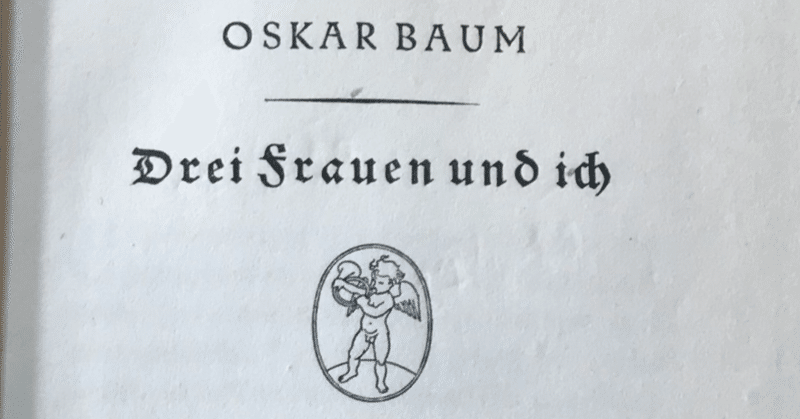
【プラハのドイツ語文学 読書ノート】オスカー・バウム『三人の女とわたし』
オスカー・バウムの『三人の女とわたし』
今回紹介するオスカー・バウムOskar Baum (1883-1941) の『三人の女とわたし Drei Frauen und ich』(1928) は、これまで紹介してきた「B級作品」とは一線を画する。民族対立を二項対立的に表現するプロパガンダじみた作品とは違い、ひとりの芸術家の成長と苦悩を比較掘り下げた、非常に内省的で味わい深い作品だ。バウムはカフカやブロートが属していた「プラハサークル Prager Kreise」のメンバーでもあり、「プラハのドイツ語作家」の中では比較的有名な部類に入る。まずはそんなバウムの経歴を紹介しよう。
作者オスカー・バウムOskar Baum (1883-1941)について

オスカーバウムは、1883年今日のチェコ共和国にあるプルゼニュPlzeň(ドイツ語ではピルゼンPilsen)で、織物商を営むユダヤ系一家の息子として生まれた。片目は生まれつき弱視で、11歳の時に事故がきっかけで全盲となる。このためプルゼニュのギムナジウムを退学し、ウィーンにあるユダヤ系の視覚障害者用施設に送られる。1902年にプラハに移り住み、シナゴーグのオルガン奏者やピアノ教師を務める。
1908年に『岸辺の存在。今日の盲人の生活から生まれた冒険と物語 Uferdasein. Abenteuer und Erzählungen aus dem Blindenleben von heute』で文壇デビューし、多くの作品を残した。1904年にはマックス・ブロートを介してカフカと知り合い、1907年に結婚してからは、カフカやブロート、フリッツ・ヴェルチFlitz Weltschといった「プラハのドイツ語作家」が属する「プラハサークル」は、バウムの家で定期的に会合を開き、お互いに自分の作品を朗読し合っていたらしい。
1922年には、ドイツ語の日刊紙「プラーガー・プレッセ」で音楽批評を担当したが、1938年ナチス・ドイツのボヘミア占領を機に解任された。パレスチナへの移住も失敗におわり、1941年にプラハのユダヤ系の病院で死去した。
『三人の女とわたし Drei Frauen und ich』あらすじ
主人公の「わたし」は目が見えない。両親はおらず、施設に入った頃からほとんど外出する習慣がなかった。しかし十八歳の時、同じく音楽を学んでいる友人ペーターの妹エーディット・カルが手配したオペラのチケットをもらい、ペーターとエーディットと三人でオペラを見に行く。エーディットの伝手で、三人は楽屋でオペラ歌手のマリナと話す機会を得る。マリナは、わたしが調律師になるつもりだということを聞くと、明日ピアノの調律をしにきて欲しいと言い、みんなの前でキスをする。劇場を出ると、ペーターとエーディットはわたしを施設行きの路面電車に乗せて見送る。しかし、施設の最寄駅に降りたわたしは道に迷い、居酒屋クリッツィンガーに迷い込んでしまう。事情を知った女給のミルカは、わたしを施設まで送ることにする。
しかし、クリッツィンガーを出てしばらくするとミルカも道に迷ってしまった。わたしは歩きながら、クリッツィンガーでドクターと呼ばれているミルカの恋人が、手術で目が治ると話していたことを思い出し、涙を流した。わたしはミルカに慰められながら施設に辿り着き、翌日再び居酒屋で会う約束をして二人は別れた。
翌日、わたしは施設長の許可を得ずにエーディットの助けを借りて施設を抜け出し、マリナのもとへ行く。マリナは、わたしが昨日初めて聞いた曲をピアノで弾くのを耳にして、なぜ才能があるのに調律師になるのかと尋ねる。わたしはマリナのピアノを調律しながら、芸術の道を勧める彼女の情熱に心惹かれる。一方現実主義者のエーディットはマリナの発言に否定的な反応を示す。別れ際にマリナは、またわたしを迎えにいくと約束する。帰り道でエーディットは、もうわたしと一緒にマリナのところに行くのはよすと言う。わたしはエーディットのことが好きだったが、芸術に燃えるマリナと比べて彼女がつまらなく見えたので、エーディットに別れを告げる。
施設長はわたしにJ.B.コッツァーという大きなピアノ会社での仕事を斡旋し、そこで下積みをさせる。しばらくしてマリナが突然わたしの職場に現れ、わたしを眼科に連れてゆく。目が見えるようになるかもしれないという希望を抱いたのも束の間、診察をした眼科医は匙を投げた。
マリナはわたしのピアノの才能を伸ばすことに責任感を感じているらしかった。彼女はコッツァーにオペラの無料券をプレゼントする代わりに、わたしの仕事量を減らし、トリューバッハという年老いたピアノ講師のもとで稽古を受けられるよう取り図らう。わたしは寝る間も惜しんで稽古に励み、いつしか作曲にも取り組むようになった。満足のいく作品が作れるようになるまではマリナに黙っているつもりだったが、ある時、マリナが稽古の様子を見に来た際に、トリューバッハが、わたしが作曲をしていることをばらしてしまう。彼女は機嫌を損ね、わたしと会ってくれなくなった。
わたしは彼女のために作品集を作り、それを彼女に送る。翌日彼女はわたしをサロンに呼んで、みんなの前でわたしの作品を演奏し、客が帰った後で、今度の演奏会でこの作品を演奏するとわたしに告げる。
わたしはクリッツィンガーにも時々足を運んでいた。そこではわたしはピアニストとしてみんなから一目置かれていた。ある日わたしは酔い潰れてミルカの部屋に運ばれる。実はわたしは、既にミルカと何度か身体の関係を持っていた。目を覚ました時、ミルカがちょうど祖父とドクターの用事を済ませて帰ってきた。わたしは、ミルカがドクターを恐れていることに気付いていた。わたしはミルカの愛を確かめようと彼女に迫るが、ちょうどその時、ドクターが部屋のドアをノックした。二人はノックに応えなかったが、しばらくして二人が外に出ると、ドクターが待ち伏せをしていた。しかしドクターは、ミルカの相手がわたしだったと知って落ち着いたようだった。わたしは、ドクターがミルカを愛しておらず、自分の道具としてしか見做していないと気づく。
わたしは施設の生徒にも嫌われ始めていた。ある日曜日、教室で眠りについたわたしの服を他の生徒たちが脱がしてしまうという騒ぎが起きた。施設長はこれ以上わたしを施設に置いておくことはできないと判断し、コッツァーにわたしを正規雇用にするよう頼み、わたしを職場近くの家族のもとに住まわせることにした。
その後わたしは新聞記事で取り上げられ、最初の楽譜を出版することになる。印税を得たことをきっかけに、わたしは工場での仕事を辞めて出版社の伝手で芸術家のアトリエで暮らし始める。続いてわたしは、自力で2冊目の本を書き上げ出版する。しかしその印税はすぐには支払われず、わたしはアトリエを追い出されることになる。アトリエを引き払う前日にマリナがやって来て、翌日からコンサートツアーに行くから今晩の壮行会に来てほしいと告げる。この時ミルカは初めてマリナに出会うのだが、わたしはミルカのことを恥じて、彼女のことをマリナに紹介しなかった。これに傷ついたミルカは、わたしに宿を提供したものの、わたしと言葉を交わそうとしなくなる。
ミルカの家で過ごし始めてしばらくした頃、エーディットがわたしを訪ねてきた。エーディットはわたしの状況を知って、自分たちの家で子どもにピアノを教える仕事をしないかと提案するが、話し合いの間にわたしの体調が急激に悪化し、わたしは病院に運ばれる。
エーディットは入院したわたしの傍にずっといてくれた。退院後わたしはカル家に下宿し、ピアノ教室を開いて生計を立てるようになる。カル家は父と母の仲が悪く、父の肩を持つエーディットも母や弟から嫌われているようだった。エーディットとわたしは一緒に仕事をしながら仲を深めていった。ピアノ教室は評判になり、わたしはまもなくアパートを借りることになった。エーディットは毎日わたしを訪ねてきた。
ある晩、わたしの家を訪れたエーディットは突然泣き出した。父が心臓発作で亡くなったのだという。エーディットは家にいられなくなった。わたしは、友人のもとに居候して仕事を探すつもりだった彼女を引き留めて一緒に暮らすことにする。わたしは一部のレッスンをエーディットに任せて、オペラを作曲し始めた。
ある日、わたしは自分が作曲したオペラの楽譜を持ってマリナを訪ねた。マリナは、わたしの楽譜を見ながら、自分の好みに合わせてそれに修正を加えた。わたしはその修正に合わせて楽譜を書き直すことにする。
その日の夜、わたしはエーディットが妊娠したことを知る。わたしは、今後の生活を憂うエーディットを安心させようとするが、内心、わたし自身も自分が子どもを持つにふさわしい状態なのかと頭を悩ませていた。子どもが生まれると、わたしは、ピアノ講師の仕事が減り、オペラの作曲もうまく行かないというスランプ状態に陥る。また、エーディットも仕事に追われるようになり、夫婦関係は冷え切ってしまう。
そんなある日、わたしは偶然ミルカと出会う。彼女はわたしに、ドクターのところで目の手術の予約が取れるようになっているらしいと告げる。以来わたしは仕事の後にクリッツィンガーに通うようになったが、ミルカは既にクリッツィンガーを辞めて娼婦になっていた。ある晩わたしはミルカを訪ねて一緒に街に出かける。二人でジプシーのバーにいるときにマリナと出くわし、一緒に来るよう誘われるが、わたしはミルカのもとに留まる。これに喜んだミルカは、明け方わたしをドクターのもとへ連れて行こうとする。しかしわたしは彼女に「手術はエーディットに伝えてからにする」と告げ、病院を立ち去る。
しかしわたしは家に帰らず、街をさまよいながらマリナとエーディットのことを考える。わたしはこれまで、一緒にいて居心地の良いエーディットを愛しているのだと思っていたが、本当は、芸術に対してストイックなまでの探求心を持つマリナに対する愛を抑圧してきたのではないかと考える。こうしてわたしはマリナの家へと向かい、このことをマリナの前で語る。しかしマリナはわたしの話を真面目に取り合おうとはしなかった。しかし、わたしが目の手術をすることにしたと告げると、マリナは喜び、エーディットには事情を伝えておくから早く病院に行くように告げる。
手術後、わたしはしばらく入院しなければならなかった。エーディットは入院中に一度もわたしを訪ねて来なかった。マリナも病院には近づきたがらず、状況を手紙に書いて送ってくるだけだった。ストレスのためわたしは、「もう目なんて見えなくてもいいから、ここから出してくれ!」と言って病院で暴れ出してしまう。後にドクターは、このせいでわたしの手術はうまくいかなかったのだと説明したが、手術の失敗は本当はドクターの手術ミスによるものらしい。
わたしはミルカに付き添われて家に帰る。エーディットは、わたしを不機嫌にさせるのを憚って見舞いに行くのをためらっていたらしい。エーディットは、お互いの将来を縛らないために別れることを提案する。彼女はわたしがいない間に、子どもを育てていくに十分な収入が得られる仕事を見つけていたのだ。これはわたしにとっては苦々しい経験だった。しかし、こうしてわたしは再びひとりきりで、妥協せずに芸術に打ち込む人生を歩み出したのだった。
感想
久しぶりに読んでいて心地の良い作品だった。文体はシンプルだが、少し婉曲的な表現が多く、何度か読み返してやっと意味が分かったというところもあった。主人公が孤独を体現するような人物だからか、他の登場人物との関係の仕方に、冷静さや距離感が感じられ、作品全体が静寂感に満たされているような感じがする。この主人公の「自我の薄さ」「孤独さ」は、村上春樹作品の登場人物に通じるような部分がある。表現も決して派手ではないが素晴らしい。施設内の寒い教室にひとり籠って作曲する主人公の頭に次々と和音が浮かんできて、現実を忘れてしまうというような描写があり、読みながらこちらも恍惚としてしまった。
また、当時の視覚障害者の「普通」が「普通」に描かれている点も面白い。作中では折に触れて、主人公が目の見える友人に「目が見える人向けに楽譜を書き直す」作業を依頼する場面があったり、交差点で通行人が一緒に道を渡ってくれるのを待つシーンがあったりと、当時の視覚障害者を取り囲む社会状況も垣間見える。障害を持つ人と友人として親しく接しているうちに、その人が何らかの障害を持っていることをふと忘れてしまうことがあるが、まさにそんな風に、途中で主人公に視覚障害があることを忘れてしまいそうになる瞬間もあった。伊藤亜紗さんの『目の冷えない人は世界をどう見ているか』という作品があるが、まさにその問いの答えが率直に表されている作品だと思う。
ただ最後の展開だけはややご都合主義感が否めない。当時女手一つで子どもを育てていけるような仕事はどのくらいあったのだろうか? エーディットは教養のある女性として描かれているから、ピアノ講師やタイピストとして働くこともできただろうが……。夫の芸術創作のために別れを決意したのだから、わたしだったら養育費くらい請求したいところだ(とはいえ多分主人公にはお金がないのだが)。
とはいえ、主人公が最終的にひとりで生きていくことになるという結末には、バウムの芸術観が強く反映されているのかもしれない。『三人の女とわたし』の中でも、理想的な芸術家像として描かれる歌手マリナは、顔こそ広いものの、自分の表現活動のために独身を貫いており、精神的にも経済的にも自立した女性として描かれている。主人公は長らく自分の表現をエーディットやマリナに理解してほしいと強く望んでいるが、この結末は、女性に対する精神的な依存欲求からの脱却を意味してもいるのだろう。「孤高の芸術家」というイメージを突き詰めた作品と言えるかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
