
ご質問にお答えします!『セリフの微妙なニュアンスを脚本上どう表現する?』
脚本家志望の方から、こちらのご質問をいただきました。
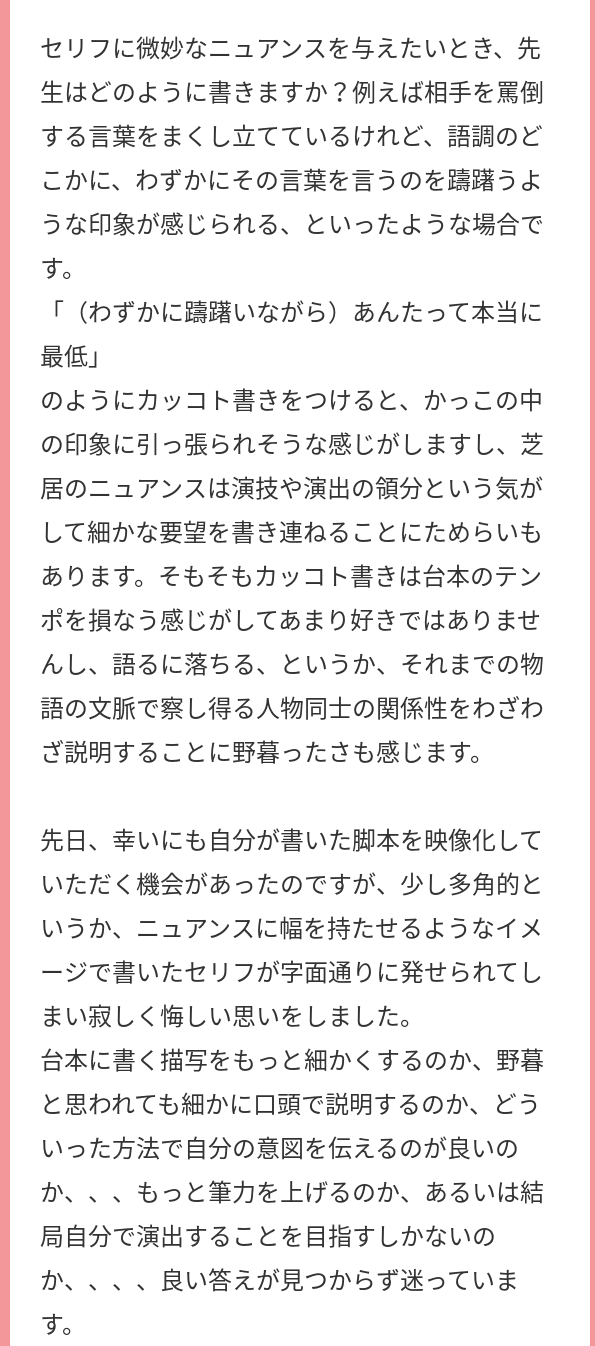
ご質問ありがとうございます。
質問者さんが書かれているように、脚本家は一般に、セリフの一つ一つに対して「こういう表現をしてほしい」と指定したりはしません。
演技、演出をする人からすれば、ストーリー展開やキャラクター描写といった判断材料はあるわけですし、脚本家が必要以上の説明を添えたり、いわゆる”決め打ち”をしすぎたりすると、演技、演出の幅を狭めることにもなります。
とは言え、脚本家が原稿上でセリフのニュアンスを伝えることが禁忌事項というわけではありませんし、「必然性があれば、簡潔に書き添えます」というのが私の方針です。
以下の例を読んでみてください。
太郎と花子が一緒に昼食を取っている。
太郎「お前、あいかわらずよく喰うなぁ」
花子「……」
太郎「?」
花子「ムカつく!」
恐らくこの後二人は揉めるんだろうなぁ、花子は太郎に「デリカシーがない」と怒り、太郎の方は「実際、めちゃめちゃ喰ってんじゃん!」とか言うのかなぁ……といったところですね。
では、次の例も読んでみてください。
太郎と花子が一緒に昼食を取っている。
太郎「(笑顔で)お前、あいかわらずよく喰うなぁ」
花子「……」
太郎「?」
花子「(泣き笑いで)ムカつく!」
太郎と花子、それぞれのセリフにカッコト書きを足しただけで、かなり印象が変わりますよね。
二人の性格がどうだとも、過去に何があったとも書いてありませんが、一つ目の例よりも、あれこれ想像が膨らむのではないでしょうか?
例えば、二人はお互いに会いたい気持ちを抱えたまま長い間会えずにいたのだが、今日は久しぶりに再会して一緒に食事をしている。
太郎は、花子の旺盛な食欲が懐かしく、微笑ましくて「よく喰うなぁ」と、からかった。
花子の方も、こういう時の太郎の口調も表情も、何もかもが懐かしくて、思わず胸にこみ上げるものがあり、言葉に詰まった。
そして、不思議そうにこちらを見ている太郎の顔を見たら、涙が堪えきれなくなった。
悲しいわけじゃなく、一緒にいられることが嬉しくて、でも泣いてしまったのが照れくさくもあり、いろんな思いが入り混じって泣き笑いになり、「ムカつく!」と言い返した……みたいな感じでしょうか。
仮にこれが、ある作品の冒頭シーンだとしましょう。
脚本家が「2つ目の例の雰囲気で演じてほしい」と思っているならば、そのニュアンスを原稿上に書き添えるしかない、と私は思います。
こういった場合は、「カッコト書きを書いても過剰な説明にはならない。むしろ書く必要がある」と判断します。
長々書いていますが、要するにお伝えしたいことは、
「過剰な説明をしたくないという質問者さんの気持ちは分かるけれど、必然性のある説明を、簡潔にする分には何ら問題はない」
ということです。
ポイントは「簡潔に」ということです。
上の例でも(笑顔で)、(泣き笑いで)と書いてあるだけで、太郎と花子、それぞれの気持ちに関して想像を膨らませる材料になるはずです。
決して「説明を長く書けば書くほど伝わりやすくなる」というものではないので、質問者さんが対応案の一つに挙げられている「台本に書く描写をもっと細かくする」というのは、得策ではないと思います。
例えば、質問者さんは「伝えたいニュアンスの例」として以下のように書かれています。
罵倒する言葉をまくし立てているけれど、語調のどこかに、わずかにその言葉を言うのを躊躇うような印象が感じられる
割と長い説明ですが、正直なところ私は、これを読んでも、質問者さんがどんな演技をイメージされているのかが掴めませんでした。
「まくし立てる」というのは、一般に「よどみなく、ベラベラ話す」というイメージですが、そうでありながら「どこかに、わずかに言うのを躊躇うような印象」を出せと言われても、一体どうすれば……というのが率直な感想です。
例えば、
花子、しばし言い淀む。が、堪えきれず、
花子「あんたって本当に最低! 自分のことどんだけエラいと思ってんの? そんなんだから、みんなに嫌われてんだよ! っていうか、嫌われてるって気づいてないでしょ? びっくりするぐらい空気読めないもんね!」
という感じで、「最初は躊躇っていたが、いざ罵倒し始めたら止まらなくなって、まくし立てる」ということなら、理解もイメージもできます。
ですが、「まくし立てながら、どこかに、わずかに言うのを躊躇うような印象」は、どうしても私にはイメージできないです。
何だか重箱の隅を突かれているような気分かもしれませんが、簡潔な表現で脚本の読み手であるスタッフ、キャストのイメージを喚起しようするなら、このぐらい事細かに分析をする必要があると私は思います。
スタッフ、キャストに対して、脚本の意図を繊細に読み取ってほしいと願う以上、脚本家の側も、表現に対して繊細でなければなりません。
脚本家というのは、言わば「文章を使って映像を表現する仕事」です。
ですが、文章と映像では情報量の桁が違いますから、非常に難しいことが求められているわけです。
それでも、「そういう仕事なんだ」と腹をくくって挑んでいくしかありません。
今後も「自分の脚本が映像になる」という経験を積み重ねることで、見えてくるものもあると思います。
また、打ち合わせの段階で、監督ときちんとコミュニケーションを取ることも重要です。
例えば、監督が脚本を読み、あるセリフに対して「解釈が何通りかあるな」と感じたとしたら、打合せ時に脚本家に「どのイメージで書きましたか?」と尋ねてくるはずです。
こういった時に、適切に、明確に答えることも、イメージのずれを回避するために重要だと思います。
これからもお互いがんばりましょう!
ご質問のある方はこちらからどうぞ。
※シナリオコンクールの規定、審査基準に関してはお答えできませんので、その点はご了承ください。
脚本、小説の有料オンラインコンサルも行っていますので、よろしければ。
これまでに脚本家志望のみなさんからいただいたご質問への回答は、こちらのマガジンにまとめてあります。
スキ♡ボタンは、noteに会員登録してない方も押せますよ!
#脚本 #シナリオ #エンタメ #質問 #マシュマロ
***********************************
Twitterアカウント @chiezo2222
noteで全文無料公開中の小説『すずシネマパラダイス』は映画化を目指しています。 https://note.mu/kotoritori/n/nff436c3aef64 サポートいただきましたら、映画化に向けての活動費用に遣わせていただきます!
