ご質問にお答えします!『シナリオ講座で教わる書き方に疑問を感じます』
脚本家志望の方からこちらのご質問をいただきました。
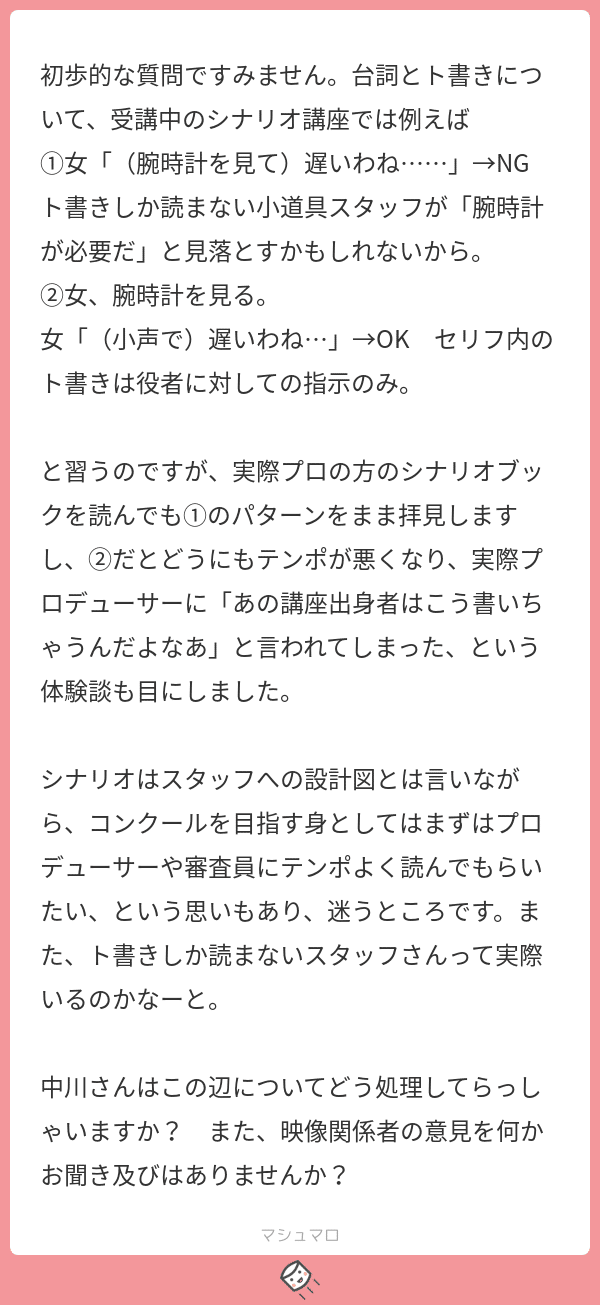
ご質問ありがとうございます。
一般にシナリオコンクールは、最終選考まで残らなければ個別の講評をもらえず、「どうして入賞できなかったんだろう?」という疑問には、自問自答するか、講座の先生や仲間と一緒に類推するぐらいしかできません。
そうなると、「もしや、自分が正しいと思っている書式のせいで落とされているのでは?」と思う人がいても不思議はないですよね。
質問者さんの不安なお気持ちは、よく分かります。
脚本家志望の人のSNS投稿で、
「コンクール入賞作がネットで公開されていたから読んでみたら、スクールで教わった書式のルールが守られていなかった。守っても意味がないということ?」
というのを見かけたこともありますし、
「脚本家の〇〇みたいな書き方してたら、コンクールだと落とされると思うんだけど……」
という不満を持つ人もいるようです。
質問者さんは今回、通常のト書きと、セリフ内に( )を使って入れ込むト書き(「カッコト書き」と呼ぶ、と私は師匠から教わりました)の違いを疑問点として挙げられています。
この種の「講座やスクールで教わったことがプロの現場にはそぐわないのではないか?」という疑問は、脚本家志望の人の中でも、特に真面目なタイプの人がよく抱くのではないかと思います。
カッコト書き問題のような、「書式のお作法」的なことは、厳密に比較すれば、講座によって、あるいは指導者によっても多少の差異があるはずです。
だからと言って、「どこかの講座の教え方が正解で、それ以外が不正解」とは言えない、というのが私の考えです。
プロの現場を基準として考えるならば、求められるのは「とにかく中身が面白いこと」であり、「面白い脚本」であるためには、「読みやすく、わかりやすいこと」が必須条件です。
「読みやすく、面白い脚本でさえあれば、”腕時計を見る”という動作を通常のト書きにしようが、カッコト書きにしようが、どちらでも構いません」
というのがプロの考え方だと認識していただいて良いと思います。
書き手がプロの場合は、質問者さんが講座で教わった書式ルールからは逸脱していたとしても、「スタッフ、キャストがストレスなく理解できる書き方」ではあるはずですし、プロとして書き続けていれば、書式に限らず、独自のスタイルが生まれてくるのは自然なことです。
そのスタイルが、脚本家志望の人が学ぶ講座の教えと厳密に一致していなかったからと言って、プロの現場で問題が起きるようなことはありません。
ここまでお読みになると、おそらく質問者さんは「それならば脚本の講座で教わるような書式ルールには意味がないのか?」とお思いになるでしょう。
この疑問に対しては、「まったくそんなことはない」「講座生は、そこで教わるルールを守るのが正しい」と私は考えます。
講座で学んでいる段階の人たちは、まだ独自のスタイルなど持ち合わせていないでしょうし、プロのように「スタッフ、キャストからのフィードバックをもらう」という経験もしていないはずです。
「教わった書式ルールからは逸脱しているけれど、現場ではこれでも”あり”なのだ」という判断が、講座生にはできない、ということです。
何事も独自の判断ができないうちは、教わったルールに従っておくのが安全です。
教わったルールを守っておけば、読み手が「面白いかどうか以前に、意味がわからない……」と感じるような、困った作品を書いてしまうことはないはずです。
質問者さんは「コンクール応募時に、プロデューサーや審査員にテンポよく読んでもらいたい」とお書きになっています。
この部分を読んで私が感じたことを率直に書くと、
「作品のテンポの良し悪しは、カッコト書きの使い方のような、小さな要因のみで決まるわけではない」
ということになります。
読み手が「テンポが悪い」と感じるのは、脚本の構成に問題がある、セリフがもたついている等、もっと重篤な問題を抱えているからであり、テンポを良くしたいのならば、より大きな問題の改善に注力すべきです。
「だけど、プロデュサーが『あの講座出身者はこう書いちゃうんだよなあ』と批判していた事実もあるんだから、カッコト書きの書き方で評価が変わる場合もあるのでは?」と、お思いになるかもしれません。
私の推測では、そのプロデューサーが指摘したかったことの本質は、「講座生レベルの人にありがちな、ト書きの過剰な描写」や「全体的なテンポの悪さ」であり、その一例として挙げたのが、たまたまカッコト書きの使い方だったということなのではないかと思います。
私の考えをまとめると、
・講座生として学んでいる段階では、書式ルールに関しては講座で教えられたことを守っておくのが安全。
・プロが書式ルールを守っていない場合があるからと言って、講座の教えが間違っているわけではない。
ということです。
上述の「コンクール入賞者が書式ルールを守っていなかった」という件について言えば、「入賞作は審査員にとって、書式ルールの間違いなど気にならないレベルで面白かった」ということなのでしょう。
言い方を変えれば、応募の時点で「この作品は中身が圧倒的に面白いのだから、書式ルールなんて関係ない!」と断言できる人以外は、ルールを守っておいた方が安全、ということです。
講座で教わる書式ルールを守ったからといって失うものは特にありませんが、無闇にルールから逸脱すれば「分かりにくい脚本になる」というリスクを自ら負うことになります。
これからもお互いがんばりましょう!
ご質問のある方はこちらからどうぞ。
※シナリオコンクールの規定、審査基準に関してはお答えできませんので、その点はご了承ください。
脚本、小説の有料オンラインコンサルも行っていますので、よろしければ。
これまでに脚本家志望のみなさんからいただいたご質問への回答は、こちらのマガジンにまとめてあります。
スキ♡ボタンは、noteに会員登録してない方も押せますよ!
#脚本 #シナリオ #エンタメ #質問 #マシュマロ
***********************************
Twitterアカウント @chiezo2222
noteで全文無料公開中の小説『すずシネマパラダイス』は映画化を目指しています。 https://note.mu/kotoritori/n/nff436c3aef64 サポートいただきましたら、映画化に向けての活動費用に遣わせていただきます!
