
ナナハン物語(猫殺し)第一話 1970年代を生きる少年達、ナナハンは少年の唯一の力だった
2017年5月の高木
街が再開発されると、その場所に長年住んでいても、昔の景色がなかなか思い出せなくなる。同じように自分達の生きた時代も次第に忘れていく。
日曜の朝、そんなことを思いながら、犬の散歩をしていた。散歩の途中にあるコンクリートの板塀。その塀一面に文字とイラストが描かれていた。長年の風雨で消えつつある。
そこには懐かしい名前があった。
「SPECTOR CRS連合」 ドクロのマークも残っていた。これは、昭和50年代のものだ。
気づくと塀の向こうの桜の木は葉桜になっていた。もうすぐ夏が来る。この歳でもまだ胸騒ぎが起こる。あの時代の夏は夢の時間だった。でも細かい事は思い出せない。
ただ楽しかった。今はない世界がそこにはあった。スマホもネットもない。高校生達の毎日はたわいないおしゃべりと噂と妄想で作り出されていた。
犬の散歩も終わり、家のポストを覗くと封書があった。封書とは今時珍しい。ダイニングの椅子に座って封書を見る。
差出人には「猫殺し」とあった。
1974年7月夏休み前
梅雨も明けて季節は夏に突入していた。その日は高校3年の1学期の期末試験、それも最終日だった。午前中だけの試験が終わると強い日差しの中、早足に学校の裏問から出た高木は、隣接する公団団地に向った。
ロックギターリストのように、肩まで伸ばした長い髪、リーバイスのスリムのジーパン、カーキ色のTシャツの上に脱色したジージャンを着ていた。
ビーサンを履いていたので、ぺたぺた音を立てていた。
うるさいなぁと思いながら高木は走っていた。
この団地内には小さな公園があり、高木はその公園脇の道にオートバイを止めていた。オートバイはHONDA CB750(4サイクル4気筒 排気量750ccの国内最大のバイク 世界を驚かせたスペック)、通称ナナハンと言われている。
夏の日差しの中でメタリックブルーのタンクが輝いていた。3年落ちの中古のナナハンだ。乗り出してからまだ2週間しかたってない。高木が1年間バイトし、親に借金までして買ったバイクだ。
ナナハンで通学する
高木の通っている都立の工業高校は、世田谷の成城学園の隅っこにあり、工場棟、サッカー場、野球場などもあり、広大な敷地を持つ学校だ。
学校の周りは空き地や畑、特に芝の畑が多く、ゴルフ上みたいな所にある学校だった。屋上からの見晴らしはよく、遠くには富士山、近くには千歳烏山の丸いガスタンクも見えた。
バイク通学は3年前で許可されていたが、宅地が増え、近隣からの騒音の苦情があり禁止された。禁止されてはいるけど、高木はかまわずナナハンで通っていた。
工業高校なのでそんな輩は沢山いた。生徒の殆どが大なり小なりバイクを持っていた。しかも学生運動のおかげで、私服通学が可能となっている。だから学校の門を出てしまえば、学校という縛りが消え自由な気分になれた。
斉藤くんが来る
高木が少しの間ナナハンに見とれていると、オートバイのエンジン音が聞こえてきた。4サイクル2気筒のエンジン音。HONDA CB350(4サイクル2気筒 本田ドリームの伝統的な排気量350ccのバイク)、通称サンパンのエンジン音だ。乗っているのは。おそらくダブりの斉藤くんだろう。年上なので斉藤くんと高木はくんづけしている。
斉藤くんは高3の時バンド活動をやり過ぎて、全く学校へ来なかった。
結果として、まだ3年生を継続している。
長い髪とイージーライダーのピーター・フォンダ風のもみあげを生やしている。ベルボトムジーパンに長袖のボーダーシャツ。その上にジージャンを羽織っている。靴はコンバース。当然ノーヘル(ヘルメットを被ってない)だ。青いタンクのサンパンを高木の横に止めた。
「学校は終わったかい」今日もサボっている斉藤くんが言う。
「斉藤くん、今日は期末試験の最終日だよ」
「そうだっけ、それより高木、今日行くだろう」
大規模な暴走族の集会が今夜あることは高木も知っていた。
やはり斉藤くんは来年も高校3年を続ける気のようだ。
「行くよ」高木は当然という顔で答えた。
「そうか、ほんじゃ何時のも場所で待っている」
そう言うと斉藤くんは4サイクル2気筒のバスドラのようなエンジン音を響かせ団地の出口に向かった。
少年達の世界が始まる
エンジン音が聞こえなくなると、団地内の木々にしがみつくアブラゼミの鳴き声が大きくなった。何かの呪文の様に聞こえる。高木は額の汗をぬぐい高い位置にある太陽を眺めた。
眩しさに目をつぶるとまぶたの裏が真っ赤になる。暫く目を閉じたままにした。
目をあける。
周りが白く光り輝いていた。そして徐々に景色に色が戻ってきた。そこには違う世界が広がっていた。
高木はナナハンを跨ぎ、セルを回しエンジンを始動た。
サンパンとは違う、4サイクル4気筒のジェット機のようなエンジン音が響いた。ヘルメットはもちろん持って無い。でもガソリンは満タン。そして今日は土曜だ。
(これから俺達の世界が始まる)
・土曜の夜
夜11時を過ぎたルート20(国道20号線)、この時間になるとタクシーしか走っていない。斉藤くんのサンパンは高木の右横を走っている。
前面に広がる黒い空間、ヘッドライトに照らされた白線が素早く後ろに飛んでいく。
高木と斉藤くんは環八通りへ入り、東名高速の用賀インター脇の道から砧のファミリーパークに向かっていた。砧のファミリーパークは環八沿いにある大きな公園だ。この辺りでは駒沢公園とともに暴走族の集会場としてのメッカとなっていた。
その日は大規模な集会だった。「鼠小僧」「ルート20」「スペクター」など渋谷、世田谷、狛江、調布、府中を中心とする有名なチームが大挙して集まっている。
高木は斉藤くんと一緒に公園の駐車場にバイクを乗りいれた。
広い駐車場がバイクや車で埋まっていた。エンジンの空吹かし音、三連ホーンの音が鳴り響いていた。バイクだけでも100台以上はある。
高木は集まったバイクの迫力に圧倒されていた。改造の限りを尽くしたバイクが水銀灯の下で輝いている。その周りには派手な服装の男女がたむろしていた。
高木と斉藤くんは隅っこに目立たないようにバイクを止めた。さすがに二人ともびびり気味だ。駐車場は満杯だ。それでもバイクや車がまだまだ集まってくる。
猫殺しと出会う
激しい爆音が響いた。見ると駐車場の入り口前の直線路では、バイクでのウィリー走行が始まっていた。マフラーが路面に擦って火花が散っている。
斉藤くんが騒音に負けまいと、大声で高木に話しかけてきた。
「すげーな!、ちょっとバイクを見てみようぜ!」
高木も、こんなに沢山の改造バイクを見るのは初めてだった。
何台か見る中で高木はKAWASAKI W1(メグロの大型バイク その伝統を受け継ぐ排気量650ccのバイク)通称ダブワンが格好いいと思った。タンクをメッキ塗装にして、マフラーをカッタータイプにしている。音が凄い、まるで地響きだ。
色々とチェックを入れながら歩いていると、黄金色のKAWSAKI 500SS MACH III (2サイクル3気筒の排気量500ccのバイク 国内最速の加速を誇る暴れ馬)が高木の目に入った。「猫殺し」のマッハ3(スリー)だ。
猫殺し本人もいる。奴は猫を見つけると捕まえて首をしめて殺すという、かなり変態的な噂のある男だ。
高木はその噂を同級生達から聞いており、出来れば近づきたくなかった。斉藤くんも猫殺しの話は知っていた。
それでも常に恐怖より興味が勝る斉藤くんが話かけた。
「どうだよ、調子は?」
猫殺しはつり目で狐顔。さらさらの長髪をかきあげながら答えた。
「うーん、まぁまぁだよ。さっきねぇ、なんか今日はエンジンの調子が悪ぃと思っていたら、その原因が分かったよ」
「ほら、これさぁ」猫殺しは、いきなりかじりかけのフランスパンを高木の目の前に差し出した。
「マフラーの中に突っ込んでいたのを忘れていた。いい焼き具合だろう」とそう言うと細い目をつり上げて笑った。
高木は静かに、その場からゆっくりと歩きだした。その後を追ってきた斉藤くんが言う。
「あいつさぁ、絶対になんかやっている」斉藤くんは猫の様に顔をゆがめた。
「シンナー?」と高木が訊くと。
「いや、もっとやばいやつ」
「やばいってなんだよ、マリファナ?」
「おお、それだ、やばいぜぇ」
高木は斉藤くんも同じ程度にやばいだろうと思ったが、黙ってバイク見学に戻った。
駐車場内は、暴走族と言われる輩がほとんどなので、当然パンチパーマやリーゼントの突っ張りの装いの男が多い。仲間内では、バミューダパンツの上に原色のトレーナーを半袖にして裏返しで着るのが流行っていた。
その中で高木も斉藤くんもヒッピー風の長髪で、ジージャン。どちらかと言えば浮いている。そう言えば猫殺しも長髪だ。
斉藤くんは高校生活をほぼドロップアウトした状態だ。
あの猫殺しは大学をドロップアウトしたという噂を高木は聞いていた。もしかすると彼はインテリなのではと高木は思っていた。
一方斉藤くんはうちの高校で落第している。彼は本当の阿呆だと思った。
暴走開始
深夜0時を過ぎるとさらにバイクが集ってきた。もの凄い台数だ。ちなみに集まった暴走族達、全員が仲良しではない。些細な事で喧嘩する。このままじゃ大騒ぎになるだろう。すでに駐車場のジュースの自販機に激しく蹴りをいれて、ピーピー警告音を鳴らしている馬鹿もいる。
このままでは警察が来て、駐車場の出口を塞がれて全員検挙されるのも時間の問題だった。
各チームのヘッド達(暴走族のチームの親分)が相談を始めた。
その結果、3グループに分かれて警察を撹乱しながら流す(あまり飛ばさないで走る)ようにと伝達が来た。ともかく集団で走る。流れを切らずに信号など絶対に止まらずに走れということだ。止まっていると警察に捕まる率が高まる。
高木は夕飯抜きだったので、腹が減っていた。このまま帰ろうかとも思ったが、折角だから少し走ってから帰ることにした。斉藤くんも同じく腹減りで帰る気満々だったが、高木に付き合うようだ。
どのグループで走ろうかと考えていると青山通りを走るグループにアフロヘアーの青井の乗る黒タンクのHONDA CB500(4サイクル4気筒の500ccのバイク、暴走族人気No,1のバイク)を見つけた。青井は高木と同じ電気科の同級生だ。
高木は青井に手を振ってから、そのグループの一番後ろについた。
青井のCB500に取り付けた自慢の三連ホーンから、ゴッドファーザーのテーマ曲が鳴り響く。
バイクの群れがヘビのように、うねりながら動いた。
カストロールオイルの匂い
高木のナナハンはキャブレター系をカスタムチューンングしており調子はいい。でも、ゆっくりと隊列の後ろを斉藤くんと走る。
暑さの中、排ガスの匂う道路でも気分は上々だった。
目の前の道路には、おそらくスペクターのヘッドの野村さんのマッハが残したと思うカストロールオイルの焼けた匂いが漂っていた。
当時は2サイクルの大型バイクが販売されており、燃料のガソリンにオイル混合しなくていけなかった。普通は分離式タンクでオイルは補給するが、当時はレーサーと同様にタンクで直接ガソリンと混合させていた輩も多かった。彼らが好んで使うのがカストロールの植物性オイルで、排煙が真っ白になり、独特の甘い匂いがした。
高木は久しぶりに高揚感を感じた。前に50台以上のバイクが走っている。凄い迫力だ。この台数で走る魅力はなにものにも代えがたい。
タクシーだらけの国道246(ニイヨンロク)を何台ものバイクがジグザクに走り抜けた。タクシーは動くパイロンみたいだった。
時折タクシーの運ちゃんの幅寄せに、「馬鹿野郎!」と怒鳴りながら、高木はナナハンを飛ばした。
斉藤くんのジンクス
祭には事故はつきものだった。
目の前で火花を散らしながら猫殺しの黄金色のマッハ3が転がった。バイクは50mくらい道路を滑ってガードレールにぶつかり止まった。
246が青山通りと呼ばれる手前、三軒茶屋を過ぎたあたりから首都高速が併走して立体交差になっている。そのアップダウンするローラーコースターのような道路をちょうど下りきった所で、道路の窪みか何かで突然弾かれたマッハ3はバランスを失い、右側面をアスファルトに擦り付け火花を散らした。
その事故を見た高木の頭に「斉藤くんのジンクス」が頭に思い浮かんだ。
「斉藤くんと走ると必ず誰かが事故る」先輩達がよくその話をしていた。半信半疑だったが、そのジンクスは本物だったようだ。
猫ごろしは、スピードが出ていたわりには、フルフェースヘルメットも被っているし、いつも着ている皮のつなぎのおかげで、怪我はほとんどなかった。悪運の強いやつだと高木は思った。
マッハ3はハンドルが極端に曲がってしまい自走はむりだった。仕方がないので、青井の知り合いがバイトしている近くのガソリンスタンドにバイクを預けた。猫ごろしはダチのリアシートに乗った。
これで何万円かのバイク部品がおしゃかになったわけだが、リアシートの猫殺しはへらへら笑っていた。
斉藤くんがサンパンを高木のナナハンの右に近づけた。
「猫のたたりじゃねぇーの!」斉藤くんが大声で叫ぶ。
高木は斉藤くんのジンクスのせいだと思っていたので返事をしなかった。さらに斉藤くんが叫ぶ。
「高木、パックれようぜ!」
斉藤くんのサンパンが急に隊列を離れ脇道に入っていた。高木もあわてて後を追った。
「何処へ行くの!」高木は大声で問うと、斉藤くんは言った。
「俺んちだ。飯食おう、腹ぺこだ」
斉藤クリーニング店
斉藤くんの家は目黒のクリーニング屋だ。周りを首都高とビルディングに囲まれている一軒家だ。目黒通りに面している外階段から広いがボロボロの木造ベランダに出ると、齋藤くんは自分の部屋に窓から入った。
そこは畳の部屋で、壁にはローリング・ストーンズとジョニー・ウインター(100万ドルのブルースギターリスト)のポスターが貼ってある。
「高木、ラーメンでいいか?」
「何でもいいよ」
「よし、待っていろ、ラーメンを作ってやるよ」そう言って、部屋から出て行った。
10分後には斉藤くんがお盆にサッポロ一番味噌ラーメンに生卵を追加したスペシャルラーメンを持って現れた。インスタントラーメンは素早く作ることが彼のポリシーになっている。
「卵つきだぜぇ」
「いいねー」
テキサスの100万ドルのブルースギターリスト
素早く食べることは二人のポリシー、彼らは3分で食べ終わった。
食後の一服。高木はハイライトを吸った、斉藤くんは喉に悪いといい、煙草は吸わなかった。
「レコードでも聴く?」タバコの煙を窓から外に吐き出している高木に斉藤くんが訊いた。
「うん、ジョニー・ウインターがいい」
深夜の2時過ぎに、開けっ放しの窓から、ジョニー・ウインターの絡みつくようなブルースギターのフレーズが流れ出した。
8月生まれの高木はこの夏で18才なる。彼女もいない。色々と諸事情があり高2の冬、サッカー部を辞めた。勉強も今は低空飛行だ。
それでも高木はナナハンライダーだった。当時の高校生にとって、この恐ろしく暴力的なスモールワールドを生き抜くための唯一の力だった。
亜子さん登場
昨日はレコードをかけ放しで、寝込んでしまった。ターンテーブルの上でレコード針がぶつぶつ言っていった。斉藤くんも横で寝ていたが、飛び起きて針を戻し、乱暴に高木を叩く。
「おい、高木、起きろ、飯に行こう」
「わかった、了解だ」面倒くさいが、そう答えた高木は立ち上った。しわしわのジーパンとTシャツ。そこにはかすかにカストロールオイルの匂がしみこんでいた。
時間はすでに11時、近所の喫茶店「ガロ」にバイクで行く。
高木は斉藤くんと一緒に遅いモーニングサービスを食べた。
タバコの吸い過ぎかコーヒーが泥水の味だ。まさにマディウオーター(ブルースギターリスト)だ。
「野音(日比谷の野外音楽堂)で今日、日本のロックバンドのライブがある。知っていた?」禁煙者の齋藤くんが言う。
「そうなの」
「なぁ、行かないか」
高木はまだ寝ぼけていたので無反応だった。そこに女の子の声がした。
「えっ、行きたい、行きたい」
声の方を見るとここでアルバイトをしている亜子さんだった。
「で、チケットはあるの?」
亜子さんが疑わしそうに斉藤くんを見た。
亜子さんは斉藤くんの中学校の頃の同級生だ。今年地元の都立の進学校を卒業し、今は青学へ通っている。背が高くストレートのロングヘアーが似合う子だ。そんなに可愛くって優秀な女の子が、何故だか高校留年中の斉藤くんのバンドで、キーボードとボーカルを担当している。
世界の、いや目黒の七不思議の一つだと高木は思っていた。
「うんにゃ、チケットなんかないよ」ゆで卵を頬張りながら阿呆面をした斉藤くんが言う。
「なーんだ、喜んで損した」
「大丈夫だよ、毛布とかがあれば、何とかなるよ」
「毛布?」高木が言う。
「そう、素手だと怪我するから」なんだかわからないが、斉藤くんが気軽に言った。
「で、いく?」
「いく!いく!」高木と亜子さんが同時に返事をした。
日比谷の野外音楽堂
高木は午4時まで斉藤くんの家で過ごし野音へ出発した。亜子さんは斉藤くんのサンパンの後ろに乗った3人ともノーヘルだ。風に亜子さんの髪が激しくなびいていた。夕刻とは言え、まだ夏の太陽は容赦なく道路を照りつけていた。
野音の裏の歩道にバイクを止め、鬱蒼とした木々の中を歩く。ヤブ蚊が寄ってくる。手で蚊を払いながら3人は歩く。するとエフェクターで歪んだギターの音が跳びこんできた。すでにライブは始まっていた。
「齋藤くん、裏口から入るの? 知り合いとかいるわけ」高木は心配になって聞いた。
「いないよ」と何時もの軽い調子で斉藤くんは答える。
「じゃ、どうするの」
「うーん、人目につかない所がある」と歩き出した。
高木達のやりとりを横で聞いていた亜子さんは気づいた。
「もしかしてフェンスを乗り越えるつもり、馬鹿じゃないの、一番上は鉄条網だよ、怪我するよ」
「大丈夫だよ、亜子もジーパンだろう、それとこれがある」と斉藤くんが片腕に抱えている毛布を指さした。
「そう言う問題じゃないでしょう、私にそんな馬鹿げた事をやらせるつもり、斉藤のアホ!」
亜子さんは怒って反対方向に歩き出した。
「高木、行こうぜ」斉藤くんは亜子さんを無視して歩き出した。
どちらへ行こうか高木は悩んだが、ライブの音を聴くとどうしようもない。斉藤くんの後を追った。
野音を囲むフェンスの前に着くと斉藤くんが言った。
「高木、ここ、ここだよ、ここを乗り越えてトイレの屋根に飛び降りる」
見ると、フェンスは編み目なので手がかりがあり簡単に登れそうだった。
ただフェンスの一番上は凶悪な有刺鉄線が張り巡らされており、これが手強そうだ。下りる側はトイレの小屋があり、屋根までは1mくいらで、これはなんとか飛び移れそうだ。
「よし、行こうぜぇ」お気楽な調子で斉藤くんはフェンスに飛びついた。
高木も慌てて走り、大きくジャンプしてフェンスに飛びついた。
斉藤くんは長髪で、見かけはなよなよしているが、運動神経はいい、素早く上に昇りつき、毛布を鉄線にかけてフェンスを跳び越えた。高木も続いて飛び越え、トイレの屋根に降り立った。
このトイレだが、トイレ内の通路には屋根がないので、高木はトイレの外側ではなく通路側に飛び降りた。気づくと斉藤くんがいない、その時、隣の女子トイレの方で、悲鳴があがった。
斉藤くんは女子トイレの通路へ飛び降りたようだ。高木は走り出した。直ぐに斉藤くんが後ろから追いついてきた。
「やべーっ、女子トイレに下りちまったよ」
「わざとだろう」
チャーと金子マリとバックスバニー
ベンチが半円に並ぶローマのコロシアムみたいな会場に入ると満杯だった。ほとんどの客がスタンディングしていた。
耳には切れの良いドラムと腹に響くベースに合わせて、ギターのカッティングが響いていた。バックス・バニーだ。
フェンダームスタングを抱えるチャーが、ボーカルの金子マリとタイミングを図っていた。
突然、金子マリのジャニス・ジョップリンのような歌声が、野音の上に広がる夕焼け空を突き抜けた。
「最高だねぇ」斉藤くんが高木の耳元で言う。
うなずく高木の前で、「チャー!」という大声が脳みそを揺さぶった。
なんと亜子さんがいた。振り向いて高木達の顔をみると
「最高!」とまた叫ぶ。
「あのさぁ、どうやって入ったの」斉藤くんが訊く。
「あの人に言ったら、入れてくれたの」
指さす方をみると、小豆色のイタリアンスーツを着たジョーがフェンスの脇に立っていった。煙草を吸っている。
「おっ、ジョーだ」斉藤くんが言う。
ジョーは日本のロック界のカリスマ的ボーカリストだ。黒人とのハーフなので体もデカいし見た目も怖い。
ジョーに直訴とはやっぱ女の子は凄いやと高木は思った。
高木はそんなストレートな性格の亜子さんが隣にいることが嬉しかった。高木が見ているのに気づくと亜子さんは笑いながら言った。
「あのさぁ、女子トイレから悲鳴が上がって、君達が走ってくるのが見えたよ」
「うるせーよ」斉藤くんが不機嫌に答えた。
「あれ、Tシャツが破れている、くっそ、ひかけちまった」斉藤くんは脳天気にうるさかった。
辺りはようやく夜の帳がおり暗くなってきた。ステージはライトアップされた。会場はさらにヒートアップしている。今度はキャロルの登場だ。このくそ暑いのに、皮のズボンに革ジャンを素肌に着ている。
おきまりのロックンロールのリフで始まった。軽快なリズムに合わせて、ボーカルの矢沢が唾を飛ばすように歌う。
「君はファンキー・モンキー・ベビー」野音がヒートアップする。
夜のバイト
会場はノリノリだ。でも高木と斉藤くんは今一乗れていない。チャーと金子まりの本格的なロックを聴いた後、売れ筋のポップなロックにやや醒めた感じであった。
亜子さんも同じような気持ちらしい。ということで、3人は早々と会場をパックれることになった。
「ありがとう」亜子さんが会場の裏口から出る時に、タバコを吸っているジョーに声をかけた。ジョーはタバコを持った手を振った。
「あれ、タバコじゃないぜ、きっと葉っぱ(マリファナ)だよ」斉藤くんが横で言う。
「聞こえるよ」高木がうるさそうに言う。
3人が林間の小道を抜けて、バイクに戻ると爆弾の様な音の固まりが明るい松明のような野音の上に響いていた。
「高木、俺、これからバイトだから」バイクに跨がって斉藤くんが言う。
「夜のバイト?」
「そう、夜のバイト。だからさぁ、亜子を送ってやって」
「えっ」
「おねがいしまーす」と亜子さん。
「あぁ、はい」
高木は少し緊張した。女の子との二人乗りするバイク(タンデム)なんて初めてだ。それに二人乗りは得意じゃなかった。
「じゃーね」と言うと斉藤くんはサンパンのエンジンをかけ、素早く夜の道路に走り出した。
真夜中のタンデム
遠ざかる斉藤くんのサンパンのテールランプを見ていた高木。横には亜子さんがいた。
どうするか悩む、高木は奥手だ。助け船を亜子さんがだした。
「どこかで、ご飯食べようよ、おごるよ、行こう」
亜子さんは高木のナナハンのリアシートに乗ると、小首をかしげた。
高木も実はかなり腹が減っていたので同意した。
「はい、どこがいいですか」
「プロペラカフェ」
プロペラカフェは調布飛行場に隣接するレストランだ。
調布に向かうにはまずルート20に出る必要がある。高木はナナハンを跨ぐと、セルでエンジンをかけた。
「亜子さん、行きます」そう高木が言うと、亜子さんは腕を高木の胴に回して手を組んだ。背中に感じる熱さに緊張した。その緊張をほぐすように高木は一息ついてからナナハンを車の赤いテールランプが流れる道路に乗り入れた。
真夜中のバトル
斉藤くんのタンデムに乗り慣れているので亜子さんは、高木の運転にスムーズに合わせてくれた。しかし、ブレーキをかけると、胸の膨らみが触れる。高木は気になってしょうがない、ちょっと嬉しいが、集中、集中、女の子を乗せて事故ったら大変だ。
「ねぇ! 奥多摩の幽霊バイクの噂だけど知っている!」風の音にまけないくらい大きな声で亜子さんが高木に話かけてきた。
「知っているよ、後ろに女を乗せたバイクの幽霊だろう」
「見たことある?」
「ないよ、だって見た奴はみんな事故る。斉藤くんのジンクスと同じだよ」
「斉藤のジンクスって、あいつそんなに凄いの?」
「まーね」
その時、高木のミラーに嫌なものが写った。それは大型バイクで、激しいローリングを道路で繰り返している。
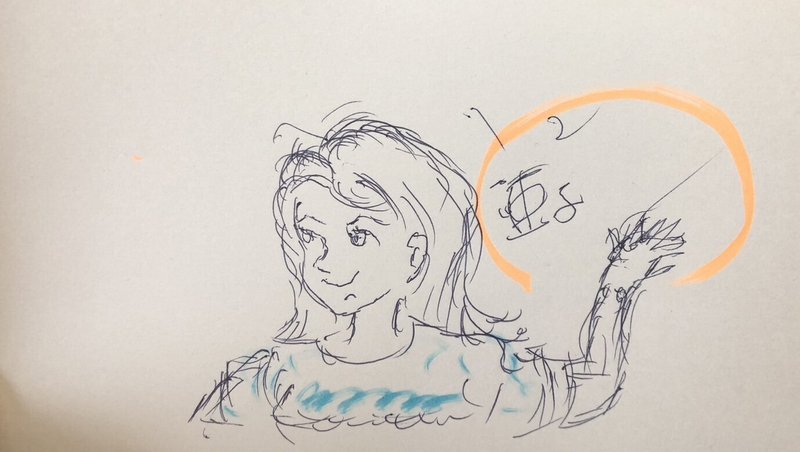
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
