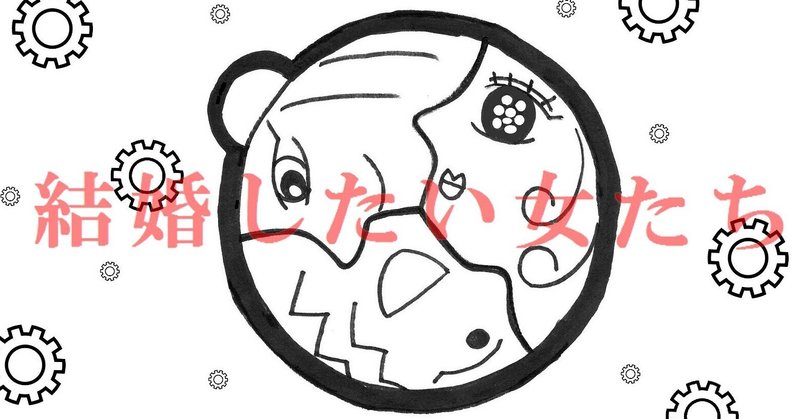
創作大賞応募作品 結婚したい女たち
1 結婚したい女たち プロローグ
「ここの石焼きパスタがホントにおいしいんだって!」
私、立野香は緊急事態宣言中にもかかわらず、友だち二人とパスタを食べに来た。美味しいお店に目がないお琴一推しのパスタ屋へ。
「やっぱ少ないね。ランチタイムはカウンターも満員になるのに。」
細長い店内は、右側に厨房とカウンターがあり、左側の壁に沿ってテーブル席が三つ、そして奥のくぼんだスペースにもうひとつテーブル席があった。カウンター席のお客さんは一つ空けてぽつんぽつんと距離をとって座っていて、テーブル席も中央の一つは空席だった。
香たちは奥の席だった。お琴が予約して取っておいてくれたのだ。ドアのない個室のようになっていて、ほかのお客さんたちを気にせずゆっくり話せる。
「で、どうよ?どんな感じ?」
「ん・・猫を飼ってるって言ったら嫌そうな顔された。結婚したら実家に置いてくんでしょ的なことも言われて。」
「あ、猫飼ってるんだ。」
「うん。東京で働いてた時に道で拾って。かわいくて連れてきちゃった。」
私は大学を出たあとしばらく東京で働いていた。でもコロナのちょっと前に仕事を辞めて、今は静岡の実家に住んでいる。
「動物はね、ダメな人はダメだからね。それは仕方ないよね。猫アレルギーの人もいるし。」
「猫アレルギー?」
「そうよ。花粉症みたいに猫の毛で鼻水やくしゃみをする人いるんだよ。」
(知らなかった。と言うことは、猫を飼っていることも結婚の障害になりうるじゃないか。)
「動物が好きな人でもね、犬好きな人はやめた方がいいよ。」
一花いちかがペペロンチーノを食べながら言った。せっかく石焼きパスタが美味しいからとお琴が連れて来てくれても、自分を曲げない一花は自分の食べたいペペロンチーノを食べている。そういうところはとても一花らしい。
「なんで?」
「犬を飼ってる人はね、命令するのが好きな人なの。そんなのと結婚したらたいへんよ。あれがそうだった。子どもの頃飼ってたから飼いたいってしつこかったもん。子どもができたから回避できたけど。」
一花は結婚して子どもも生んだのだけど、離婚して今はヨガのインストラクターをしている。
「あ、それ聞いたことある。猫好きな人は放任主義だから自由にさせてくれるんだよね。干渉してこないから結婚生活もうまくいくって。」
物知りのお琴は何でも知っている。犬と猫にそんな違いがあるなんて。一花は人の心理に詳しいし、この二人と話すと必ず色んなことを教えてもらえる。
「あ、そだ。忘れてた。これ作ってきたの。どうかな。」
私は水引で作ったイヤリングをテーブルの上に置いた。
「わ、かわい!」
「冬用?」
「うん。シュトーレンのイメージで作ってみた。どうかな。」
「かわいいよ!」
いつでもお琴は褒めてくれる。
「チェコビーズを散りばめてみたんだけど。どう?」
赤裸々に意見を言ってくれる一花をちらりと見た。
「つけていい?」
「うん。」
一花はバッグからポール&ジョーの白い貝殻の形の鏡を取り出して首を振りながら見ている。
「いいね、これ。角度によって光ったりくすんだりする。黒い服に合わせたらいいかも。」
お洒落な一花から『いいね』がもらえるとホッとする。
「チェコビーズのね、ファイヤーポリッシュって言うのがね、いい艶が出ててるんだけどギラギラしてなくてきれいで。」
思わず熱く語りそうになったけど、興味なさそうな二人を見てそれ以上話すのはやめた。
「私もいい?」
とお琴もイヤリングをつけてスマホの自撮りでチェックしている。
「あ、そうだ。ね、前くれたあのピアス。もう一つ作ってもらえないかな。」
一花の言うそれはこの春にフルーツゼリーをイメージして作ったピアスのことだった。
「うん、いいけど。なくしたの?」
「ちがうの。あれをね、レッスンの時につけたままだった時があって。軽いからさ。つけてる感じがしなくて。そしたら生徒さんから「そのピアスかわいい!」ってウケてさ。」
「売りなよ!」
と、お琴がカシャッと写メを撮りながら言った。
「もちろんお金は払うから。その生徒さんがね、もしかしたらプライベートレッスンをさせてもらえるかもしれなくて。スタジオには内緒で。すっごいいい人でね、弁護士の友だちがいるから子どもも取り返しなよって親身になってくれて。」
「取り返すの?!」
お琴がスマホを下ろして一花を見た。私もびっくりして一花を凝視した。
「まさか。そんなことしないよ。でもプライベートレッスンはしたいのよねえ。ご主人が会社経営してるからいろんな人を紹介してもらえそうだし。うまくいけば独立できるかも。」
一花は産んだ息子を旦那の家に残してきた。とられたと言うか。向こうの親が男の子だから置いて行けと言ったとか。
「育てられないのよ。妊娠した時に仕事辞めちゃったんだから。変な話だよね。子どもを育てるために仕事を辞めたのに、今は仕事を辞めちゃったから子どもを育てられないんだから。」
そう言って一花は寂しそうに笑ってた。
「プライベートレッスンってかっこいいね。一花ならできるよ。んで旦那を見返してやれ!」
お琴が笑いながら言った。
「その人の写メある?できればその人のイメージで作りたいけど。」
「あるある。きれいな人でさ。あのもらったやつぴったりのイメージの人だよ。同じのでいいと思うけど。」
と言って見せてくれたその人は、優しそうな色白の美人だった。
「そだね。あれ似合いそうだね。」
「一緒のにしてくれる?お揃いがいいんだよね。」
「あ、そっか。そだね。材料残ってるから一緒の作るね。いつ欲しい?」
「なるべく早くがいい。いい?」
一花はすまなそうに目を細めた。
「うん。だったら来週にはできるよ。」
「ありがと!あげたら友だちにも作ってほしいって注文来ると思うんだよね。顔の広い人だから。ヨガだけじゃないのよ。料理教室とかいろいろ通ってるんだって。」
趣味で作っているアクセサリーだけど、「売る」のがやっぱり夢だ。ああ、夢は広がる。
「私も仲のいい先生たちに聞いてみよっか。買うかな・・ケチばっかなんだよね。お母さんたちなら買うだろうけど、私が売っちゃやばいし。」
お琴は小学校の先生をしている。何でも知っていて気遣いもできて立派なお仕事もしていて、どうして結婚できないのか不思議に思うけど、
「いい人に出会わないのよ!」
と、私と同じことを言う。
2 結婚したい女たち プロローグ
「ねえ、今度さ。」
鏡をしまった一花が神妙な顔をした。
「山に登らない?」
「山?どこの?」
お琴は遠足で子どもたちと近くの山へ登ったことがある。
「どこでもいい。生徒さんに誘われて登ったらよかったんだよね。また登りたくて。行かない?」
一花がお琴と私を期待の目で順番に見つめた。
「いいよ。あんまり高いのはちょっとあれだけど。」
お琴がそう言うと、一花が私を見た。
「香はどうかな。日帰りでいいからさ。」
「わたしもいいよ。去年富士山に登ったの。ご来光、めっちゃよかった。」
「え?!」
「え?!」
二人が同時に声を上げた。
「富士山?!」
「すごいじゃん。」
「うん、めっちゃよかったよ。」
私はあの感動のご来光を思い出してにやついた。思わず笑みが出るほどに美しかった。でもそれだけじゃない。言葉では言えない神々しい朝日だった。
「泊まりで登ったの?」
一花が意外だと言うように聞いてきた。
「うん。山小屋に泊まった。たまにはね。お父さんもいいよって言ってくれたし。」
「そうだよね。ずっと家にいたんじゃ気が滅入るもんね。息抜きもしなきゃね。」
お琴がホッとしたように言った。私のことを心配してくれてるのだ。
私が仕事を辞めて実家に戻ってきたのは母が病気になったからだ。入退院を繰り返す母に代わって家のことをしている。
「じゃ、決まり。今年中にどっか登ろうね。お琴、車出してくれる?」
「うん、もちろん。」
この夏、私たち三人は川堤でバーベキューをした。その時もお琴の四駆で行ったのだ。荷物がたくさん積める、アウトドア用の大きな車だった。でも本人曰くアウトドアはほとんどしないんだそうだ。
「仕事で何かと運ぶことも多くてさ。買っちゃったんだけど、アウトドア好きと間違えられちゃうんだよね。」
あの車を見たら誰だってそう思う。
「もったいないよ。またバーベキューしようね。」
「バーベキューじゃなくても、どっか行こうよ。」
と、一花もかなりあの車を気に入っていた。
山にぴったりのあの車で山に行けるなんて、やけに本格的なアウトドアになっちゃうな。私は想像しただけで楽しくなった。
「あのね、東京の同僚がね、このコロナ禍にデキ婚したんだよ。」
「え?!」
お琴の顔色が変わった。
「ジビエみたい。」
一花は無表情で呟いた。そのつぶやきにスイッチが入ったお琴が、
「そうだジビエ、ジビエ!」
と、ぎゃはぎゃは笑った。
「ジビエ?」
私は、はてな顔で一花を見た。そんな私にお琴が言った。
「たくましいってこと!」
お琴は笑いが止まらないようで、最後はむせた。苦しそうに水をのどへ流し込んでいる。
「人はそうあるべきよ。」
そんなお琴には目もくれず、一花が毅然と言った。
「コロナだからって何もできなくなるなんてヘンよ。家に閉じこもってさ。」
と言ってから、「あ、ごめん。」と私に小さく言った。
「ううん。外に出たい人には辛いよね。」
「でもさ、デキ婚って、ステイホームで出来たんじゃないの?」
のどの調子を取り戻したお琴が言った。
「今外を出歩けないから、家で会うのが多いらしいよ。だからそういうことになるんじゃない?」
「そういう相手がいればね。」
と一花は憮然とした顔のままだ。
「その人がね、すごいの。運命の相手だって言ってた人とデキ婚したの。尊敬しちゃう。」
「しとめたってわけね。そういう人にはコロナはいいかもね。」
聞きたくなさそうな一花とは正反対にお琴は、
「うらやまし!それぐらいしなきゃ結婚なんてできないのかもね。」
と話に乗ってくれた。
「私もそう思った。がつがついかなきゃダメなんじゃないかなって。」
この話を聞いた時はあまりの衝撃に、お琴じゃないけど笑いが止まらなくなった。でも笑ってる場合じゃない。見習わなきゃって心を入れ替えた。手本にできるほどの性的衝動を引き出してくれる男に出会いたいと、今は思っている。
「その人ね、『自分は犬だ』って言ってた人なの。」
「あ、なるほど。それは続かないよ。」
結婚も離婚も、人生を知り尽くしている一花の分析が始まった。
「その結婚、幸せだと思う?そういうのってすぐに限界が来るよ。子ども産んだら特に。子どもが出てきたらもう相手できないもん。赤ちゃんってホント大変なんだから。」
「でも好きな人と一緒になったんだから幸せなんじゃない?ソウルメイトと結婚できるの羨ましいよ。」
と、この結婚の衝撃がおさまっている私は言った。
「好きな人だって好きじゃない人になるんだから。」
一花は自分のことを言っている。
「結婚すると彼氏じゃなくなるって言うもんね。」
というお琴の言葉のあとは沈黙になった。
結婚したら楽しくって幸せで喜びに満ちて生きていけると思ってるけど、現実はどうなんだろう。結婚したことがないから、結婚したらどうなっちゃうのかなんて全く分からない。
結婚していた一花からは、結婚が楽しかったなんて一度も聞いたことがない。でもまたしようとしてる。
結婚したくて婚活してるけど、「結婚って何なんだろ?」とふと我に返る時がある。
どうして結婚したいの?本当にしたいの?
と、自分へ問いかけても歯切れのいい答えは出てこない。
3 結婚したい女たち プロローグ
沈黙を破るように一花が言った。
「今日のお琴、なんか違うよね。メイク変えた?」
一花と香にじーっと顔を見られたお琴は、気付いてくれてありがとう!と心の中で喜びの声を上げた。
「わかる?カラー診断へ行ってきた。」
嬉しそうなお琴を一花と香は益々じーっと見つめた。
「イエベのスプリングだって言われて、メイク一式買っちゃった。そんなに見ないでよ。はずいじゃん。」
「いいね。合ってる。カラー診断っていいね。」
好きな色を身に着けるのが常識。パーソナルカラーなんててんで興味のない一花にしては珍しい言葉だった。
「かわいい。いつもより可愛らしいよ。」
一花に続いて香からも褒められて、お琴は飛び上がりたいくらいに嬉しかった。一花はもちろん、香も決してお世辞を言わない。その二人からこんな風に言われるなんて。今夜は嬉しくて泣くかもしれない。カラー診断に言ってよかったと、胸がジーンとした。
一花は名前のとおり一輪の花が咲いているかのように、すらりとした体に小さな顔がちょこんと乗っている。癖のない整った顔立ちは、汗でも取れないメイクがいつでも施されている。
香はふんわり柔らかな印象の色白のかわいこちゃんだ。同じ年とは思えないほど肌艶がいい。さすが東京で働いていたと思わされるほど、メイクも服もお琴にはどこに売っているのかさえ見当もつかないくらい洗練されている。
そんな二人と女子会をするたびに、自分はなんてダサい女なんだと思わされていた。
えらのはった大きな顔。くびれのない寸胴体型。どうしたってかわいくなんてなれない。でもどうにかしたい。専門家ならどうにかしてくれるだろうと、意を決してカラー診断へ行ってきたのだ。
「オータムの色が好きなんだけど、明るいスプリングの色の方が似合うって言われて。勇気出してつけてみた。」
照れながらもお琴は満面の笑みで言った。
「服も替えた方がいいって言われて。上の服だけスプリングにするのでいいらしくって。これも買っちゃった。」
お琴は明るい萌黄色のシャツをつついた。
いつもくすんだ色の服を着ていて同じ年とは思えない貫録を醸し出していたお琴が、今日はあか抜けている。その変身ぶりに香は思わず言った。
「すごい似合ってる。いいなあ。私もカラー診断してもらおっかな。」
「しなくていい!」
「しなくていい!」
お琴と一花が声をそろえて言った。
「え?なんで?」
キョトンとする香に一花が言った。
「香はパーソナルカラーをつけてるよ。ね。」
と、お琴に賛同を促す。
「うん。そうだと思うよ。一花もそうだと思う。二人とも合う色が好きなんだと思うよ。」
決して二人がこれ以上かわいくなるのを邪魔しようとかそういうことじゃなくて、お琴は本当にそう思っている。
「一花は合ってるよね。いつもピッタリ。ビビットな色、似合うよね。」
自分のことはさておき、香も一花の個性的な色使いは一花という女をうまくバックアップしていると思っている。
「一花はウインターだと思うよ。濃い紫とかピンク、好きでしょ。香はサマーじゃないかな。水色好きでしょ。淡い色が似合うから。」
「へー、そうなんだ。」
一度カラー診断へ行っただけでもうカラーセラピスト並みの知識を披露できるお琴に香は純粋に感心した。
香は東京にいた頃どれだけデパコスへ通ったか。毎月通っていたのにビューティーアドバイザーさんに任せっきりで、人に説明できるほどわかっていない。
「あとね、骨格診断て言うのもあってね。今度それを行こうと思ってる。」
「あ、それ知ってる。」
一花がこの話題に飛びついた。
「お琴はストレートだと思うな。香はウエーブ。私はナチュラル。」
「へー、そうなんだ。」
ヨガインストラクターだけあって、一花は骨格に詳しい。雑誌でみかける診断だけど、自分がどれなのかさえわからない香は、さらりと診断してくれる一花も尊敬せざるを得ない。
知識や経験を存分に披露できる二人といると、香は何もできない女の気分になる。
「私たち全然違うね。カラーも骨格も、バラバラ。」
と、内心自虐的に香が笑った。そんな香の心も知らず、
「ほんとだ。」
と、お琴と一花も笑った。
4 結婚したい女たち 出会い
体型もパーソナルカラーも性格も、何もかもが違うけれど、一緒にいると楽しくて仕方がない。お琴は一花と香とランチを食べながら話すこの時間が、自分の中でとても大きくなっていることに気づいていた。月一、多い時は隔週で会ってしまう。もちろん招集するのはお琴だ。
大人になってからこんなに仲のいい友だちが出来るなんて、なんてラッキーなんだと、婚活をしていてよかったなどと思ってしまう。と言うのも、この三人が出会ったのは婚活パーティーでだった。
運命の男に出会おうと気合いを入れて参加したのだけど、運命の女に出会ってしまった。
最初は一花だった。
あれは二年前。コロナの前で二十八歳だった。三十歳までに結婚したくて、パーティーがあれば何でも参加していた。そのパーティーに、いつもいる女がいた。人目をひくモデル体型に小ぶりな顔で、姿勢がよくて動きも美しかった。
最初は嫌だった。男の人たちの視線が一斉に注がれるのだから。そういう人がいるだけで、体型にも顔にも自信のないお琴は負けた感に襲われて帰りたくなってしまう。
ところがその女といつも帰りのエレベーターで一緒になるのだ。
お琴はいいなと思う男がいなければ、最後のカップリングタイムの番号を書かない。終わった瞬間、さっさと会場を出る。すると同じように出てくる女がいて、エレベーターに乗り込んでくる。それがあの美女だった。
最初は「へー、こんな人でもカップリングできないんだ。」と驚いた。でも何度も会ううちに、私と同じなのかもと思うようになった。
男をじっくり選んでいる。
めぼしい人がいなくても「とりあえず」の発想で番号を書いたりしない。思いどおりの人に出会うまで妥協することがないのだ。
三回目にエレベーターの中でどちらともなく、
「また会ったね。」
と笑った。そして、
「お茶する?」
と、カフェで話し込んだ。
一花はバツイチだった。早くに結婚して子どもも産んだと言われて動揺したけど、子どもは育てていなかった。離婚の時にもらったマンションに住んでいて、ヨガのインストラクターをしていると言う。同じ年でこうも違うものかと、自分の人生は薄っぺらいなと思った。
両親が共に学校の先生をしているお琴は、当然学校の先生になるもんだと子どもの頃から思っていて、実際そうなった。本当になりたかったのかと疑問に思うくらい、何も考えずに教師の道を歩き出した。
子どもは好きだしお給料もいいし、仕事に不満があるわけではないけど、どこか満たされない思いがある。それを表すかのように、自分には不似合いな大きな車を買ってしまった。
そんなお琴には、好きなヨガを教えている一花は輝いて見えた。
一花と友だちになってからは、婚活パーティーへ行くのが別の意味で楽しみになった。終わったら一花とお茶しながら話せる。コロナが始まっても積極的にパーティーへ参加するのは、一花に会いたいから。
これぞ本末転倒。
そんな自分を笑いながらパーティーの予約を入れていた。
ところが今年の初めのパーティーに、初めて一花を見た時のような気分にさせる女がいた。
マスクをしていても笑っているように見える、苦しんだことなんて一度もありませんと言っているかのような、かわいい女だった。
男性だけじゃない。女性たちからも注目の的になっているのに、そんなことには気付いていないかのように、ほわんとしたままなのだ。
(こんな子、婚活しなくても結婚できるだろ!)
とお琴は思った。
そして一花と目を合わせてため息をついた。今日の一花との話は長くなりそうだ。バーで飲みながら話したいけど、開いているお店はあるだろうか。そんなことを考えていたのに、パーティーの最後に、おや?と思った。
その女が、最後のカップリングタイムに早々と帰り支度をしているのだ。これはまさか、と一花と目を合わせた。
案の定、帰りのエレベーターで一緒になった。うつむいたままのその女に、一花が声をかけた。
「はじめて?」
「え?はい、そうです。」
「私たち去年からやっててさ。これからお茶行くけど、来る?」
「え・・いいんですか?行きます。」
声もかわいいその子は、マスクをとってもやっぱりかわいかった。丸い大きな目に、ぷっくりとした小さな唇。そして「香」という名まえどおりいい香りがした。
神様はなんて不公平なんだと思わされた。
でも話を聞くと神様はやっぱり公平かもしれないと思った。病気の母親の看病のために仕事を辞めて実家に戻ってきたと言うのだ。
「若いのに大変だね。」
と同情したお琴に、
「そんなに若くないですよ。だから婚活も頑張ろうと思ってて。」
と、なんと同い年だった。お琴と同じように三十歳までに結婚したくて婚活を始めたと言う。
「今ずっと家にいるから、出会いが欲しくて。」
「リモートでもできるの、知ってる?」
母の看病というあたりから、やけに一花が香に話しかけるようになった。
「うん。でもリモートがいいって言うと、できないっていう男の人がけっこういて。」
「だねだね。もうコロナも二年目なのに。この時代にリモートできないって公言できるの、ある意味スゴイと思うよ。」
お琴も移動時間のいらないリモート婚活に力を入れているが、あまり活発には出来ていない。
その日は「あ、もう帰らなくちゃ。」と夕飯の支度のある香に合わせて、すぐお開きになった。一花と二人残って駄弁ろうかと思ったお琴だったけど、いつもは帰りたがらない一花が腰を上げたから、大人しく店を出た。
冷たい空気に顔がピリリと引き締まった。でもお琴の心は熱かった。新しい仲間ができてこれからもっと楽しくなるような予感がしたから。
今年三十歳を迎える女三人は、こうして出会ったのだった。
5 結婚したい女たち 一花の憂鬱
「いつにしよっかな。」
一花は自宅マンションのリビングでスケジュール帳をめくった。結婚していた当時のままの三人掛けの大きなソファ。その上に足も上げて座り込み、膝の上に手帳を置いてウキウキと山登りの日程を立てていた。
「新月満月の三日間は避けて・・。今月の祝日がいいかな。」
お琴が賛成してくれるのはわかっていた。香が難しいかと思っていたけど、まさか富士山に登っていたなんて。運動なんてしなさそうに見えるのに、今日だってビックリしたけど自転車で来たって言うし。
「ママチャリだから恥ずかしいんだけど。天気が良かったから。」
と、大きなカゴが前にも後ろにもついた自転車で、ランチのパスタ屋に来た。
「買い物とかゴミ出しで乗ってるんだけど、前にスーパーの駐車場で『おかあさん』って呼ばれてさ。失礼だよね。どう反応していいかわかんなくて困ったよ。」
それを聞いてお琴はゲラゲラ笑った。
「『はーい!』って返事しとけばいいよ。」
「やだよ。子どもを乗せるのはついてないのにさ。」
プーと顔を膨らませながらも、香はその自転車で帰って行った。その後ろ姿は「おかあさん」にしか見えなくて、一花もお琴につられてゲラゲラ笑った。
あの二人といるとお腹の底から笑える。思い出して一花はまた笑った。
まずは私が登った山へ連れて行こう。お琴は心配ないけど、やっぱり香が気になる。なだらかで歩きやすかったし、分岐も少なかったから迷うこともないだろう。一度登ってるから案内できるし。
来年はもう少し高い山へ登りたい。できれば一花も富士山にチャレンジしたい。あの二人と登ればきっとご来光を拝めるはずだ。
この夏のバーベキューでもそうだった。天気予報で台風直撃と言っていたからダメかと思っていたら、当日は嘘のような晴天だった。
「晴れ女の香がいるからだ。」
と言ってお琴が笑った。
「私も雨降るときあるよー。」
と言う香だったけど、仕事で沖縄に行った時も台風直撃のはずが逸れて快晴だったことがあった。
一花はすぐに「次の祝日にどう?」と二人にlineを打った。そして、五つも持っているSNSのアカウントを次々とチェックしていった。それに加えてヨガの生徒さんから誘われたオンラインサロンにも参加している一花は、毎日スマホに忙しい。
この部屋にいる時はほとんどスマホを見ている。まるでスマホの中に住んでいるように。でもその方がいい。結婚していた時から住んでいるこの部屋は、そこら中に思い出が散らばっている。
家具はそのまま使っているし、かなり捨てたけどまだ自分のじゃないモノが出てくる時もある。以前の生活を思い出したくない一花は、なるべく部屋にはいないようにしている。朝ヨガと夜ヨガの担当にしてもらって、一日中スタジオにいる。寝る時だけ家に帰るような生活だ。それでもコロナで外出がしにくくなって家にいる時間が増えてしまった。
そんな時間を潰したくて、生まれつき勤勉な一花はどんな生徒さんともコミュニケーションが取れるようにと、スマホで情報収集をしていた。だけど今は中毒とも言えるほどに情報収集で一日が終わってしまう。
でもそんな自分を一花は好きだった。頑張って勉強すればするほど、自分らしくいられるような気がするから。亡くなったママが褒めてくれるような気がするから。
一花は生まれつき父親がいなかった。私生児だった。母が一人で育ててくれたのだ。一花を育てるために働いて働いて、働き続ける母を少しでも喜ばせたくて一花は勉強した。いい成績を取ると、
「一花ちゃん、すごいわ。」
とママがうれしそうに笑った。その笑顔で一花はもっと勉強した。
「一花ちゃんの頭はあの人に似たのね。」
ママが父親の話をしたのはその時だけだった。
高校生になると一花はバイトもした。少しでもママを助けたくて。そんな時によくしてくれた先生がいた。何かイベントがあると、その整理係のバイトを教えてくれた。変なバイトをしてしまわないかと心配してのことだったらしい。自治体や予備校関係の安全なバイトをするように導いてくれていた。
「ちょっと古いけど。」
と卒業生が置いていった問題集をくれることもあった。
お琴といると、あの先生を思い出す。親身になって励ましてくれる雰囲気がよく似ている。ヨガインストラクターとしての独立も、
「ヨガって今ネットでレッスンしてるんでしょ。だったら自分でやっちゃえば?一花なら人気Youtuberになれるよ。」
と、お琴が言い出したことだ。
2LDKのこのマンションは一部屋空いている。その部屋でヨガのレッスンをオンラインでするのもいいと、一花も考えた。でもそうするとここに一日中いることになる。それはまだ精神的に辛い。今のように早朝からスタジオへ行って、そこでオンラインレッスンをするのがいい。
でも独立も夢見てしまう。
そんな時に仲良くしてもらっている生徒さんから「プライベートレッスン」の言葉が出て、夢が現実味を帯びてきた。
6 結婚したい女たち 一花の憂鬱
ぶるるっ。
一花のスマホが鳴った。お琴からの返信だった。
コロナで学校の遠足も運動会も中止になったお琴には、突然の一花からの山登りの提案がちょうどよかった。ノリノリで「その山の近くに天然酵母のおいしいパン屋があるから寄りたい!」と打ち返して来た。
そんな返事に一花はクスリと笑った。どれだけ美味しい食べ物屋さんを知ってるのよ。
笑いながらも、そうやってお琴に連れられて外食するのは一花の楽しみでもあった。外食なんて幼少時からほとんどしたことがなかった。それがお琴と友だちになってからは、毎月どこかのお店で食べるようになった。
そのどのお店も生徒さんたちに自信を持ってお勧めできるところばかりだ。こういう情報も生徒さんたちはすごく喜ぶから、そういうことに疎い一花はとても助かっている。
ただ、会うたびに色んな情報をくれるお琴と話すと、もっと私も情報を持っていなくちゃと、スマホ活動に力が入るのも事実だ。
高校の先生が良くしてくれたのは、私の生まれ育ちに同情したからじゃない。あれは私の成績が良かったからだ。私のような境遇の生徒、離婚して片親とか親がほぼ無職とか色んな生徒がいたけど、先生が目をかけるのは成績上位の生徒だけだ。私のような家庭環境だと、成績が良くなかったら逆の意味で目をつけられてしまう。それがわかっていたから必死に勉強した。
お琴といると、そのことも思い出してしまう。頑張り続けないと仲良くしてもらえなくなるかもしれない。なるべく私も知っていることを話すようにして、お琴と釣り合えるようにしていなきゃ。そんな思いでスマホをいじくりまわしてもいた。
その夜の瞑想は穏やかだった。
朝晩の瞑想は一花の大切な日課だ。毎日していても毎回違う。二人と会う日の瞑想は気持ちいい。特に会った日の夜の瞑想は、ママが生きていた時のような安心感を感じられる。まるでママが側にいるような気持ちで座れるのだ。
瞑想と言えば、
「たった三十分喋っただけなのに、あんなにむかつくことばっか言える人間がいるなんて信じられる?あれから一週間たつけど、まだ腹の虫がおさまんない。思い出しちゃって夜眠れないよ。」
と、お琴が婚活で会った男が本当にむかついたと怒っていた時に、
「瞑想したら?」
と勧めてみたことがある。
「瞑想?」
「マインドフルネス。寝る前にすると落ち着くよ。」
「どうやってするの?」
「リラックスして座って、呼吸に集中するだけ。簡単にできるよ。」
「一花、やってるの?」
「朝と夜にやってる。スッキリするよ。今やってみる?」
「やるやる。」
それで三人は二分間目をつぶった。
「どうだった?」
と一花がきくと、
「二分って長いね。あの男のことじゃなくて、学校の子どもたちのことがあれこれ出て来た。んで、このあとのデザートをどのケーキにしようかって考えちゃった。」
「香は?」
「んー、呼吸がわかんなかった。わたし息してないのかと思った。」
「なにそれ、ウケる!」
とお琴が爆笑した。
「でも前にした時よりは集中できたかも。目をつぶったからかな。」
「え?!瞑想したことあるの?」
悩んだことなんてありません!て感じの香がどうして瞑想をするのよと、一花は驚いた。
「うん。友だちに誘われて座禅会へ行ったの。あの時は目を開けたままだったよ。壁に向かって座ってね、床をじっと見続けるの。何なのかよくわかんないまま終わっちゃった。」
「続けるとわかるようになると思うよ。」
と言いながらも、一花は香が瞑想で地獄を見ることなんてないんだろうなと思った。
一花は瞑想を始めた頃、座るたびに結婚していたころのことが津波のように思い出されて号泣することがあった。それでも座り続けていたら同じことを思い出しても辛くならなくなった。調子のいい時は微笑むママが出てくるようにさえなった。
瞑想なんてしなくても幸せそうな香は、瞑想で何を見るんだろう?
香は今でも謎が多い。
東京で何の仕事をしていたのかも知らない。お琴が尋ねたことがあったけど、「派遣で働いてた」としか言わなかった。そのうち話してくれるだろうか。
そして私も二人に話すんだろうか。私生児だったことを。ママも死んで天涯孤独の身であることを。
その日が来るのを期待している自分に、一花は気づいていた。
7 結婚したい女たち ~ 香の苦悩 ~
家中の掃除機をかけ終った香は自室へ戻った。お昼ご飯の準備まで二時間ある。その間は自分の時間を楽しめる。香はウキウキと水引を取り出した。一花からオーダーをもらったピアスを作るのだ。
病気の母の代わりに実家で家事をしている香は、家事の合間に水引アクセサリーを作っている。と言っても、水引デザイナーになりたいわけではない。ただの趣味だ。
きっかけは、貰いモノの和菓子の詰め合わせについていた水引の飾りだった。縦にあわじ結びを連続で編んだもので、このままブックマークとして使えると書いてあった。それを見た香は思った。
(これって私でも作れる。)
すぐに部屋へ戻り、クローゼットの中に置きっぱなしの段ボール箱から水引を取り出した。それは、東京で水引アクセサリーのワークショップへ行った時にもらってきた水引だった。
(たしか作り方の紙もあったはず・・。)
ごそごそと箱の中をあさると、あった。ワークショップの先生がくれた、あわじ結びと梅結びの編み方が書いてある紙だった。
さっそくブックマークを作ってみた。あっという間にできた。
(たしかあれもあるはず・・。)
香はまた段ボールをあさった。取り出したのは小さな瓶。中には半透明の色鮮やかなビーズが入っていた。それは結衣ちゃんに連れられて行ったビーズアクセサリーのワークショップでもらったビーズだった。
水色の水引で作ったブックマークに同じく水色のビーズをつけてみた。
(うわ!)
香の顔が輝いた。
(私にも作れた!)
仕事を辞めて住んでいたマンションも引き払い、実家で家事をする毎日は最初は忙しくて大変だった。働いていた時の方がどれほど楽だったか。
家事ってこんなに大変なんだと認識を改めると同時に、主婦ってすごいなと思った。働きながら主婦もしている人のすごさも初めて知った。
くたくたになって寝ても、夜中に母が騒ぎ出すこともあった。母は癌で闘病中なのだが、闘病の影響なのか精神が不安定になってしまった。
突然わめき立てて手が付けられなくなることもある。
そんな状態だから日中母を一人にしておけない。頼むから母の看護をしてほしいと父に呼び戻されたのだ。
しかしそれは看護と言うより、監視。
そして監視と言うよりは忍耐だった。
まさに二十四時間の耐久戦。長距離走が大の苦手だった香に我慢しながら続けるなんて、耐え難い苦痛だった。
そんな終わりのないストレスを抱えての生活だったけど、家事には少しずつ慣れてきた。母の状態も同じ部屋にいなくてもいいくらいに調子がいい。それで自分の時間が持てるようになった。
そんな時に目覚めた水引アクセサリー。これがマラソンの給水ポイントのようにいい気分転換になる。
自分で作ったブックマークを見ていたら、ブレスレットにしたくなった。ブックマークを手首に巻き付けてみた。
(かわい!)
急いでピンクの水引でブレスレットも作ってみた。でも円で閉じてしまうと着脱が難しくなってしまう。
(たしかあれがあるはず・・。)
またまた段ボールの中をあさってみると、あった!
マルカン、マグネット式の留め具、やっとこ。アクセサリーを作るための道具はそろっていた。
水引の両サイドに留め具を取りつけた。
(私にも作れた!)
シンプルなのが素朴でかわいい。しかも紙素材で軽いからつけていても気にならない。忙しく家事をする時につけていても邪魔にならない。
そこから香は水引で作るアクササリーにハマった。ピアスに指輪。思いつくものを次々と作るようになった。
世界で一つだけのアクセサリーができるたびに、香は宝物を手に入れたような気分になった。
しかし、自分がつけるには限界がある。誰かにあげたい。
最初は母にあげた。母は見るなりこう言った。
「売りなさいよ!」
そんな母に香はこう言った。
「こんなの誰が買うの?誰でも作れるよ。」
毎日コツコツアクセサリーを作る香に、父も言った。
「売れ!」
そんな父に香はこう言った。
「水引を教えてくれた先生でさえ、『売れない』って言ってたんだよ。私の作ったものなんて誰も買わないよ。」
売らなくても誰かにはあげたい。「あげたい」は「作りたい」と同じだから。それで友だちになった一花とお琴にあげた。そしたら
「売りなよ!」
と、お琴が両親と同じことを言った。そんなお琴に香はやっぱりこう言った。
「こんなの誰でも作れるよ。買う人いるかな?」
「わたし作れないから。作れない人は買うよ。」
お琴の言葉に「なるほど」と思った香は、ネットで売ってみようとその気になった。でもネットで水引アクセサリーなんていくらでも売られていた。
同じようなものだけじゃない。もっとデザインがステキなものもたくさんある。それを知っただけで香は萎えた。
(私のなんて・・。)
売り出しても、それこそ二十四時間注文を受け付けて、もし注文が来たらすぐに送りに行かなきゃいけないし。
(めんどくさそう・・。)
そうやって香はすぐに諦めた。
作るのは楽しい。だけど「売る」ことまではしない。何が自分にブレーキをかけるのか。それさえ考えようともせずに、香はただこう思っていた。
好きなことを仕事にしている一花はステキだ、羨ましい。と。
8 結婚したい女たち ~ 香の苦悩 ~
いつでも背筋がシャンと伸びた一花は、言葉も真っ直ぐだ。ズバズバモノを言うからきつい性格かと思ったけど、言ったあとにこちらの心情を配慮したことも言うから、正直で誠実という印象がある。
ひっつめてきれいにまとめた髪のように、一花が乱れるとこなんて見たこともない。
(どうして離婚したんだろ?
不思議でたまらない。
男の人にはわがままを言うのかな?)
一花が男に甘えているところなんて想像できない。そのくらい一花は自立した発言が多い。そして頭もすこぶるいい。出身高校が県下一の進学校だし、国立の大学へ行って大手企業で働いていたそうだ。そんな会社なら産休制度も充実しているはずなのに、妊娠して辞めちゃうなんて。
「もったいないことしちゃったね。」
と香が言ったら、
「・・・。でもそのおかげでヨガに会えた。」
仕事がなくて子どもも取られちゃって、何もない状態から一花はヨガという天職を手に入れていた。
「ふう。」
香はため息をついた。仕事を辞めたのは香も同じ。でもヨガで輝く一花と違って香には何もない。
くすぶる心に気が重くなる。その時、飼い猫のミーちゃんが鳴いた。
「みー。」
かわいい声に我に返った香が見たのは、今まさに愛読書のアネモネ最新号に爪を立てようとしているミーちゃんだった。
「ミーちゃん。だめ!それはまだ読んでないの!」
慌ててミーちゃんを抱き上げた。
「爪、伸びて来てまちゅね。切りまちゅね。」
香はミーちゃんを膝の上にのせてパチンパチンと切り始めた。
こうやってミーちゃんの世話をするのは、水引でアクセサリーを作っている時とはまた違った幸福の時間だった。
ミーちゃんとの出会いは運命的だった。
香は東京でイベント会社へ派遣されて働いていた。あるイベントの前日、準備に追われて帰りが遅くなった。くたくたに疲れて重い体を引きずるように歩いていたら、
「みー。」
と、か細い声が聞こえた。声の方を見上げるとブロック塀の上に子猫がいた。満月を背にこちらを見ているその猫は、純白に輝いていた。
思わず見惚れた香の手はその猫へと自然に伸びた。「おいで。」と話しかけても逃げない。両手でその小さな体をつかんだ。やっぱり逃げない。
(野良猫かな?それにしては大人しい。飼い猫?でも首輪も何もつけてない。)
胸の中で心地よさそうに抱かれる子猫を見ていたら、疲れなんて吹っ飛んだ。そしてそのまま連れて帰った。
(飼われているならいなくなるだろう。)
そう思って、仕事へ行く時にベランダへ出しておいた。でも夜家に帰ると子猫はベランダにいた。
「みーちゃん。」
子猫の鳴き声をそのまま名まえにした。名まえをつけると益々かわいくなった。家に帰るのが楽しくなったし、夜はミーちゃんと散歩をするようになった。お休みの日にはミーちゃんを連れて公園やカフェへ行くようにもなった。
「わー、かわいい!」
猫好きな人がミーちゃんを見てそういうと、香は嬉しくてたまらなかった。次第にミーちゃんを見せびらかせたくて、出かけるようになった。かわいい服を着せて一緒にお出かけするのが楽しくて仕方なかった。そしてこんなふうに思うようになった。
(ミーちゃんが赤ちゃんだったら・・。)
そうだったらどんなにいいかと思うようになっていた。そして今ではその思いが婚活に力を入れさせる。
「髪、切ろっかな。」
ミーちゃんの美しい白い毛をブラッシングしながら、ふと香はそう思った。
お琴の変身ぶりはすごかった。メイクや服の色を変えただけで、あんなに雰囲気が変わるなんて。少し疲れた雰囲気のあったお琴が、華やかな明るい印象に変わっていた。
(私も変わりたい。)
肩より下まで伸びた髪。東京にいた頃は肩ぐらいの長さをキープしていた。それが今は伸びっぱなしになっている。
あしたの朝一に行けばお昼前に帰って来れる。香はすぐにヘアサロンに予約を入れた。
次に会うのは山登りでかな。二人とも驚くかな?ふふ。楽しみ!
こうやっていい刺激をくれる友だちが香は大好きだ。頑張ってキラキラ輝いているのを見ると、香も何かしたくなる。東京にいた時は結衣ちゃんがそうだった。
結衣ちゃんとは仕事で出会って友だちになった。二つ年上の結衣ちゃんは、香のように派遣で働いていた。でも香と違ってあえて派遣で働いていた。
「私ね、推しのために生きてるの。」
結衣ちゃんは男性アイドルグループの一人にハマっていた。その推しのコンサートツアーがあると、全公演を観に行くのだ。推しと同じホテルに泊まって、日本各地を回るのが結衣ちゃんの生きる理由になっていた。
テレビも見ない、アイドルも知らない香には目が点になる話だった。でも推しのために努力を欠かさない結衣ちゃんは輝いて見えた。
手作りアクセサリーも、結衣ちゃんは推しのために挑戦した。推しが「夜空のようで好きだ。」と言っている天然石、ラピスラズリ。それを使ったブレスレット、指輪、ピアスの三点セットをプレゼントしたいと言って、ワークショップへ作りに行ったのだ。先生はとても親切で、結衣ちゃんの思いに応えて推しのイメージに合ったデザインまでしてくれた。
細かい手作業が苦手な結衣ちゃんは、ワークショップの時間内に作れないこともあった。そんな時は一人で出直して作りに行っていた。
元々手先の器用な香は、どれもすんなり作れた。ワークショップの時間が余るほどに、あっという間に作ってしまえた。結衣ちゃんに申し訳なくて
「手伝おうか?」と声をかけたけど、
「自分で作りたいの。」と四苦八苦しながら作っていた。
そんな推しのために頑張る結衣ちゃんの姿に、香は大いに刺激を受けた。
(私も頑張ろ!)
そう思ってアクセサリー作りの道具を一式そろえた。でも一つ二つ作ったところで飽きてやめてしまった。
そうするとまた結衣ちゃんから誘いがかかるのだ。
「推しがやったって言うの。私もやってみたいの。一緒に行かない?」
と、座禅会へも行った。座禅は何をやっているのかさっぱりわからずに終わってしまった。でもお坊さんの話はとてもよかった。
世間の価値観とはズレていても、自分の価値観に従ってコツコツと続けることが大切だと、大リーガーのイチローを例に挙げて噛み砕いて話してくれた。それを聞いていたら、まるで結衣ちゃんのことじゃないかと思った。
休みの日と言えば、部屋で映画を観て一日が終わってしまう自分が情けなくなった。
(結衣ちゃんのようになりたい。)
そう思った香は、水引のワークショップへ行った。結衣ちゃんに誘われたわけでもなく、初めて一人で行ってきた。水引が好きだったわけではない。休みの日の朝に予約を入れられるのが、たまたま水引だったと言うだけだった。それでも香にとっては記念すべき自発的なワークショップ体験だった。
これも器用な香には難なく作れた。先生も「あぁ、らく♡」と、一度説明したらサッと作ってしまえる香にご機嫌だった。褒めてくれる先生に気を良くした香は、家でも作ろうと、たくさんの水引を買って帰った。
そしていくつか作ったのだけど、やっぱり飽きてやめてしまった。
香のこの飽きっぽさは男にも同じだった。
9 結婚したい女たち ~ 香の苦悩 ~
しかし香の男運のなさは、その飽きっぽさによるだけではなかった。
最近また始めたミーちゃんとの夜の散歩。この散歩の時、香は男性用のジャージを着る。夜ということもあって防犯のために、メンズのジャージにワークキャップをかぶるようにしている。この格好だと驚くほど誰も香を見ない。普段知らない人からじろじろ見られる香には、誰からも見られないのは新鮮だし、安心感が半端ない。
イスラムの女性がブルカをつけている時、もしかしたらこの安心感を味わっているのかも。
そんなことを思ったりしながら、香はこの格好で好きなだけ夜の東京を歩き回ったものだ。
しかもこの男物のジャージがベランダに干してあると防犯になる。香は東京でそうやって生きていた。
「何見てるんですか?」
ミーちゃんがかわいくて仕方ない香は、会社でもミーちゃんの写メを眺めてにやついていた。そんな香に三歳下の同僚が上目使いで訊いてきた。
「猫。」
「え?猫飼ってるんですか?」
「うん。拾ったの。見る?」
香の思惑どおり「かわいい!」とべた褒めしてくれた。すっかり気を良くした香に、「ミーちゃんを見たい、家に行っていいか。」と言ってきた。たいして仲も良くないし、家に来られるのは嫌だと思ったけれど、なんともしつこかった。毎日顔を合わせるたびに、見に行きたいとねだって来るのだ。
あまりにしつこいから「いいよ。」と言ってしまった。そしてその女子が休日、家に来た。
実物のミーちゃんを見て、「うわー、かわいい!!」と喜んでくれたから満足した香だったが、実はこの女、目的はミーちゃんじゃなかった。
この頃、香は毎週末実家に帰るようにしていた。母親が病気になってから実家の状態はひどかった。掃除もされずにぐちゃぐちゃ。父親も精神的にまいっている感じだったので、香は掃除をしたり食事を作ったり、家事をしに実家へ帰るようにしていた。
金曜日の夜に行って、日曜の夜に東京に戻ってくるのを繰り返していた。でもイベントが近づくと週末も仕事で帰れなかった。そんな時は少しホッとした。実家へ帰るより東京で働いていた方が、体も心も楽だったから。
それでも次第に疲れがたまって来た香は、いつも眠そうにしていることが多くなった。そんな香を、会社の人たちは彼氏ができて忙しいのだと勘違いした。写メを見てにやついたりしていたから、ますます男がいると思われていたのだ。
そんな中、この女は香の男を確認しに来たのだ。案の定、ベランダには男性用のジャージが干してあった。
ビンゴ!
すっかり男がいると思い込んだその女は、香にこう言った。
「わたしケント君は運命の人だと思ってるんです。ソウルメイトだとしか思えないんですよ。」
ケント君は前のイベントで一緒に仕事をした人で、2歳年下の長身のイケメンだ。実は先日ケントに誘われて、香は米津玄師のライブへ行ってきた。いい感じの雰囲気で楽しかったのだけれど・・。
「そうなんだ・・。いいね、ソウルメイトに出会えて。」
香は自然とそう言った。張り合う気なんて起こらない。「どうぞ。」と欲しがる人には与えてしまう。
そしてケントからの連絡は来なくなった。そしてなんとなんと、二人は結婚したのだった。
10 結婚したい女たち ~ お琴の不都合な現実~
勤務先の小学校から二㎞離れた場所で、田んぼの隣にあるアパートにお琴は住んでいた。学校で子どもたちとの騒がしい時間を過ごしても、この静かな部屋が疲れをいやしてくれる。
お琴は一年中出しっぱなしのリビングのコタツに座っていた。そして天然酵母パンをお皿いっぱいに乗せて、Youtubeを開いた。
以前なら食べながらゲームをしていた。家にいる時は大概オンラインゲームをして過ごしていたのだ。でもある時、オンラインゲーム中にリクが言った。
「オレ、結婚することになったから。」
突然の言葉にお琴は固まった。でも自分の手とは思えないほどに素早く、
「そっか。おめでと!」
と打っていた。
リクとは大学生の頃に付き合っていた。卒業してお互い赴任先の学校で忙しく働き始めたら、次第に会わなくなった。でもオンラインゲームでは会っていた。付き合っていたころと変わらずゲーム仲間のままだった。
どちらも会おうと言い出さないから、もう付き合ってはいないのだと思ってはいた。そしてあの日、突然リクが結婚すると言ってきた。
顔が見えなくて、声も聞こえなくてよかった。お琴はそのあと泣きながらプレイした。
リクが来なくなったらゲームはつまらなくなった。それでやっと気づいたのだ。リクと繋がっていたくてゲームをしていたのだと。
傷心のお琴になんの因果か、追い打ちをかけるように一つ下の弟も来月結婚するとLINEが来た。
(男たちに先を越されるなんて・・。)
お琴は何が何でも自分も結婚してやる!と一念発起、婚活を始めたのだった。
ゲームをしていた時間はお笑いの動画を見るようになった。食べたいものを食べたいだけ食べながら。
でも今は違う。一花と香と出会っておしゃれに目覚めたお琴は、美容チャンネルを見るようになった。食べたいものを食べたいだけ食べながら。
食べることはやめられなかった。
動画を見ていればキレイになれるような気がしていたのだ。
そして今夜もメイク動画を見ながらパンを食べていた。
一花の化粧は今日も崩れなかった。今日は一花と香と山に登ってきた。ウオータープルーフを使っているらしいけど、それにしても崩れない。一花の顔がべたつくとこなんて見たこともない。汗もかいていなかったし。やっぱり根本的に体が違うのだろうか。
そう言えば山頂でパンを食べた時、一花も香もほとんど食べていなかった。一花は水をたくさん飲んでいたっけ。香はどうだったかな・・。
お琴は思い出そうとしたけど、パンがおいしかったことしか思い出せない。おいしくて三つも食べた。そうだ、香がひとつくれたんだ。
(香は食べたのかな・・?)
予告なくショートカットで現れた香。髪を切ったらますます幼く見えた。香のことを考えていたら、お琴はぷっと吹き出してしまった。あれを思い出したのだ。
三人で下っていた時、登って来たおじさんが香の耳元で「今日はいい天気でよかったねー。」とささやくように言った。そしたら香が「おえー!」と言ったのだ。
気持ち悪かったのだろう。それはわかる。でもだからって、そんな反応をしておじさんが気分を害すとか、そういうことを何も考えない香。
一花は固まった。お琴は笑うしかなかった。
「香!それはダメだって!」
「だってー。」
お琴は笑いながらも、小学生の子どものように素のままでいられる香をスゴイと思った。
そして今日はそれだけじゃなかった。もっと驚いたことがあった。
秋晴れの広い空の下、山頂で景色を楽しんでいたら外国人の登山者に話しかけられた。何を言っているのか分からず「どうしよう・・。」と一花と顔を見合わせていたら、なんと香が答えたのだ。
ビックリして一花と二人で固まった。
しばらく香と話していたその外国人は、
「Thank you very much!▽□×○△××!」
と言って、手を振りながら去っていった。
「なになに?なんて言ってたの?ていうか、香、英語話せんの?!」
「うん。トイレどこ?って。最後は邪魔してごめんね、景色楽しんでねって言ってた。」
香はイギリスの高校と大学へ行ってたそうだ。
「お父さんの仕事で海外へ?」
「ううん。外国に住みたくてホームステイで。」
東京に一人で住んでいたことだけでも信じられないのに、外国へ一人で行ってたなんて。
そんな香の意外な一面を知ったお琴は、ある生徒のことを思い出した。
小学校五年生のその子は、いつもボーっとしている子だった。五年生にもなると多くの子どもたちは大人のように振る舞い始める。友だちの世話をしたり、ルールを気にしたり、周りの人に合わせて行動するようになる。大人の手が全くかからない。でもその子はあまり周囲を気にしないから、お琴はいつも目をかけて声をかけて、手を焼いていた。成長が遅いのだと思っていたのだ。
ところが、家庭訪問で自宅へ行った時、お琴は目を見張った。下の弟妹三人の面倒を甲斐甲斐しくみるその子は、学校とは打って変わってちゃきちゃきしていた。まるで別人。
(家で大変だから学校では気を抜いてたんだ。)
それ以来、お琴はその子への見方を改めた。極端に言えば、問題児から優等生。心配から信頼へ変わった。
香のことも偏見で見ているのかもしれない。あの可愛らしい姿に惑わされている。いけないな、とお琴は反省したのだった。
11 結婚したい女たち ~お琴の不都合な現実~
(ヨガウェアを買わなきゃ!)
お琴は最後のパンを口へ放り込んだ。口をモグモグさせながら検索すると、出るわ出るわ、お高いウェアがずらりと並んだ。
どれもスレンダーで長い脚の人用に思える。一花ならどれを着ても似合うだろう。
今日の山登りもそうだった。一花はピタッとしたレギンスに透け素材の長袖を羽織っていた。山登りのスタイルではなかったけど、違和感はなかった。あの格好でスタスタと街を歩くように山も登る姿はかっこよかった。
香は富士山に登った時に、登山用のウエアや靴、サンバイザー、リュック一式を揃えていた。鮮やかな水色に白のラインが入ったウエアに、ピンクのシューズ。香らしい華やかな出で立ちだった。
一方、お琴と言えば・・。学校の体育の授業で着るジャージ。紺色で地味と言えばまだよくて、ダサいと言ってしまえば悲しくなる。
せっかくパーソナルカラー診断をしてもらったというのに。ジャージもイエベ春カラーにしなきゃ!て言うか、山登り用のかわいいウエアを用意しなきゃ!!
と、山を登りながら反省していた。なのに今はヨガウェアを買おうとしている。と言うのも、一花のヨガレッスンを受けることになったからだ。
「ねえ、ヨガをね、教えさせてくれないかな?」
と、帰りの車の中で一花が言った。お琴と香は「どういうこと?」と意味が分からなかった。
「新しいポーズを作りたくて。そのお試しの生徒になってほしいんだ。リモートでいいからさ。」
「やるやる!」
香が嬉しそうに叫んだ。
「今ずっと家にいて運動不足でさ。散歩は始めたんだけど。ヨガもまたしたいなって思ってたの。」
東京にいた頃は週一でヨガに通っていたそうだ。
「わたし、体硬くてやばいよ・・。」
お琴は言葉に詰まった。ダイエットのためにも運動はした方がいいけど、ヨガなんてできるだろうか。
「体は硬くてもいいんだよ。やってると柔らかくなってくの。ね、そうだよね。」
香はすっかりノリノリだ。
「みんな体は違うから。ポーズもみんな違うの。自分のポーズをとればよくて。体の硬い人の方が、ポーズがどんどん変わっていくから面白いと思うけど。」
「嫌ならいいけど。」
と続きを言いそうな一花に、思わずお琴は言った。
「やってみる!」
なぜなら、ここでヨガを断ったら二人に取り残されるような気がしたから。
一花と香と一緒につるんでいるだけで、自分もかわいくなったような気分になれるし、実際にかわいくなれるような気がしていた。二人のかわいいところを真似して取り入れていけば、私でもかわいくなれるのだ!そう思い始めていたお琴は、このヨガを断ることなどできなかった。
一花に教えてもらえるなら大丈夫、私でもできる。
そう自分に言い聞かせながら、お琴はウエアを選んだ。そして勢いでヨガマットもいっしょにポチった。
不思議なもんで、ウエアとマットを注文したらヨガをしたような気分になった。ひと仕事終ったあとのように気が緩んだら、焦りにも似た思いが出て来た。
アクセをくれる香と、ヨガを教えてくれる一花に自分を釣り合わせなきゃ。
私も二人に何かしたい。
できることを考えてみたけど、学生時代に作った石鹸くらいしか思い浮かばない。
手作り石鹸なんて、あげても迷惑になるだけかも。二人ともいい香りのする自然素材のソープを使ってそうだし。
自分にできるただ一つの手作り石鹸をためらうお琴は、二十代をゲーム三昧で過ごした自分を悔やんだのだった。
12 結婚したい女たち ~一花の不都合な現実~
市内のほぼ中央にある九階建てのマンションに、一花は一人で住んでいる。寝室の隣にある部屋へ久しぶりに入った。何も置いていないその部屋は知らない部屋に思えた。
ここは夫の部屋だった。デスクと椅子に加えて趣味の楽器なんかが所狭しと置いてあったけど、離婚と同時に夫はすべてを運び出した。
その部屋のカーテンをカフェ風のレースに付け替えて、床は水拭きをして隈なく拭いた。クローゼットの中も掃除しようと開けたら、
(あれ?なにかある。)
上についている棚に箱があった。開けてみると、息子が生まれた時にもらった赤ちゃんの靴下だった。あの頃は、履かせる間もないほどに次から次へと、たくさんの服をもらった。あっという間に大きくなる息子には、すぐにサイズが合わなくなって、結局箱から出すこともなかった。
(なんでこんなとこに。もう一人生まれたら履かせようと思って取っておいたのかな?)
夫は優しい人だった。母も亡くなってしまって独りぼっちだった一花に深く同情して、
「40歳までに結婚したいんだ。」
と、出会って半年で結婚した。16歳も年上で一花にとっては父親のようにも思える人だった。
とここで、これ以上思い出さないように一花は頭を振った。気を取り直して壁に姿見の大きな鏡を置いた。これから冬になると乾燥するから加湿器も置きたい。ZOOM用のカメラも置かないといけない。配置を考えながら一花は楽しみでならなかった。次の日曜日、この部屋でお琴にヨガを教えることになったのだ。
きっかけはほんの思いつきだった。
お琴と香と山へ登った帰りに「ヨガを教えさせてほしい」と、口から出てしまった。
プライベートレッスンへ向けて、新しいポーズを開発中ではあった。生徒さんの体の悩みは一人一人違う。肩こり、腰痛、冷え、頭痛、むくみ、いろんな症状を抱えている。それを改善してあげられるポーズを提供できれば、独立も夢じゃなくなるだろう。
でも一花にはできるポーズでも、生徒さんたちにはどうだろうか。どんな反応を示すのかは想像もつかない。教えながら試行錯誤したのでは信頼を失ってしまう。そんなことを考えていたから、ついお琴と香に頼んでしまった。
そしたら意外な反応があった。快く引き受けてくれると思ったお琴が難色を示し、断られるかもと予想した香が、喜んで引き受けてくれたのだ。しかも香は2年ものヨガの経験があった。
いつでも想像と違う香。
あの時もそうだ。突然英語を喋り出した。ネイティブのような発音でペラペラだった。留学していたと言うし。
きっとお金持ちのお嬢さんだ。香のあの幸せそうな雰囲気は、裕福な家庭で生まれ育ったからなのかもしれない。私生児の私とは全く違う。
だからこそ一花はあの時「もっと頑張らなくちゃ!」と内心焦って、そして出た言葉が「新しいポーズを作るために教えさせてほしい」だった。
リモートで日曜日の夜に三人でヨガをした。香は一度言えばすんなりポーズを取れた。でもお琴はそうはいかなかった。体をどう動かせばいいのか、全く分からない様子だった。ほぼお琴に付きっ切りになったのだけど、香は気にしていないようだった。
そしてなにより、一花はお琴の素人ぶりが嬉しかった。
なぜって、生徒さんがヨガなんてしたことのない友だちや家族を連れてくることがあるからだ。ヨガって何?というレベルの人がレッスンに混ざると、大変だ。そういう時のためにポーズの難易度を下げたバリエーションを用意しておくといいのだけど、その練習になる。
お琴の指導に時間がかかって、30分の予定が1時間になってしまった。「30分は短くない?」とレッスン前に言っていた香は満足そうだった。でもお琴は「もういやだ。」と言い出すんじゃないかと心配した。
なのに次の日、「次はリモートじゃなくて直に教えてほしい」とLINEが来た。一花はビックリしたけど嬉しかった。お琴のこういうところが大好きだ。
というわけで、この部屋でレッスンをすることになったのだった。
13 結婚したい女たち ~一花の不都合な現実~
リビングのローテーブルの脇で、ヨガの動画を見ながら一花はポーズをとっていた。
いろんなインストラクターがヨガの動画を公開している。インストラクターをしていても、誰かのレッスンを受けるのは勉強になる。ヨガの練習を欠かさないのは、一花のヨガ歴が短いからだ。
離婚してからヨガを通い始めた一花に、スタジオからすぐに声がかかった。
「インストラクターしない?」
「え?わたしが?!」
一花はビックリした。ヨガを始めてまだ数か月。ポーズさえまだよくわかっていない。
「インストラクターの養成講座があるから、通ってみたら?」
生まれつきのほっそりと長い手足に小さな顔。そんなモデル体型に加えて、一花の体は柔らかかった。
子どもの頃はバレリーナに憧れた。バレエを習いたかったけど、そんなことをママに言えるわけもなかった。そんな時にバレエを習っている友だちが「教えてあげる!」と言って、一花にレッスンをしてくれたのだ。
その子のお家は大きかった。自分の部屋もあった。しかも家でもバレエの練習ができるようにと、鏡とバーがとりつけてあった。
レッスンで教えてもらったことを、そのまま先生になりきって教えてくれた。終わるとお母さんがおやつをくれた。そのおやつが一花にはごちそうだった。あまりにおいしかったから、持って帰ってママにもあげた。
学年が上がり別のクラスになったら、レッスンしてもらえなくなった。
「塾に行くことになって。そんな時間ないからママがダメって言うの。」
そしてその子とは疎遠になった。一花は自分の家庭環境が原因かもと思った。年齢が上がるにつれてそう思うことが多くなっていった。
それでも一花は教えてもらったことを自分で続けていた。
そうやってバレエの基礎をしていたから、一花の体はとても柔らかかった。ヨガのポーズをとっても、まっすぐに上がる長い脚や、伸びた背筋はとてもきれいだ。
離婚して仕事もなくて虚ろな心でいた一花には、スタジオからの誘いは自分を認めてくれる唯一の支えになった。
だからすぐに養成講座に通った。スタジオの受付で働きながら、持ち前の勤勉さであっという間に終了した。ヨガを始めて1年しか経っていなかった。
レッスンを担当すると、自分よりもヨガ歴の長い生徒さんたちばかりだった。「もっと頑張らなきゃ!」と、ほかのインストラクターのレッスンに生徒として参加して、ポーズを磨いた。そんな一花のレッスンは人気になった。
たくさんの生徒さんが来るようになったけど、コロナが始まった。今もスタジオへ来てくれる生徒さんはいる。でも多くの人はオンラインレッスンになってしまった。
寂しく思っていたけれど、オンラインでいろんな人のヨガを見られるようになったのはよかった。まだヨガを始めて4年目。教えているとは言え、ただの一ヨギーに過ぎないのだと思い知らされるほどに、動画のヨガは個性豊かだ。それを見ていると、一花も自分なりのポーズを提供できるようにならなくては!と思うのだった。
そうやって力の入る一花だったけど、お琴と香に教えていると、あの子どもの頃にバレエを友だちに教えてもらっていた時のように、楽しくて仕方がない。
好きなことをただ好きだからしているとき、なんて幸せな気持ちになるんだろう。
しかもお琴がやる気モードになってくれた。かけがえのない友人二人に出会えて、一花は最高に幸せだった。
ただ気になるのは、香だ。
バレエを教えてくれた友だちも、プライベートレッスンを言い出してくれた生徒さんも、みんな一花とは違う「いい」家庭の人たちだ。不思議とそういう人たちと仲良くなることが多い。
それは、自分がそういう育ちのいい人たちに憧れがあって好きだからかもしれないと、一花は思っていた。
だって夫もそうだった。
経済的に恵まれたご両親に育てられて、夫自身も大手企業で働くエリートだった。
そして一花の父も、たぶんそういう人だ。父がどこのだれだかなんて知らないけど、ママの「あの人は頭のいいエリート」という言葉から、一花は勝手に「裕福な家庭に生まれ育って一流大学を出て一流のお仕事をしている人」が父なんだと思っている。
そんな父はたぶん一花が生まれたことさえ知らない。母を捨てて母のことさえ覚えていないだろう。父にとって一花はいない存在なのだ。
そんな父のように、夫も一花を捨てて出て行った。息子を取り上げて一花を独りぼっちにした。マンションを一花にくれるほど優しい夫。でもそんな人に一花は捨てられたのだ。そのことを考えるとたまらなく寂しくなる。
ヨガのインストラクターを始めて「自尊心」が戻ってくると、逆に寂しさは募るばかりだった。誰かに認められたい。側にいてほしい。それで婚活を始めた。ところが、夫探しのはずが、運命の女たちに出会ってしまった。お琴と香がいるからもう前ほど寂しくなくなっている。
でも香のことが心配になって来た。
香も子どもの頃バレエを習っていたことがあったそうだ。
「先生が厳しかったから、すぐやめちゃった。」
と笑っていたけど、一花にはうらやましい話だ。
習いたくても習えない人がいて、習いたくないのに習う人がいる。生きているとそんなことばかりだ。
香があのバレエの友だちに重なる。いわゆる「育ちのいい人」なのだ。いつか香にも捨てられるのだろうか。
自分の生まれ育ちを決して話してはいけないと、心に強く刻んだのだった。
14 結婚したい女たち ~香の不都合な現実~
市の中心街から少し離れた閑静な住宅地。そこに香は住んでいる。
「ミーちゃん、あしたはお出かけでちゅよ。」
雪のように白いミーちゃんの毛をブラッシングしながら香はウキウキしていた。明日はヨガのレッスンを受けに一花の家へ行くのだ。
「お琴だけ一花の家で教えてもらうなんてずるい!」と抗議したところ、月に一度は日曜日のお昼にレッスンをしてもらえることになった。
夜は家事に忙しくていけないけど、父のいる日曜日の昼間なら行ける。
「猫を見たい!」
というお琴のリクエストに応えて、ミーちゃんのお披露目もするのだ。
「おめかし、ちまちゅよ。」
明日の衣装をミーちゃんに見せた。
ピンクのレースが三枚重なった上に、リボンと大きなパールのついたチョーカーだ。付け襟のように見えて、服を着せなくてもとてもかわいい。
「みー。」
答えるようにミーちゃんが鳴いた。
「はいはい、知ってまちゅよ。ミーちゃんのお気に入りのチョーカーでちゅね。」
ミーちゃんの首にチョーカーをつけて、右足には水引で作ったピンクのバングルをまいた。
「ぴったり!」
チョーカーの色に合わせて作ったピンク色のバングルは、ミーちゃんをますます上品に見せた。
香は自分もバングルをつけた。香のは色違いの水色だ。
「二人も喜んでくれるかな。」
一花とお琴にも色違いで作った。あした渡そうと思っている。
最初にあげたアクセサリーはブレスレットだった。あの時は、渡すまで喜んでもらえるか心配だった。だって、お琴も、あのお洒落な一花さえも、アクセサリーをつけない。ネックレスもピアスも指輪も、ブローチさえつけているのを見たことがなかった。
でもあげたら二人ともむちゃくちゃ喜んでくれた。一花は常時身に着けてくれているし、お琴は仕事以外、特に婚活の時につけてくれてるそうだ。
「友だちの作った水引のアクセだって言うと、いい話題になってさ。盛り上がるから助かってる。」
お琴からそう言われて、香の笑顔は止まらなくなった。
一花からは、
「軽いし、どんな格好にも似合うからつけやすい。」
と言ってもらった。前はレッスン中もつけてたって言うし。嬉しくってたまらない。
あの二人は単純に喜んでくれるから安心してあげられる。比奈ちゃんにあげた時は嫌な気分になったけど。
比奈ちゃんは、小学校の同級生だ。地元に帰って来て半年ほどした時、偶然コンビニで再会した。
「香ちゃん?」
レジの店員から名まえを言われて驚いた。コロナ前でマスクをしていなかったその顔は、どこか見覚えがあった。
「比奈ちゃん?」
中学までしか住んでいなかったから、14年ぶりの地元は知らない町に思えた。そこでの懐かしい友だちとの再会は、家事に疲れた香の胸をときめかせた。すぐに連絡先を交換して、会う約束をした。
次の日曜日、カフェでお茶を飲みながら話し込んだ。小学生の時、初めてお店で友だちと食事をしたのも、比奈ちゃんとだった。あの時は小学校の6年生だった。比奈ちゃんの声はあの頃よりも少し低くなっていた。
ひとしきり話しこんだ最後に、比奈ちゃんからこう言われた。
「富士山、登りに行こうよ!」
「え?富士山?山なんて登ったことないよ。」
「だいじょうぶ。わたし慣れてるから。行こうよ!」
誘われたらなんでも挑戦する香だが、山登りはさすがに答えに詰まった。でも比奈ちゃんとは湖へ泳ぎに行ったり、水族館へ遊びに行ったり、色んな所へ遊びに行った。もちろんいつも比奈ちゃんに誘われて。断る理由なんてない。
「うん、行く。」
久しぶりの幼馴染とのお出かけに香は浮足立った。家に閉じ込められているような気分になり始めていたから、3000メートルの高さまで登るのだと思うと、まさに天にも昇る喜びだった。
そして、ちょうど水引を始めた頃だったこともあり、比奈ちゃんに指輪を作って持って行った。
15 結婚したい女たち ~香の不都合な現実~
初めての山登りは人生最大の試練に思えた。それは日本一高い富士山だからというよりは、強風が吹いていたからだ。
(吹き飛ばされる!)と香は何度も思った。
途中から案内をしてくれて一緒に登っていたおじさんが、「雨が降ってないだけましだよ。」と言った。
(雨降りの次に大変ってことじゃん!)
と香は心の中で毒づいた。
実家での慣れない家事生活で、香の心はくさくさしていた。生来の前向きで明るい心はどこへやら。何を見ても聞いても否定的にしか考えられなくなっていた。
それでもなんとか八合目の山小屋にたどり着いた。でもその時には家に帰りたくて仕方がなかった。
(あんな家なのに帰りたくなるなんて。)
いいリフレッシュになるだろうと期待したからこそ、こんなに高いところまで登って来たというのに。家にいる時より疲れ果てている自分に嫌気がさした。
(もう私には楽しいことなんて起こらない。)
そんな気分になっていたら、追い打ちをかけるようにおじさんが言った。
「晴れてたら星がきれいなんだけど、今日は残念だね。」
案内のおじさんは、いかにこの山登りが素晴らしくないかしか言わない。
どこまでも引っ付いてくるこのおじさんが鬱陶しくなっていたら、比奈ちゃんが、
「おじさん、ありがとう。ここまで来れたのおじさんのおかげだよ。久しぶりにあったから二人で話したいんだ。ありがとね!」
と、うまいこと追い払ってくれた。
やっと二人っきりになれた香たちは、昔のように話し込んだ。外では山小屋が吹き飛ぶんじゃないかと思うほどの強い風が吹いていた。それはまるで、小学生の頃にビュービュー吹く風とゴロゴロ鳴る雷に、「こわいこわい!」ときゃーきゃー叫んで比奈ちゃんと家の中で遊んだ時のようだった。
「これ、作ってきたの。あげる。」
香が水引の指輪を渡すと、比奈ちゃんはこう言った。
「香ちゃんは、ほんとに違うよね。お金持ちだし、留学するし、東京で働いてたし、こんなものも作れるし。私なんかとは全然違う。」
予想外の反応だった。子どもの頃は、おもちゃのアクセサリーをあげっこして遊んでいたのに。あんなに楽しかったのに。
香は悲しくなった。
思い返せば、中学生になってから友だちの態度が変わり始めた。
「あのマンションって、香ちゃんちのなの?」
ズバリ聞いてくる子もいた。
香の父は五棟のマンションを所有している。そのマンションに住んでいる男の子がいて、その同級生は変な目つきで香のことを見るのだ。
小学生の時はそうじゃなかった。友だちはそんなこと知らなかったし気にもしていなかった。ただ、友だちのお母さんたちは、あの男の子のような目つきで見てくることがあった。
先生の香への態度もどこか違った。香の父のマンションに住んでいる先生もいたけれど、香にはそれがどういうことかなんてわからなかった。
だって父は役所勤めをしていた。公務員なのだ。おじいちゃんは早くに亡くなって、おばあちゃんがマンションを所有していた。小学生の時、父の唯一の兄弟だった伯父さんが亡くなった。その時のお葬式で、気落ちしたおばあちゃんと大人たちが何やら騒いでいたのは覚えている。
でも父がいつマンションを譲り受けたのか、詳しいことを香は知らない。家でマンションのことが話題になることは一度もなかった。
なんとなく学校で居心地の悪かった香は、留学することにした。中学を卒業するとすぐにイギリスへ行った。子どもの頃から英会話を習っていたし、夏休みに外国で過ごすことも多かった香に言葉の壁はなかった。
父の知り合いの家にホームステイさせてもらって念願の外国暮らしを楽しんでいた。ところが大学を卒業する時、突然また日本に住みたくなった。でも地元に帰りたいとは思わなかった。自分の住む場所じゃないと思っていたから。それでなんとなく東京で働いた。
就職活動の仕方がわからなかったから、派遣会社に登録した。英語関係の仕事に強い派遣会社で、TOEICのスコアが九百点ある香を大歓迎してくれた。そしてすぐに外資系のイベント会社へ派遣された。
そこでは主に英語でのメールのやりとりを担当した。たまに通訳をすることもあったが、社員さんが通訳、香が翻訳、という区分けになっていた。
イベントの準備が始まると出勤して、メールの連絡を英語でとったり資料や原稿を翻訳したりした。そんな業務は仕事の速い香には容易くて、かなり暇だった。
みんなが忙しそうにしていると手伝うこともあったけど、「香さんは、いいですから。」と、除け者にされることが多かった。
イベント前日や当日はさすがに香も一緒になって準備に追われたけれど、イベントが始まってしまうと、通訳要員として、また別格扱いになった。バタバタ動き回るみんなを手伝おうとすると「香さんは座っててください。」と、立っていることも許されなかった。
そしてイベントが終わると、出勤も許されなかった。次のイベントの準備が始まるまで香は用無しだったのだ。
16 結婚したい女たち ~香の不都合な現実~
次のイベントまでの長い休日は結衣ちゃんと遊んで過ごすことが多かった。結衣ちゃんに連れられてワークショップへ行くのは、役に立たないとわかっていながらも、スキルアップしていくようで楽しかった。
派遣会社は詰め込むように仕事を入れようとしたけど、「多すぎるとしんどい。休みたい。」と言う香に配慮して、たまにほかの仕事を入れる程度だった。
沖縄へ行ってほしいと言われた時、香は旅行を兼ねた仕事でラッキーだと思った。でもまさか恐怖に震えることになるなんて。
それは医療関係の学会の仕事だった。外国からの講師の通訳だったから、「医療関係の言葉はわかりません。」と言ったのだけど、事前に原稿を渡すからどうしても受けてほしいと言われた。
沖縄は魅力的だったし、お金もべらぼうによかった。お世話になってる林さんの強い懇願に、ついOKを出してしまったのだけど。
行く前から雲行きは怪しかった。原稿が来ないのだ。待っても待っても来ない。焦っていたら出発2日前になってやっと来た。徹夜で読み込み、医療用語の日本語も調べてなんとか翻訳した。
ところが台風直撃だと天気予報が言うのだ。
(せっかくの沖縄が・・。)
期待外れにがっかりしながら、飛行機は飛ぶのだろうかと不安な中、成田へ行った。
そんな香の心配はよそに、無事飛行機は飛んだし着いた沖縄は旅行のパンフレットのように快晴だった。しかも空港には「学会の皆さま、ようこそ!」と大きな垂れ幕がかかっていた。
普段のイベントは東京国際フォーラムでの仕事が多かった香は、大きなイベントの仕事をしているのだという自負があったけど、町をあげて歓迎してくれる今回のイベントに心が震えた。
キャリアアップしたような気分になったのだ。
この仕事を受けてよかった。来てよかった。仕事を頑張って沖縄も楽しむぞ!
と思っていたら、担当の人からこんなことを言われた。
「立野さんのホテルは、別のとこにしましたから。もし誰か来ても、絶対にドアは開けないでください。何かあった時はすぐに僕に電話してください。絶対に帰らないでくださいよ。」
あまりの深刻な言い方に、香の顔は険しくなった。
「どういうことですか?」
と問い詰めると、なんと前回の学会で通訳をした女性が強姦されかかったと言うのだ。しかも通訳相手の講師から。そんなことがあったから今まで専属のようにいつも通訳をしていた女性だったのだけど、もう二度と嫌だと言っているそうだ。
「当日帰っちゃったんですよ。ほんとに困って大変だったんですよ。絶対帰らないで下さいよ。医療関係の通訳ができる人って少ないから、来てくれて本当に助かりました。今回はもちろん同じ講師ではないし、万全の安全管理をしてますから。大丈夫ですから安心してください。」
と、無理に笑う担当者に香は言葉を失った。
(それは強姦されかかったんじゃなくて、されたんじゃないだろうか・・・。)
事前の打ち合わせが済むと、ディナーも断り(←これは担当者がうまいこと言って断ってくれた。)、日も暮れないうちから香はホテルの部屋にこもった。
フロントには気分が悪いから電話は取り次がないでほしいと頼んだ。
せっかくの沖縄の夜を、香は不安と後悔を抱きしめて過ごすしかなかった。
それでも学会が終わってしまえば、なんてことはない。みんないなくなって怖い話なんてすっかり忘れて、香はしばらく沖縄に残って南国を楽しんだ。
来週にはまた東京でイベントの仕事が始まる。またみんなに会えるのが嬉しい香は、お土産をたくさん買ったのだった。
久しぶりに会社へ出勤すると、家に帰ったように「おかえりなさい!」と出迎えられた。
「またよろしくお願いします。」と笑顔であいさつ回りをして、沖縄のお土産を渡した。そんな時、比奈ちゃんのように「さすが香さん、沖縄ですか。」と嫌味を言って来る人もいた。「僕たちとは違うよね。」と。
香は(またか。)と思った。中学の頃を思い出すのだ。
地元でも東京でも、どこにいても浮いてしまう。
よく考えればイギリスでもそうだった。当たり前だけどイギリスで香は外国人だった。異人の中でアウェイ感は当然あった。でも日本人の留学生の中でも、ネイティブのように英語を話す香は浮いていた。
(居場所がない。)
そんな気分になることが多い香だった。
17 結婚したい女たち ~香の不都合な現実~
そして今この地上三千メートルにも香の居場所はなかった。気の沈む香に比奈ちゃんはダメ押しするようにこう言った。
「香ちゃんって、全然変わらないよね。昔のまんま。」
香にとって「変わらない」は「大人になれない」ということ。実家で両親と暮らす香は、家事をしているとは言え、子どもの頃と同じような気分になっている。
暗い表情の香に、比菜ちゃんは手を振りながら慌てて付け足した。
「ちがうよちがうよ、いい意味でだよ。うらやましいの。さっきのおじさんにもさ、全然変わってなかったから思い出しちゃった。覚えてる?お菓子をくれたおじさんがいたでしょ。」
それは小学校のすぐ近くのログハウスの家のおじさんのことだった。
香たちが小学校に入学して一年くらいした時、学校を出てすぐの角に新しいお家が立った。おしゃれな木の門には広い駐車場への扉と、お家の方への扉が二枚付いていた。駐車場への扉は押せばどちらにでも簡単に開いたから、子どもたちの恰好の遊び場になった。
まるで通学路のようにその扉を通ったのだ。
駐車場でおしゃべりをする子もいたし、何度も扉を行ったり来たりする子もいた。そのお家のおじさんが、ある日出て来た。
大きな子どもたちは怒られると思って走って逃げていった。取り残されたまだ小さい香たちに、おじさんはこう言った。
「おやつあげるよ。食べにおいで。」
みんな喜んでおじさんについていった。池のある大きな庭に面した縁側に、座布団と湯呑みが置いてあった。おじさんはそこに座ると、お煎餅の袋を開けて大きなお皿に盛った。
そのお煎餅を食べながら庭で遊んだのだけど、香は遊べなかった。なぜって、おじさんの膝の上に座っていたから。
と言っても、座りたくて座ったわけじゃない。おじさんに座らされたのだ。
「あの時の香ちゃんの顔。思い出してもおかしくて笑っちゃう。今日もおんなじ顔するから笑っちゃった。」
比奈ちゃんの話を聞いていた香は鮮明に思い出した。池を見たかったのに、おじさんが放してくれなくて、ぶーたれていたのだ。そしてあの時も比菜ちゃんが助けてくれた。
「香ちゃんもおいでよ!」
と言って香の手を引っ張ってくれたのだ。膝から滑り落ちるように香は解放された。
「お菓子をもらっちゃいけないって、叱られたんだよね。おいしかったのにね。」
「あれね、知ってる?ハヤトくんがちくったんだよ。」
「え?」
ハヤトは香の父のマンションに住んでいる同級生だ。
「あのおじさんね、香ちゃんがいる時じゃないとお菓子をくれなかったんだよ。それでハヤトくんがいじけてさ。お母さんにちくったの。」
香は絶句した。
知らなかった。いつも香のことを変な目で見てきたのは、お菓子の恨みだったのだろうか。
香は子どもの頃にタイムスリップしたように当時のことをあれやこれやと思い出して、思い出に浸った。ところが、そんな香を一気に現在へと引き戻す痛烈な比菜ちゃんの言葉が飛んで来た。
「実はね、わたし来週結婚するの。」
突然のことに香は声が出なかった。でも絞り出すように何とか「おめでとう」を言った。
「変わってない香ちゃんと話してたら、結婚前に一緒に山に登りたくなっちゃって。留学して会えなくなっちゃったでしょ。また一緒に遊びたいなって思ってたから。来てくれてありがとう。いい思い出になった。」
留学中に比菜ちゃんは手紙を送ってくれた。友だちの近況とか、今日本でこんなことが流行ってるよとか、長い手紙を何回も送ってくれた。それを読むのが外国での暮らしにどれほど慰めになったか。大切な友だちの比菜ちゃん。その比菜ちゃんが結婚するなんて。
その夜は眠れなかった。地上から高すぎるのもあったかもしれない。でも香の頭の中は正体のわからない不安でいっぱいだった。
お金持ちで留学もして、いつもうらやましがられていた香だけど、今はどうだ。仕事もない。男もいない。実家で家事をして時間が過ぎていくだけだ。比奈ちゃんは結婚すると言う。きっとすぐに子どもを産んでお母さんになるだろう。香は置いてきぼりをくらった気分になった。
重苦しい頭と山登りの疲れでうつらうつらした香は、夢を見た。ミーちゃんと話す夢を。
次の日の朝の目覚めは良かった。夢とは言えミーちゃんに会えたのが良かったのだろう。
家に置き去りにしたミーちゃん。きっと寂しくて私に会いたがっている。だから夢で会いに来たにちがいない。香は今すぐミーちゃんに会いたくなった。
家に帰るのを楽しみにしながら、まだ真っ暗な中、山頂まで登った。きのうの強風が雲を吹き飛ばしたように、雲ひとつない空だった。
白み始めてしばらくしたら朝日が顔を出した。朝日を下に見るなんて。神の世界にいるようだった。神聖な日の出は、美しい世界に生きていることを香に思い出させてくれた。
このまま年だけとってしまっていいのだろうか。
香はもうすぐ二十九歳になる。
わたしも幸せになりたい。家事三昧で引きこもってなんていられない!
昇っていく朝日に元気をもらった香は、婚活することを決意したのだった。
18 結婚したい女たち 一花の家
香はマンションの六階にいた。一花のヨガのレッスンを受け終ったところだ。お琴はシャワーを浴びに行ったが、香はたいして汗をかかなかったのでシャワーは遠慮した。着替え終わるとヨガの部屋を出てリビングへと歩いて行った。
玄関から奥へ伸びた廊下には、右手にヨガの部屋と寝室、左手に今お琴がシャワーを浴びている浴室やトイレ、ランドリーがある。
一花の住んでいるところはどんなとこだろう。
ドキドキしながら香は突き当りのドアを開けた。左側にはリビングが、右側にはダイニングとカウンターキッチンがあった。リビングとダイニングはつながっていて、ベランダに沿って広がっている。ベランダの向こうには大きな空が広がっていた。
「ステキ!」香は窓へと一直線に歩いた。町は這うように空の下に縮こまっている。町全体を見渡せる景色は見ているだけで気分がいい。香はまるで自分が住んでいるかのように嬉しくなった。
窓にへばりつく香の耳に、何やら鈍い音が聞こえた。キッチンを振り返ると、一花が下を向いてごりごりと音を立てている。
「なにしてるの?」
香はカウンター越しにキッチンの一花に尋ねた。
「チャイのスパイスを挽いてるの。飲むでしょ?」
「うん。でもお昼食べに行かないの?」
午後からすることになっていたレッスンは、お昼前の11時に変更になった。きのうの夜、そう一花からlineが来たとき、レッスンの後いつものように3人でお昼を食べるのだと察した香は、即OKと返信した。
「お惣菜作ったんだ。お琴がパンを焼いて来てるから、それを食べようよ。」
「え?!だったら私もなんか作って来たのに。」
「香はいいよ。今日も早くて大変だったでしょ。大丈夫だった?」
心配そうに言う一花に香は小さくうなずいた。10時半にお琴が車で迎えに来ると言うので、今朝はいつもの家事をこなしたあと休む間もなくお昼の支度をした。そしてヨガの準備をして飛び出して来たのだ。
「パンをね、香にも食べさせたくって。」
「そうそう。絶対ばれたら怒るだろうから。」
と、シャワーを浴び終わったお琴がリビングへ入って来た。
香はぶーとほっぺたを膨らませて口を突き出して言った。
「お琴がパンを焼くなんて知らなかったよー。」
「でしょでしょ。だから今日いっしょに食べようと思ってさ。」
そう言いながらお琴はキッチンへ入って行った。そして食器棚からお皿を三枚取り出して、ダイニングテーブルへ並べた。その慣れた手つきで香はピンと来た。
「いつもレッスンのあと二人で食べてたの?!」
自分たちだけズルい!と怒る香に、一花とお琴は笑った。
「私も手伝う!」
香もキッチンへ入り、「お箸はどこ?」と食事の準備に取り掛かった。
いそいそ動き回る二人を見て、一花は幸せだった。
夫は何も手伝わない人だった。コップひとつ自分で出さない人だったのだ。こうやって一緒に食事の準備をしてくれる人だったら・・。息子ももう大きくなっている。今ならこうやって手伝ってくれたのだろうか・・。
ありもしない今を想像してしまう自分を一花は、いけないと振り払うように香に話しかけた。
「お母さんの調子はどうなの?」
「ほとんど動かなくて体は弱ってるみたい。でも精神的にはね、かなりいいよ。ミーちゃんのおかげだと思う。」
香が東京から連れて来た猫のミーちゃんを、香の母はいたく気に入った。一日中膝に乗せていたこともあった。そんな日の夜はミーちゃんがぐったりしていたもんだから、香は思わず「ミーちゃんに何したのよ!」と、怒ったこともあった。
「何もしてないわよ。かわいいから抱っこしてただけじゃない。」
と言われても、どうしてこんなにミーちゃんの元気がなくなるのか、わけがわからなかった。しかし、次第に母の精神が安定して笑顔が増えてくると、それに比例するようにミーちゃんも元気になっていったのだ。
「猫は癒しの動物って言うからね。お母さんの心を直してたんじゃない?」
一花の言葉に、香はそのとおりだと思った。母だけではない。香のこともミーちゃんは癒してくれる。香が疲れてぐったりとしている時に限ってミーちゃんはすり寄ってくるのだ。そしてミーちゃんを抱っこしていると、香の疲れは吹っ飛んでしまう。
「見せてよ。」
とねだるお琴に、すっかり忘れてかごに入れっぱなしのミーちゃんを外へ出した。
「よくこんなかわいい猫を拾ったね。飼い猫じゃなかったの?」
「それは私も心配したんだけど違うみたい。首輪もしてなかったし、毎日私のベランダに返って来たし。」
ミーちゃんを抱っこしながら、香はいかにミーちゃんとの出会いが幻想的だったかを二人に語った。
満月を背に香を見つめるミーちゃんに魔法をかけられたように引き寄せられたことを。そしてそれ以来ずっと一緒にいることを。
「しかもその満月がね、射手座の満月だったの。」
ミーちゃんに出会ってから香は外出することが多くなった。それまで休日と言えば結衣ちゃんの誘いがなければ、映画やドラマを見て部屋に一日いることが多かった。それがミーちゃんが来てから、夜の散歩を始めた。次第に夜だけじゃなくて、昼間もミーちゃんを連れてカフェへ行ったり出かけるようになった。閉じこもりがちだった香が積極的に出歩くようになったのだ。その変化が、外の世界へ飛び出すという射手座の性質にピッタリ合っている。
星読みをかじった香は星座と絡めて話したのだけど、お琴は何のことだかさっぱりわからなかった。でも一花はこう言った。
「なるほど。そうだね。射手座っぽいね。わたしとお琴が出会った日も満月だったんだよ。」
「え?!なにそれ、何の満月だったの?」
興味津々な香に、一花はにやりと笑って言った。
「蟹座。」
母性や家庭を表す蟹座の満月にお琴と出会ったのは、まさに運命だと一花は思っていた。なぜなら独りぼっちの一花にとって、お琴は家族のように大切な存在だから。
「なになに?全然わかんないよ。」
話についていけないお琴に、香と一花は月星座のことを説明した。占いで使われる太陽星座だけではなくて、月にも星座がある。内面的なことは誰でもこの月星座に影響を受けているのだと。
「もしかして一花もやってる?新月と満月の日に。」
「もちろん。」
香の期待どおり、一花は大きくうなずいた。
「なになに?なにしてるって?」
さっぱりわからないお琴に二人は声をそろえて言った。
「パワーウィッシュ!」
新月と満月の日に願い事を書くと、未来がそのとおりになるというパワーウイッシュ。
「お琴もやりなよ!」
二人がしているのなら、しないわけにはいかない。
「やるやる!」
お琴はすぐにスマホでパワーウィッシュノートをポチったのだった。
19 結婚したい女たち 一花の家
「ミーちゃんに会って変わったって言うのさ、その月星座?のこともあるかもしんないけど、猫って神の使いって言われてたんだよ。古代エジプトで。」
お琴の言葉に香の顔は輝いた。
「そうなんだ!」
ミーちゃんは天からの贈り物。私の天使。神さまが私にミーちゃんを与えてくださったのだ。なんてステキなんだ。香は喜びで興奮した。
「エンジェル・ミーちゃんでちゅね。」
ミーちゃんをなでる香にお琴が「抱っこさせてよ。」と手を出した。香が渡そうとしたところ、
「いたっ!!!」
なんとミーちゃんがお琴の手をひっかいたのだ。
「ミーちゃん!」
香はビックリした。ミーちゃんがそんなことをしたのは初めてだ。
「お琴だいじょうぶ?ごめんね。ミーちゃん、ひっかいちゃダメでちゅよ。」
きのう爪を切っておいたのが良かった。お琴の手に傷がつくことはなかった。
「ちょっとチクッとしただけ。なんともないよ。それより、いつもそうやって話しかけてんの?その赤ちゃん言葉うける、やばい!」
ゲラゲラ笑うお琴に、香のいつもの「だってー。」が出た。
そのやりとりに一花も笑った。この家で、こんなに大声で笑うなんて。もう自分は新しい人生を生きているのだと実感した。
「おなかすいた。食べよ!」
お琴の言葉に三人はコの字になって食卓についた。一花が壁を背に、お琴はキッチンを背に、香はリビングを背に座った。全員が窓の外の青い空を眺めながら食べられるように。
「ロールパンに挟むのにいいかなって思って。」
一花が作ったお惣菜は茄子とブロッコリーの炒め物と、キャベツ・人参・玉ねぎの千切りを甘酢で和えたものだった。
「こっちのロールパンはチーズ入り。で、こっちの小さいのはチョコチップを入れたミニロール。」
お琴が手際よくロールパンに切り込みを入れて詰め始めた。
「お琴いつからパン焼くようになったの?」
「山登ったじゃん?あの時のパン屋のチラシ、読んだ?」
香は山登りに行った時に食べたパンのことを思い出した。天然酵母のおいしいパンだった。でもチラシなんてあったっけ?と覚えていない。
「低温熟成湯種法で作ってるって書いてあったんだよ。」
「冷蔵庫で発酵させるやつ?」
「あ、香知ってるんだ。」
「うん。東京にいた時パン教室行ってたから。」
「え?じゃ、作れんの?」
「んー、自分では作ったことないよ。先生が一次発酵まで準備してくれてたから、成型して二次発酵させて焼くとこしかやったことない。」
みんなと楽しく話しながら好きな形を作って、トッピングも好きにできて、しかも焼き立てを食べられる。そんなパン教室が香はお気に入りで、パンを食べたくなった時だけ通っていた。
「湯種はわかんない。なにそれ?」
「小麦粉をお湯でこねるってだけなんだけど、そうするともちもちしておいしいんだよ。」
「時間がたっても、もちもちのままだよね。」
一花はお琴からもらったパンを朝食に食べている。三日経っても焼きたてのパンみたいにもちもちしていておいしいのだ。
「このロールパンももちもちしてるね。おいしい。」
「いっぱい焼いてきたからさ、持って帰ってよ。」
お琴はカウンターに置いてある袋を指差した。香はひょいと立ち上がると袋の中を覗いた。
「わ!こんなに!焼くのたいへんじゃん。何回焼いたの?」
「大きいオーブン買ったから1回だけだよ。」
「え?!」
香も一花もぎょっとした。今食べるようにテーブルには大きいのだけで六つ、一花へのが四つ、香にはなんと両親の分もあって十個もある。それに加えてチョコのミニロールが数え切れないほどあるのに。
「一回でこんなに焼けんの?どんだけ大きいの買ったのよ。」
「業務用買っちゃった。」
照れ笑いのお琴に、一花と香は目を見張りながら笑った。
お琴はパンを焼くようになって、毎日パンを食べるようになった。湯種法だと一週間たってもおいしいから、週末に一週間分焼いておくのだ。そのために一度にたくさん焼ける大きなオーブンを中古で買った。
「平日働いて、週末だけパンやケーキを作って売る人っているよね。お琴もしたら?めっちゃおいしいよ、お琴のパン。」
香の言葉にお琴は、
「いや、わたし公務員だからさ。それはやばいっしょ。」
と笑った。
「でもね、結婚して主婦しながらパン屋もいいかな、なんて思ったりする。」
「え?先生辞めちゃうの?」
「んー・・、わたし、両親共働きだったからさ。弟がいたから寂しくはなかったけど、子ども産んだら家にいてあげたいかなって思ったりするんだよね。」
お琴の言葉に一花は緊張した。
このまま話が生まれ育ちのほうへいったらどうしよう。
こわくてテーブルをじっと見つめた一花だったが、
「ベランダに出てもいい?」
という香の申し出に救われた。
「もちろん、いいよ。」
香とお琴がベランダへ出た。香を追いかけるようにミーちゃんも出ていった。
「景色めっちゃいいねー。一花もおいでよ。」
香がダイニングの一花を振り返った時、香の顔をかすめるようにミーちゃんがひょいとベランダの手すりに飛び乗った。
「うわ!」
びっくりした香は後ろにのけぞった。そしてなんとその勢いで上げた手がミーちゃんに当たってしまった。
「あぶない!」
手すりから落ちそうなミーちゃんをガードするようにお琴が手すりの向こう側に腕を伸ばした。お琴の腕をクッションにミーちゃんはひょいと手すりに戻ると何もなかったように歩き出した。
「みーちゃん危ないでちゅよ。ここは六階でちゅよ。落ちたら死んじゃいまちゅよ。」
香はミーちゃんを抱きあげると、
「景色キレイでちゅねー。見えまちゅか?」
と自分の顔の横にミーちゃんの顔が来るように抱っこして、景色を見せた。
「だからその話し方、やばいって!」
赤ちゃん言葉の香を一花と笑おうと思ってお琴が振り返ると、意外にも一花は笑っていなかった。蒼ざめた表情で下を向いていた。
「一花?」
お琴の言葉に顔をあげた一花は、
「わたし高いとこ苦手だから・・。」とまたうつむいた。
そう言われると、リビングとダイニングにまたぐ広いベランダなのに、何も置いていない。部屋の中には大きな観葉植物がひとつ置いてあるのに、ベランダには植物もない。一花ならハーブをベランダで育てていそうなのに。
それどころかベランダ用のサンダルもない。洗濯物もベランダに干していないようだった。現に、リビングの窓の内側には、突っ張り式の洗濯干しが取り付けてある。腰の高さと頭の高さに竿が水平に渡してあって、タオルが一枚とハンガーが二つかかっている。室内干しをしているようだった。
ほとんどスタジオにいる一花のことだから、突然の雨で干した洗濯物が濡れないように外には干さないのだろう。そう思ってお琴はあまり気にしなかった。
「え?ベランダ出られないの?もったいないね。こんなにいい景色なのに。」
そう言う香に一花は、
「景色はここからも見えるよ。」
「あ、そっか。そだね。」
高所恐怖症なのに六階に住み続けることにも「大変だね。」の一言だけで、香もあまり気にしなかった。
20 結婚したい女たち 一花の家
景色をひとしきり楽しんだ香とお琴がダイニングに戻ると、やっぱり一花の元気がない。
「一花、どした?」
お琴が心配して声をかけた。それで気づいた香も、
「顔色悪いよ。」
と一花をじっとみつめた。
「最近いそがしくて。あんま寝てなくて。」
リビングにはたくさんの本が乱雑に置いてあった。開かれたページには人体図のイラストが載っている。ヨガのポーズをより深く理解するために、一花は解剖学の本で骨格筋の勉強をしているのだ。
もう人気ヨガインストラクターなのに、向上心を持ち続けて独立のために努力し続ける一花を、香は尊敬の眼差しで見た。
ところが暗い雰囲気にしちゃいけないと思った一花は、
「ごめんごめん、だいじょうぶだから。ね、それよりミーちゃんの足のそれ、香とおそろ?」
と話題を変えた。
ミーちゃんの足には香の作った水引のバングルが巻かれている。香の腕に巻かれた水色のバングルと色違いのピンク色だった。
「あそれ、私も気になってた。作ったの?」
とお琴も香に聞いた。
「うん、二人にも作って来たよ。」
香はカバンからバングルを取り出すと二人に渡した。一花には濃い紫にピンクが一筋入ったのを。お琴には萌黄色に黄色い筋が入ったのを。
「うわ!ありがと!!」
お琴が大声を出して喜んだ。
「これ、とめなくてもいいんだ。」
「うん、テクノロートを編みこんでバングルにしたの。固いでしょ。」
テクノロートは形状記憶のプラスチックで、針金のように使える。マスクのノーズワイヤーとして使われる便利な手芸ツールだ。これを一緒に編みこんだことで、自分の腕の太さに合わせて形を決められる。
ブレスレットとは違って留め具なしで、好きなとこに巻き付けて使えるから、きつすぎたり緩すぎたりすることもない。とても便利だ。
「色はね、二人の色にした。お琴のはね、前に着てた緑のシャツに合うと思う。」
「だねだね、この色スプリングの色だよね。ありがとう!」
腕の細い一花は肘よりも上、わきの下辺りにつけて、
「これ広げたり閉じたりできるんだ。すごいね。」
と感動している。
期待どおりに喜んでくれる二人に香は大満足していた。そんな香に一花がおずおずと切り出した。
「香、あのね、これをチャクラカラーで作ってもらえないかな。」
「わー、それいいね。作ってみる!七色だよね。」
ヨガでは体の中を「気」が流れていると考えられている。そしてチャクラとはその「気」が集まったり出たりする、高速道路のインターチェンジのようなものだ。股から頭頂まで体の中央を垂直に七つ並んでいると言われている。下から赤、橙、黄色、緑、水色、紺色、紫色と色もついている。
ヨガのポーズは、このチャクラを活性化する意味もある。チャクラの状態は人によって弱かったり強すぎたり様々だ。弱いと気が滞って体がだるくなって動きが鈍くなる。逆に強すぎると気が流れ過ぎてイライラしたり怒りっぽくなったり、落ち着きがなくなる。
一花は各チャクラに焦点を当てたレッスンを作ろうと思っていた。生徒さんの体に合わせてチャクラを正常な状態に戻していくコースを、プライベートレッスンでしようと思っている。
各チャクラをクリアしたら、このバングルをあげるといいと思った。クリアしたことが目に見えてわかりやすいと、すべてのチャクラをこなそうという意欲にもつながる。
しかも紙素材の水引は、自然志向の強い生徒さんたちにはウケがいい。きっと全部そろえたくなるはずだ。
その話を聞いた香の目はここ数か月で一番に輝いた。
「それ、すごいよ!」
そんな面白いことに、自分のバングルが一役買うなんて。大きな企画に参加する気分が一気に高まった。
「一色だけで作るのは出来ないんだ。テクノロートは透明と白色だけなの。今日のこれみたいに筋を入れるか、それか私やミーちゃんのみたいにグラデっぽくすると自然になるけど。グラデでいい?」
香が作るものならなんだってかわいいに決まっている。今までもらったどれも色合いがきれいでステキなものばかりだ。香のアクセサリーに全幅の信頼を置いている一花は、
「バングルのことは香にお任せするよ。」
と言った。
「ありがと。試作作ったら見てね。七色だから時間かかるかも。」
突然舞い込んだ大仕事に香はワクワクした。同じ家事を繰り返すだけの毎日が一気に華やいで思える。
「五セット欲しいんだ。」
実はプライベートレッスンをさせてもらえる生徒さんがもう三人見つかっている。一人は最初にプライベートレッスンをしてほしいと声をかけてくれた三波さん。二人目はそのお友だちの怜さん。この二人にはお試しでレッスンをした。そしてこれから毎週することに決まっている。
三人目は怜さんの妹さんだ。今年子どもを産んだばかりで産後太りをどうにかしたいと言っているそうで、紹介してもらうことになっている。来週お試しレッスンをしに行くのだ。
小さいお子さんがいる人たちには、自宅でできるプライベートレッスンは喜ばれる。今教えているスタジオでも託児サービスはしている。でも子どもが小さければ小さいほど、家を出ることだけでも大変だ。家に来てもらえるプライベートレッスンは、ママ友の口コミで生徒さんが増える可能性がある。
一花はなんとかこのプライベートレッスンを軌道に乗せようと頑張っていた。それで思いついたのがチャクラを取り入れたシステムだった。
「バングルはひとついくらになる?」
一花の問いに、香はキョトンとした。
「んー、よくわかんない。材料費払ってくれたらそれでいいよ。」
「だめだめ!ちゃんと払うから。」
前回、三波さんと怜さんのピアスはランチ代を払うという曖昧な支払い方になってしまった。香と対等な関係でいるためにも、きっちり払わなくてはならない。一花は慌ててスマホで検索した。
「七千円とかあるね。」
「え?!それは高すぎ!」
「二千円、千二百円・・。千二百円でいい?」
自分が買うのにも、これから香のアクセサリーを生徒さんに売ることになったとしても、売りやすい値段でもある。
「それは高いよー。」
「いやいや、香、水引だよ。手作りだし。高くないって。」
お琴はたまらず口を出した。水引という日本の伝統工芸を使ったアクセサリーは、お店で簡単に買えるものじゃない。珍しいからつけているだけでお洒落に思われる。香のくれる水引アクセサリーは、お琴にとっては宝石のように貴重だ。
「んーじゃあ半分の六百円でいいよ。」
「それだと、ピアスとか指輪の値段がつけられなくなっちゃう。バングルは大きいから千二百円にしよ。」
一花はあの好評だったイヤリングや、生徒さんたちが買いやすい指輪を売りたいと思っていた。
赤ちゃんを子育て中のお母さんでも、水引のアクセサリーは紙だからつけやすい。しかも、紙なのに意外と水にも強い。以前ポケットに入れ忘れて洗濯してしまったのだけど、大丈夫だったことがあった。
さらに、水引アクセサリーはレッスンの付加価値として申し分ない。ヨガできれいになって、水引という珍しいアクセサリーも買えるという、一花ならではのヨガレッスンにしたかった。
「そっか。じゃあ、千二百円・・。友だち割引で千円でいいよ。」
一花が生徒さんたちに香のアクセサリーを売ろうと考えていることが、香には嬉しかった。一花はかけがえのない大切な友だちだ。
「香・・、ありがと。」
一花と香は目を合わせて笑った。
この日は、夕飯の支度に間に合うように帰らなければならない香の時間が許すまで、三人はこれからしたいことを言い合った。
お琴はパン、一花はプライベートレッスン、香は水引アクセサリー。
言い合ううちに、「あれ?」っとなった。
「男の話が出ない!だめじゃん!!」
お琴のダメ出しに「ほんとだ!」と三人は大笑いしたのだった。
婚活で出会った三人なのに、最近はめっきり婚活の話をしなくなっている。もうタイムリミットの三十歳になったと言うのに。
「婚活もがんばろうよ!」
お琴の発破に、
「うん!」
と頷く香。希望は声に出して言うほうが叶うと信じる一花も声を大きくして言った。
「きっと出会えるよ!」
それに続けて三人は一斉に叫んだ。
「運命の男に!」
そんな三人に混ざってミーちゃんが「ミー!」と鳴いたことに、誰も気づいていなかったのだった。
21 結婚したい女たち お琴の選択
駅前のビルの三階にある結婚相談所Love&Peace。そこのコーディネーター桜咲は我が目を疑った。
今目の前にいるのは、三年前に入会した水野琴音のはずだ。しかしあの野暮ったい容姿は消え失せ、明るく柔らかい印象になっていて同じ人物とは思えない。
最近すっかり活動をしなくなっていたらこれだ。婚活以外で男ができて結婚が決まったのかもしれない。突然面談しに来たのは、その報告をしにきたにちがいない。桜は何を言われても平気な顔でいられるようにと身構えた。
ところが男の話は一向に出てこない。嬉しそうに女友達の話ばかりするのだ。しかもそのつるんでいるというのが、同じく三年前に入会した木下一花と、二年前に入会した立野香だった。
木下一花は婚歴はあるが容姿端麗、一人が寂しいと言って積極的に婚活していたから、すぐに決まるかと思っていたら、とんと活動しなくなった。水野さんの話では、ヨガインストラクターの仕事をスタジオ以外でも頑張っているらしい。仕事の方へ傾いてしまったようだ。
立野香は学歴も家柄も申し分ない上に、あの可愛い顔。男性たちからの申し込みが殺到した。それを一人一人丁寧に対応していたからすぐに決まるかと思っていたら、ぴたりと活動しなくなった。今も沢山の男性から申し込みがあるのに、ウンともスンとも言わなくなっている。そんなんだから、いつの間にかコーディネーターの中では「眠り姫」とあだ名がついてしまった。
まさか婚活仲間と遊んでいたとは。しかも、あのお嬢様の立野さんが農業を始めたと言う。驚いた桜は思わず口を挟んだ。
「立野さんも農業体験に?」
「そうですよ。香って、ああ見えて行動力がすごくて。前回はネコのミーちゃんを連れて来てました。いい息抜きになってるみたいなんですよ。」
農業体験は、お琴が二人を誘った。
パン作りを始めたお琴は、同時に料理にも目覚めた。きっかけは一花の手作り料理だった。
一花の家でレッスンの後お琴のパンを食べようとなったら、「お惣菜作るね。」と一花があっという間に一品作ってくれたのだ。
共働きの両親だったこともあって、子どもの頃から出来合いのお惣菜を食べていたお琴は、コンビニの惣菜を買って食べるのが常識だった。自分で焼いたパンには、コンビニのポテトサラダを挟むのが定番になっている。
料理なんて一時間とかかけてする厄介な大仕事だと思っていた。そんなお琴だったから、「え?もう出来たの?!」と、五分で作られた美味しい炒め物は魔法のように思えた。
「コンビニのとかより、自分で作った方がいいよ。体だけじゃなくて心にもその方がいいよ。」
と一花に言われたお琴は、そういえば、と思い出したことがあった。
お琴のクラスの男の子で、乱暴で手が付けられなかった子がいた。でもその子が、お母さんが妊娠をして家にいるようになったら、大人しくなったのだ。「寂しくて凶暴になっちゃってたのかな。」と思っていたら、その母親と面談をした時に意外なことを聞いたのだ。
最初の子、この男の子を産んだ時はデキ婚で、出産前日まで働いていたそうだ。産んだ後もすぐに職場に復帰したそうで。でも今回の二人目の妊娠では産休をもらって家にいることになった。それで料理を始めたそうなのだ。
「今まで手料理なんてほとんどしたことがなくて。でも作るとこの子が美味しいって食べるもんだからうれしくて。」
そういう母親にその子は、
「お母さんの料理おいしい!」
と、嬉しそうに叫んだ。その顔は、あの暴れん坊とは思えない無邪気な笑顔だった。
その話を職員室でほかの先生にしたら、こう言われた。
「あの子、とても行動がよくなったでしょ。それ、たぶん食べ物よ。出来合いのものを食べてるとキレやすくなるって言うからね。」
そう言われて、出来合いばかり食べているお琴は、そんなわけないと思ったのだ。手料理じゃなくてお母さんと一緒にいる時間が増えたから、精神が安定したのだと思っていた。だからコンビニ弁当を食べ続けたし、子どもが出来たら仕事を辞めた方がいいと思ったりしていた。
でも一花に、
「食べ物って、体だけじゃなくて、心も作ってると思うんだ。レトルトやコンビニのばっかり食べてて鬱っぽくならない?自分で作った作り立てを食べたほうが、元気出るよ。」
と言われたら、そうかもと思えた。
それで、一花に作り方を教えてもらったら「え、それだけ?」と驚くほどシンプルだった。
「そうよ、切って塩コショウで焼くだけ。火を止めたあとにごま油をかけるといい風味が出て美味しくなるよ。」
言われたとおりにやってみたら、お琴にもすぐに作れた。しかもおいしかったのだ。食べながら一花にlineで報告した。そしたら、
「ポテトサラダ好きなんでしょ。だったら、それも自分で作れば?」
と、レシピを送ってくれた。
それもまたとても簡単だった。電子レンジでジャガイモをチンして潰して、スライスした玉ねぎと塩コショウを混ぜるだけなのだ。ただし、スライスした玉ねぎは30分間放置してから混ぜるとなっていた。「なんで?」と打ち返したら、
「置いとくと、あの玉ねぎの辛みが甘みに変わるの。美味しくなるよ。」
と返信が来た。
さっそくやってみたら、本当にそうだった。玉ねぎを甘くするには、キャラメル色になるまで何十分も炒めないといけないと思っていた。それが置いておけば甘くなるなんて。魔法に思えた。
「料理っておもしろい!」
そこからお琴は食に興味を持つようになった。
調べていくと、ショッキングな事実に行き当たった。なんと、日本の食料自給率は30%を切っているという。種に関してはほぼ100%輸入なんだそうだ。その種も、自家採取できない種、F1種で、つまり、外国が毎年種をくれなかったら、日本で作れる野菜はないというのだ。
お琴は焦った。
「いつ食糧難が来てもおかしくないじゃん!」
その話を学校でほかの先生に話したら、自然農法の農業体験があると教えてもらった。種をまいて育てて収穫までさせてもらえると言う。
自分で野菜を育ててみたいと思ったお琴は、それに参加することにした。勿論あの二人を誘って。
22 結婚したい女たち お琴の選択
町から車で三十分走ると、野生の木々が生い茂る村がある。そこで大々的に苺のハウス栽培をしている杉野さんが農業をいろんな人に体験してもらいたいと、使っていない畑二面を農業体験用に開放していた。
一人一畝を割り当ててくれて、お琴の隣は香、香の隣は一花の畝だった。
三人が参加したこの日は、ほかにも十人ほどいた。ほとんどは夫婦で、農薬を使わない安全な自然農法だけあって、子ども連れが多かった。
まずは畝作りから始まった。野菜を育てる場所にこんもりと土を盛るのだ。九十センチの幅で二十センチの高さ、長さは二メートル。粘土遊びのようでもあり、土木工事のようでもあり、初めての畑作業に三人ははしゃいだ。
「香、上手だね。」
お琴は隣の香の畝が同じ幅で真っ直ぐに横たわるのを見て感心した。自分のは広かったり狭かったり、そして最悪なことに畑の側面に対して斜めに横たわっている。
「直したげる。」
香はそういうと、畝の幅と同じ長さの枝を置きながら幅をそろえ始めた。あっという間に同じ太さで畝が伸びた。
「まだちょっと斜めだね。そこ削ってこっちに足せば直ると思うよ。」
「わかった。やるやる!」
お琴は香に言われた部分の土を掘り返して、反対側へ盛り直した。
「きれいになったね。」
「うん、ありがと!この枝いいね。香ホント頭いい!一花も使いなよ。」
枝がお琴から香へ、香から一花へと手渡された。それを使って一花も自分の畝の幅をきれいに直した。
「あなたたち、上手ね!」
杉野さんの奥さん、実紀が声をかけた。
「一花ちゃん、それグッドアイディア!」
笑顔で一花が手に持つ枝を褒めた。
「これ香が使ってて。スゴイですよね。」
一花もお琴も誇らしげに香を見た。でも実紀はちらりと香を見てチッと舌打ちをするように目を逸らした。そして、
「じゃあ次は種を蒔くから、好きな種を取って来てね。」
と、一花に言った。
好きな野菜を植えていいと言われて、お琴は「これで鍋しよーね。」と、大根と白菜を選んだ。
香は人参とカブ、一花は小松菜とちぢみ菜を選んだ。
「食べるの楽しみー!」
種を土の中へ埋めながらお琴が言った。それを聞いて香と一花は笑った。
「お琴、早いよー。まだ種じゃん。」
三人でけらけら笑っていたら、一花の隣の壮太君も笑った。
壮太は今回の農業体験の唯一の独身男性だった。婚活女三人より一つ年上で、介護施設で調理をしているそうだ。無口で、朝集合した時は大きな木の下で手を振って何かしていた。変わった人という印象が強かったが、三人につられて笑ったことで、少し打ち解けた。
「今日はここまで。これから芽が出るまで周りの草を抜いたり水をあげることになります。来れる人は平日の好きな時に来て世話してもらって構いません。週末しか来れない人は、私たちが代わりに水だけはあげます。草は週末に抜いてください。」
実紀さんからそう説明されて、お琴と香は水やりを頼んだ。一花は意外にも自分で水やりをしに来ると言う。
「お琴と香の分も私がやっといたげる。」
と、言い出しっぺのお琴よりもやる気になっていた。
最後は杉野さんの大きな家の庭でお茶を飲んで話し込んだ。一花と実紀さんは気が合うようで、すっかり仲良くなっていた。でも香にはなぜだか冷たい実紀だったから、あまり話に入れない香は、壮太がまた大きな木の下で手を振っているのを見つけて駆け寄った。
「何してるんですか?」
突然かわいい香に話しかけられて、壮太は顔を赤くしながらも答えた。
「九字切り。」
「九字切り?何ですかそれ?」
それは日本で昔から伝わる護身法の秘術で、密教や忍者が使っていたという。九つの文字を表す印を手の指で結び、縦と横に手刀を切ることで、邪気を払って場を清め、魔除けになると言う。
そこから香は、なんと一時間も壮太から九字切りのレクチャーを受けたのだった。
「もう置いて帰ろうかと思いましたよ。壮太君に送ってもらえばいいかなって。」
「立野さんが?」
それを聞いて桜は腑に落ちなかった。香はあの少女漫画のようなファンシーな顔立ちだけど、話をするととても現実的だ。そういう男性を好きになるとは思えない。どちらかと言うと木下さんの方がそういう人は合うような気がする。
「で、もう帰るけどって声かけたら、『私も帰る!』って戻ってきたんですよ。『邪魔しちゃった?』って言ったら、『え?なにが?』」って。ただ九字切りを知りたかっただけだったみたいで。一花が『壮太君のこと気に入ったの?』ってズバリ聞いたんですけど、『ああいう人タイプじゃない。』って香はケロッとしてて。」
立野さんらしい。桜はありありとそんな立野香を想像できた。
「香のスゴイとこは、あのとき壮太君に教えてもらって、もう覚えちゃってて。毎日九字切りをお母さんにしてるって言うんですよ。」
「え?病気のお母さんに九字切り?」
「はい。病気治癒の呪文があるそうで。」
そうなのだ。香は壮太から教えてもらった印を結びながら、天地玄妙神辺変通力治を唱え、母親の病気を治そうとしていた。自分がこの家から解放されるためにも必要なことだと、大真面目にやっていた。
突然娘が自分に向かって印を結び呪文を唱えるものだから、
「あんた、なによ!」
と、香の母はギョッとした。ところが、
「これね、病気が治るおまじないなの。昔からあるんだって。お偉いさんたちがしてたんだよ。」
と言われて今ではされるがままだ。これをしている間は、ミーちゃんが神妙な顔で香をじっと見つめるような気がする。そんなミーちゃんを膝に乗せて、香に印を切ってもらうのが日課になっている。
「なんだか拝まれてるみたい。お釈迦様になった気分よ。」
と言う母に香は、
「お陀仏だ―!」
と言って二人で笑った。
「次に行った時、香がミーちゃんを連れてきたんですよ。で、壮太君には目もくれないでミーちゃんにつきっきりで。ほんとに壮太君には興味ないみたいで。」
壮太はがっかりしているように見えた。シャイな壮太は自分から話しかけることなんてできないから、結局香と話すことはなかった。
「で、思ったんです。農業体験は既婚男性が多いし独身がいてもやっぱ香を気に入るだろうし。だから、農作業と婚活は一緒にできないなって。いっしょに畑をしてくれる人がいたらなんて思ったんですけどね。」
香と壮太が話し込んでいた時にお琴は大いに焦った。自分は何をやっているんだと。女子力をあげようとメイクもお洒落も、そして料理までするようになったというのに、肝心の男がいないじゃないか。香のように積極的に話しかけなくてはいけない。婚活をしなきゃいけない!
そしてあの事を思い出したのだ。
お琴が結婚相談所で入会手続きをしていた時、ちょうど桜に挨拶をしに来た女性がいた。
「ありがとうございました!桜さんに頼んでよかったです。すっごいいい人と出会えて。ありがとうございました!」
その声は、今まさにこの世の幸せをすべて手に入れたという喜びに満ちていた。
「そうだ、私も桜さんに頼もう!」と思いついたお琴は、今日桜に会いに来たのだ。
長々と一花や香の話をしていたが、やっと本題に行き着いたお琴は桜の目をじっと見つめて言った。
「桜さん、誰か紹介してもらえませんか?」
結婚が決まったと報告を受けるのかと思っていたら、紹介して欲しいと言われて、桜はビックリした。でも、すぐに気を取り直した。
この道四十年の桜は、ここまで変貌したお琴の努力に思いを馳せた。そして自分を頼って来てくれたことを嬉しく思った。
何が何でも水野さんの努力に応えたい。
「わかりました。ぴったりの人をご紹介しますね。」
桜は自信を持って請け負った。
23 結婚したい女たち 香の選択
(私も行きたくない!)
お琴から「次の畑は行けない」とlineが来た香はそう思った。
でもまずは様子見に「手はどう?」と一花にlineを打った。するとすぐに手の写真と「もう治ったよ!」が来た。
うっすら痕は残るが、ほぼ治っていた。帰る時に蒼ざめた顔つきだったから、実紀さんが言うように感染症にかかっていたらどうしようと心配していたけれど。何ともなくて香はホッとした。
(よかった。まさかミーちゃんが一花をひっかくなんて・・。)
ちらりとミーちゃんを見た。いつもの可愛いミーちゃんがいる。
前はお琴のこともひっかいたことがあった。あの時は爪を切ったばかりで事なきを得たけど、今回は違った。そもそもミーちゃんを連れて行く気なんてなかった。それがあの朝、朝食の片付けも風呂掃除も終わり、もうお琴が迎えに来る時間だと慌てて出かける準備をしていた。そしたらミーちゃんが近づいてきて「みー」と鳴いたのだ。その顔はどこか寂しそうだったから、
「お留守番、嫌でちゅか?一緒に行きまちゅか?」
と聞いたら、
「みー!」
と元気良く鳴いたのだ。それは香には「行きたい!」と聞こえた。それでそのままミーちゃんを連れて行ったのだ。
案の定、畑でのミーちゃんはアイドルのようだった。「かわいい!」とみんなが寄ってきた。ただし実紀さんを除いて。彼女だけはいつものように、気に食わなさそうな顔でミーちゃんも香も見るのだった。
作業を始めるとミーちゃんのこともすっかり忘れて、香は畑仕事に熱中した。自分で植えた種からたくさんの芽が出ていたのだ。
「一花ありがとね、お水。いっぱい芽が出てる。」
香は植物を育てるのが苦手だった。部屋に観葉植物を置いても必ず枯れてしまうのだ。そんな自分でも野菜が作れる。香はうれしくてたまらなかった。
「芽がたくさん集まっているところは、ひとつを除いて間引きしてください。」
と実紀さんから声がかかった。そこで香とお琴は間引きに勤しんだ。平日も通っている一花は、もうきれいに間引いてあったから、一花に教えてもらいながら引っこ抜き始めた。
「20cm間隔で残しておくといいよ。」
と言われても、せっかく出た芽を抜くのは気が引ける。つい、小さくて育ちの遅い芽ばかりを抜いてしまう香に、
「香、そこも全部抜くの。残すのはひとつにしないと大きく育たないんだって。」
と一花から声がかかった。
「だって、かわいそう。こんなに立派に芽を出してるのに・・。」
香は生育の良さなんて関係なく、生きている場所のせいで引っこ抜くことを理不尽に思った。
能力主義や実力評価が叫ばれる社会だけど、実際はどうだろう。この間引きと同じ。どんな人間なのか、何ができるのかなんて関係ない。どこにいるかで実を成すチャンスが与えられるのだ。
香はまるで自分はこの間引かれた芽と同じようだと思った。社会から間引かれた自分が惨めで悲しい。沈む心で「ごめんね。」とつぶやきながら二つ並んだ大きな芽のひとつを抜いた。
ところが不思議なことに、ひとつ抜いたら次を抜くのはもっと楽に抜けた。次第にスポスポと同情もためらいもなく、まるで機械仕掛けのように次々と抜けるようになった。
とその時、「みー!!!」とミーちゃんの悲痛な声がした。
ハッとして顔をあげた香が見たのは、畑の横で子ども二人に囲まれたミーちゃんだった。とっさに香は叫んだ。
「こらー!ミーちゃんをいじめちゃダメ―!!」
鬼の形相でミーちゃんのもとへ走っていって抱き上げた。
「ミーちゃんになにしたの!」
と怒鳴りつけると、子どもたちは黙ったままうつむいた。この二人は両親に連れられて農業体験に来ている兄弟で、兄は小学校五年生、弟は小学校二年生だ。
「なにもしてないよ。」
お兄ちゃんの太一がつぶやくように言った。
「じゃあ、なんでミーちゃんが鳴いたの!」
怒りにまかせて問い詰める香に、弟の信二が言った。
「お兄ちゃんが石投げた。」
「投げたの?」
香は太一をじっと見つめた。決して逃がさないぞという気持ちだった。太一は観念したように、こくりと頷いた。
「そんなことしたら、バチが当たるからね!」
香は憤慨して叫んだ。そして可哀想なミーちゃんをなでながら傷がついているところはないかと調べた。怪我はしていないようだった。
香がミーちゃんに気を取られているのをいいことに、太一は逃げるように走っていった。それを追いかけるように信二も走っていった。
ぷりぷりしながら香は畝へ戻った。
「バチが当たるって何?」
お琴と一花が心配そうに香を見た。畑で作業をしている人たちに香の怒鳴り声は丸聞こえだったのだ。
「子どもがミーちゃんに石を投げたの。ひどいよね!」
「子どもなんて、そんなんだよ。」
と、小学校の先生をしているお琴は笑った。一花は、
「ミーちゃんは大丈夫なの?」
と心配してくれた。
「うん、うまくよけたみたい。どこも怪我してない。」
と話していたら、あの二人の母親が来た。
「ごめんね。太一はやんちゃで。困ってて。」
四十二歳の女性だった。「大丈夫でしたから。」と香が答えていると、
「太一!戻ってきなさい!」
と、父親が大声で叫んだ。十歳年上というご主人は体格のがっしりとした人で、運送会社で働いているという。
「もう全然言うこと聞かなくて。いつもああなの。困ってて。」
奥さんはそれだけ言うと子どもたちの方へ歩いていった。
「きょうは人多いよね。増えたよね。」
香が見回すとざっと三十人はいる。子ども連れが多いとは言え、最初に来た時の倍の人数だ。
「まだまだ増えるって。隣の畑まだ空いてるでしょ。あそこもいっぱいになるらしいよ。」
通い詰めている一花はかなりここに詳しくなっている。
「そろそろお昼にしましょう。間引きの食べられそうなのはこの籠へ入れてください。壮太くん、お願いね。」
実紀さんの号令で香たちもお昼の準備に入った。調理の仕事をしている壮太は料理を手伝うらしい。
通い慣れている一花は、「野菜洗おうよ。」とお琴と香を洗い場へと連れて行ってくれた。そこにはご主人の杉野さんがいて、
「あ、一花ちゃん。じゃ、頼むね。」
と土の付いた野菜を置いて行ってしまった。
三人は亀の子たわしで大根と人参を、そして小松菜を洗った。洗い終わると台所の壮太のところへ持って行った。大根と人参を千切りにしてほしいと言われてお琴と香が切った。小松菜はきのこと炒めるというので、一花が切った。
トトトトトンと調子よく小刻みに音を立てながら切る香の手元を見て、お琴が叫んだ。
「香、なにそれ、やばいって。」
香の千切りした人参は、コンビニのサラダに入っているような糸のような細さだったのだ。
「ちょっと、すごい!」
一花も嬉しそうに叫んだ。
「毎日やってるから、慣れちゃって。」
大笑いする三人に、実紀さんが近づいてきた。一花が、
「見てくださいよ、香すごいんです!」
と言うと、
「あらほんと。」
と、ぷいっと行ってしまった。
「どうしよう、私の大根、こんなに太いよ。」
お琴の切った大根は香の人参の5倍は太さがあった。その大根と人参を甘酢で和えながらお琴は自分の下手さを笑った。
「いろんな食感が出ておいしくなるよ。」
と慰める香に、
「香、それまじ嫌味じゃん!」
と言い返すお琴。三人はまた大笑いした。
楽しく料理をし終わると、香はミーちゃんの食事の準備に取り掛かった。車へ戻り、ミーちゃんお気に入りのキャットフードをカップへ入れてみんなのところへ戻った。
そして、ここから、あの地獄が始まったのだった。
ここから先は
¥ 300
小説「梅すだれ」を連載中です!皆様の支えで毎日の投稿を続けられています。感謝の気持ちをパワーにして書いております!
