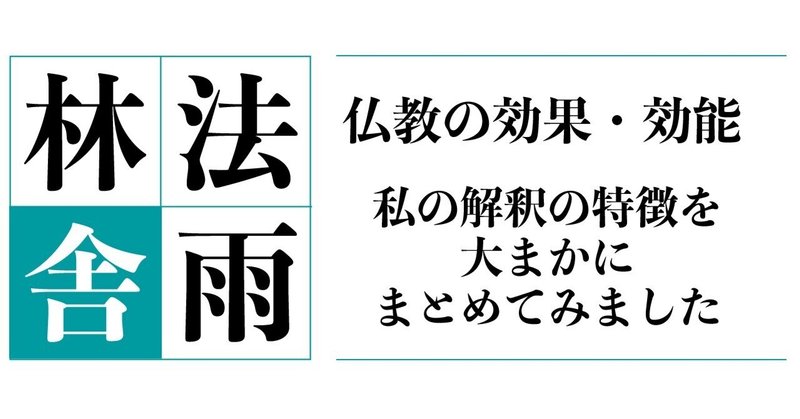
仏教の効果・効能
仏教を学んだり信仰したりすることの意義とは?
「宗教」というものは体験して初めてわかるものですので、外から見ているだけですと、どこか掴みにくいものがあります。もしかすると、この文章をお読みの方の中にも、「少し興味はあるけれど何だかよくわからないなあ。」というモヤモヤを抱えている方もいらっしゃるかもしれません。
最近は、何もかもがスピーディーで、ネット上の記事も最初に「この記事を読むとわかること」と内容の要約が載っていたりします。私自身、仏教はじっくり時間をかけてじわっと理解を深めていくものという感覚がありますが、この時代に生きているので、自分の頭の中を整理するのも兼ねて、お釈迦さまのお教えを学ぶことが人にどのような変化をもたらすものなのかをまとめてみたいと思います。
私の解釈の特徴について
この効果・効能について考えるにあたりまして、まずは私自身がどのような視点で仏教を見ているか、ということを書かせていただきたいと思います。といいますのは、お経というものは読み手のバックグラウンドによって光のあたる部分が微妙に異なり、解釈・表現が変わってくるものと思うからです。
例えば、20年程前に話題になった書籍、「生きて死ぬ智慧」は生命科学者でいらっしゃる柳澤圭子さんによる般若心経の現代語訳でした。書籍の帯には「心訳」という言葉が書かれていましたが、まさしく言い得て妙、柳澤さんの生命科学者としての知識と、人生でご経験されたことが混ざりあって、深遠で力強い訳となっており、私自身、心の奥底が震えるのを感じました。学問的ではなく直感的に理解されている印象を受けました。
私のお経の解釈も学問的ではありません。研究者のように文献を忠実に辿るということではなく、直感的に感じて理解したことを書かせていただいているという意味で、エッセイのようなものです。そのため、論拠が曖昧であったり、論理的には飛躍している部分も出てきてしまうことをあらかじめお許しいただきたいと思います。
その上で私の解釈の特徴をあげるとすれば、それは、人間の思考性にスポットライトをあて、その思考の働きの中に仏様のご存在を見出そうとしていることであります。
したがって、私の考える仏教の効果・効能は、
心が変わり
↓
物の見方が正しくなり
↓
思考性が整う
ということに集約されます。
例えば、〈無量義経十功徳品第三〉には、「仏さまのお教えに沿って生きるとどのような良いことがあるか」が「功徳」としてあげられています。
『第一に、是の経は能く菩薩の未だ発心せざる者をして菩提心を発(おこ)さしめ…』
『慈心(じしん)を起(お)こさしめ…』
『嫉妬を生ずる者には随喜の心を起こさしめ…』
『慳貪の者には布施の心を起こさしめ…』
『瞋恚(しんに)盛んなる者には忍辱(にんにく)の心を起こさしめ…』
『懈怠(けだい)を生ずる者には精進の心を起こさしめ』
『散乱の者には禅定の心を起こさしめ…』
『愚痴多き者には智慧の心を起さしめ…』
のように第一の功徳として示されているのは、まさしく心と思考性の変化です。「経」即ち「お釈迦さまが説かれたお教え」は、何よりもまず「菩提心」というやる気・向上心を起こさしめるものであります。
そして、具体例としては、「慈悲心が湧いてくる」「元々は嫉妬深い人だったとしても、他者の喜びを自分のことのように共に喜ぶ心持ち」になり、「物惜しみするケチな人の心にも人に施す心が湧き上がる」。「傲慢になりやすい人は謙虚になり」、「キレやすい人には辛抱強さが身につく」。「怠け癖がある人には頑張る力が授けられ」、「気が散りやすい人は心が常に落ち着いた状態になる」。「クヨクヨ愚痴って嘆いているような人であっても、解決手段を思いつく智慧が与えられる」等など・・・経典の言葉そのままですと難しい印象を受けるかもしれませんが、内容は極めてシンプル。素朴に「こんな心の人になれたらいいなあ」と思うことばかりです。
人間はつい欲張ったお祈りをしがちですが、経典には「信仰すると裕福な暮らしができるようになります。」などということは書かれておりません。人間の都合で祈るのではなく、仏様の説かれるお教えに適った祈りにしなければいけません。
少し話がそれましたが、仏教の効果・効能は「心と思考性に良い変化をもたらしてくれること」であるのはお分かりいただけたと思います。
信仰しても「苦」の原因となる事象そのものはなくならない
さて、仏教の効能・効果の大筋が見えたところで、仏教の大元を見直してみたいと思います。お釈迦様は四苦八苦に代表される「苦」に悩み、その問題を解決するために出家されたと伝えられていますが、お釈迦さまのようにご修行をされて悟りを開かれたとしても、それらの「苦」の原因となる事象がなくなるわけではありません。どんなに懸命に祈ったところで死から逃れることはできないのです。
では、お釈迦さまはどのように「苦」の問題を乗り越えられたのでしょうか?
心が変化することでものの捉え方が変わる
先ほどあげましたように、お釈迦さまのような修行をしてもたらされるのは次の変化です。
心が変わり
↓
物の見方が正しくなり
↓
思考性が整う
つまり、心が変化することでものの捉え方が変わり、苦が苦でなくなる、と説いているのです。
「苦が苦でなくなる」と言いましても、無感覚になるわけではありません。生きていれば、辛いこと・悲しいこともあるでしょう、むしろ、人生は苦悩の連続と言った方がいいかもしれません。お釈迦様はこの世を「苦海」と言われています。
しかし、そのような世界であっても、仏様のお教えに沿っていれば、「苦」の中に意義を見出すことができ、倒れることなく前に進んでいくことができるようになる・・・これが最大の効果・効能といえるでしょう。
このような効果・効能が得られるようになるには、「人間には永遠不滅の霊魂が内在しており、その霊魂が主体になって輪廻転生が繰り返されている」、「人間が生きる目的は人間存在の主体である霊魂をレベルアップすること」という仏教独特の世界観・人間観が多少なりとも信じられるような心境になっていることが必要ですが、これについてはまた追々書いていきたいと思います。
人間は、一人で生まれて来て、苦海を生き抜き、一人で死んでゆかなければなりません。自分の人生は自分で背負うしかないのです。
暗闇の中、一人ぼっちでいるのは心細いことです。そのような人間にとって、お釈迦様の説かれたことは道を照らす灯火になるかもしれません。灯火とは「正しきモノの考え方」です。明かりさえあれば、一歩一歩、向かうべき方向に歩んでゆくことができるのです。
明るい心には仏が宿るよ
というお言葉があります。明るい心をもたらす働きこそが仏様のお力、明るい心自体が仏様と言っても良いでしょう。
自分自身がしっかりとした思考性を持っていれば心は光るものです。仏様は外にいらっしゃるのではなく、自らの心の中にいらっしゃるのです。「外の仏様にすがる」のではなく「内なる仏を育てる」、それが「成仏」、「仏に成る」ということだと、私は思います。それが仏の道を歩んだ先にあるゴールです。
経典の内容をベースにした物語を創作して書籍化することを目標にしております。よろしければサポートをお願い申し上げます。
