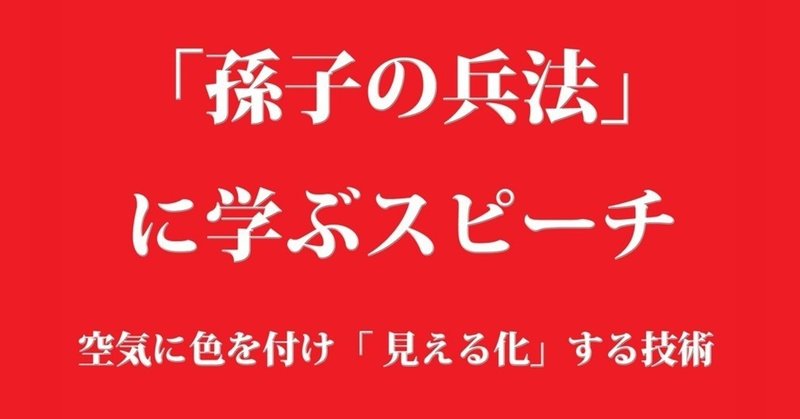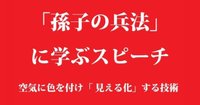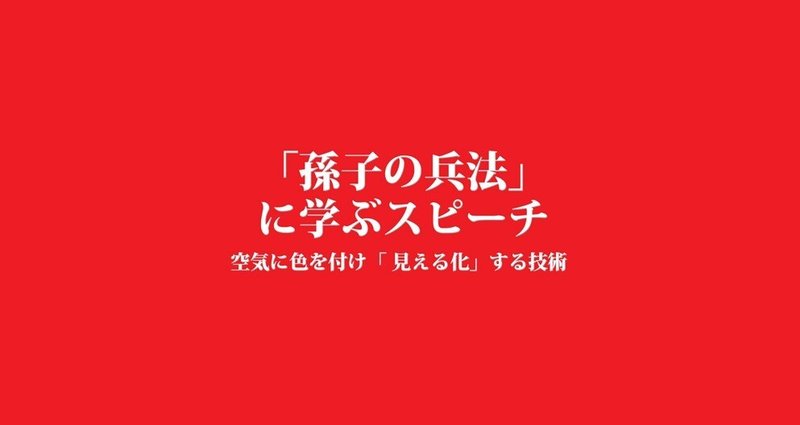
孫子の兵法13篇を、スピーチ(広い意味での言葉の運用)を成功させるための方法論という観点で意訳。合わせて現実の事例に即して解説
巻末付録①「ミニ講座 スピーチライターの実務に学…
- 運営しているクリエイター
#スピーチ
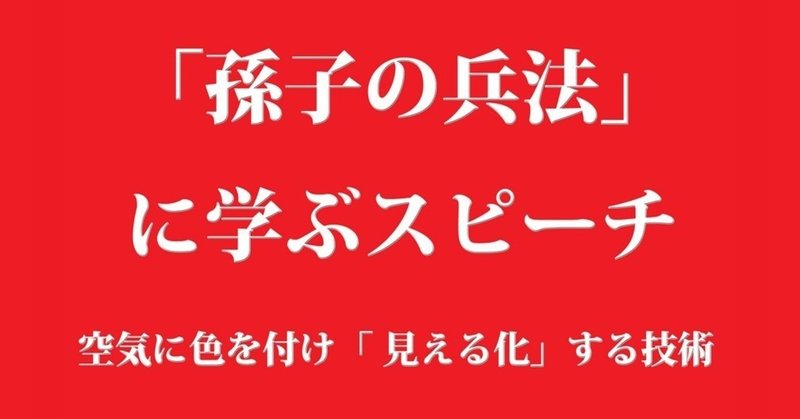
「孫子の兵法」に学ぶスピーチ 空気に色を付け「見える化」する技術(巻末付録①「ミニ講座 スピーチライターの実務に学ぶ」)
スピーチライターの役割は、「(書いた物を)読み上げるスピーチ」における原稿作成です。基本的には以下の手順で仕事を進めていく形になります。 1.話す人に取材を行う。 スピーチの目的は「話す人の身の丈(人格・見識)の高さ」を「見える化」することです。 仮に身の丈に合わないスピーチを行ってしまうと、後で「あの人はいっていることと、やっていることが違う」という事態を招きます。 人によっては、「自らの見識のなさを、盛りだくさんの情報でカバーしたい」という人もいますが、悪い意味で
¥100