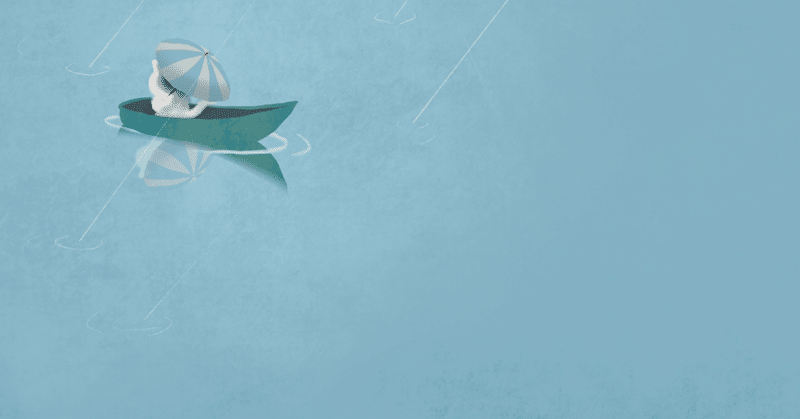
舟を編むを読み丸【読書感想文】
読書家の元に生まれているのに23歳になるまで読んでいなかった『舟を編む/三浦しをん』を読んだ。
サラリーマン的な群像劇だと思って入ったら、不器用で生真面目なラブロマンス込み込みのハッピー小説だったらしい。小説はほとんど読み切らない自分でも、キャッキャしながら読めた。
読んだ動機は「言の葉って、面白!(NHK教育みたいなリューク)」だ。辞書編纂って絶対ムズいよね〜という好奇心も含め、ずっと前から読みたいとは思っていて「これ絶対好きだから!今暇なら!」と自分から自分に向けてオススメしたような感じだ。12年越しの読み始めだけど、思っていたよりスパッと読めた。
・馬締光也の質感が凄い。このロジカルなのか感覚派なのかわからない薄ら変さ、魅力的。ドラマ最新版(上司版)が野田洋次郎なのもなんか頷ける。見てないけども。
・香具矢さんが応える部分の胸のアツさは言わずもがな。というか展開全部が行って欲しい方向に進む。ベタだとわかっていても……うおおおおお!!いけいけいけいけ!!
・松本先生の言葉が凄い。偉大。本当に居たんじゃないかってくらい重量感がある。
・洒落のバランスがすごくちょうどいい。一般的な茶化しやモノの感知の仕方って、実際これくらいだよね!っていう。
・全体的に「社会への自分自身の熱を感じる瞬間」みたいなものにもフォーカスされていて、なんだか働きたくなる。
・紙の質感についてとか、辞書編纂のパズル的な側面とか、うっわそうだよな!!って膝を叩きたくなる要素が散りばめられてて飽きない。
・なにより辞書に「大渡海」ってつけられる(フィクションだからこその)嬉しさが凄い。言葉の海を渡る、って聞こえたぜ?
「言葉とは、言葉を扱う辞書とは、個人と権力、内的自由と公的支配の狭間という、常に危うい場所に存在するのですね」
「言葉は、言葉を生み出す心は、権威や権力とはまったく無縁な、自由なものなのです。また、そうであらねばならない。(後略)」
ここも凄かった。言葉のアップデートや簡略化は(日本人ならより明確に)感じる問題点で、お偉いさんにあたるキャラがこれを口にしているのが本質的かつ有難すぎる。
松本先生についていけてよかったです!!!って最後の方なのに思っちゃった。
その言葉を辞書で引いた人が、心強く感じるかどうかを想像してみろ
これも説得力があった。辞書で言葉を知った時のワクワク感と欲しかった説明を引けた時の心強さは、(今でこそ薄い気持ちとはいえ)昔から変わらずにある。想像力と言葉だけで、人はどこまでも飛び渡っていける。
ベタな展開であることで「言葉と辞書」がテーマである一冊にしかできない読み心地の軽さと伝えたい重みの両立を見た気がする。
純でテクニカルな恋物語、誰が読んでも納得のテンポ感。節々のユーモアや言葉の節々へのこだわりが、暖かく艶やかに光ってるんだな、と感じた。
本屋大賞っぽさというもの、これでこそペストセラー!って感触がひしひしとあって(感じ方が学生並みなのかもしれないけど)楽しく読めた。充足感やよし。
こなまるでした。
フォローとスキを求めています
