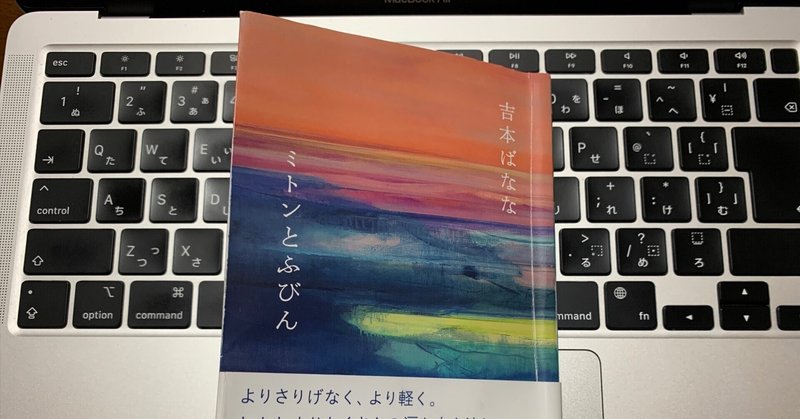
旅の意義、後半
吉本ばななさんの「ミトンとふびん」の残りを読んだ。
人が亡くなると、親しい人は、その後にも残っているかもしれない何かを追い求めてしまう。生き残った人は、亡くなった人との繋がりをどこかで保ちたいと思う。何を考えていたのかを後から追って確かめたくなる。「カロンテ」の主人公がしていた、ローマへの旅の目的である。この旅の前半では、主人公は、亡くなった親友の痕跡を求め続け、何かを思い出すとは涙を流していた。何をしても、何かが足りないような気分になっていた。しかし、旅も後半に差し掛かるころ、主人公は奇跡のような出会いをすることで旅の目的を達成し、親友がいなくなったことを乗り越えた。達観できたと言っても良いかもしれない。そんな奇跡は、なかなか現実には起こらないような気もするが。
亡くなった人との繋がりを見つけにいくことで、この主人公でもあったように、確かに悲しみが増幅することはある。それに対して主人公は、奇跡のおかげもあって、人間関係の面でやるべきことを果たすことで、向き合った。一方で、やるべきことを果たすと、また状況は変わる。ローマという街との出会いも、そこでの人との出会いも、その親友を介していたからこそ起きていたことだったからだ。その親友がいなくなった後、自分の使命を果たした主人公は、その街に行く理由もなくなり、そこでの知り合いと会う理由もなくなる。これはこれで寂しい気もする。実際、主人公が最終日の夜に流した涙は、親友のいなくなったローマで一人ぼっちでいることによる淋しさも原因にはあるだろうが、親友の痕跡を探す旅が終わろうとすることで、親友を通して感じていた、その街や知り合いへの親近感が薄れることも原因にあるのではないだろうか。
この話のようには奇跡が起こらなくとも、時間が解決してくれる側面もある。その時間の力は半ば強引ではある。生きている人は、次第に自分の目の前の生活に追われるようになり、亡くなった人といた実感が薄れていってしまうのだから。記憶力が良ければ、思い出は薄れないかもしれない。写真だって映像だって、形にして残せる時代だ。しかし、実感は確実に薄れていくと思う。私は、そんな、実感が薄れていくことが怖い。これは、なにも亡くなった人にのみ言えることではない。離婚や別れを機に、繋がりが切れることだってある。友達とだって、卒業や結婚、引越しで環境が変われば、会うことや話すことが減ることもあるかもしれない。目の前の人生を生きていく自分にとって、その人たちは過去の人になっていく。逆に、その人たちにとっても、自分は過去の人になっていく。時間に抗っても、阻止することはできないのが辛い。いつまでもこだわると、自分だけが世の中から取り残されていくだろう。未練だと正直に認めよう。でも、それを認めたところで、この辛さは、どう乗り越えれば良いのだろう。本から、少々離れてしまった。
最後の話、「情け嶋」は、ヒリヒリする心を癒してくれるような話に思えた (少なくともそう思った瞬間はあった)。自分がどんな人生を歩み、どのように死んでいくのか、静かに考えさせてくれる。
いつの間にか、自分が他の人の人生の中で要らないものになっている、そんな苦痛を乗り越える主人公。主人公は感情の起伏が無いのかと思ったら、隠している、表に出せていないということが、余計に読者の私をヒリヒリさせた。しかし、八丈島での、特に登山での思考を経て、人生の最後に何が残れば良いのかを読者にも分からせてくれた。
「最後に見るのがそれなら、人生悪くない。」
なんと生きるのが楽になる言葉だろう。そんな景色を見ることになるだろうと、想像できることが羨ましい。しかし、そんな景色を悪くないと思えるのも、その想像の中で自分に向けられる視線が、自分にとってかけがえの無い人 (パートナーである必要はない)や、自分を認めてくれる人によるものであるからだろう。
そして、その想像を通して、主人公は自分の心の働きに回帰させている。そのことで自分を納得させている。シンプルで分かりやすい。でも本質的だ。
一方で、
「どんなに他人と親しくなり、その人のことをわかったつもりになっても、結局その他人とは自分の中に生きているその人にすぎない。その人本人ではない。」
私がこの本の中で、最もヒリヒリした言葉だ。人間関係の限界を感じさせる一言だ。私は、自分が他の人と同化したいと思っているなと自覚することがよくある。それは、支配欲による感情ではなく、相手のことがたまらなく羨ましくなってしまうという感情によるものだ。羨ましくなるものは、その人の社会的地位や収入、学歴ではない。その人の価値観に、なんて素敵な生き方、考え方なのだろうと思って羨むことになるのである。でも、相手に同化するのはおろか、結局は、いくら親しくなろうとも、いくら信頼しあっていても、相手を全て知ることもできない。それでは、相手から自分がどう思われているかすら分からない。想像で補完あるいは修正し、ある程度の所で自己満足をして納得するしかないのだろう。それを辛く思う自分を突き放すかのような言葉である。
この本を通して、私は旅の意義が一応は分かった気がする。旅は、自分の存在意義を分からせてくれるのだ。それは、旅先の土地で出会うあらゆるものによって。「ミトンとふびん」の主人公は、レストランで出会った人々によってそれを自覚できた。その意味では、ヘルシンキへの新婚旅行だけではなく、父親との再会も、旅行と言えたのかもしれない。旅先では、自分は見知らぬものに囲まれる。自分と世界との間には境界が実際に存在するということを、たとえ大自然のど真ん中でなくとも、小さな田舎の中にいようとも、思い知らせてくれる。それで、ただ終わりのこともあれば、感情を大きく揺さぶられることもある。何か自分にゆかりのある旅先だったら、「カロンテ」の主人公のように悲しくなることもあるだろう。でも、旅先での出会いと、その時の自分の思考が、自分の役目を明示してくれるのだ。それを通して、旅に行く人は、旅から帰った後に自分が進むべき道を自覚できるようになるのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
