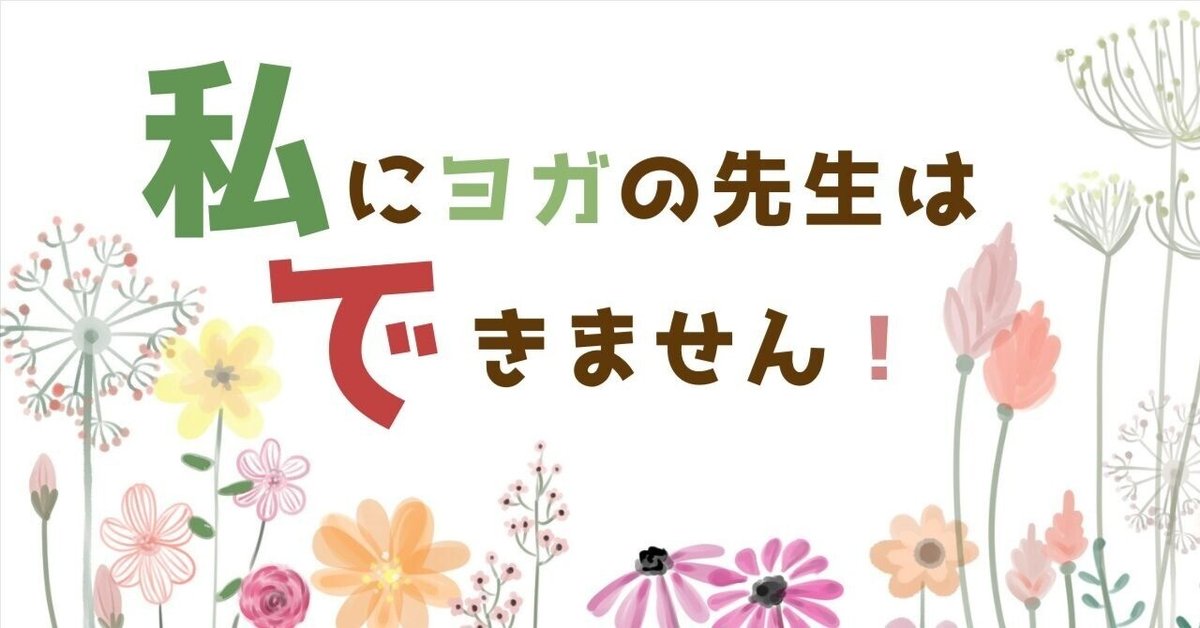
私にヨガの先生はできません!【第二十二話】突然の電話
翌日、仕事がお休みの私は、アクセサリーの梱包作業を手伝うために、午後からカレンの家を訪れていた。そのまま夕食を一緒に食べようという話になっている。
「あ、これ新しいやつ? 可愛い!」
「そやろ? 入荷してみてん。でもなあ、もうライバル店はすでに販売してるから、一歩出遅れた感じやわ」
カレンがため息交じりに言った。
「そっかあ」
どうやら、先月と状況は大きく変わっていないようだ。
ふいに、部屋の隅に視線をやると、そこには、ソーイングセットと作りかけの小さなぬいぐるみのようなものが置かれていた。
ひょっとして、ハンドメイド作品を作って、出品する予定なのかな。
「あ、ハンドメイド再開したの?」
「え? ああ、こないだ実家帰ることあったから、持ってきてやってみてんけどあかんわ。やり方忘れてしまっててな。まあ、もう少し粘ってみるわ」
カレンが言った。
「やってたの、もう結構前だもんね。でも、絶対欲しいって人いると思う!」
「そやろか」
作りかけのぬいぐるみを手に取り、まじまじと眺めながらカレンは言った。その目にはまだ迷いが見てとれる。
「うん! 絶対!」
私が元気良く相槌を打ったときだった。傍に置いてあるバッグの中でスマホが震えた。
「知らない番号。ん? でも、どこかで見たことあるような気も……」
スマホを手に取りながら言うと、カレンは眉をひそめた。
「怪しいな。番号、調べるわ」
カレンは自身のスマホへと手を伸ばす。私が画面に表示されている番号を伝え、彼女がネットの検索画面に入力していく。
「あ! フィットネスクラブやて。アルタイル。あれ? いと葉が働いてるとこの姉妹店ちゃうの?」
カレンが言い終える前に、私のスマホはぴたりと動きを止めた。
「え? なんだろう?」
そもそも休みの日に電話がかかってくるなんて珍しい。それも、姉妹店からなんてこれまで一度もなかった。
「かけ直してみた方がいいんとちゃう? ええよ。ここでかけて」
私のピンとこない様子を察してか、カレンがそう口にする。
「うん。そうしてみる」
私は着信履歴の画面をタップして、電話をかけ直すことにした。色々考えてみるも、着信の心当たりはちっとも浮かばない。
「お電話ありがとうございます。フィットネスクラブ・アルタイルでございます」
電話の向こうで雲井さんの声がした。「お疲れ様です」ではなく「お電話ありがとうございます」だ。
これは、お客様向けの応答文章。あ、そうか。店舗スタッフじゃないから、電話機のディスプレイに『笹永いと葉』って表示されないんだ。そんなことを頭の片隅で考える。
「あ! お疲れ様です! あの、ついさっき、お電話をいただいていたみたいで。出れなくて申し訳ないです」
私は早口でつらつらと言葉を並べた。
「ああ! 笹永さん。お休みのところ、すみません! ベガからご連絡先をうかがったんです」
「いえ。どうされましたか?」
「あの……。もしも可能だったらなんですけど、緊急代行をお願いできないかと」
「緊急代行ですか?」
思わず緊張感が走るその言葉を耳にするのは、久しぶりだった。
インストラクターが、レッスン当日に風邪やなにかしらの事情により行けなくなったときの代行のこと。通常の代行との違いは、その名の通り、即座に対応しなくてはいけないということ。
つまり、会員さんは、レッスンのインストラクターが変更することを知らずにやってくることになる。
「実は、橘さんが急遽体調不良で早退されることになったんです。ええっと、レッスンの時間は十四時半からで内容はホットスタジオでのアロマヨガです。ご存じの通り、うちは三つスタジオがあって、私も同時刻にポールストレッチのレッスンがあるんです。他にその時間、代行ができそうなスタッフもいなくて……。外部のインストラクターさんにも連絡はしたんですけど、繋がらなくて」
雲井さんは焦ったように言う。
そりゃそうだ。店舗としてなるべく緊急休講は避けたい。タイムリミットまでに代行を探さなきゃならないんだから。
あと、一時間しかない。
気持ちとしては協力してあげたい。アロマヨガ、やったことはないけれど、リラックスヨガをベースにアレンジすればいいから、きっとできないことはない。
でも、人気インストラクターである橘さんのレッスンの緊急代行というのは気持ち的にかなり重い。レッスンを受けにくる人たちは「橘さんだから」という理由で参加している人ばかり。それが突然、別のインストラクターが担当しますとなるのだから、当然がっかりするはずだ。よく知っているスタッフやインストラクターならまだしも、面識のない私が登場するとなると、アウェイにもほどがある。
私の中では二人の自分が対立していた。「せっかくのお休みで、友達と過ごしているのだから代行する必要はないよ。カレンにも失礼だし」という声がする。すぐに「それが理由じゃないでしょ。本当は怖いからやりたくないだけ。さあ、断るの?」という反論が聞こえてくる。
「十四時半ですよね……」
私は困ったようなニュアンスで、呟くように言った。
今は十三時過ぎ。断るとしたら、時間帯を理由にするのが無難だ。
「はい。やっぱり、急で難しいですよね。申し訳ないです、突然電話してしまって」
「いえいえ。謝らないでください。またお役に立てそうであれば、お声掛けください」
「はい! ありがとうございます。では失礼します」
雲井さんは、そう言って電話を切ろうとした。
ふとカレンの方を見ると、作りかけのぬいぐるみを手に持ったまま、テーブルの上に置いたスマホ画面をスクロールしている。きっと、ハンドメイドのやり方を思い出すために、調べているのだと思う。
そのまなざしは、真剣そのものだった。画面の向こう側を睨みつけているんじゃないかってくらいに。
私は急に理由をつけて、目の前の状況から逃げようとしている自分が恥ずかしくなった。
「あ、待って!」
気が付くと、私は大きな声を上げていた。
「えっ?」
雲井さんは電話を切りかけていたのだと思う。驚いた声が受話器越しに聞こえてくる。
「どした?」
手元のぬいぐるみから視線を上げたカレンも首をかしげる。
「今から急げば間に合うかもしれません! 私が、代行します!」
そう伝えて、私は電話を切った。
「どうしたん?」
カレンが目を丸くさせている。
「カレンごめん! アルタイルでヨガの緊急代行してくる。三時間くらいで戻ってくるから、抜けさせてほしい」
「大変やな。あたしは全然ええよ」
「ほんっとごめん。先に約束してたのカレンなのに。でも、今、行かないと私、後悔しそうだから! 埋め合わせはちゃんとする」
私は鞄を持って立ち上がると、勢いよく頭を下げた。
「気にしてへんて。ほら、急ぐんやろ。代行、頑張りや」
カレンはそう言って、部屋の扉を開けてくれる。
「うん!」
私はカレンの家を後にして、駅まで早足で歩くと電車に飛び乗った。一駅で降りて、一度自宅に戻る。引き出しからヨガウェアを引っ張り出し、ボストンバッグに詰め込んで再び駅まで急ぐ。
アルタイルまでは最寄り駅から電車で四駅だ。
本当はポータブル音楽プレイヤーと水素水ボトルをとるために、二駅先のホットヨガスタジオベガに寄りたいけど……。
それだと時間ギリギリだし、最悪間に合わない可能性もある。
仕方ない。
「雲井さんに借りよう」
多分、そのくらいなら協力してもらえる。
私は駅のホームの端っこで目を閉じ、深呼吸した。それからアロマヨガの構成について考える。大丈夫。いつもやっていることを違う環境でやるだけだ。
でも、もしも……。
満足してもらえなかったらどうしよう。普段、橘さんのレッスンを受けている人たちだ。私のアロマヨガでいいんだろうか。
脳裏に浮かぶのは先日の夢だ。一人、二人とレッスンの途中でスタジオを退出していく人の背中……。いや、よそう。今考えることじゃない。私は頭を左右に振った。
代わりに、片井さんの言葉を思い出す。
彼はこう言った。
「とにかくやってみて、今の自分が出せるパフォーマンスを出せればいいやっていう感覚でいることにしています。うーん。結果に対する自信というより、ちゃんと、目の前の人に向けて仕事をやりきる自信っていうのかな?」
そうだ。
私が今、意識しなきゃいけないのは、参加してくれる人たちに向けて、自分のパフォーマンスを出し切ること。
「うん!」
そう思うと、少し気持ちが楽になった。
この連載小説のまとめページ→「私にヨガの先生はできません!」マガジン
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
