
夏に煮物を長持ちさせる方法など。江戸時代の古文書『廣益秘事大全』解読①
嘉永四年(1851)の古文書『廣益秘事大全』は、日常のちょっとした豆知識、病気を治す方法、身体のツボ、穀物や野菜の知識、食物の保存方法の5つの分野において、たいへん詳しく書かれた百科事典のような書物です。
古文書にはこうした類のものは多く、以前も食物の保存方法などについて、別の書物に記載されているものを取り上げてみましたが、今回は数をたくさん集めて、もっと追求したものと捉えていただければよいかと思います。
かなりの長丁場となりますが、1回当たりは読みやすい分量に整え、全5冊完訳してみたいと思いますので、よろしければぜひお付き合いください!
まずは「奇巧妙術類第一」。日常生活の豆知識編です。


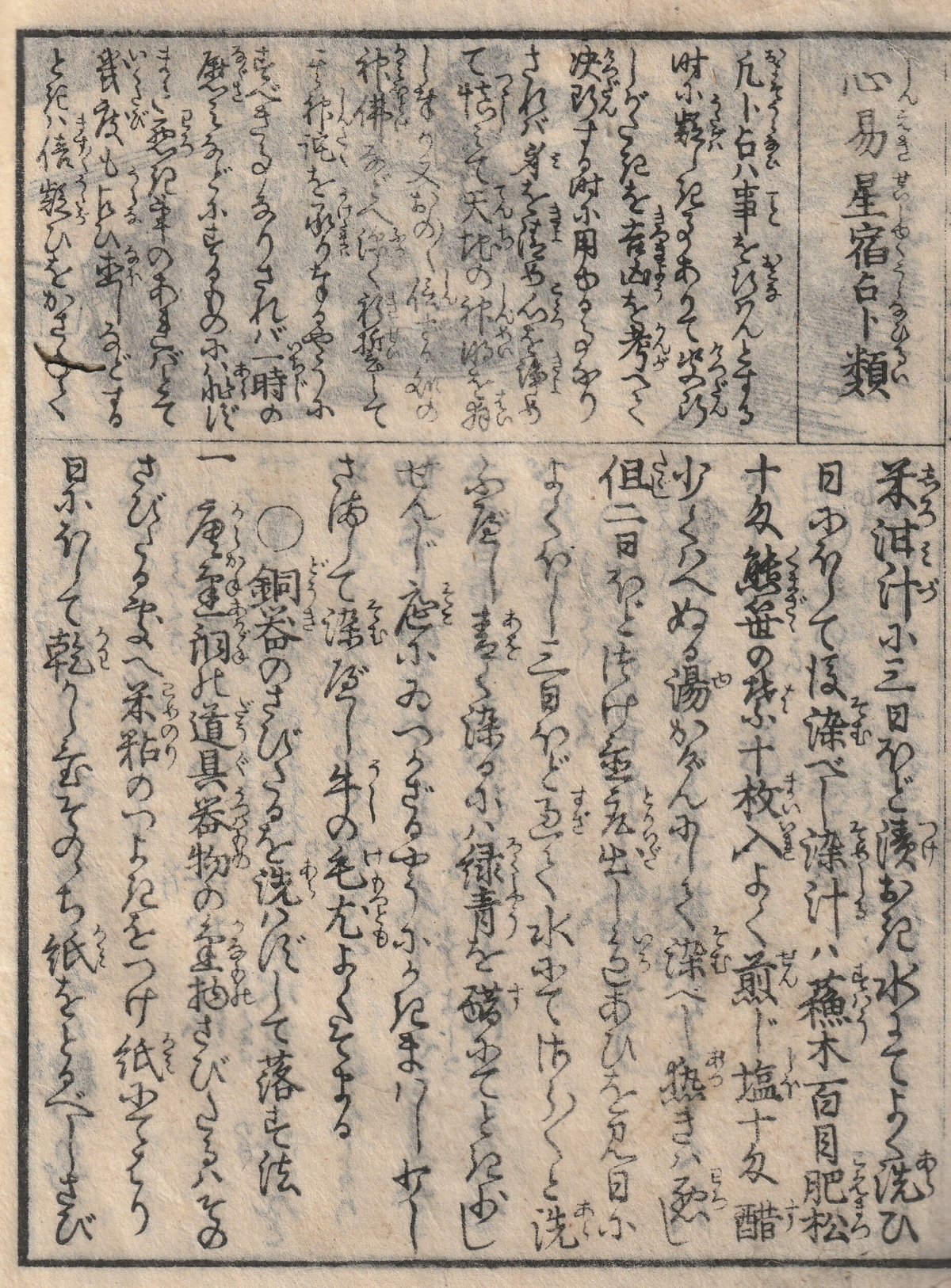
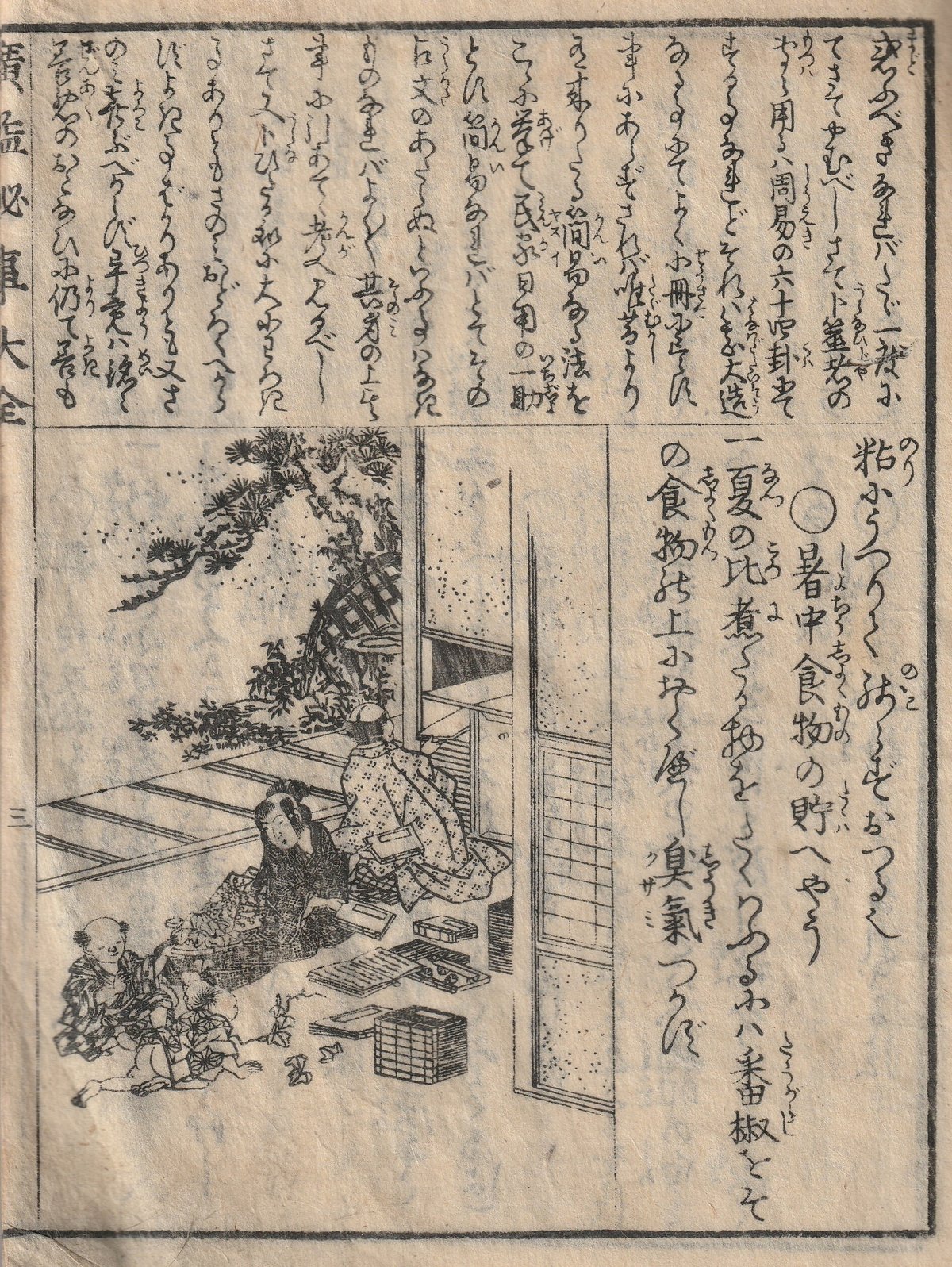
1.書物を虫食いから守る方法
書物の間に朝顔の葉もしくは実を紙に包んで
入れておく。この方法は効果絶大。
2.書物が海水に濡れたのを直す方法
大きな桶などに水を入れ、塩を少し加える。
書物の表紙を外し、水に浸して静かに海水を
洗い出す。そして、板で上下から強く挟み
押し付け、その後に干す。
乾いたら打盤※でむらなく打てば、
皺は自然と伸びて元に戻る。
※打盤=洗濯物を打って柔らかく
するための木製の台
3.水草を長く保つ方法
蓮・河骨・沢桔梗などの水草を
長く生かそうと思えば、まず糸で根をくくり、
その下から切る。水を含んで長くしおれず、
2・3日してしぼむ花も10日ほどもつ。
4.銀箔の色が変わらない押し方
銀箔を押した上から礬水※を薄く引くと
長く錆びない。
※礬水=膠とミョウバンを溶かした水
5.毛の類を染める方法
馬の毛を早稲藁の灰汁でよく洗い、
米のとぎ汁に3日ほどつけて、
水でよく洗って日に干した後、染める。
染汁は蘇木百目(375g)、肥松十匁(37.5g)、
熊笹の葉10枚を入れてよく煎じ、
塩十匁(37.5g)、酢少々を加え、
ぬるめのお湯にして染める。
このとき、熱いお湯は避けること。
2日ほどつけた後取り出し、
色合いを見ながら日によく干して
3日過ぎたら水で軽く洗う。
青く染めるには緑青を酢で溶いて少し煎じ、
底にたまらないようにかき回し、
少し冷まして染める。
牛の毛がもっともよく染まる。
6.銅器が錆びたのを洗わずに落とす方法
唐金・銅の道具や器物の金物が錆びたら、
その錆びた箇所へ強い米糊をつけ紙を貼り、
日に干して乾かす。その後紙をはがす。
錆は糊に移って残らず落ちる。
7.暑中に食物を保存する方法
夏に煮物を保存するには、
唐辛子をその食物の上にかけると
臭気がつかない。
【たまむしのあとがき】
煮物が痛まないように唐辛子をかけると良いとありましたが、そうすると夏の煮物は全部唐辛子風味になってしまうと思うのですが・・・。
唐辛子味の筑前煮とか、どうなんでしょう。
腐らないことが最優先なのでしょうね、きっと。
冷蔵庫のありがたさが身に沁みます。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
