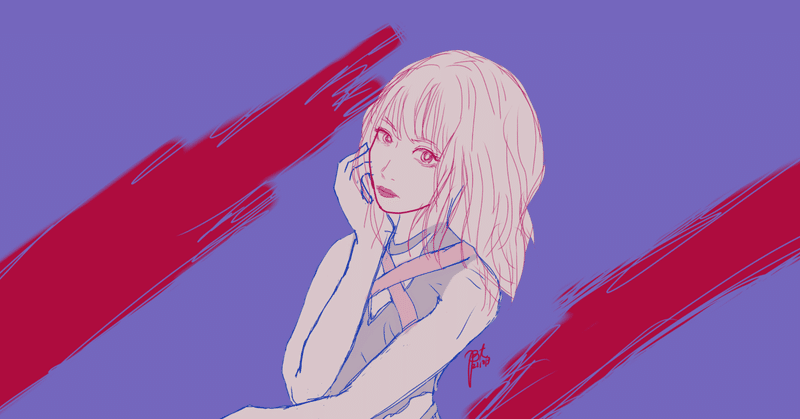
ショートショート「明日は大学祭#会計」
私はこの街での暮らしを気に入っている。
地元出身の子たちは、地味だし田舎なのに何がいいのって言うけど、私にとってはそこがいい。
人は少なからず多からず。大人しくて特に面白いことも言わない。大きな工場地帯はあるけど、大学の近くまでは煙は届かない。
アルバイトは大学の近くのファミレスで厨房を担当している。表に出たくない私にとってはありがたい仕事だ。まかないも美味しい。
サークルだけは友達の誘いでうっかり大学祭実行委員会に入ってしまったけど、会計というこれまた表に出ない役職につけたのでまあいいとする。因みにその友達はとっくの昔にここを去っている。
他大学の手伝いなどに行った際はみんなと一緒に設営やばらしをするけど、普段は部室でパソコンに向かい会計ソフトに入力したり、領収書を持ってきた部員にお金を渡したりして事務作業に勤しんでいる。
だから、直属の後輩である野崎が泣きを入れてきた時は久しぶりに心を乱された。
「どうしよう、瑛美さん、広告が気に入らないからってT興業がお金払ってくれないんですよ~」
野崎は一学年下の男子学生だ。背が高くがっしりとした体格だが、性格も体も軟弱だった。T興業はそんな気弱な野崎が飛び込み営業をして掴んできた契約だった。
「何?印刷がうまくいってないの?」
私は隣に座る野崎に一瞥もせず、パソコンに入力作業を行いながら質問した。
「全然。この通り、もらったデザイン通りに」
野崎はパンフレットを開けて見せた。
「イベント・パーティーへのコンパニオン派遣ならT興業におまかせ!」
という文章の下にミニスカワンピの女の子3人のイラストと会社名があった。
「じゃあ、何でお金払ってくれないの?」
「位置が嫌だって」
広告はパンフレットの中盤、ページの右端にあった。
「位置はどこがいいって言われていたの?」
「言われていません」
「じゃあ、どこの位置が嫌かは訊いた?」
「それは…」
野崎は下を向いた。
私は額に手を当てて野崎のほうを向いた。
「そうだね、うん、そうだ。そこまで私や広報に言われていないもんね」
「はいー」
二人の間にしばし沈黙が流れた。
「野崎、ご飯食べた?」
「いえ」
私は部室の壁かけ時計を見た。
午後八時が訪れようとしていた。
「第二会議室でお弁当とは別に葉山さんがいろいろ作っているみたいだから食べに行ったら」
葉山さんとは大学祭実行委員会の会長だ。会長職は毎年、みんなのご飯の面倒を見ることになっている。
「でも。どうしましょう、広告料」
涙目になっている野崎を尻目に、私は黒のトレンチコートを羽織った。
「私が行ってくるよ。あんたはちゃんとご飯食べて」
そう言うと、私は部室を後にした。
T興業は繁華街の外れにあった。袋小路の手前にあり、点滅を続ける街灯が私を苛つかせた。
古い五階建てのビルの二階にT興業はあった。
階段から仕事を終えたコンパニオンらしきが数人降りてきた。
彼女たちを見送った後、私は階段を昇った。
T興業の看板の横には受付専用の電話があった。
私はその受話器を取り、受付へつながる番号1を押した。
「はい、T興業でございます」
若めの男性の声がした。
「夜分遅くに失礼いたします。わたくし、Q大学大学祭実行委員会の町田瑛美と申します。広告担当の方はいらっしゃいますか」
「あー。野崎君の。何、女の子が来たの。へえ、まあ、入ってよ」
「ありがとうございます」
受話器を置き、私は一度心を無にして入った。
「失礼します」
中は小さな事務所だった。入って真正面に大きな机があり、そこに黒のスーツを着た男がいた。
「お忙しいところ、すみません」
「いや、いいんだ。社長の河合です」
河合は、私の姿を上から下、下から上へと見た。
「さすが、見た目のQ大学。野崎君もなかなかいい男だったけど、あなたも美しい。うちのコンパニオンにスカウトしたいくらいだ」
私は一笑した。
「働くならもっといい事務所か高級なクラブがいいです。こんな小規模なところじゃなくて」
一瞬、河合は顔を歪めたがすぐに口元を緩めた。
「いいね、気の強いところも美人の証拠だ」
「ありがとうございます。ところで、野崎からパンフレットの広告の位置がお気に召さないということで代金を支払ってもらえないと聞いているのですが」
「ああ。もっといい場所を期待していたんだよね」
「契約をする際のヒアリング不足があったみたいですね。その点に関しては謝罪します。申し訳ございません」
私は、床に座り込み土下座をした。
「やめてくれよ。そんな芝居じみた事」
河合の足が近づいてきた。
「いいえ。これはこちらの不手際ですので」
「ほんと、やめてくれ、なあ」
河合は私の顎を掬った。
しゃがみ込み、私の顔をじっと見ている。
体全体からたばこのにおいがした。
「美人のお願いだったら聞いてあげたいけど、気に食わないものにお金を払えないんだよ」
話し終えた河合の口の際に悪意が見えた。野崎と私をからかって遊んでいるのだ。私の血は一瞬で沸騰した。
「学生や思ってなめたことしたらあかんぞ、ボケ」
私は河合の足首をつかみ、手前に引っ張った。
その場で河合は床に倒れた。
私は河合に馬乗りになり、顔にフックを五回入れた。
「誰か、来てくれよ!」
河合が苦し紛れに叫ぶと、奥の部屋から中肉中背の男二人が現れた。
眼光は鋭いものの、だらしない腹を見てこれはいけると思った。
男たちは私の周りを囲んだが、一人に強いジャブを入れた後、ハイキックで顎を蹴り、もう一人にはボディを三回打ち込み膝をついたところでわき腹にキックを入れた。二人ともあっさりと床に倒れた。
「あんたの子分、簡単やな、鍛えなあかんで」
口から血を出し、倒れたままの河合に教えてあげた。
「はあ、あんた、何者だよ」
「そんなんええから、はよ金払えや」
私は、河合のズボンの後ろポケットから財布を取り出し、1万円札をあるだけ抜いた。
「ここまでの交通費ももろとくで」
河合へからかうように伝えたあと、私は踵を返した。
「ほな、失礼しました。手え抜いてやったんやから警察に言うなよ。まあ、言うてもええけど」
「お前、エイミーか」
顎にハイキックを入れた男が苦し紛れに言った。
「さあ」
振り返ることなくドアを閉めると、急いで階段を降りた。
タクシーを拾って学校へ戻ろう。
私は路地裏を走った。
ここにも私のことを知る人間がいたことに、内心震えていた。
エイミーというのは、私が地下格闘技でお金を稼いでいたころの名前だ。
中学生の時、親が離婚して、母親と一緒に暮らしていたけど、その母親が帰ってこなくなった。
同じような境遇の子はパパ活とかしていた。でも、私はどうしてもそれが嫌で、ケンカの強さを武器にすることにした。
知り合いに地下格闘技の世界を教えてもらい、私はそこで紅一点の姫になった。
エイミーという名で働いている時に、ある男性を瀕死の状態まで追い込んだ。
それがきっかけで警察に捕まり、しばらく少年院でお世話になった。
服役している間、本を読むことにはまり、進学をすることを考えた。
出所後、バイトをしながら勉強をして高卒認定試験をパスし、大学受験をした。いくつか合格したうち、一番学費が安かったQ大学に進学した。
奨学金を借りることも出来、縁のない街での生活が始まった。
ただ、私と同じような人生を送ってきた人もいるわけで。
だから、私を知っている人間がこの街にいたのは不思議なことではないのである。
大通りで拾ったタクシーの中から街の夜景を見つつ、私は今までのことを考えていた。この街ともお別れしなくてはいけないかもしれない。
自分のこぶしを月の明かりに照らしてみたら、少し悲しくなった。
部室に戻ると、野崎が駆け寄ってきた。
「大丈夫ですか、瑛美さん」
「大丈夫だけど。お金、回収してきたから。安心して」
私は自分の席へと向かった。
「さっき、T興業の河合さんから電話があって」
背筋がぞっとした。警察に通報したのだろうか。
「何か、言ってた?」
トレンチコートを脱ぎつつ、恐る恐る聞いた。
「『惚れた』って」
「は?」
「瑛美さん、何したんすか」
「何もしてないよ」
寒気はすぐに暑さへと変わった。
「『大学卒業したら、結婚したい』って。やけに切なそうに言ってましたよ」
「へえ」
初めて河合の顔を見た時の澄ました表情を思い出す。
悪くない。
どうやら、この街での私の生活はまだ続きそうだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
