
本を読む②-1
やっと2冊目更新します。
今回は・・・
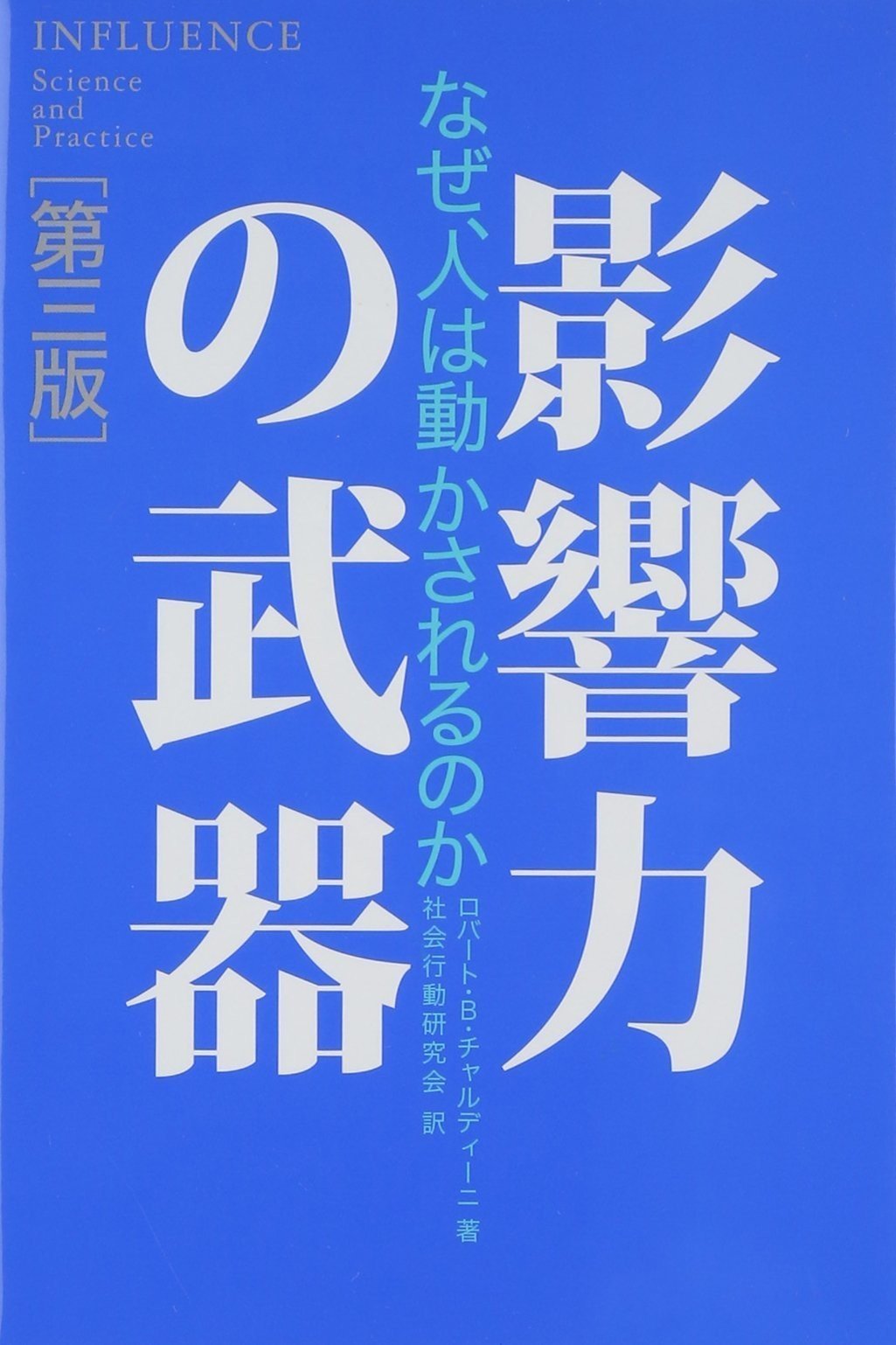
この自粛期間中、YouTubeである方のチャンネルに出会い、そこで紹介していた本です。
もろに影響されて購入したのですが、P476もある本で、読み切るのに時間が結構かかりました。
この量をまとめることが果たしてできるのだろうか、不安ではありますがアウトプットしていかないと身にならないのでやってみます。
人間の行動をつかさどる基本的な心理学の原理
著者は、相手から承諾を引き出すテクニックとして、承諾の心理を学びました。その中で6つの原理が人の承諾には大きな影響を与えていると述べています。
・返報性
・一貫性
・社会的昭明
・好意
・権威
・希少性
これらの原理を上手く使うことでこちらの要求を相手に承諾しやすくなる、つまり相手に対して影響力を発揮することができると述べています。
カチ・サー
固定的動作パターンと言われ、テープの動作で例えられています。
ある情報を得たとき、「カチ」とボタンが押され、「サー」とテープが回る場面を例えたものです。
これ、自分の言葉で訳してみると「うん、わかった」って軽く返事をすることかなと思います。
人の話をよく聞けない、聞こうとしない人、忙しさなどからその時余裕がなかったり心理的な圧力を感じてる時など、相手の話の内容を一片の情報のみに自動的に反応してしまうことを指します。適当に相づちをうつみたいな。
先入観を持った時もそうじゃないかと思います。
効率は良いかもしれませんが、大事な内容を聞き逃す事にもつながります。
先入観でいうのなら、「高い」は高価で、「安い」は質が低いもの、とでもいいましょうか。
このテクニックを使って人間にあることを試した実験があります。
人間行動の原理に、「理由を添えると頼みごとが成功しやすくなる」というのがあります。
例えば、ある図書館でコピー機の前で、自分より先にコピーをとろうとした人に対して
「すみません、5枚だけでいいので先にコピーをとらせてもらえませんか?急いでいるので」
というお願いする人の承諾率は94%。
「すみません、5枚だけ先にコピーとらせてもらえませんか?」
とお願いする人の承諾率は60%という結果になりました。
この2つの質問の違いはわかるでしょうか。
「急いでいるので」という言葉を使ったかどうか、ではないそうです。
この実験者が3番目の頼み方を試したところ
「すみません、5枚だけコピーを先にとらせてもらえませんか?コピーをとらなければならないので」
この頼み方でも93%の人が承諾をしてくれたそうです。
違いは「ので」という単語を最後に使ったかどうか。
この実験では、後ろから声をかけられた人は「ので」という単語に対して「カチ・サー」(はい、わかりました)と自動的に反応したことが示されたのです。
これとは対照的に、十分に全ての情報を分析したうえで反応することを「コントロールされた反応」といいます。
このように、些細な言葉を使うことで、人に影響を与え、自分の要求を相手に承諾させるという、いわば詐欺師のようなテクニックについてこの本では述べています。
コントラストの原理

人の知覚にはコントラストの原理というものが働いています。
順番に示されるものの差異に対して私たちはどのように認めるのか、ということです。
例で言うと、私たちは2番目に掲示されるものが最初に掲示されるものとかなり異なっている場合、それが実際以上に最初のものと異なっているように見えてしまう傾向があるそうです。
上のパソコンの価格表示についてイラストのような広告がそうです。
最初に高い金額を掲示し、次に安く値段を掲示することでその商品があたかもお得な商品であるという印象を与えます。
人の場合、最初に出会った人が魅力的で、次に出会った人がそうでなかった場合、最初に出会った人がより魅力あるように感じる傾向があります。
その逆も言えますね。
よくテレビで見る合コンの話しがそれでしょうか。
合コン主催者が呼んだ女の子は、自分よりもかわいい子たちを呼ばない、とか。
私たちはこのような情報を掲示されることで、「カチ・サー」と自動的に反応してしまうことがしばしばあります。手っ取り早く反応できるし、効率よく処理することができる反面、うまく操られているのかもしれないということを覚えておかなければなりません。
コントロールされた反応を身につけることで小さな損の積み重ねに対する防衛策を身につける必要があります。
返報性

他者から与えられたら、お返しを義務付けるルール。
ギブアンドテイクとでもいいましょうか。
良いことしてもらったのだから、お返しに・・・という良心に基づいたもの。しかし、時には拒否されることもありますよね。
それすらも計算されることもあります。
「拒否したら譲歩」
例えば、私があなたにある要求をします。
あなたがその要求を拒否したとすると、どのような感情を抱くでしょうか。
関係性にもよりますが、なんとなく申し訳ない、悪いことした気になりませんか?
次に私が二番目の要求をあなたにしたら、どうでしょうか。
言い方を変えます。
一番目の私の要求が確実に拒否されるような大きな要求であるとします。
あなたはもちろん拒否します。
次に私が二番目に要求することは、一番目に要求したことよりも小さな要求だとします。
私は一番目の要求から譲歩したことになりますし、あなたも「そのくらいなら」と譲歩した気持ちになりやすくなりませんか。
これらの心理を上手く使うと、つまり私は最初から二番目の要求をあなたに承諾してもらうのが目的だったのです。
この「拒否したら譲歩」という方法が成功しやすいのは、返報性のルールを取り入れてることによります。
このように、返報性のルールに知覚のコントラストの原理を組み合わせ、さらに「拒否したら譲歩」法もうまく使い分けていくと、恐ろしいほどの強力な力が生み出されます。
私たちはこういったテクニックによって影響を受けることになるのです。
防衛法としては、要求に対して一歩さがり、きっぱりと割り切ることが重要です。「~しなければ」という感情に支配されないようにしなければなりません。
一貫性

コミットメント
これは、最初に読んだ本「決定力」にも出てきた確証バイアスというものに近いのではないでしょうか。
ひとたび決定を下したり、ある立場をとる(コミットする)と、自分の内からも外からもそのコミットメントと一貫した行動をとるように圧力がかかる。
他人にわかりやすい形で自分の立場を明確にすると、そうでありたいという一貫した人に見られたいという気持ちが生じやすくなります。
これって、責任感を上手く操るということかな、と。
あと、言ったからにはもう後には引けない、とかそういう感じでしょうか。
無責任な人には効き目がないかもしれませんが、善人である、まじめな人ほど利用されやすいのかもしれません。
簡単に手に入るもの、なかなか手に入らないもの
このコミットメントというのは、時として人に大きな影響を与えることになります。1959年に発表された研究内容には、「何かを得るため大変な困難や苦痛を経験した人は、苦労なく得ることができた人よりも得たものの価値を高く見積もるようになる」という考えです。
ある団体に加入を希望した人への加入儀礼とした新人いじめや、ある部族では大人になるための儀式として肉体的な苦痛を味あわせることがあります。
軍隊もそれです。加入儀礼の厳しさが新規加入者の集団に対するコミットメントを著しく高めることを示したのです。
これって、部活とかにもある体罰にも言えることで、実際に被害?体罰等を経験した人たちは、「あの苦しい訓練(練習)のおかげで自分が強くなった、逞しくなることができた」と思い込ませることができるのです。
だから団体に対する忠誠心も強くなることから、こうした加入儀礼(いじめ、体罰等)は簡単になくならないようです。
いわば洗脳?に近い形なのかもしれません。
子育てにおいて
このコミットメントさせるというのは、子育てにも影響を与えます。
子どもに何かをやらせようと思うのなら、決して魅力的なご褒美で釣ろうとしたり、強い脅しをしてはいけません。子どもに圧力をかけても、一時的に取り組む(取り組まざるを得ない)だけで、その効果は持続しません。
私はサッカーのコーチなので、保護者の話でよく聞きます。
「〇〇しないとサッカーやめさせる」とか。
子どもにどうしてもこうなってほしいと思うのなら、親のさせたい行動に対して子どもが自分で責任を感じるようなお膳立てをしなくてはなりません。
ここが難しいんですけどね。
子どもにコミットメントを自らさせることの方が効果が持続するという研究発表があるそうです。
この部分はとても勉強になりました。
子どもはもともと責任感あるし、まじめなので大人が上手く「影響力の武器」を使って子どもを誘導させることが大事ですね。
変わるべきなのは子どもではなく大人側なのでしょう。
防衛方法
自分でコミットメントをしたはいいが、やりたくもない要求を飲まされそうになった時は、2つの防衛方法があります。
1つは、胃からのサイン。
相手に丸め込まれそうになった時、胃からのサインを感じるそうです。それを感じたら、自分の馬鹿げた一貫性のせいでその要求を飲もうとしていることに対して、客観的にみてそんなの必要がないと自分に説明することです。
2つ目は、心の奥底からの合図です。
自分のコミットメントに対して、いまいち自信が持てなかったりする場合、一旦距離をとります。時間を遡ることができたら、同じようにコミットメントするかどうかを自分にもう一度問いかけることが必要です。
プライドが高かったり、経験豊富な50代以上の人がこういったコミットメントを利用した戦術に引っかかる確率が高いそうです。
この一貫性はとても内容が難しく、自分の言葉でまとめることがうまくできませんでした。
内容はまだ半分あるので、本を読む②-2へ続きます。
