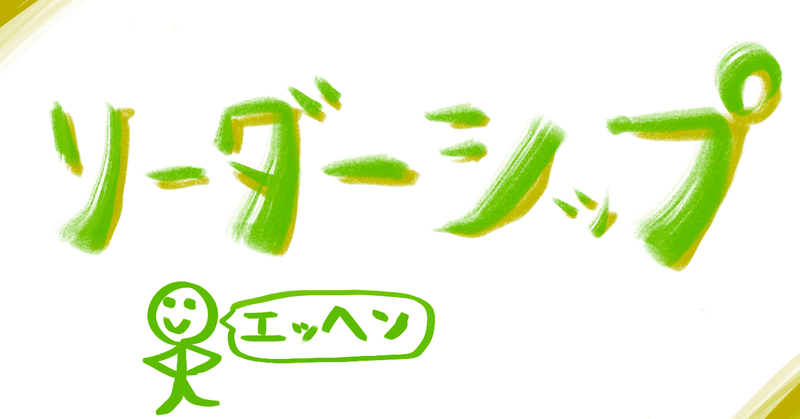
リーダーシップ論
おはようございます。
寒い日は湯たんぽがお気に入りの小松です。
さて今日は、私が考えるリーダーシップ論についてツラツラと書いていきます。
特に興味がない方は目を閉じて片脚立ちすることをオススメします。私は体力維持のためルーチンでやってます。
県庁というデカい組織の中ではチームとして業務を進めていくためにマネジメントする側とされる側に分かれます。
私は県庁の中で8人のチームメンバーを率いる課長としてリーダーの役割が求められています。
そんな私が普段からリーダーシップにおいて6つのポイントを意識しています。
1.任せる
チームの中には実務を行うプレイヤーが存在します。プレイヤーの一挙手一投足を逐一管理していると、プレイヤーは自分で考えなくなります。
自分が気になるのでマイクロマネジメントで逐一管理したい気持ちも分かりますが、自分で考えて仕事をしてもらうには任せることが大切です。
2.道を整える
プレイヤーが気持ちよく業務を推進するために邪魔になりそうな小石があれば、つまずかないように取り除くのもリーダーの仕事。
若手のメンバーは知識が乏しく何も分からずに闇雲に業務をやってる場合があります。
仕事には大抵守るべき型があり、そのことをある程度先回りして教えておくことも大事だと思います。
型ができてくれば自分の知恵で応用して問題解決を図ることもできます。
「守・破・離」です。
3.決める
組織として右か左か悩むときは必ずあります。安全性と経済性、確実性とスピード感などトレードオフの関係を踏まえて誰かが決断する必要があり、その仕事はリーダーの本質的な仕事です。
右もあるけど左もあるとポジションを取らず評論家みたいなことばかりで判断しない人間はリーダーには向いていません。
組織を社会を停滞させて無駄な仕事が増えるばかり。
どこかの県知事は球磨川にダムを造るか造らないかを議論だけして何も判断しない無駄な8年間を過ごしました。
4.モチベーションを高める
プレイヤーのやる気をいかに高めるか、いかに維持するか?良好な仕事環境を整えるのもリーダーの仕事です。
頑張って仕事してても誰にも認められなかったり後ろ向きの仕事がつづくと誰でもモチベーションが下がってしまいます。
期待を寄せることや感謝の言葉をメンバーにかけて士気を高めることもリーダーの大切な仕事です。
5.学ぶ
社会の変化が激しい中で組織として進むべき方向性を指し示すのもリーダーの仕事です。
例えば、少子高齢化が急速に進み人口減少社会で人手不足が顕在化してるなか、デジタル技術やドローンなど新技術・新工法の活用を積極的に採用して業務効率化を図ることが重要です。
そういった中で、プレイヤーに消極的な姿勢があれば改善するよう促したり、研修会を開催したりとリーダーシップをとります。
組織の大きな方向性を指し示したり具体な新技術を業務に落とし込むには日々の自己研鑽や学ぶことが大切なのは言うまでもありません。
6.学ばせる
とにかく日本の社会人は勉強しません。
平均の勉強時間は6分です。
自己成長を促すために学ばせることもリーダーの仕事です。勉強してほしいのであえて業務の範囲で宿題として要求することもあります。
プレゼンスキルだったり業務の専門的な知識だったりは当然ですが、住民意識の向上や業務の複雑化・高度化で身に付けるべきスキルは年々増えている印象があります。
そんな状況なので若い伸び盛りのメンバーで私の言葉を素直に傾聴できるメンバーに対しては意識して学ぶことを強要します。
最後に
大きな組織では、ある程度年齢を重ねると、不幸にもリーダーの役割を与えられた人がいて、そんな人の下で仕事してると毎日が面白くありません。
また配属ガチャで自分がやりたい仕事じゃないこともあるでしょう。
だけどやってみると意外にも自分の特性とマッチすることがあったり、自分の個人的なスキル向上につながったりします。
「塞翁が馬」ってやつで、何がいいのか分かりませんね。
どこの部署にいても楽しく仕事してる人って周りにいませんか?
何事も前向きな姿勢で一緒に仕事してて楽しい人いますよね。
そんな人になれたらいいですね。
以上、また明日お会いしましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
