
【読書記録】「対象喪失 / 小此木啓吾 著」
たまには趣向を変えて、自由に書きたいことを書いてみる。
ずっと書こうと思っていた読書記録がおろそかになっていたので、
溜まっていたものを少しづつアウトプットしたい。
今回はこちら。
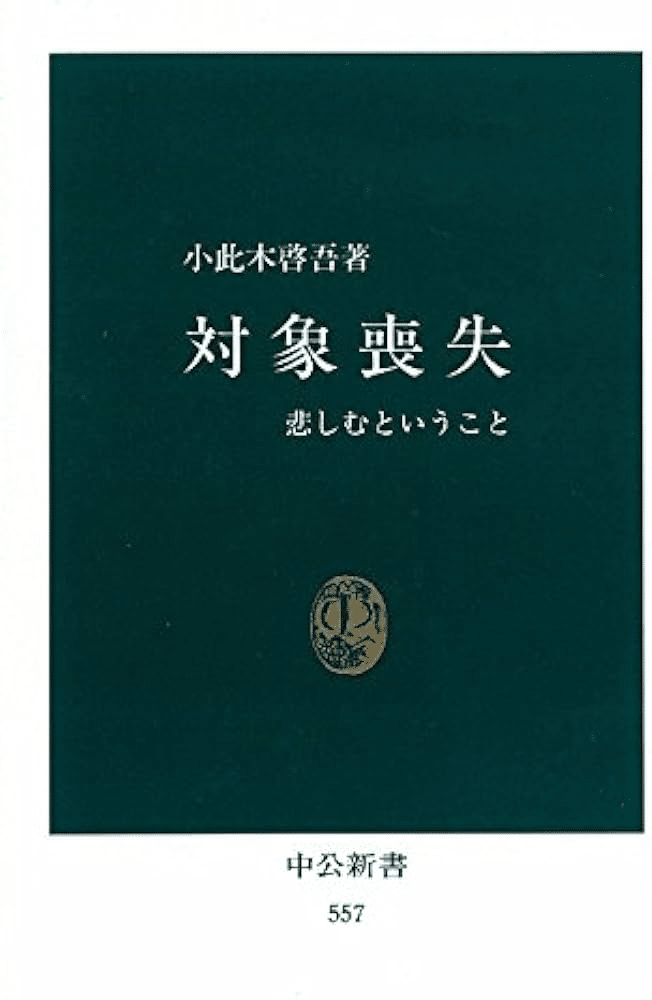
中公新書から、「対象喪失 / 小此木圭吾 著」
もう亡くなられてしまったが、日本の精神分析シーンを牽引された
小此木圭吾先生の一冊。
「実は隠れた名著」と、
かつて先輩から勧められて、ずっと積読になっていたのを読んだ。
これがまた大変濃厚な一冊で、
執筆欲を駆られるものだったので、書いておきたい。
人生は喪失を避けられない
私たちは、生きていて実に多くのものを失う。
大切な人、物、かけがえのない時間、青春、若さ、家、お金、繋がり…
生きていればいつかは死ぬことと同じくらい、
何かを失うことは確実なことだ。
それに向き合った一冊。
初版は1979年。ただ内容はまったく色褪せない。
私たちは何かを失うけれども、それをうまく消化していくため
人間の文化の中には、実に多くの装置がある。
喪に服す、という通り、お葬式はそのひとつだ。
初七日〜四十九日までの一連の法要。
外的な装置があることで、私たちはひとつの区切り・節目を持つことができる。
ただ相談にあたっていると思うのは、
外的な節目と、内的な節目は必ずしも一致するわけではないということ。
外的なお葬式と、こころの中のお葬式は、えてして時間的なズレがある。
内的な節目を迎えるための作業のことを、
心理学では、「喪の作業(モーニングワーク)」と呼ぶ。
大学の授業などでもキューブラー・ロスの「喪のプロセス」は有名で、
聞いたことがあるだろう。
あえてここでは書かない。
こころの臨床は、ある種、
本質的にいえば喪の作業そのものであるといっても過言ではない。
未来へ進むには、過去をふりかえり、
弔うことが必要な局面があるのである。
あまり明るいものではないが、そういうものは社会の表に出てこないし、
出せない。
そうした人様には見せられない、日陰の作業を行うために、
私たちこころの臨床家はいる。
さて、では私たちは、どうすれば人生における喪失を、
うまくこころに収納して生きていけるのだろう?
本書における喪の作業へのまなざし
本書はこころの営みを一貫して対象喪失の観点から見ていく論考である。
たとえば動物行動学から見ても、
対象の喪失反応は直接的な死の原因になるという。
また失意・絶望からくるがんの発病。
強制収容所の体験、アイヌの喪失体験、乳幼児の喪失体験、、
それらがメンタルに及ぼす影響を列挙していくところから本書は始まる。
それは今日からみる、「ACE(小児期逆境体験)研究」を彷彿とさせる。
小此木先生の視線は、そのまま
精神分析における喪失、に移っていき、
ひいてはフロイト自身の人生の喪失に及んでいく。
精神分析と喪の作業
こころを扱うカウンセリング、といわれる営みの原型をつくったのはフロイトである。
週何回・何時間、決まった時間に会って自分の話をする、といった今日の「型」をつくったのは彼だ。
ところが彼がつくった精神分析は、
実は「フロイト自身の喪の過程」から生まれたことはあまり知られていない。
本書はその点の指摘にもかなりの分量、割かれている。
「夢判断」という彼の最初の代表作は聞いたことがあるだろう。
あの本は、
彼が人生の毀誉褒貶の中で切り捨ててきた、親しい人物、論敵、友人など
あまたの亡霊が彼の夢の中に現れては消えていく、
フロイトのこころの墓場の風景を見ているような著作である。
その本は、彼の父親の死を背景として、書かれた。
父ヤーコブの死
「夢判断』(1900)の第2版の序文でこう書いている。
「この本は、私自身の自己分析の一部であり、また、私の父の死すなわち、一人の人間の生活のいちばん重要な事件、いちばん悲しい喪失に対する反応である」。
すでに年老いた82歳の父親、ヤーコブが1896年、10月26日に死去するまで、当時40歳のフロイト(1856〜1939)は、かなり冷静な医者らしい態度で、父親の死に対している。
フロイトのこの相当歳の離れた父への思慕の念は、
すでにかなり研究されている。
「エディプス・コンプレックス」という理論でさえ、
彼の父親の、とあるスキャンダルと喪失に対する、こころの防衛の産物として生み出されたものではないかといわれている。

フロイトの人生と対象喪失
もう少し本書の流れに沿ってフロイトを追ってみたい。
彼の人生の中で、対象喪失に関連した論考は多い。
「夢判断」以降で、彼が初めて明確に対象喪失に言及したのは
「喪とメランコリー」という有名な論考である。
これは対象喪失と「うつ」の関連について考察されたものだ。
そこを皮切りに、彼はこころの病気の背景に
性理論とは異なる「対象喪失」という道すじを見出すようになる。
・小説の分析から「グラディーヴァ」
・強迫症のケース症例から「症例:鼠男」
・原始民族の習俗から「トーテムとタブー」
それぞれ対象喪失の悲しみへの防衛反応としての、こころのあり様を描いた。
死者への怖れ、死後の従順…
そして大きな発見は、「思考の全能」という概念である。
一言でいえば、
「対象が亡くなったり、いなくなってしまった時に、
なおその対象に愛情や憎しみを抱き続ける人物は、
夢や空想、思考の全能によって、
その対象との関わりを持つことができる。」
これは「鼠男」症例の患者自身が表現したものだが、
「自分の観念や思考は、死者を再生させたりと、自分の願いをそのままこころの営みの中で現実のものにすることができる全能感に発している」という。
小此木の「対象喪失」によると、本書の後半は、
「フロイトの精神分析の思考の道筋イコール、
そのままフロイトの喪の作業そのものであり、
それは彼の周辺の人物たちの存在なくしてはできなかった」、とまとめている。
いわばフロイトは、
「相手の不幸や悲しみの中に自分と同じ苦悩を見出し、その相手を助けることを通して、自分自身の苦悩の昇華をしていたのだ」と。
それを小此木は、「投影同一視による喪の作業」と表現している。
自分と同じ身の上の人を、無意識に助けたくて動いている自分----------
私たちも日常生活の中で、
知らず知らずのうちに、大なり小なり、やってはいないだろうか。
もちろんカウンセリングは、本来的にクライエントのためのものなので、
カウンセラーが自分を癒す作業は、
自己分析の中である程度ケリをつけていることが必要である。
対象喪失は今日も普遍的なテーマ
新書なのに、中身は相当フレッシュで、オリジナリティに溢れた本書である。
テーマが普遍的だからだろう。
フロイトに学ぶというより、フロイトの人生から学ぶものが大きい、と言える。
それくらい業の深い人物だと思う。
昭和に書かれた本書なので、
「携帯電話の普及が、
人と人の距離感や喪失の否認に一役買っている」とあるが、
時代は変わり、SNSの時代はもはや天井を抜けて、逆の現象になっている気もする。
距離が近づきすぎて、対象喪失が目に見えすぎる。
集団への同調圧力=同一視、が過剰で、
むしろ集団からの排除を怖れる心理、喪失への不安に
むしろ若い層は苦しんでいるような気もする。
現代的な視点から色々語り合いたくなる本である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
