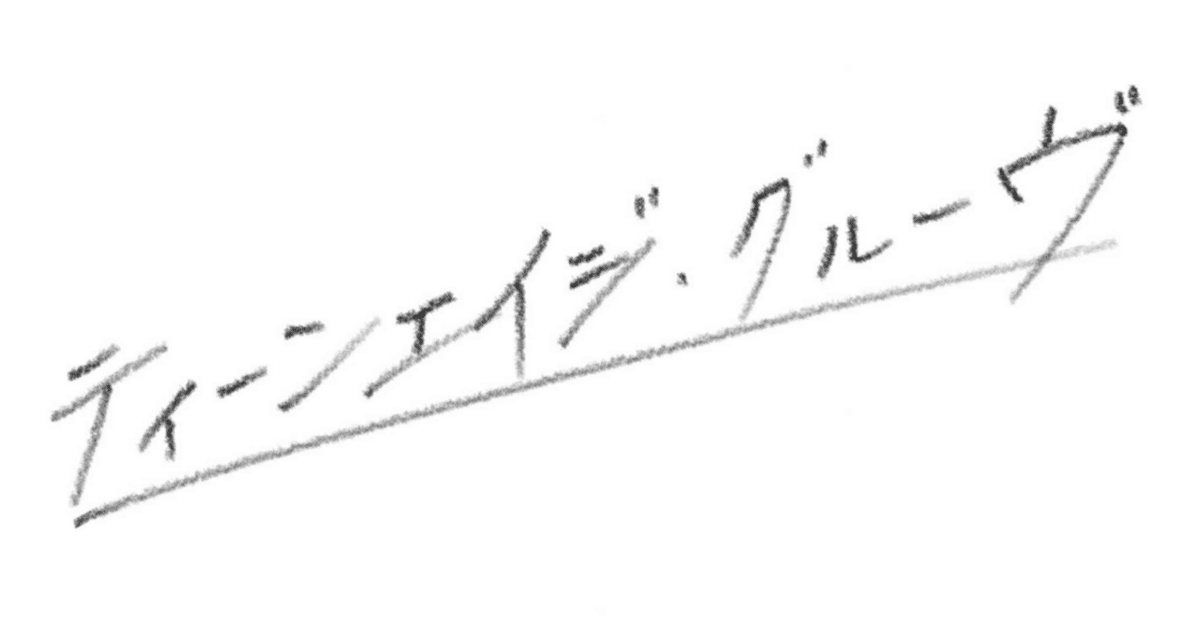
【EPISODE】 『ティーンエイジ・グルーヴ』 第1話 「心優しい君へ」
あらすじ
音楽が大好きな少年・仁稀と、メンバーの事故をきっかけに、いつしか歌うことに意味を見出せなくなってしまったマット。人生の岐路に立った二人は、交流を重ねるうちに新たな夢を模索していく。
未来への不安、大いなる希望、何気ない小さな幸せ。
様々な思いを胸に、仁稀はマットや同い年のラッシュ、胡花、ヘンドリー、ウォンミン、世羅、快とともに憧れだったエンターテイナーの道を歩み始める。
いつも周りの期待に応えようと一生懸命に頑張ってきた。
みんなに喜んでもらえるように、本当の心を隠しながら生きてきた。
だけど、それは間違いだったということに気づいた。
―― Rare 1st MINI ALBUM “Boy Meets Girl” より
○
――四年前。
テレビの中から大きな歓声が聞こえてくる。
これから一体何が始まるのだろうか。期待がどんどん膨らんでいく。
画面の中央には巨大なステージが見え、壮大なオーケストラと共に青白い光が浮かび上がる。スタジアム全体の興奮が一気に高まっていく。
ステージから炎が勢いよく燃え上がると、ダンサー達が白くひらひらとした衣装を羽ばたかせながら現れる。音楽に合わせて力強く踊る彼らのダンスは、繊細かつ美しい。思わず見蕩れてしまう。
「キャアアアアアアアアアア‼︎」
観客達の視線が一点に集まっていく。
今宵のライブの主役がご登場だ。
ダンサー達の間を黒いライダース・ジャケットで着飾ったマット・グレンジャーがゆっくりとステージの中央へ歩いていく。
メンバーのジョニー・アンダーソン、ダニエル・カルロ、ボビー・キーチもそれぞれの位置につき、爆音を鳴り響かせる。
マットはスタンド・マイクの前で仁王立ちし、息を吸い込んで伴奏の音圧に負けない声量で歌い始めた。
If you’re alone
(もし君が一人でいるのなら)
I’ll reach for your hand
(僕が手を握るよ)
Again and again
(何度でも)
Everything’s gonna be alright
(大丈夫、全てうまくいくさ)
非現実的な世界観と会場いっぱいに響き渡る圧倒的な歌声。
もう最高としか言いようがない。
彼らの名は『スーパージャイアンツ』。世界を代表するアメリカ出身のロック・バンドだ。
「……す、すごい……!」
六歳の仁稀(宇対瀬仁稀と書く)は、テレビの前に釘付けになりながら、彼らのパフォーマンスを楽しんでいた。
大勢のファンは彼らを見つめながら手拍子をしたり、リズムに合わせて腕を振っている。知らず知らずのうちに彼らの歌を口ずさんでいる。まさに会場全体が一体となっているかのようだった。
マットは、芯を持つような鳴りの強い声をマイクに乗せて、感情を表現しながら歌っている。そんな彼の姿に、仁稀はずっと憧れていた。
「……ボクもいつか、みんなを笑顔にできるような歌手になりたい……!」
仁稀が目を輝かせながら呟くと、母・美帆(宇対瀬美帆と書く)がにっこりと微笑んだ。
「仁稀ならきっとなれるよ。お母さんが保証する」
「ほんと?」
「うん」
美帆は強い眼差しで仁稀を見つめる。その榛色に輝く瞳に、仁稀の笑顔が鮮明に映り込むようだった。
「今の時代はどこへだって自由に行けるし、なりたい自分になんだってなれる。だから自信を持って、夢に向かって突き進んで良いのよ」
美帆は仁稀の手を優しく握る。仁稀は手のひらから伝わる温もりを感じながら、美帆に思いきり抱きついた。
「……ありがとう、お母さん……!」
仁稀が嬉しそうに笑うと、美帆は仁稀を包み込むように抱き寄せた。そして、我が子の幸せを願うかのように目を閉じた。
○
――四年後。
とある河川敷に、多くの人だかりができている。
一〇歳の仁稀は、坂本九の『上を向いて歩こう』を弾き語りしていた。
歌声に耳を傾け、楽しそうに手拍子を始める観客たち。
その様子を遠くから、黒いキャップ帽を被った男性が見つめている。
「………………」
アウトロに差し掛かると、仁稀は弾き語りを終えて一礼をする。一気に大歓声が巻き起こると、仁稀は微笑みながら前を向いた。
X X X
仁稀の住む町は、古き良き風情が残る豊かな田園都市だ。人口は約五〇〇〇人ほどで、時代の雰囲気を感じる大柄なモルタル駅舎がそのまま残っている。
町の真ん中には綺麗な河川があり、その近くには公園がある。今日、そこで仁稀は親友・灼(大槻灼と書く)の勧めで弾き語りをした。
夕暮れ、仁稀は親友の灼(大槻灼と書く)と共に家路を歩く。
「いや〜、仁稀くんはやっぱり歌がうまいなぁ。なんだか仁稀くんの歌声を聴いていると力が出てくるんだよね」
「……そ、そんな……! ……お世辞なんて……」
「お世辞なんかじゃないよ。仁稀くんには人の心を動かす力がある。実際にあそこにいた人たち、みんな仁稀くんに夢中だったし、俺の目に狂いは無かった!」
「……いや、でも……、みんながみんな、僕の歌を聴いてどう思ったかなんて分からないし……」
「みんな最後は全員笑顔で拍手してたから大丈夫だよ」
「……いや、でも……」
仁稀がそう呟くと、灼は立ち止まり「……あぁ〜! も〜!」と勢いよく捲し立てながら話し始める。
「仁稀くんは、ホント自信無さすぎ! ……まぁ、今日むりやり河川敷で歌を歌ってもらったのは悪いと思ってるけど、あぁでもしないと、仁稀くん、いつまで経っても自信ないままで終わっちゃうと思ったし! だから、俺はもっと仁稀くんに自信を持ってほしくて今日誘ったんだよ! ……ていうか、思い出してごらんよ! 今日、歌ってたとき、みんなどんな顔してた?」
そう言われて、仁稀はさっきまでの記憶を振り返っていた。
「…………笑ってた…………」
「だろ? 仁稀くんには十分、人を元気にする力がある! だからさ、もうちょい自分の凄さに気づきなよ! 仁稀くんはめっちゃくちゃ凄いんだからさ!」
灼は息を荒くし興奮しながら言うと、仁稀は顔を赤くしながら口をもごもごさせた。
「……あ、ありがとう……」
仁稀が恥ずかしそうに微笑むと、灼は息を整えた。
六歳の頃に母・美帆(宇対瀬美帆と書く)を亡くし、祖父・晃恭(宇対瀬晃恭と書く)の元に引き取られたからというもの、仁稀はその内気な性格から中々周囲に馴染めず、学校で友人を作ることができなかった。そんな時に声をかけてくれたのが同級生の灼だった。灼は仁稀にとって良き理解者であり、唯一どんなことでも話し合える仲である。
「……夢なんだろ? 歌手になるのが」
「……うん……!」
やがて、二人はT字路に辿り着く。灼は親指を立てて笑顔を浮かべた。
「なら、絶対に歌手になれるよ。俺は信じてる!」
その言葉を聞いて、仁稀は拳を握りしめながら答えた。
「……ぼ、僕、頑張るよ……!」
「うん!」
二人はしばらく見つめ合うと「アハハ!」と笑い合って手を振った。
「それじゃあ、仁稀くん、またね!」
「うん! ありがとう、灼くん! またね!」
そう言って別れると、仁稀はコーラルレッド色の屋根が目立つ家に向かった。
X X X
レトロな雰囲気と洋風なテイストが組み合わさった店の扉から優しい鈴の音が鳴り響く。
ここは、晃恭が四〇年前に立ち上げた老舗レコード・ショップ『宇対瀬レコード』。
最新のアルバムやシングル、幻の名盤など様々なジャンルの作品を取り扱っており、老若男女・幅広い年齢層の人たちが楽しめるような店となっている。
今日は休業日のため、晃恭は外に出て看板の拭き掃除をしていた。
「ただいま、お祖父ちゃん」
「おかえり、仁稀」
晃恭は「イタタ……」と腰を摩った。
「お祖父ちゃん、無理しないで。僕がやるよ」
仁稀が心配そうに話す。しかし、当の本人は年齢を感じさせない動きで掃除を続けた。
「大丈夫、大丈夫! 毎日の日課なんだ。それに、ずっと中にいては運動不足になってしまうよ」
晃恭は優しい微笑みを浮かべると、仁稀は「もう、お祖父ちゃん……」と言わんばかりの表情を浮かべながら、驚かそうと思いきり抱きついた。
「おっとっと……!」
一瞬よろけたが、晃恭は体勢を整えて嬉しそうに仁稀を抱きしめた。
「フフフッ、……どうかしたのかい?」
「いや。ただ、お祖父ちゃんが温かくて落ち着くなぁって思って……」
「そうかそうか……! ハッハッハ」
仁稀は晃恭のことが大好きだった。
優しくて親切で、物腰の柔らかいお祖父ちゃん。両親のいない仁稀にとって、晃恭はたった一人の家族だった。
「まだまだ甘えん坊さんだな、仁稀は」
「へへへ……」
晃恭は仁稀の頭を優しく撫でた。
「さっ、中に入って晩ご飯の準備をしよう」
「うんっ! 今日のご飯はなに?」
「唐揚げだよ」
「唐揚げ⁉︎ やったー!」
二人は店の中へと入り、晩ご飯の準備に取り掛かろうとした。
X X X
仁稀と晃恭は店の二階に住んでいる。
リビングの他に洋室と和室があり、アンティークな小物や数々のトロフィー、盾、そして美帆の写真が沢山飾られている。
祈りを捧げるように手を合わせると、仁稀は美帆の姿を見つめた。写真の中の美帆は、優しい微笑みを浮かべている。その表情を見てるだけで、どんな不安も吹き飛んでいくようだった。
「ご飯できたよー」
晃恭に呼ばれ、仁稀は「はーい」と返事をしながら出来上がった料理をテーブルに運んだ。食卓には、ほうれん草のおひたし、きゅうりの浅漬け、豆腐とワカメの味噌汁、ご飯が並ぶ。
晃恭はアツアツの鶏の唐揚げを真ん中に置き、仁稀と向かい合わせに座った。
「わぁ……! 美味しそう……!」
「ハハハ! さっ、食べよう」
「うん!」
二人は手のひらを合わせる。
「いただきまーす!」
仁稀は大好きな唐揚げを口いっぱいに頬張った。
「ん〜! 美味ひい!」
「そうかい! 良かった良かった」
晃恭が微笑みながら、唐揚げを口に運ぶ。
仁稀はそんな晃恭を見て、しみじみするように微笑んだ。
六歳まで東京で暮らしていた仁稀は、唯一の親類縁者である晃恭に引き取られ、東北の田舎町に引っ越してきた。慣れない環境に戸惑うことも多くあったが、その度に晃恭がいつも隣で支えてくれた。仁稀はそんな晃恭に感謝を伝える。
「お祖父ちゃん」
「ん? なんだい?」
「いつも美味しいご飯を作ってくれてありがとう」
「ハハハ、こちらこそ、いつも美味しく食べてくれてありがとう、仁稀」
二人はそう言って笑い合った。
「そういえば、お母さんも仁稀みたいにご飯を美味しそうに食べていたなぁ」
「えっ、お母さんも?」
「うん。そうだよ。仁稀みたいにまだ小さかった頃も、口いっぱいにご飯を頬張って幸せそうに食べるんだ」
晃恭は懐かしむように話した。
仁稀の母・宇対瀬美帆は、日本を代表するシンガーソングライターである。デビュー・シングルはミリオンセールスを記録し、以降も発表してきたアルバムは全てチャート一位を獲得。一躍トップアーティストの仲間入りを果たした。
そんなアーティスト活動とは裏腹に、家ではごく普通の母親として接していた美帆。自分の息子には、寂しい思いをさせたくないと毎日必ずご飯は一瞬に食べていた。
「……たしかに、お母さん、一口大きかったかも」
仁稀がそう言うと、晃恭は「ぷっ……!」と声をもらした。
「アハハ! そうだなぁ!」
「だよね! アハハ!」
二人の笑い声が家中に響き渡る。幸せな時間はしばらく続いていった。
○
――次の日。
仁稀はギターを持ちながら河川敷を歩いていた。
階段を降り、昨日いたベンチに座るとケースからギターを取り出した。隣には黒いキャップ帽を被った男性がうなだれて座っている。
その男性を気にしつつも、仁稀は『Supergiants』の『Everything’s Gonna Be Alright』を弾き語りし始めた。
すると、今まで下を向いていた隣の男性が顔を上げる。
仁稀は青い空を見上げながら目を閉じた。
澄んだ空気と花の香り。
やがて、あたたかい光が町を照らし出すと、仁稀はサビを歌い出す。
周囲に段々と人が集まり始めると、一気に目の前に人だかりができた。
一番を歌い終え、演奏が二番へと移ると、隣から歌声が聴こえてくる。
仁稀は驚きながら横を見た。隣のベンチに座る男性が、二番を歌っている。
男性は芯を持つような鳴りの強い声で、感情を表現しながら歌っている。その歌声に、仁稀はしばらく体を硬直させていた。
「お、なんだなんだ?」
「誰だろう……」
観客たちがどよめき始めると、仁稀はその歌声に興奮を抑えきれずにいた。
(す、すごい……! こ、この声……、もしかして……)
仁稀は男性を見つめる。
その時、仁稀は気付いた。目の前にいるのは、紛れもなく『Supergiants』のボーカル、マット・グレンジャーだと。
仁稀は拳を握り、力を入れる。マットは仁稀にアイコンタクトを送った。仁稀は目を閉じ息を吸い込んだ。そして、声を出す。
If you’re alone
(もし君が一人でいるのなら)
I’ll reach for your hand
(僕が手を握るよ)
Again and again
(何度でも)
Everything’s gonna be alright
(大丈夫、全てうまくいくさ)
二人のセッションに耳を傾け、観覧する多くの人たち。やがてその場にいる全員が手拍子を始める。夢中になって歌う二人。
目の前を見ると、さっきまで目を逸らしていた人たちがこちらへ視線を向けてくる。
仁稀とマットはお互いに視線を向けて微笑み合う。そして、サビの最後まで気持ちを通わせるかのように歌い上げる。
二人の歌声が町中に響き渡る。
しばらく静寂が周りを包んだ。やがてその静寂は鳴り止まない歓声へと変わっていく。
「おおおおおおおおおおおお‼︎」
「すごぉぉい!」
「カッコいいぞ! 二人とも!」
仁稀とマットは深くお辞儀をする。
観客たちはさらに大きい拍手と歓声を送る。
二人が顔を上げると、皆、笑顔で仁稀たちを見つめていた。
仁稀が振り向くとマットが親指を上げ、ニコッと笑っていた。涙が出そうになるのを堪えながら、仁稀はゆっくりと微笑んで、再び観客たちの方へと顔を向けた。
すると、どこからか声が聞こえてくる。
「えっ? この人、マット・グレンジャーじゃない?」
「うそっ⁉︎」
「本当だ!」
「ヤバい!」
やがて周囲がざわつき始め、皆、スマホを手に持ち始める。
マットが慌てていると、仁稀は手を握る。
「一緒に来てください……!」
「えっ……?」
「いいから!」
「う、うん……!」
仁稀はマットの手を引っ張った。
二人はその場を急いで走り去る。
「アアアアアアアアアアアア‼︎」
早く家にたどり着こうと、車を追い越し、電車を追い越し、マッハの勢いで走り去る。
仁稀は叫びながら走っていると、ふと背後から『ゾクッ』というとんでもない威圧を感じた。覚悟を決めて、後ろをチラッと見る。
「ちょっ‼︎ 待てよおおおお‼︎」
「ぎぇぇぇぇぇ‼︎⁉︎」
町人たちが鬼の形相で追いかけてくる。
「ちょっ‼︎ 待てよおおおお‼︎」
「それっ‼︎ キムタクうううう‼︎」
二人は叫びながら必死に逃げた。
X X X
『Supergiants』とは、多くの世代から絶大な人気を集め、音楽界に大旋風を巻き起こしてきた男性四人組ロックバンドだ。彼らは世界各地で起きている様々な問題に思いを寄せ、楽曲を通し、社会にたくさんのメッセージを投げかけてきた。
六年前に活動休止をしてしまったが、常に進化を遂げてきた高い音楽性と文学性は、今も尚、世のアーティスト達に大きな影響力を与え続けている。
そんなレジェンドの手を引っ張りながら、仁稀はマットとともに走り逃げ、『宇対瀬レコード』の裏口から中へと入る。
「……ハァハァ……!」
「……な、なんとか……逃げ切ったぁ……!」
二人は息を吐きながらその場に座り込む。
すると仁稀はビクッと体を震わせながら、マットへ頭を下げた。
「ほ、本日は誠にっ! 誠に申し訳ありませんでしたぁ!」
仁稀が頭を下げると、マットは驚く。
「いやいや! どうして謝るんだい⁉︎」
「だって、本家本元の目の前で歌を歌うなんて……! 僕は……僕は……なんてことを……!」
仁稀は顔に血が上るのを感じて、思わず両手で顔を覆った。マットは「そんなに落ち込まなくても……」と苦笑いをし、仁稀を宥めた。
「あ、あの、ほ、本物の、マット・グレンジャーさん……ですよね……⁉︎」
「あぁ」
仁稀は「……す、すごい……」と震えながら目を輝かせる。
「……ぼ、僕、宇対瀬仁稀と言います。ここは、お祖父ちゃんがレコード屋で……、今はここで二人暮らしをしています……!」
「そうか……! よろしくな。仁稀くん」
マットは優しく微笑んだ。
「僕『Supergiants』の大ファンで……! 全部のアルバム持っているんです!」
男性は驚いたように目を見開く。仁稀は興奮しながら話を続けた。
「特に四枚目のアルバム【Earth】が大好きで、ジャケットも真似して描きました! 収録されているのは一〇曲だけど、どれも名曲揃いで特に『Everything’s Gonna Be Alright』は絶対に聴き逃せないレジェンド級の曲で……」
仁稀、ハッと我に返る。
「す、すみません……! つい……!」
すると男性は、涙を流している。
「……アハハ……す、すまない……!」
仁稀は恐る恐る問いかける。
「あ、あの……。差し支えなければお聞きしたいのですが……」
「ん? なんだい?」
「もしかして、六年前に何かあったんですか……?」
「えっ……?」
「……だって、マットさんが、こんな田舎町にいるなんて信じられないし……」
「…………」
マットは「ふぅ……」と息を吐く。
「うん。ちょっと、昔のことを思い出してね」
「昔のこと……?」
「あぁ……」
マットは下を向く。
○
――遡ること六年前。
ブルックリンにあるレコーディング・スタジオの中では、マットが作曲をしていた。
ピアノを弾きながら、楽譜を書く。すると女性スタッフがマットの後ろに立ち、声をかける。
「ハーイ! マット、今、どこまで進んでる?」
マットは楽譜を書きながら「もう少しでできるよ」と、必死そうに言った。
「マット! 次はこの企画テーマ曲をお願いするよ!」
男性スタッフが駆け足でスタジオに入ってきて、用紙を手渡す。
マットはただ「あぁ」と感情がないままに答えた。
X X X
真夜中になり、マットはピアノの上でうなだれていた。
同級生で同じ『Supergiants』メンバーのジョニー、ダニエル、ボビーは、彼を心配していた。
「マット……」
「大丈夫か?」
ダニエルとボビーが声をかけると、マットは顔を両手で覆った。
「……俺、どんどん空っぽになってる気がする……」
マットは三人に向かって「みんなに申し訳ない……」と、頭を下げる。そして、その場を離れ、スタジオを出た。
「マット!」
ジョニーはマットを追いかける。
「ちょっ! 二人とも!」
ダニエルとボビーは心配そうに二人を見つめた。
外は大雨が降っている。雨音は強く、激しく反響していた。
X X X
雨が降りしきる中、マットは傘もささずに走っていた。
その後ろをジョニーが追いかける。
「マット……!」
声を上げるが、マットは振り返らない。もう、彼の耳には何も届いていないようだった。
マットは止まらず足を走らせる。
やがて、広い道路へ飛び出すと、車が猛スピードで走ってくる。ヘッドライトがマットを照らす。
「マット!」
驚きながら立ち竦むマットをジョニーが後ろから押し出す。
――その瞬間、ドンッと、鈍い音が聞こえた。
マットが後ろを振り向くと、ジョニーは車の前で倒れていた。
「……ジョ……、ジョニー……」
声をかけても、ジョニーは返答しない。目を閉じたまま、血を流し倒れている。
マットはその時、取り返しのつかないことをしたと確信した。ジョニーは、俺のせいで事故に遭った――と。
○
――そして、再び六年後。
マットは日本各地を渡り歩いていた。
グループを離れてからというもの、マットは何もできずにいた。メンバーのみんなに申し訳が立たない、そう思うと、自分の生きている意味すら分からなくなっていた。
もう、誰も傷つけたくない。
誰も自分のことを知らないところへ行きたい。
そんな思いで毎日を過ごしていた。
だが、心の中では音楽を諦めきれない自分がいた。
マットはやがて、東北のある田舎町に辿り着く。
しばらく歩いていると、何やら人だかりが見えてくる。近づくと、河川敷前で坂本九の『上を向いて歩こう』を弾き語りしている少年がいた。
マットは遠くから少年の姿を見つめる。
少年の歌声にマットは固まっていた。
○
「……これが、ここに来た経緯だよ」
「そう……だったんですか……」
仁稀は暗い表情を浮かべる。マットは、むりやりに笑顔を作った。
「俺はいつも周りの期待に応えていれば良いと思っていたんだ。『そうすればみんなに喜んでもらえる』って、そう思っていたんだ……。……でも結局、仲間を傷つけてしまって……、それから黙ってみんなの元から逃げたんだ……」
仁稀はマットを見つめる。
「思い返せば、俺はずっと中途半端なまま生きてきた。結論を出せず、見て見ぬふりをして……。ホント、自分の一番悪いところだよ」
仁稀は涙を流した。
「……どうして……どうして……無理に笑うんですか……?」
マットは仁稀の方を向く。
「……ぼ、僕は、自分の悪いところに気づけたのって、とてもすごいことだと思います。それができる人って中々いないと思うので」
マットは目を見開く。
「何より、その思い出があったからこそ、今のマットさんがいるんだと思いますし……。過ぎてしまったことはやり直せないけど、これから前を向いて自分の納得のいく道をゴールまで突き進めば良いと思います……!」
仁稀はマットの両手を包み込むように握った。
「もっと、自分のことを優しくしてあげてください……!」
マットの目から、涙が止めどなく溢れ出す。そして、仁稀を抱きしめた。
「……うん……うん……! ……ありがとう……。……ありがとう……」
仁稀も微笑む。
「……俺、ずっと考えていたんだ。自分にはもう歌う資格なんか無いって。……でも、君の歌を聴いて思ったんだ。『あぁ、自分はやっぱり音楽が大好きなんだ』って。だから、俺、良かったよ。君のおかげで自分を取り戻せた。今日のこと、絶対に忘れない。これからも、一生懸命自分と向き合いながら頑張る。……仁稀くん、今日は本当にありがとう」
マットは優しく微笑みながら仁稀の頭を撫でる。
仁稀は涙を拭い、笑顔を見せた。
「……やっと確信した気がする。君の歌の力が」
「えっ……?」
「君は大勢の人達に、その歌声で元気を届ける力がある。これは、本当にすごいことだよ」
マットの言葉を聞いた瞬間、仁稀は体が震えているのが分かった。
「……俺は、心優しい君へ恩返しをしたい」
仁稀は顔を赤くしながらマットの目をまっすぐ見つめる。
「……仁稀くん、俺と一緒に音楽で世界を変えないか?」
仁稀は目を見開いた。
「そ、それって……」
「そうだ」
マットは言葉にする。
「君、歌手を目指さないか?」
仁稀の目から涙が溢れ出てくる。
あの日から、目指してきた夢。それが今、叶うかもしれない。仁稀は迷わず答えた。
「……はいっ! 僕は……僕は……! ……歌手になりたいです……!」
マットは優しく笑いながら仁稀の頭を撫でた。仁稀はマットの目をまっすぐ見つめる。マットは微笑んで手のひらを前に出した。
「それじゃあ、改めて、これからもよろしくな。仁稀くん」
仁稀も涙を拭って、微笑みながらマットの手を握った。
「はい……! よろしくお願いします……! マットさん……!」
二人はもう一度ハグをする。
すると突然、中から声が聞こえてくる。
「仁稀〜、帰ってきたのかい?」
晃恭は仁稀とマットの姿を見つめる。
「え?」
「え?」
「え?」
三人はお互いに目を見合わせた。
「えぇぇぇぇぇぇぇ⁉︎」
晃恭は驚きを隠せず、大声を出しながらその場にあった傘をマットへと突きつける。
「お、お祖父ちゃん……‼︎」
マットは声も出せずにその場に固まる。晃恭は今までに見せたことのない、まさに鬼のような形相でマットを睨みつけた。
「……君は、何者だ……⁉︎」
マットと仁稀はお互いに目を合わせながら、ただその場に固まっていた。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

