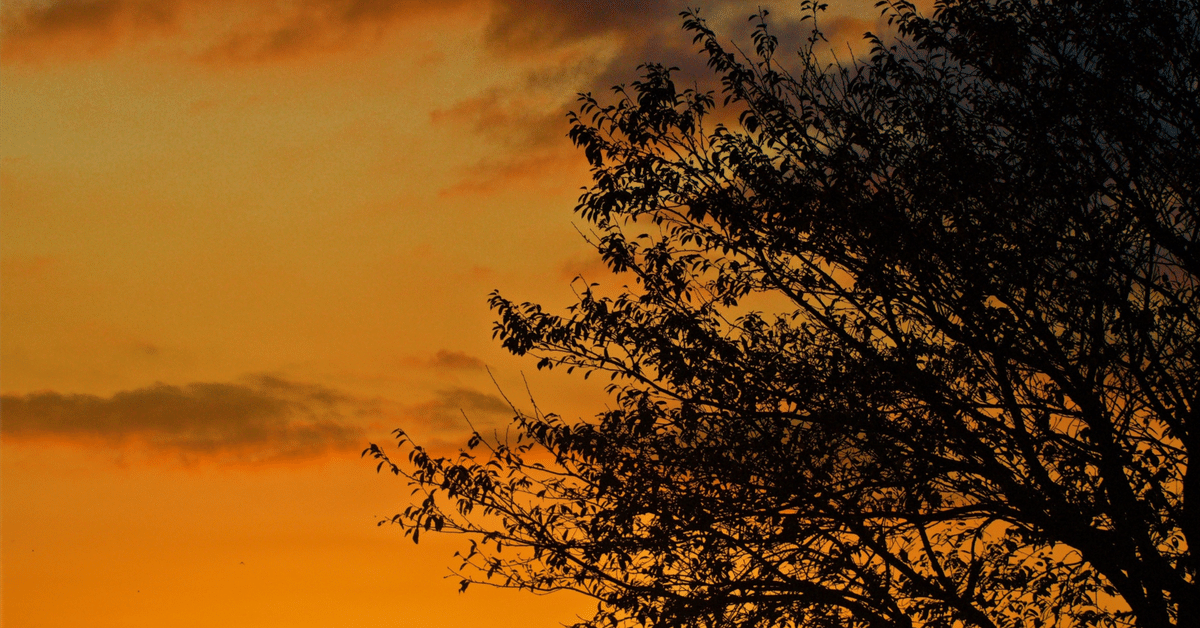
「そこが知りたい! 入管法改正案」について その3 送還停止効の例外について〜「送還忌避者」を産みだしているのは入管自身。まずは、そこから変えるべき。
つづいて、「そこが知りたい!」で課題として挙げられていた各項目とその解決策についてです。
https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00007.html#midashi02
「そこが知りたい!入管法改正案」では、国連勧告には全く出ていない「送還忌避」問題をトップに持って来ました。今回の入管法の一番の狙いがよく分かる位置づけだと思います。
前科のある人を国内から排除するだけで良いのか?
まず、「送還忌避者」のうち、前科を有する者が3分の1くらい、6分の1くらいが実刑前科を有する者だということが、箇条書き2つ目に挙げられています。
このような手法を「モラル・パニック」の扇動、というのですね。この点については、稲葉剛さんの「論座」の論考でこの言葉を知りました。
そして、仮に前科があるからといって、日本社会から排除すればそれで良いのでしょうか。
法務省は、再犯防止のために重要なものとして、住居と仕事を挙げています。
そして、2021年2021年3月に京都で行われた第14回国連犯罪防止刑事司法会議(京都コングレス)で採択された京都宣言では、次のとおり述べられています。
5 我々は,刑事分野における国際協力を促進し,強化することにより,犯罪を防止し,これと闘うための地球規模の協調的な取組を強化することを行う。
38 社会及び個人の保護の必要性や被害者及び加害者の権利に十分に配慮した上で,地域コミュニティの積極的な参加を得て,加害者の社会復帰を促進するためにコミュニティに おける更生環境を推進する。
とあります。
また、政府が公表している令和2年版再犯防止推進白書(概要)でも「『京都宣言』の交渉過程において、『誰一人取り残さない社会』の理念を背景に、国際社会において再犯防止を推進すべきとの合意が形成」されたとあります。
つまり、
・犯罪防止のためには社会内の環境を整えるのが重要(宣言38)
↓
・犯罪防止のためには国際協力の促進が重要(宣言5、再犯防止推進白書)
というのですから、刑務所から出た外国人についても、「仕事」「住居」を中心とした社会内環境を整えるべく、国際協力をするのが重要ということになります。
ですから、「前科者は本国に送還してしまえ、後のことは知らん。」という態度は、京都宣言に反し、京都コングレスのホスト国としては大変恥ずかしいものといえます。
詳しくは以下をどうぞ。
どうして刑務所に行くことになったのか?→国策の犠牲者も
そして、犯罪に手を染めてしまい、刑務所に行き、それでも本国への送還を拒んで日本に居続ける人もいます。
それはどういう人たちなのでしょうか。
2019年6月に大村入管で餓死したナイジェリア人男性は刑務所を仮出獄後、帰国を拒んで収容が続けられ、餓死しました。送還を拒んでいたのは、日本に子どもがいるから、ということでした(大村入国管理センター被収容者死亡事案に関する調査報告書12頁参照)
ヨーロッパ人権裁判所や、自由権規約委員会であれば、このような方を強制送還するのは、条約違反であると判断されていたことでしょう。以下は、2021年4月21日に衆議院法務委員会で配布した資料です。この件より遙かに激しい前科を有する方についても、家族生活の方が重要として強制送還が違法としています。
また、私が受任したり相談を受けたケースでは1990年の入管法改正で日系人に定住者の在留資格が認められるようになり、家族で来日した際小さかった子どもが成人して犯罪に手を染め、刑務所に行き、その後入管に長期収容された方が何人もいます。
当時、まともな受入体制がないまま家族で来日。子どもは、学校に行っても、見たこともない日本文字を使っているのですから、当然勉強もついていけません。学校に行っても居場所がなくてドロップアウトしてしまい、少年時代は少年院に。成人してからも当時の仲間との付き合いが断ち切れず、犯罪に手を染めて、実刑判決を受け、出所後入管へ。でも、家族は日本にしかいない、その時点では本国には知り合いがいない、だから日本に残りたいという人たちです。
以下の書籍では、10歳で来日した日系人の子どもが犯罪を犯し、入管に収容されるまでの実体験を描いています。
1990年の入管法改正をリードし、日系人の受入れの扉を開いたという元東京入国管理局長、「ミスター入管」と呼ばれた坂中英徳氏は、次のように述べています。
入管法を改正して二つの法律で“在留資格”をつくり入れたんですけどね。ですから、子どもの教育のこととか、社会統合のことを,一切、僕なんかの頭になかったわけです。僕の頭になかったということは、政府関係者にも誰にもなかったわけですよ。突然ブーっと入ってきたと。ああいう受け入れ方は駄目ですよ。僕自身、反省してますけどね。
チャプター(6)
現在「送還忌避者」と括られ、前科者、危険人物だから排除すべきという印象づけがされている人たちの中には、少なからず、このような政府の人権条約違反の対応や、無策による犠牲者もいるはずです。
複数回申請について
「そこが知りたい!入管法改定案」では、「現在の入管法では、難民認定手続中の外国人は、申請の回数や理由等を問わず、また、重大な犯罪を犯した者やテロリスト等であっても、退去させることができません(送還停止効)。外国人のごく一部ではあるものの、そのことに着目し、難民申請を繰り返すことによって、退去を回避しようとする人がいます。」とされています。
「保護すべき者」が確実に保護されていない。
複数回申請については、色々なところで言われているとおりで、認定されるべき人が認定されないから、繰り返しているのです。
「3 入管法改正の基本的な考え方」では、
今回の入管法改正案の基本的な考え方は、次の3つです。
①保護すべき者を確実に保護する。
②その上で、在留が認められない外国人は、速やかに退去させる。
③退去までの間も、不必要な収容はせず、収容する場合には適正な処遇を実施する。
とされています。①は、これまで保護すべき者を確実に保護してこなかったことを自認しているように読めます。
トルコ国籍のクルド難民
日本で最も顕著なのは、トルコ国籍のクルド難民です。
以下の記事によれば、
トルコ国籍クルド人は、2018年に日本で563件の難民認定申請をしているが、同年を含めて過去1件も難民認定を受けていない。他方、2018年の世界におけるトルコ国籍者の難民認定率は45.6%だった
とのことです。
その後、2022年5月に札幌高裁で勝訴判決が出され、それを受けて7月に初めて入管はトルコ国籍のクルド難民を難民認定しましたが、その1件しかないのです。
「世界で最も迫害された少数民族」ロヒンギャも
また、2023年2月20日公表の「現行入管法の課題」にも引用されている、「参与員が、入管として見落している難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません。」旨発言した柳瀬房子さんが代表を務められていた「難民を助ける会」でも「世界で最も迫害された少数民族」とされているビルマのロヒンギャですが、
以下の記事によれば、難民として認定されたのは、ごく一部。300人中17人と1割にも充たないのです。
タリバン政権下のアフガニスタン・ハザラ人ですら
20年以上前の話にはなりますが、2001年に私が調査した結果では、オーストラリアの難民再審査審判所(Refugee Review Tribunal)で、アフガニスタン出身のハザラ人で難民と認定されなかった例は認められませんでした。
他方、当時私は日本で収容されたアフガニスタン難民の弁護団一員として、入管手続やら収容からの解放やら難民不認定処分に対する訴訟に関与していましたが、私たち弁護団の依頼者30人強(一人以外はハザラ人)は誰一人難民として認定されませんでした。
当時、ハザラ人がどれだけ酷い目に遭っていたかは、以下をご覧下さい。
「保護すべき者」が保護できていないのに
このように、いみじくも、「ここが知りたい!入管法改正案」で自認してしまっているとおり、「保護すべき者」が確実に保護できていないのです。だから、彼らは複数回申請せざるを得ないのです。
ところが、2023年入管法案にはこの点を手当てする仕組みは何一つありません。
解決方法としての送還停止効例外は誤っている
しかし、「そこが知りたい!入管法改正案」では、3回目の申請の場合は、原則として入管内部の手続中であっても送還できるようにしようとしています(「4 入管法改正案の概要等 (2)送還忌避問題の解決 ①難民認定手続中の送還停止効に例外を設けます。」)。
「保護すべき者」を確実に保護できていないにもかかわらず、複数回申請を濫用者であると決めつけ、退去させることを可能としようというのです。
方向性が間違っています。
「ただし、3回目以降の難民認定申請者でも、難民や補完的保護対象者と認定すべき『相当の理由がある資料』を提出すれば、いわば例外の例外として、送還は停止することとしました。」とありますが、誰が「相当の理由がある」と判断するのか、その判断について申請者は意見を述べる機会はあるのか、不服申立はできるのか、訴訟はできるのかなど、条文のどこを見ても手続がわかりません。2023年3月7日に筆者が移住連の省庁交渉で出入国在留管理庁の担当者に質問をしたときも、結局誰が判断権者なのかすら答えられませんでした。
さらに、送還停止効の例外は、3年以上の実刑に処せられた者及びテロリスト等にも及びます。
ですが、3年以上の実刑に処せられたかどうかということと、難民該当性は全く関係ありません。
難民条約33条2項は「締約国の安全にとって危険であると認めるに足りる相当な理由がある者または特に重大な犯罪について有罪の判決が確定し当該締約国の社会にとって危険な存在となった者」については、送還禁止の対象外とすることを容認していますが、2023年法案にある無期若しくは3年以上の実刑判決だけでは、「締約国の安全にとって危険」であるとか、「特に重大な犯罪について有罪の刑が確定し当該締約国の社会にとって危険な存在となった者」とは言えません。難民条約違反の疑いが強いです。
そして、テロリスト等に該当するかどうか判断するための手続規定が全くありません。仮にその疑いがあるにしても、本国へ送還することによる本人のリスクと、難民と認定して日本に在留することとのリスクを比較衡量する、比例原則に則った判断が必要です(UNHCRの2021年4月9日意見概要参照)
まずはちゃんとやれ
2022年11月3日の自由権規約委員会は以下のとおり懸念を表明し、勧告をしていますが、これに対しても今回の法案はスルーしています。
委員会はまた、難民認定率が低いという報告(第7条、第9条、第10条および第13条)にも懸念を抱く。33 これまでの勧告を考慮し、締約国は、次のことを行うべきである。
(a) 国際基準に沿った包括的な庇護法を速やかに採択すること。
「そこが知りたい!入管法改正案」では、「③難民認定制度の運用を一層適切なものにします。」として、法改正事項ではない取組を挙げていますが、国連はちゃんと法律作れ、と言っているんですね。
平成26(2014)年12月に、第6次出入国管理政策懇談会・難民認定制度に関する専門部会が「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果(報告)」において様々な提言をしているのに、その取組は遅々として進んでいません。8年以上経っているのです。今回、「一層適切なものにします。」と言っても、信用できないです。まずは、そちらをちゃんとやってから言うべきです。
濫用かどうかも司法審査の対象とすべきなのに
出入国在留管理庁が公表している「令和3年における難民認定者数等について」によれば、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している 案件(B案件と呼ばれます)は申請者2413人中33件、わずか1.4%に過ぎません。もともと濫用者は少ないのです。
そして、難民申請者の異議棄却後裁判を受ける機会を奪ってチャーター便によって送還した事件で、裁判を受ける権利(憲法32条)等違反とした東京高裁2021年9月22日判決は、濫用かどうかを含めて司法審査を受ける機会を保障すべきとしました。
司法審査をするためには、難民不認定処分という出入国在留管理庁の判断がされるのが大前提です。ところが、送還停止効の例外を設けるということは、その前提となる処分がされる前に、送還することができることになります。司法審査の機会を完全に奪い去ることができてしまうのです。
先の東京高裁判決に対して国は上告することなく確定しました。判断に服したのです。それなのに、司法審査の機会どころか、その大前提となる行政による判断を経るまでもなく強制送還ができるようにするという、今回の入管法は論外です。
先にも引用したとおり、「そこが知りたい!入管法改正案」には、「難民認定申請を繰り返すことによって、退去を回避しようとする人」は「外国人のごく一部」と書かれています(下図参照)。

入管ですら、「ごく一部」しかいないと認めている濫用者のために、日本独自の厳しい基準で不認定にされている、本来「保護すべき者」を排除するのが、今回の法案です。方向性が間違っています。国連の勧告に従い、「国際基準に沿った包括的な庇護法を速やかに採択する」ことを、まずは検討すべきです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
