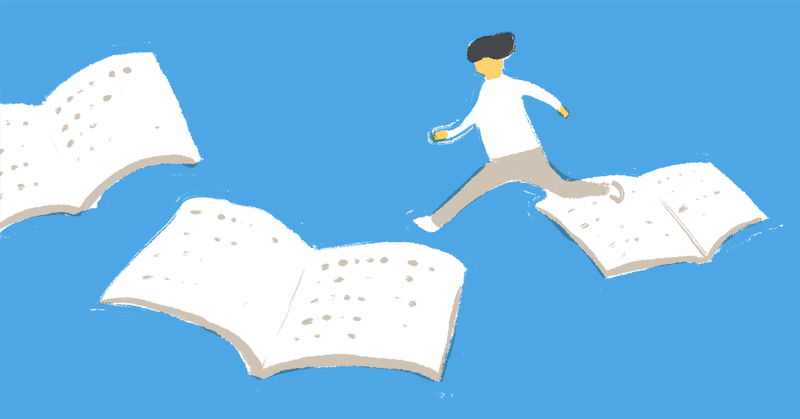
マニュアルのゴールは、守破離。
右も左も分からない、社会人1年目を終えて理解した事の1つとして、
マニュアルのゴールは、作って守るものではなく、変えていくものだということ。
最初は、作業に慣れることへ必死だった。
今も余裕がある訳ではないが、
慣れるために大事にしていたのは、マニュアルの作成だった。
とにかく、マニュアルを作って、周囲の真似をすること。
マニュアルに不備があれば、それは自分が今まで見えてなかった視点として
その度に、メモをとり、アップデートしての繰り返しだった。
そんな中で、マニュアルのゴールは守破離だと、
作って終わりではなく、
そこから、ブラッシュアップする前提とすること。
理由は、アニュアルの質が、作業の質をあげ、考え方の質をあげるからだ。
(守破離について)「守」は、師や流派の教え、型、技を忠実に守り、確実に身につける段階。「破」は、他の師や流派の教えについても考え、良いものを取り入れ、心技を発展させる段階。「離」は、一つの流派から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる段階。
アニュアルの質が、作業の質をあげ、考え方の質をあげる。
“守る”とは、言い換えると現状維持。
現状維持の時点で、平行線か下るだけで、
上がることはないというポイントもあるが
より具体的な理由として、
アニュアルの質が、作業の質をあげ、考え方の質をあげるからだ。
マニュアルとは、仕組み化することだ。
作業工程を統一して、全員にとって、
より良い環境を整えるためにマニュアルを作成するので
当然、作業の質は全体的に期待できる。
そして、大事なのは次だ。
(ただやらされている状態だと難しいが、)
作業の質が上がると、考え方の質に変化が起きる。
マニュアルとは、これまで蓄積された試行錯誤の末に得られた
現時点でのベストアンサーだ。
1つの作業だけでなく、
その作業の前後にある他の作業との兼ね合いも俯瞰し決められている。
(守の段階)作業の質(真似の質)が上がると
自然とマニュアルの中身に対する理解、
つまり、“なぜこうした方がいいのか。”、“どうして、この作業が必要なのか。”
という、作業の目的が自分なりに咀嚼できるようになる。
離の段階
そうすると、(離の段階)例えばこんなことが出来るかもしれない。
マニュアルへの自分なりの解釈が生まれるので
「実は、〜した方が良かったりして、、」と
より良い形を模索するために、試行錯誤が始まったり、
あくまで、感覚の世界だった話が、理詰めされていくかもしれない。
ある程度のところまで、ノウハウに落とし込める時もあれば
感覚の世界で、なかなかマニュアル化しづらい作業もあると思う。
そんな感覚値で進めていた作業も
もしかしたら、他の人と共有できるような形にできて、
タイミングによってむらがあった生産性が安定するかもしれない。
マニュアルは、作ること、守ることが、ゴールではない。
マニュアルは作って終わるものでも、守るものでもない。
“もっと良い方法はないのか。”
向上心を生み出すための、源泉がマニュアルだと思う。
全員がちゃんと同じ事が出来るようになるからこそ
会話など、コミュニケーションの質も上がってくる。
そして、その度に出来上がるマニュアルは
自分たちのそれぞれの現場に対する思考が反映され、
マニュアルがまた、その思考と熱量の質を上げてくれる。
だからこそ、
ただその通り真似をして終わるより
守破離に根ざしたマニュアルが大事なんだと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
