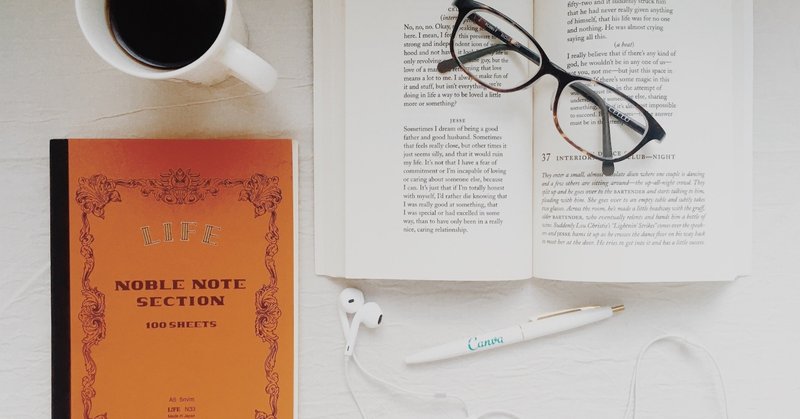
(056) 成瀬尚志編『学生を思考にいざなうレポート課題』(ひつじ書房, 2016):剽窃のできないレポート課題を出す方法
春学期のオンライン授業もそろそろ終わりが近づいてきました。期末試験が行われたりレポートが出される時期です。しかし、オンライン授業で公平な試験を行うのはなかなか難しいです。他の人の手助けをその場で受けたり、LINE経由で受けたりすることが可能だからです。また、学生1人であっても、本やインターネットで調べることができますので、暗記型のテストは使えません。
そんなわけで、今期は試験ではなくて、レポート課題が多くなるのではないかと予想しています。そうすると教員を悩ませるのは、レポートにおける「剽窃」、つまりコピペ問題です。たいていの教員は、学生のレポートを読めば、どこからかコピーしてきたものかどうかわかります。しかし、コピペを見つけるのに労力を使うくらいなら、最初からコピペのできないレポート課題を出せばよいのです。
この本は、コピペできないレポート課題の出し方について具体的に書いています。
論題のレベルによるコピペできない課題の例
レポート課題の出し方、つまり論題をどのように指示すればコピペのできない課題になるでしょうか。それを論題のレベルとタイプから説明しています。
まず、内容の分析レベルです。「◯◯とは何か」や「◯◯について論じなさい」という論題はよくあります。しかし、このパターンの課題は剽窃を招きます。「◯◯とは」という検索ワードで山ほど出てくるからです。調べること自体は悪くありません。それをそのままコピーすることが問題なのです。
したがって、このような論題では、文体の指定をするといいということを、この本は教えてくれます。具体的には「◯◯とは何か。AさんとBさんの対話によって書きなさい」というような課題です。このようにすれば、学生は検索して調べたあとに、自分なりに対話を創作しなければなりません。その過程で、自分が調べた内容を分析し、理解していきます。
同じ分析レベルでは「◯◯とは何か。重要点を3つあげ、その理由を書きなさい」という論題もコピペを防ぎます。これもただ調べただけでは書けません。内容を理解して、自分なりに重要度の順位をつけて、理由づけすることが必要だからです。
2番目に、内容の活用レベルです。たとえば「◯◯が活用されている事例を挙げなさい」というような論題は、内容を理解した上で、具体的な事例を探さなくてはなりません。その過程で理解が深まります。
同じ活用レベルでは、「◯◯ということを学んで、あなたの考え方は以前とどのように変わったか」という論題もいいでしょう。自分自身のことを書かなければならないので、コピーはしづらいはずです。また「◯◯について書いたものを、誰かに読んでもらい、質問をもらった上でその返答を書きなさい」というのも、同様にコピーしづらいレポート論題です。
3番目に、総合レベルの課題です。たとえば「◯◯をあなたはどう評価しますか」というような解釈や評価を問う課題です。この課題でレポートを書くためには、内容を理解し、分析し、何らかの評価軸や自分の価値観を明らかにして考察していくことが必要です。そのためコピペでは間に合いません。
最後の4番目は、探究レベルの問いです。これは自ら問いを立てて、それに対して答えていくという形です。ここまでの3つのレベルのレポートは論述レベルということができます。それに対して、この探求レベルでは論証が必要になります。ですので、最も難しいレベルになります。なぜなら、内容を理解した上で自ら価値の高い問いを立てることが必要だからです。
たとえば「授業の内容について、自分で問いを立ててそれに回答しなさい」というレポート課題になります。このような課題を教員はよく出します。しかし、それはかなり困難な課題であるということを自覚しておく必要があります。
フィードバックとしての添削は必ずしも有効ではない
学生に書いてもらったレポートについて何らかのフィードバックを返すことは重要です。しかし、多くの教員が気づいているように、添削指導は必ずしも有効ではありません。その理由の1つ目は、赤を入れられた学生はおそらく気分が良くないということです。2つ目は、自分が文章を適当に書いたとしてもどうせ誰かが直してくれるだろうという考え方に陥ることです。つまり、添削指導はその苦労の割に効果的ではありません。
添削指導をする代わりに、レビューをするといいでしょう。つまりその文章についてのコメントを書くということです。レビューには、学生同士でレポートを読み合う「ピア・レビュー」と、教員がコメントを書く「教員レビュー」があります。いずれにしても、レビューをしてもらったあとに、自分の文章を改善するというプロセスがなければあまり意味はありません。
レポートを評価するルーブリックに2つ
レポートを評価するときはルーブリックを使います。ルーブリックには2つの種類があります。全体的ルーブリックは成績をつけるときに使います。それに対して観点別ルーブリックは指導をするときに使います。観点には形式的なものと内容的なものがあります。形式的な観点(たとえば、段落の先頭は一字下げるなど)は、チェックリストの形式で書くこともできます。一方、内容的な観点は、表現、一貫性、ロジック、独創性などが3〜5段階で評定されたものです。
査読プロセスを体験してもらうのもアイデア
この本には書いてありませんけれども、ピアレビューによって査読プロセスを体験してもらうというのも試みる価値のあるアイデアです。匿名化された他の人のレポートを読み、A, B, C, Dで評価し、どこを改善するべきかをコメントとして書いてもらうのです。コメントはレポートの作者に送られ、作者はコメントへの回答書と修正対照表を作って、元のレポートを改訂します。
教員は回答書と改訂されたレポートを総合的に評価します。また、良い査読コメントを書いた人にはボーナスポイントを与えることもできるでしょう。
ここから先は
ご愛読ありがとうございます。もしお気に召しましたらマガジン「ちはるのファーストコンタクト」をご購読ください(月500円)。また、メンバーシップではマガジン購読に加え、掲示板に短い記事を投稿していますのでお得です(月300円)。記事は一週間は全文無料公開しています。

