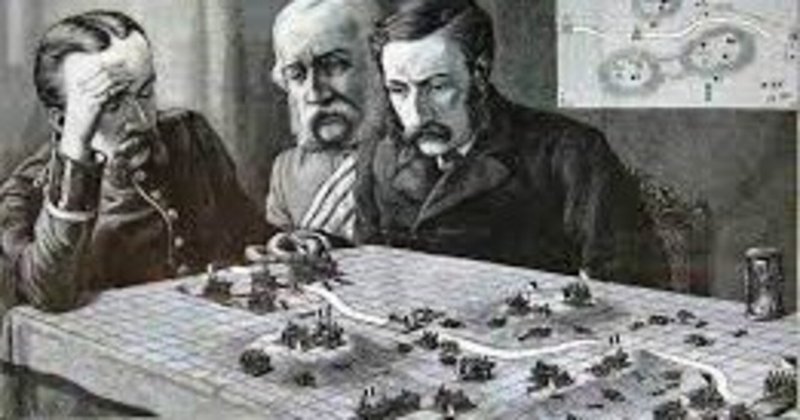
認知負荷を減らすプロジェクト会議の進め方
限られた会議の時間を有効に使いたい
プロジェクトの進捗確認会議で、自分が提議したいことがあったとします。そのための調査をし、資料もつくりました。ところが自分の番になる前の別の議題で、誰かのふとした発言がきっかけで誰かの話が誘発され、そのまた誰かの話が長くなり、その議題に会議の所要時間のほとんどを使ってしまい、自分に残された時間がなくなってしまった――。会議の場でそんな経験をされた方はいらっしゃらないでしょうか?
異なる仕事内容、状況、リズム、一日・一週間の予定のある人々を、同じ時間に集めて拘束する会議の開催回数と時間は限られています。限られた時間を有効活用したいのに、それを妨げる大きな原因が二つあります。人間の「思考」のクセと「話し言葉」です。
常に動きたがる思考
会議で寝たり内職していたりしない限り、話を聞いていれば、なにがしか頭は動きます。そこで頭に思い浮かんだことを、人は簡単に口にできます。議題について、かねてから考えていたことを開陳する機会だと思って話したり、ネットや新聞で見た関連情報を提供したりします。
タイムラインを占有する話し言葉
こうした発言は、口から出て、耳に入る。口から出ている間、その人の発言は、会議で交わされる議論のタイムラインを占有する。言葉は線形で一つずつ出てくる。誰かの発言をキッカケに別の誰かが発言すれば、占有しているタイムラインが接ぎ木のように伸びる。その議題について深い議論になることもあれば、些末な議論(おしゃべり、知った情報の提供)になることも、本流から外れて枝葉に伸びてしまうこともある。これらの発言は濁流のように押し寄せて、しばしば司会者も場をコントロールできなくなる。
問題に対処するルール
この二つの原因によって、もともとの会議の時間はある一つの議題に使われてしまい、他の議題の時間を圧迫します。話されるべきだった議題は次回会議に持ち越されたり、特定の関与者の間で個別に議論されますが、決定には関与者全員が集まる会議である必要があり、その議題の決定や実行の時間を遅らせます。これらの問題の対処方法として、「発言のルール」づくり、「制限時間を設ける」といったものがあります。
発言を勝手にしない(司会者に許可されてから発言する)、議題は事前に共有して質問したいことも事前に司会者に送っておくといった「ルール」を設けることは有効に思えます。また、会議のアジェンダなどで記載されている議題に予め時間を割り振っておき、その制限時間が来たら強制的に議論を打ち切るという「制限時間」(及びルール)を設定することも有効そうです。(将棋の持ち時間のように、発言者一人一人に持ち時間を与えるという有効なようなジョークのようなルールも見たことがあります)
ルールを機能させるためのトリアージ
しかし、これらのルールや制限時間だけでは機能しません。与えられている(残されている)時間を鑑み、発言の許可にも時間配分の調整にも、その発言及び議論がプロジェクト全体のどこに位置付けられていて、それはプロジェクトにとって、今時点あるいはこの先どのくらい重要か?という軽重の判断が必要です。いってみれば、司会者は議論・発言のトリアージをしなければなりません。
外在化表現によって認知負荷が高くも低くもなる
この位置づけと軽重の判断を、司会者が頭の中で行うのは非常に「認知的負荷」が高い行為です。会議のアジェンダには議論すること・決めたいこと・論点・所要時間を書き込んでいるかもしれませんが、発言の重要性を判断することを助けてはくれません。議事録をリアルタイムでモニターに映し出していたとしても同様です。
アジェンダや議事録といった情報を頭の外に出して表現したものを「外在化」と言います。人間が情報を表現し、説明・理解したり判断したりするには認知的負荷がかかりますが、外在化の表現がどのような形態かによって認知負荷が増減します。認知負荷が高いと、情報の表現・説明・理解に時間がかかるだけでなく、誤った判断につながるリスクもあります。
解決方法としての「プ譜」
常に動きたがる思考。タイムラインを占有する話し言葉。認知負荷を高め、判断を難しくする外在化表現。これらの問題を解決するフレームワーク、つまり外在化表現が「プ譜」です。
プ譜はプロジェクトの目標と成功の定義、資源や環境などの条件、プロジェクトに関わる諸要素と施策の関係性や構造を一枚で表現します。一般的にはプロジェクトの進め方・計画を表現するものとして使われていますが、会議のアジェンダにも、議事録にも使うことができます。
プ譜についての詳しい説明は、お手数ですがリンク先の記事を読んでいただくとして、このままプ譜を会議の進行・判断を助ける外在化表現として使用する方法について説明を続けます。
プ譜を使用した会議の進め方~事前準備
説明のための題材として、架空の「プロジェクト管理ツール」のプ譜を挙げます。このプ譜はプロダクト開発計画を表現したものになりますが、これをそのまま会議のアジェンダとしても議事録としても使おうというのがこの記事の趣旨です。

会議の事前準備の手順は下記のとおりです。(前提として、プ譜はPPTやGoogle Slide、Miroなどで作成します)
最新のプ譜をコピペして、編集可能な状態(書き込み用プ譜)にし、一方のプ譜は残しておく(アーカイブ用)
書き込み用のプ譜のURL・紙をプロジェクトメンバーに送る
会議で特に相談したいことがある各中間目的・施策の担当者は、予め最新のプ譜の該当箇所に色をつけるか、吹き出し・コメントで入力しておく(※会議前日の正午までなど期限を設ける)。→これがアジェンダになる
司会者とプ譜を記述し更新する役割の人(Project Editor。以下、PE)が相談して、各項目に割りふる想定所要時間と開始~終了時間(順番)を記載しておく。ふりかえりの所要時間は異なるが、バッファの時間を10~20min残しておく。

プ譜を使用した会議の進め方
書き込み用プ譜を全員が見られる状態にする(画面共有、プロジェクター投影)
書き込み用プ譜に記載した順番で、実行した施策の結果、起きたことやわかったことを、該当する施策や中間目的担当者が発表する。
PEが吹き出し・コメントで書き入れる(事前に書き込まれていれば、追加・修正事項をPEが記録する)。仮説通り進んでいるものはそのままでOK。終わっていたらグレーにしたり取り消し線をつけたり、削除したりする。中間目的の実現状態は%で表示する。
書き込まれたものに対し、観察・評価、対応を検討して、決定する。このときの議論・発言は、PEが該当する吹き出し・コメントにつなげて書いておく。
→これが議事録代わりになる。
→「どう考えてどう決定したか?」という「決定過程」も必ず記入する(これによって、その決定がどのような理由で行われたのかが残る。なので上書きを絶対にしない)決定したことをコピペ・プリントし、一方のプ譜を残しておく
もう一方のプ譜から評価・検討のコメントを除き、変更・修正のあった項目をプ譜に反映する→これが仮説を更新したプ譜になり、次のふりかえりの際のアジェンダになる。

肝心なのは常に画面やモニターにプ譜を出し、全員で見ながら、相談・評価・決定し、その場で更新することです。プ譜は一局面一シートにして記録・更新することで、将棋の棋譜のように意思決定のプロセスを残すことができます。


全体像を可視化することのメリット
このようにプ譜を用いて進める会議は、常に目標と成功の定義が目に入っており、その全体像・構造が可視化されているため、まず会議での発言がプロジェクトのどこに位置づけられているかがすぐにわかります。
発言内容が「ある機能のアイデア」のようなものである場合、その機能を実装すると、プロジェクトのどの要素に影響があるのか?ということがわかりやすくなります。
また、プ譜では要素間の関係性や取り組むべき順序も表現しており、発言が「今、重要なのか、まだ先のことなのか?」の判断もつきやすくなります。ポッと出の適当な思いつきという名のアイデアも、それがどこにも紐づかなければ採用されないといった、抑止効果もあります。
常にプ譜を目に入れることで、発言の位置づけ・構造の把握といった認知負荷のかかる行為のコストを下げ、判断のスピードと質を向上させるといったことが期待できます。また、アジェンダも議事録も兼ねるため、こうしたドキュメント作成にかける時間も減らすことができます。
こうしたプ譜を用いた会議は、Saasのプロダクトマネジメントやカスタマーサクセス、海外子会社の経営改善、新製品のPoC、採用広報、書籍出版、制度策定など多岐に渡ります。自分のプロジェクトでも使ってみたいと思われた方は、ぜひ下記の動画をご覧頂いて、まずはプ譜の作成から取り組んでみて下さい。
未知なる目標に向かっていくプロジェクトを、興して、進めて、振り返っていく力を、子どもと大人に養うべく活動しています。プ譜を使ったワークショップ情報やプロジェクトについてのよもやま話を書いていきます。よろしくお願いします。
