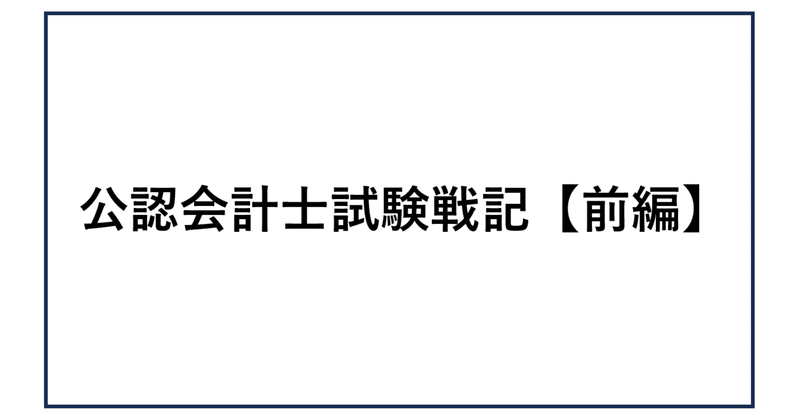
公認会計士試験戦記【前編】
はじめに
今回のnoteでは、私の公認会計士受験生時代を振り返りながら、合格するまでの道のりをお話ししてみたいと思います。
当時を振り返りながら書くということで、過去が美化されている部分も少なからずあるかもしれません。そのため、少し割り引いて読んでいただければと思います。
公認会計士を目指す前、私がどのようなことをしていて、なぜ公認会計士を目指そうと思ったのか、そして合格までにどれぐらいの挫折があったのかについて赤裸々に書いてみたいと思います。
元々スポーツ一筋で勉強はしてこなかったので、私の背景を含めてお伝えすることで、「こういう人でも合格するんだったら自分もできる」と思っていただけると嬉しいです。
ちなみに大変長文となっております。あらかじめご了承ください。
それでは早速いきましょう。
チャンスの女神様は前髪しかない。
公認会計士を目指す前
大学入学当初は野球部
公認会計士を目指そうと思う少し前の話。
大学入学当初は野球部に所属していました。
レベル感は、全国制覇を目指せるような大学ではなかったのですが、全国大会出場は目指せるといった感じです。
当時は、監督が元プロ野球選手で、しかもプロでも監督をされた方が退任後に大学野球部の監督になったというような形で、学校自体が野球に力を入れているような大学。そんな大学だったので、私の大学当初の目標は、プロ野球選手にはなれないかもしれないけど、社会人野球に進んでセミプロぐらいになれたらいいなというような感じでした。
ちなみに、高校時代はそこそこ強いとされる高校で野球をやっていたため、大学でも野球をやることを前提に推薦で大学へ進みます。ただ、推薦の枠としては指定校推薦で進学したため後々野球部を辞めたときも学校には残れる形となり結果的にこれが良い選択になったのでした。
もっと補足をお伝えすると、中学から高校に進学する際も、野球部に入るということであればほぼ誰でも受かるような形だったので、これまで真剣に受験勉強をしたことはないという人生を送っていました。
そんな野球一筋の中、大学一年生のときに手首と腰の怪我と、イップスというボールが投げられなくなるメンタル的な症状になってしまい、野球を辞めるという選択をしました。
辞めたのは大学一年生の5月。大学の野球部には高校3年の1月から参加していたので、5ヶ月ほどで辞めるという比較的早めの退部になってしまいました。
これまでずっと打ち込んできた野球を辞めるということで不安もありましたが、辞めたときの感覚は「やっと解放された」というような感じでした。
イップスになってから、ボールを投げられるイメージがわかずに苦しかったのですが、もうこのようなことで悩まずに済むということで、とても大きなストレスから解放された瞬間だったのです。
簿記との出会い
このような形で小学校三年から大学一年まで続けてきた野球を辞めることになったのですが、辞めてからは何をやっていいのか分からない生活が続き本当に退屈でした。
野球部に所属している現役時には、早く引退したいと思っていて、引退ライフというものを夢見ていましたが、いざ野球部を辞め無限の自由時間が生まれると、今度は逆に何か夢や目標に向かっているときが一番楽しいのではないかということに気づかされました。
そのため、何か夢中になれるようなものはないかと、色々と探してみたりしましたが、結局見つからず、大学一年の前期はごく普通の学生生活を過ごします。
今当時を振り返ると、野球を辞めたことについて失敗だったと思うことや後悔することはありません。
ただ、公認会計士試験に合格するまでは「野球を辞めたことが正解だったのかな?」と自問することが何度もありました。
そんな地味な大学一年生の前期を送っていたのですが、そんな中にも一つだけ気になるようなものがあり、それが大学で受講した簿記というものです。
簿記に夢中になりたいと意識することはなかったのですが、授業中に問題を解き、最後に合計残高試算表の貸借が一致した瞬間だけは達成感があり、その感覚は楽しいと感じました。
目指せ簿記検定
そんな簿記との出会いだったのですが、気づけば定期試験前に簿記について自宅で勉強をしている自分に気づきました。
みなさんは試験前に勉強することが当たり前だと思います。一方、私は野球漬けの日々を送っていて、脳まで筋肉みたいな人間だったので、定期試験前に勉強するということはこれまでほとんどありませんでした。
もっというと、高校時代は宿題もなかったので、自宅で鉛筆を握るということもほとんどありませんでした。
そんな私が、簿記の定期試験前にテスト勉強をしているということで、自分の中でも簿記は好きかもしれないなと思い始めました。
そんな中、簿記の最後の授業で、夏休みから11月の日商簿記検定に向けて、簿記検定講座が始まる旨の話しを聞き、せっかくだから受けてみようという軽い気持ちで簿記検定講座の申し込みを行ったのでした。
無事申込みを終え、夏休みは少し簿記に打ち込んでみようかなと考えている中、ちょうど二つ下の弟が甲子園出場を決めるという嬉しいニュースが飛び込んできます。野球を嫌な思い出で辞めて、もう野球をすることはないと思っていた私にとってもこの出来事は嬉しく、結局簿記検定はそっちのけで甲子園まで応援に行くことになりました。
甲子園の応援では、弟が試合に出たときはまるで自分が試合に出ているかのような緊張感に包まれました。活躍して欲しいというよりも、弟は学年が2年で先輩たちと一緒に甲子園出場みたいな形だったので、ミスなく無事終わって欲しいというような気持ちだったのだと思います。
ただ、応援するのは楽しかったですし、家族親戚みんなで大盛り上がりでした。
このように甲子園の応援に行ったこともあり、結局夏休みに簿記に打ち込むという目標は達成できず。講義に参加できなかった分はweb講義を視聴するというような形で、与えられた分の課題をこなしていると、夏休みが終わってしまったのでした。
ただ、弟が甲子園に行って活躍する姿を観たことで、嬉しさと同時に、あの場所に自分が立てなかった悔しさも残り、大学時代は野球以外で何か大きなことを成し遂げようと思うようになりました。
日商簿記3級
このように大学時代に野球以外で何かを成し遂げたいと思うようになり、俄然簿記の勉強にやる気が芽生えます。そして、まずは日商簿記3級に合格しようと決意。夏休みは思ったより簿記の勉強が捗らなかったということもあり、11月の3級までにギアチェンジしようと思いながら、毎日簿記のテキストや問題集を解くようになりました。
そして日商簿記3級の試験当日。
人生で初めて真面目に受験をする私にとっては全てが新鮮でした。試験前に必死にテキストを読み込む人達をみて緊張感が高まります。それと同時に、やっぱり何かに打ち込むっていいなと思いながら、私も負けないように必死にテキストの内容を読み込むのでした。
当日の問題はなかなか難しかったです。試験が終わってすぐは、手応えはあったけど自信を持って受かったとは言い切れないというような感じで、もっと勉強するべきだったという後悔が残りつつも、初めての受験ということで、達成感もありました。
そして迎えた合格発表当日。ネットで自分の受験番号を見つけて無事合格。合格証書が郵送で届き、3級にもかかわらず嬉しさから額縁に入れてテレビの横に飾りました。
そんな感じのデビュー戦でした。
日商簿記2級と1級,からの一時撤退
3級合格後は、みるみる簿記にのめり込むようになり、次は2級を目指すようになります。
3級のときは、大学主催の簿記3級講座を受講して勉強したのですが、何の自信か2級は独学で受かるのではと思いはじめ、市販のテキストと問題集を買って勉強を開始。
しかし、現実は甘くなく結果は惨敗。11月の3級を受けてから、3ヶ月後の2月に2級を受けたのですが、箸にも棒にもかからず受験直後に100%落ちたなというような感覚でした。
このような感じで2級は落ちたのですが、引き続き謎の自信だけは残っていて、「もう2級は一通り勉強したし、1級を受けよう」と考えます。
そのため、大学2年に上がるタイミングで、TACの日商簿記検定1級講座を申し込みました。
休むことなくすぐに1級講座の勉強を始めると、2級や3級とレベルが違い「これほんとに受かるのか?」というような感覚に陥りました。商業簿記テキスト3冊、工業簿記テキスト3冊と、一通り勉強して一周するだけでも大変というくらいの範囲だったのです。
1級を勉強してからすぐの頃は、毎朝5時に起きて朝二時間半勉強、学校から帰ってきてまたニ時間ほど勉強という感じでいいペースで進めていました。
しかし、なかなか問題をスラスラ解けるようにならず、少ししてから一回目の壁にぶつかります。
問題を思うように解けないので徐々に簿記が面白くなくなり、ストレスもたまっていきました。1級の勉強を始めて3ヶ月ほど経った頃だと思います。
そして、毎日の勉強の努力に成果を感じられず、勉強そっちのけで友達と遊ぶようになり一時撤退という形になりました。
今振り返ると、このときは焦りすぎていたと思います。レベルが高くなってくるとテキストを一周しただけでは問題を解けるようにならないことは当たり前です。それにもかかわらず、過去の勉強経験が少ない私にとっては当時そんなことを考える余裕はありませんでした。「やっぱり俺に勉強は向いてないのかな」と思うことが増えていきネガティブになってしまったのです。
これから受験をされる方には是非「一回で全て覚える」という気持ちを捨てて、忘れてもいいからテキストを早く一周しようというような軽い気持ちで挑んでいただければと思います。
そうすると二周目に忘れていても、「まぁそんなもんだよね」とストレスなく勉強できると思います。
復帰
7月の頭に簿記1級を一時撤退してから、10月の中頃まで一切勉強をせずに遊び続けていました。
振り返ると、これまでの人生ずっと野球に打ち込んでいたことから遊ぶという経験をしたことがなかったのですが、大学2年の7月上旬から10月中旬までは文字通りひたすら遊んでいました。
ただ、最初の方は楽しい遊びも、ずっと続けていると面白いもので、このままでいいのかなと真剣に考えるようになり、途中で投げ出した簿記検定のことが時より頭をよぎるといったことが度々ありました。
このような気持ち悪さから、何か現状を変えないとと思い始め、フィットネスジムでアルバイトをはじめます。
この時は、簿記の勉強に戻るということも考え、少しずつ勉強を開始しましたが、もしかすると俺のやりたいことはやっぱりスポーツに携わることなんじゃないかという考えもあり、逃げなのか挑戦なのかわからずとりあえずフィットネスジムで経験積んで将来はプロスポーツ選手のサポートができればいいなと考えたりもしてました。
フィットネスジムでアルバイトをしてみると、野球部時代に自分がやっていたトレーニングなどを人に教えたりするだけでお金がもらえることに不思議な感覚を覚えます。
これまで、野球部時代にチームメイトとトレーニングについて教えあったりすることはあってもお金が発生するということはなかったのですが、ここではジムの会員にトレーニングを教えると感謝されるだけでなくお金までもらえるということでこの職も悪くないなと思うようになりました。
ただ、このようにトレーナーという職業に興味を持ちつつも、簿記のことは常に頭の片隅に残っていました。
そんな中、フィットネスジムの社員さんと仕事について話す機会が多々あり、しかも幸運なことにプロ野球選手の指導をしている方もいて、プロスポーツ選手のトレーナーとしてのお話も聞くことができました。トレーナーの仕事についての魅力や、逆に良くない部分も全て教えていただきました。その結果、トレーナーは自分の目指すところではないという思いに至ります。
私自身は誰かをサポートするよりも自分で挑戦してみたいという気持ちの方が強かったので、そこまで向かないだろうということでこのような結論に至ったのでした。
そうすると反対に、やっぱり「俺には簿記しかない」と考えるようになり、徐々に勉強を再開してエンジンが掛かるようになりました。
簿記検定後の方向性
このような流れで、また簿記の勉強を本格的に再開することになったのですが、3ヶ月以上も1級の講座から離れると、もちろん予備校の組んでくれたスケジュールでの合格は困難になります。しかし、幸いにDVDコースを申し込んでいたので、視聴期限というものがなく、最後まで講義を終えることができました。
ただ、2016年11月の1級合格を目指しているコースだったのですが、私が講義を見終わったのは、2017年の2月ごろでした。
ちなみに、2017年2月に1級の講義を終えましたが、それと同時に日商簿記検定2級も一応合格しました。すでに1級まで勉強していたので、2級の勉強は、試験一週間前から市販の答練を買ってきてそれを2回転ほどさせるだけでした。
このような勉強だったのですが、1級に比べると2級の難易度は圧倒的に低く、試験を終えた後は、100%受かったと思いました。そして結果も余裕を持って合格という感じでした。
そんなこんなで2級合格と1級の講義完了ということになったのですが、簿記の勉強を本格的に再開したことで、もう一度やりたいことを考える機会が生まれ、1級の後の方向性を真剣に考えるようになります。
そして、色々と考えた結果、簿記検定の後は税理士か公認会計士を目指すかで悩み始めました。
このとき考えた将来の夢は、会計事務所を経営しながら他者に縛られず自由に働いて、趣味にもたくさんの時間を使えるような人生を送れたらいいなと漠然と考えました。
色々と悩んでいる中で、①日商簿記1級には合格したいと考えていたため税理士を目指すと日商簿記1級が遠回りとなること、②税理士試験は長期戦になりがちなのに対して公認会計士試験は短期戦だったこと、③どうせ目指すなら会計系の試験の中で一番最難関と言われる試験に合格したいという3つ思いから公認会計士を選びました。
公認会計士を目指すと決めてからは、どの予備校にするかを色々検討し、TAC、大原の個別面談などを受けたりもしました。
私の場合は、公認会計士の予備校代は自分で出すと決めていたので、個別面談を受ける中で担当の先生が自校の長所などを説明していても、ほとんど費用面しか気になりませんでした。
そこで思ったのが、予備校代が高すぎるということです。当時、バイトで貯めていた貯金が400,000円ほどあったのですが、この2つの予備校に入るなら倍の貯金をする必要があり、結構しんどいなと思っていました。
そんな中、ある一冊の本と出会い予備校を決めることになるのですが、それは中編でお話しできればと思います。
私は費用の面などもあり、公認会計士を目指すと決めてから実際に予備校に入るまでにタイムラグがありましたが、これから受験される方でまだ予備校を決めていない方は1日でも早く予備校に入り勉強を開始することをおすすめします。
予備校選びは重要ですが、今思うのは結局受かる人は大手であればどの予備校でも受かるだろうと感じているからです。
そのため、予備校選びに時間を使うよりも、早く予備校に入り、その迷う時間を勉強に使った方が合格には近づくと思います。
中編へ続く
以上が、公認会計士を目指す前のお話でした。
本来は、1つのnoteにすべてをまとめようと考えていたのですが、書き始めると止まらなくなってしまい、結局、前編・中編・後編を分けることにしました。
中編では、公認会計士を目指してから、二度目の短答式試験までのお話しをできればと考えています。
是非中編、後編も読んでいただけると幸いです。
前編を最後までお読みいただきありがとうございました。
【中編はこちら】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
