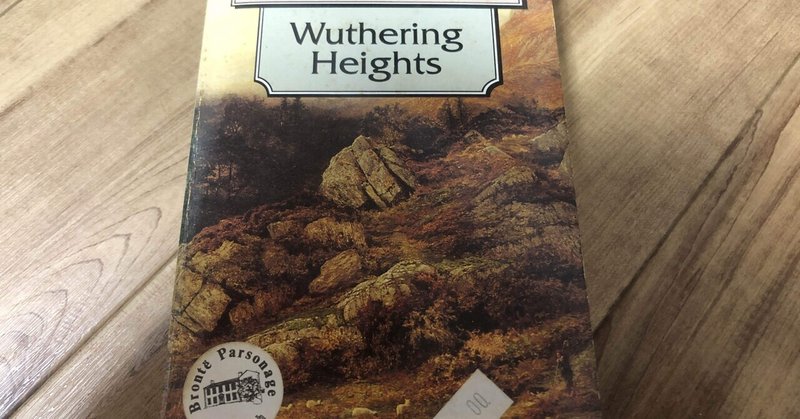
【小説】オールトの海でまた 🌕2
⭐️
ようやくここまで辿り着いた。太陽はとっくに沈んでいて、空には星々が瞬いている。ほんとうなら、陽が昇っていないうちに、この場所へ到着するつもりはなかったのだけれど。
だが、目的地に向けて一歩ずつ進む以外の、なにがぼくにできたというのか?
とにもかくにも背負っていたリュックを投げ捨て、腰を下ろした。お尻の下で、土がひやりと冷たい。疲れた。立っている気力も残ってない。足の裏ではマメが潰れて、どくどくと脈打つたびに疼く。じきにこの痛みも薄まっていく。ここ何日も繰りかえしてきたから知っている。
でもいいんだ。もうなににわずらわされることもない。靴と靴下を脱いで裸足になり、丸めた寝袋を枕にして、その場に寝転んだ。雲ひとつない空が視界を覆う。ひとの気配はずいぶんと後方に置いてきた。目を瞑ってしまおう。運がよければ、朝まで眠れるかもしれない。
手がくさい。どこかで猫の死骸にでも触れてしまったのだろうか・・・。
・・・・・ひとつ、思い出したことがある。暖房であたためられた病室で、ぼくらはいつものように向かいあっていた。前後の話の流れは思い出せないけれど、たしか小夜はぼくにこう言った。
「人間に踏み荒らされていない土地が、この国にもまだあるの。北に行けば未開拓の草原がいくつも広がっていて、そこには本物の静寂が横たわっているのよ」
そうだ。いままでどうして忘れていたのだろう。ぼくがこの場所を選んだ理由は、彼女がこの場所を選んだからだ。ぼくは彼女の望みを知り、それを叶えるために奔走したけれど、彼女もまた、ぼくの望みを叶えようとあがいていたのかもしれない。どうしてその可能性に至れなかったのだろう。
だめだ。思考がうまくまとまらない。
少し落ち着こう。
いまさらながら、半袖のシャツしか持ってこなかったことを後悔している。北は予想していたよりも肌寒かった。ここには風を遮る山や木々もない。さやぐ青々とした草原が、地平線の彼方までつづく。寝袋に包まればいい話なのだけど、いまはまだ、首筋をくすぐるこの感触や、そよ風が運んでくる夜のにおいを味わっていたい。
鈴虫の鳴き声が、宵闇に凛と響いている。一匹が鳴き終わっても、また次の一匹が鳴きはじめる。夏の間、延々とつづくこの連鎖を、わずらわしいと思ったこともあったものだ。草葉の陰では名前のない獣が、息を潜めてこちらをうかがっている。それが仮にたち性質の悪い羆でもあったならば、すべてが単純明快になる。時折、夜の鳥が翼を空気に打ちつけ、切り裂いてゆく音が聞こえる。背中の下を這う、みみずや土竜たちのうごめ蠢き。汗の乾いたシャツに浸みこむ、土の温度。星明かりごときでは、これらを明るみにすることはできない。ぼくはただ、耳を澄まし、感じとるだけだ。
やっぱり手がくさいな。
そういえば小夜は、こうも言っていたっけ。
「あなたがいてくれるから、わたしは絶叫しながらガレージの窓ガラスを素手で叩き割る、なんてことをせずに済んでいるの。ほんと、やすりかおろし金みたいなひとよね」
二人の距離はもう永遠に引き裂かれてしまったけれど、たまに小夜が見せるあの表情を思い出すと、たとえ一本の絹糸のように細くかすかではあっても、彼女との繋がりはまだ保たれていると錯覚してしまう。けれども彼女の発した言葉を、ぼくの記憶にある表情を、いまこうしてパースペクティブの海に放りこんでみると、事はまったく違った様相を呈してくるようにも思える。隣を歩き、同じ方角を向いていると盲目的に信じていたのは、ぼくだけだったのではないだろうか。彼女はぼくの見えているものが見え、ぼくの見えていないものまで見通していたのではないだろうか。
小夜の言ったことは間違いなどではない。ぼくは常に削る側の人間であって、削られる側の人間ではなかった。きっと試みようとしてくれたひとは何人かいたのだろうけど、ぼく自身が無意識のうちにそれを拒んでいた。幼少のときから後生大事に抱えつづけてきたものがある。それを炎にくべ、灰へと変えつづけなければ、ぼくみたいな人間は生きてはいけないというのに。ほら、結局そのツケは巡り巡って、いまこの瞬間に返ってきている。背負いきれなくなった大荷物は、それ自身が手の隙間から零れ落ちてゆくのではなく、ぼく自身を——手を、足を、心臓の鼓動を、思い出を——無慈悲に、荒々しく削りとってゆく。ここ数年、ぼくが口から発していたのは、決して言葉などではなかった。言葉の皮を被った、ただの古ぼけて朽ちた振動でしかなかった。
もうたしかなものはどこにもない。肉体も精神も薄く引き伸ばされ、霞のようにあいまいになってゆく。ぼくの魂は時間の流れとともに四散し、ぼく自身にもなにがどこに在るのかわからなくなってしまった。けれどもそれだけじゃない。淡く溶け、広がってゆくのと同時に、すべてに内在する、すべての中心の一点に向けて、収斂、あるいはダイブし、沈んでいくのもまた、ぼくの魂だ。仮に宇宙やひとの生が崩壊へと歩みつづけているのだとしたら、人間は無意識のうちに抗っているのかもしれない。拡散してしまわないように。そうだとしたら、それはなんとちっぽけで、なんとなまくらな武器だろう。容赦なく踏み潰されるのを知っていてもなお、こんなものを振りかざしながら、前進と後退を同時に、無限に繰りかえし、たったひとりで泣き喚いていたのがぼくだ。この地平と自己以外に、ぼくの帰るべき場所など存在しなかったのだ。小夜にはそれが見抜けていたのだろうか。わからない。それをたしかめる術はもう、この世のどこにも存在していない。
そうだ。いずれにせよ、物事が最終局面に至ったいま、ぼくが望むのはたったひとつだけだ。ぼくはぼくのままでありたい。認識が最期を迎え、彼方へと沈んでいくとき、ぼくにはそれがわかるだろうか。もうどちらでもいいのかもしれない。認識も記憶も、所詮ぼくにとっては、彼女の名を叫ぶための手段でしかないのだから。潰えるのなら、異なる手段を見つけだすだけのこと。そしてすべてが潰えたその先には——。それこそが、ぼくの恋焦がれた地平線なのだ。ぼくがぼくのままでいられるのなら、そのほかのものなどすべて、宇宙の果てに溶け去ってしまえばいい。
眠りは当然のように訪れてはくれない。だがそれはもう諦めた。やらなければならないことができた。意識を研ぎ澄ませば、まぶた瞼のずっと奥のほうで、悲鳴に近い錆びついたような軋みが聞こえる。何年も前から付きあいのあるものだ。小夜に出会うよりも前から、骨の髄に居座っていたものだ。そいつがいまにも暴れだそうと、機をうかがっている。それを抑えこむ力は、もうぼくには残っていない。そしてこうすることが、ぼくへの憐れみに対する手向けとなるのだろう。
鈴虫が鳴いている。ぼくは思い出す。
でなければ、とても夜明けまで正気を保っていられそうにないから。
🌕1
「退屈だわ」
十一月の半ば、陽が短くなっていく季節だった。斜めに入りこんだ陽光が、病室を外から照らしていた。
聞き慣れた台詞を耳にして、読んでいた本から顔を上げると、ベッドの上で、なにかを期待しているような目でこちらを見る小夜の視線とぶつかった。ぼくはため息をついた。読んでいた箇所に人差し指を挟み、いったん本を畳んだ。
「きみはいま、ひどいことを言ったという自覚があるかい?」ぼくは言った。「友人がお見舞いにきているのに、そのひとを前にして退屈だ、なんて」
「だって、退屈で退屈で仕方ないんだもの」小夜は言った。「気づいてる? あなた、今日この部屋にきてから挨拶くらいしかしゃべってないのよ。相沢くんってあれよね。お寺にぶら下がってる鐘楼みたい。自分からは音を出さないのに、打てばうるさいくらいに鳴り響くの」
ぼくはふたたびため息をついた。小夜の目は爛々と煌めいている。いつもの暇つぶしとわかってはいても、これではあんまりだ。なにか言い返そうと思って、彼女にケチをつけれそうなものを目で探した。
小夜はぼくと同じように、読みかけの本を、指で閉じきらないようにして太腿の上に置いていた。その本の表紙は擦り切れていて、描かれた荒野の絵が手汗で茶色く変色していた。小口は陽に焼け、ページをめくるたびに、乾いた独特なにおいのする風を読者に振りまく。なぜそれを知っているかと言うと、小夜に頼まれ、古本屋でそれを購入したのがぼくだからだ。
「きみが退屈している原因をぼくに押しつけないでくれ」とぼくは言った。「そうやって何度も何度も同じ本ばっかり読んでたら、そりゃだれだって飽きるさ。いい加減ほかのも手にとってみたらどうなの?」
小夜はうーんと唸って返事を考える振りをした。だが実際に返ってくる言葉など、わかりきっている。
「わたしが最後まで読み終えることのできる物語が、ほかにもあるのなら考慮してもいいわね」そう言って彼女は持っていた本を目の前でひらひらと振ってみせた。「でも、そんなお話、少なくともいままではこれしかなかったもの」
「ただのひとつも?」
「全部クライマックスの直前で、もうその先を知りたくなくなっちゃうの」
ぼくは小夜が手に持った本をくねくねと振りまわしているのを目で追った。
「きみがそうしてほしいなら」ぼくは言った。「いくつか見繕ってこようか? ぼくの個人的な趣味も混じってしまうだろうけど、きみの好みにあわせるようにするよ」
小夜は首を振った。「必要ないわ。少しでも退屈する可能性のあるものには、手を触れる気にはなれないから」
「でもそれだと、自分の知らない新しいものに、いっさい触れられないじゃないか。つまらなければ、途中で投げ出してしまって、またつぎのおもしろいものを探せばいい。それすらもいやなのかい?」
「いや。勘弁して」
ぼくは机の上に置いてある花瓶を見つめた。それは小夜の両親が持ちこんだもので、翡翠のように|《れいろう》玲瓏な色あいの、底が六角形をした高価そうな陶器だった。その手前には、柑橘系の精油が浸みこんだ華奢なハンカチ。この部屋の主の、お気に入りのにおいだ。ちらっと小夜のいるほうへ目をやると、彼女の瞳からはまだ輝きが失われていなかった。ぼくは口を開いた。
「同じストーリーばかりを読みつづけるなんて、そっちのほうがつまらないと思うけどな。きみがどうしてそこまでその本に、飽きずにのめりこんでいるのかわからないよ」一瞬の間のあと、ぼくは付け加えた。「もちろん、非常に魅力的な物語ではあるけれど」
「飽きてないなんてことはないわよ」小夜は笑いもせず、顔をしかめもせずに言った。「何度も暇さえあれば手にとっているの。飽きてないなんてことはない。でも仕方ないじゃない。これ以外に、わたしの知っているお話なんてないんだもの」
彼女との会話は、毎回このような形で進行する。着地点も現在地も存在しない。
「こんなふうに死んでみたいなって思うのよ」と小夜は言って、本の表紙にもう片方の手を置いた。「このお話の登場人物みたいに」
「ふうん。キャシーみたいに? それともヒースクリフみたいに?」
「その二人も悪くはないわね。でもロックウッドも悪くはないわよ」
「ロックウッド?」ぼくは当惑して尋ねた。「彼はたしか、物語のなかでは死ななかったはずだけど」
「肉体的には死んでないけどね。でも胸の内で育てた恋心がこんな砕けかたをしたら、わたしには耐えられなさそう。彼も同じだったと思うの。キャシーへの叶うはずもない恋が実らなかったときに、彼の精神の一部は死んで、いつか肉体が滅ぶまで、それが息を吹きかえすことはなかったのよ、きっと」
ぼくは喚きながら髪を掻きむしりたくなるのを堪えた。「忘れちゃってるようだから教えてあげるけど、きみは一週間前にはこう言っていたよ。『東京タワーの頂上からフライングスーツで飛び降りて、最後には勢いよく踏み潰されたゴキブリみたいに、どこかへぶつかって微塵に飛び散って死んじゃいたい』って」
「死にかたをたったひとつしか選べないなんて、そんなのあまりにもひどすぎるわ」彼女は心底、憂えたような表情で言った。「いいじゃない。いまのわたしにはこれくらいしか望みがないんだもの。許されて然るべきよ。思い描く夢をたったひとつに絞れなんて、好きな食べ物をひとつ決めて、これから先の人生をそれしか食べずに生きろ、って言ってるのと同じよ。あなたはそれで平気? 今日から一生、梅干ししか食べてはいけませんって言われて、はいわかりましたって頷けるの?」
「いや。白米やラーメンも食べさせてほしいな」
「わかってもらえたようでなにより」小夜は腰まで覆っていた布団の位置を直した。ぼくらの間に埃が舞い、陽光のなかで幾何学模様を描いた。
「それでもひとは死にかたをひとつしか選べないよ」ぼくは言った。「きみに選ぶ権利があったとして、だけど」
「素敵だと思わない?」小夜はぼくを見て言った。「このお話の登場人物みたいに終わりを迎えるのって」
ぼくは天井を眺め、少し考えてから、悪くないかもしれない、というようなことをこたえた。小夜は満足そうに頷いて視線を落とし、本を開いて読書を再開した。瞳から輝きは失われ、彼女は彼女の世界に戻っていった。ぼくはしばらく、そのまま小夜のつむじを見つめた。やがて彼女にばれないように肩をすくめ、ぼくも自分の世界に沈んでいった。
次に顔を上げたときには、陽が暮れかけていた。この様子だと、寮へ着く頃にはきっと真っ暗になっている。海沿いの夜道はぞっとしないというのに、つい時間を忘れてしまっていた。
小夜は手元のタブレットで動画を見ていた。どうせジブリの映画か好きなアニメでも見ているのだろう。イヤホンを耳に引っかけ、眉間にはしわを寄せていた。弱まっていく陽光が、彼女を横から照らしていた。
ぼくは本や飲みかけのペットボトルを鞄にしまい、ヘルメットを脇に抱え、立ち上がった。小夜は顔を上げなかった。
「今日はもう帰ることにするよ」
小夜はうーんと唸った。ぼくは鞄を肩にかけ、出口へ向かった。途中で振りかえって声をかけた。「また土曜日にくるよ」
小夜はタブレットをにらんだままだった。ぼくが引き戸の取っ手に手をかけたとき、背後でつぶやく声が聞こえた。「運転、気をつけてね」ぼくは部屋をあとにした。
階段をおり、受付カウンターや待合室の前を通って建物を出た。中庭ではまだ人々が談笑していた。ぼくは夕光が照らすレンガ敷きの遊歩道を歩き、花のないそめいよしの染井吉野の細腕を見上げながら、敷地の西側へと向かった。波打つトタン屋根つきの駐輪場には、関係者の自転車が綺麗に列を成して停められていた。そのなかに混ざっているただひとつの異物——二五〇cc、ホンダのホーネットがぼくの脚だ。ぼくは屋根の下からバイクを引っぱり出し、キーホルダーのついた鍵を鍵穴に突っこんだ。チョークレバーを微妙に調節してスターターを押すと、一発でエンジンがかかり、車体が電気モーターを同時に十台くらい動かしているような唸り声をあげた。エンジンがあたたまるまで、ぼーっとその場に突っ立っていた。顔を上げて城のある公園の方角を見た。天守閣の頂の角部分だけが、木々の向こうにわずかにのぞいていた。城は灰色の薄いシートで上から下まで覆われていた。耐震補強の工事をするとかで、この年の秋から作業が進められていた。工事が完了するのは一年後の夏になる予定らしい。日曜日以外は無骨で疲れたように色褪せたトラックが、朝から列を成して公園に集う。日中は作業がつづくのだけど、その音はこの病院までは聞こえない。小夜はいつもそれを残念がっていたっけ。
エンジン音が、高く、凝縮したような音に変わっていた。ぼくはチョークレバーを元に戻し、足を振り上げてシートに跨った。フルフェイスのヘルメットを頭に被ると、まわりのすべての音がくぐもって聞こえ、自分の鼓動や呼吸音が頭蓋骨のなかで響いた。グレープフルーツのにおいが鼻をくすぐった。小夜の残り香だ。手袋をはめ、クラッチを握り、左足でスタンドを払った。車体の重みが右足にかかり、太腿が緊張した。背後を振りかえり、軌道上にだれもこないことを確認した。ギアを入れ、クラッチを徐々に繋ぎ、ゆっくり発進させて出口へ向かった。東海道は仕事帰りの人々が乗る車で混みあっていた。渋滞でいらつく彼らを尻目に、左折して一三五号線に乗り入れた。車の流れがぐっと減った。山並みの向こうに沈む夕日を横目に見ながら、海岸沿いを南へと走った。
🌕2
熱海の街の朝は決してはやくはない。観光客はそれほど急いで宿を引き払ったりはしないし、街は彼らにあわせて目覚める。犬の散歩や気まぐれな宿泊客、ホテルの朝食をつくるコックなど、少数の人間が昇りはじめた朝日を浴びる。
朝日は昇ったばかりで街は薄暗い。海岸線が南北につづき、海に出っぱったデッキは遊歩道として北のサンビーチまでつづいている。ここは海の街なのに、海岸から数十メートルも内陸へ行けば急勾配ののぼり坂がはじまり、そのまま緑成す山へと繋がっている。遊歩道に設えられた欄干の向こうの桟橋には、からっぽの遊覧船が何艘か繋がれていて、波が寄せるにつれ、船も上下した。デッキを北へ進みつづけると、サンビーチに辿り着く。人工のビーチは灰色で、まだ日中の時間帯ほど輝きを取り戻してはいない。朝日が昇ってまだまもない頃、子供のいる家族連れと出会うことがある。子供はぬいぐるみや車輪のついたおもちゃを腕に抱え、寝起きで元気がない。親が連れだしたのか、子供が無理についてきたのか。この街のような温泉街では珍しい光景でもなかった。
信号を渡ると街中へ道がつづく。坂をのぼり、旅館やホテルがくっつきあいそうなほど密集する地帯を抜ける。宿の前は無人で、まだ浴衣姿の宿泊客も、黒スーツのコンシェルジュも姿を現していない。側溝の隙間や流れる川のところどころで、白い蒸気が宙に向かって噴き出している。あちこちで温泉が湧いているため、地熱で街全体が茹でられているみたいにあたたかい。土産屋や、ストリップ劇場や、風俗店が押しこめられた、寂びれた商店街がある。キャバクラの前には何倍にも拡大された人気嬢の写真が貼られていて、太いマジックペンで塗られたようなつけまつげの下から、コケティッシュな目線を通行人に送っている。ぼくはこの前を通るたびに、なんだかひどく申し訳ないような気持ちになって顔を伏せ、足早に通り抜けてしまう。ひとたび観光客が足を踏み入れないような細い路地に入れば、表向きの顔は鳴りを潜める。建物は古く、無駄が多い。敷石の上には毎日、新鮮な犬の糞を見かける。このあたりに陽の光が訪れるのは最後の最後だ。
早朝のランニングは、もう何年も前からつづけている習慣だった。仕事のある日にはその三時間前には布団から這いあがり、部屋の外に備えつけられた共用の流し台で顔を洗い、トイレで用を足し、靴紐を結んで寝巻の恰好のまま寮を飛び出す。コースは気分次第でころころ変わる。ビーチまで走り、街中を抜けることもあれば、坂の上、山襞へと針路を向けることもある。帰りにはいつも海沿いの道に出て、潮風と昇ったばかりの朝日を体に受けながら、デッキの上を足音高く進む。
欄干に寄りかかり、呼吸を整える。漁へ向かう漁船がエンジン音を響かせ、防波堤の陰へと消えていく。彼方に水平線が見える。この街は東を向いていた。海面が波に揺れ、陽光をあらゆる方向に反射している。風が少し吹いていた。太陽が正面からぼくを射抜く。目を細め、手をかざして光を遮る。これは新たな一日を迎えるための儀式のようなもの。欠かせぬ習慣。ぼくはしばらく、そうして手の届かない遠い場所へ想いを馳せる。やがて太陽に背を向け、走って寮に戻る。
部屋に帰り、着替えを大きめの巾着袋に詰めて、寮から車道を挟んで向かいにある、ぼくが勤務するホテルの大浴場に向かう。古い寮にはお風呂が設けられていないため、汗を流したいときは一度、外に出なければならなかった。裏のシャッターをかがんでくぐり、従業員用の入口からなかに入る。エレベーターで最上階に向かう。脱衣所で汗に濡れた服を脱ぎ、軽く畳んで籠のなかに積みあげる。大理石でできた大浴場には、すでに宿泊客が何人かいて、首元まで温泉に浸かりながら、巨大な窓ガラスから外を眺めている。ぼくは中心に穴の開いた椅子に座ってシャワーを浴び、まだ乾いてもいない汗を流す。その後は決まって、重たいガラス扉の向こうの露天風呂へ足を向ける。外の浴槽には滅多にひとがいない。そこからは熱海の街を一望できた。海岸線が、まっすぐ北へ向かって伸びている。ぼくは全裸に潮風を受けながら手すりから身を乗り出し、山の斜面に広がる街を見下ろす。並び立つ建物が陽の光を明るく照りかえしている。朝の車の流れができている。ひとびとの営みが目覚めつつある。仕事にまにあうぎりぎりの時間まで、ぼくはそうやって暇を潰す。
昼休みになって地下にある従業員食堂を訪れると、すでにフロントやレストランの社員で席の大半が埋まっていた。漆喰の壁に掛けられたホワイトボードを見ると、この日の献立は野菜のかき揚げときつねそばだった。ここでは毎週水曜日の昼は麺類と決まっているのだ。ぼくは食堂のおばちゃんに挨拶をし、壁に貼られた名簿に鉛筆でチェックをつけ、プラスチックでできた黒塗りのお盆をひとつ手にとった。湯の張ったどでかい寸胴鍋が、業務用のガスコンロの上であたためられていた。鍋の内側の縁にはてぼが四つ引っかけられていて、ぼくはそのなかのひとつに冷凍のそばを一玉入れた。そばが茹であがる一分の間に、丼と皿を食器棚から引っぱり出し、丼には熱々の出汁をそそぎ、皿には野菜のかき揚げとおかわり自由のサラダを盛った。コンロの前に戻って自分が選んだてぼをつかみ、鍋の上で麺を軽く湯切りしてから静かに丼に入れた。最後に菜箸で大きな油揚げを一枚つまみ、麺の上にのせた。汁がこぼれないようにお盆を水平に持ち上げ、食事を終えて立ち上がった人々を避けながら隅っこのほうへ進んだ。奥にはまだだれも席についていない四人掛けのテーブルがひとつあった。そんな決まりはないのだけど、ぼくらのような期間雇用のアルバイトのために、いつもこのテーブルには社員の人間は座らなかった。ぼくがこのホテルにきたときにはすでにあった、暗黙の了解のようなものだ。ぼくは苦もなく席を確保することができた。ほかのアルバイト——いまはぼくともうひとりしかいない——はまだきていなかった。お盆を置いて椅子に座り、箸立てから箸を一対抜いた。七味をかけたかったけれど、このテーブルに置いてあった瓶の中身はからだった。わざわざほかのテーブルに借りにいくのも面倒だった。ぼくはひとりで食事をはじめた。
麺を半分ほど食べ進んだ頃、桧山さんが大きな肩を揺らして食堂へ入ってきた。彼はホワイトボードのメニューをじっと眺めたあと、食堂のおばちゃんとしばし言葉を交わした。その後、ぼくとまったく同じやりかたで自分の食事を準備し、丼と皿ののったお盆を大事そうに抱えて、テーブルの間を無駄のない動きで器用にすり抜け、ぼくの向かいに腰を下ろした。桧山さんは箸立てから箸を抜きとり、七味の小瓶を持ち上げて顔をしかめた。彼は立ち上がって近くのごみ箱にそれを放りこみ、別のテーブルから開封してまもない瓶を借りて席に戻った。
「ずいぶんと遅かったですね」ぼくは顔を上げて話しかけた。「お昼になってからだいぶ経ってます。なにかトラブルでもありましたか?」
桧山さんは瓶のふたを開け、尋常じゃない量の七味を丼にふりかけた。「いえ、なに。いつものやつですよ。気づきませんでしたか? 掃除機を客が通る通路に置きっぱなしにしていたとか、回収したはずのベッドシーツが何枚か足りないとかで、鬼の首をとったかのように、上へ下への大騒ぎです」
「気づく前に、ここへおりてきてしまったみたいですね」とぼくは言った。「またいつものあのひとですか」
桧山さんは頷いて立ちのぼる湯気のなかに顔を突っこみ、豪快に麺をすすった。彼は小瓶を返しに行かなかった。ぼくはそれを拝借し、出汁の表面が半分埋まる程度に七味をふりかけた。
「でも今日はまた一段とひどかったです」桧山さんが湯気越しに言った。「今日はほら、はやい時間に団体の宿泊客がくるはずだったでしょう? だからその分の客室は午前中に清掃を終わらせていなきゃならなかったのに、それが全然で」
「終わっていなかったんですか? たしかぼくがチェックリストをたしかめたときは、そのあたりの部屋はすべて〝清掃済み〟だったはずですけど」
「どうやらあのひとが間違えてチェックを書きこんでしまったみたいです」言葉の合間にも、彼は口いっぱいに麺をすすった。同時に野菜のかき揚げ、サラダも彼の胃袋に吸いこまれていく。「おかげで清掃が済んでいないとわかったときは大変でした。例のごとく、ふなばし船橋さんが人目もはばからず、廊下のまん中で怒鳴り散らしていました。見ていてかわいそうなくらいでしたよ」
「たしかにあれは何度見ても気持ちのいいもんじゃありません」ぼくはここで大事に汁を浸みこませておいた油揚げにかじりついた。「でも、桧山さんがここへきたということは、清掃は終わったんですね」
桧山さんは首を振った。「ぼくだけが先におりてきたんです。『残りは正社員だけでやるから、お昼に行って大丈夫だよ』と船橋さんに言われて」
「ふむ」ぼくは丼を両手で抱え、七味で朱に染まった出汁を飲んだ。桧山さんもぼくと同じように丼を抱え、ごくごくと喉を鳴らした。ぼくは丼を置き、いくらかのびてしまった麺を箸の先でつまんで引っぱり上げた。麺に張りついた七味の粉が、重力に負けて汁の元に戻っていく。ぼくはつぶやいた。「それじゃあぼくら二人とも、覚悟しておいたほうがよさそうですね」
桧山さんは怪訝そうな顔をした。
「これを食べ終わったら、長い愚痴に付きあわされそうですから」
桧山さんは笑った。そのあとは二人とも無言で食事を進めた。ぼくのほうが卓につくのがはやかったというのに、食べ終わったのはほとんど同時だった。まだ食堂は混んでいた。食事を終えてからも、席を離れず話に花を咲かせているひとたち。テーブルの間で聞き慣れた冗談が飛び交う。笑い声があがる。ぼくらはなんとなく同時に席を立ち、喧騒を縫って流し台に並んだ。スポンジに洗剤を数滴垂らし、慣れた手つきで自分たちの食器を洗った。丼と皿と箸についた水気をタオルで拭きとり、すべて所定の位置に戻した。食堂のおばちゃんに、ごちそうさま、と声をかけてぼくらは出口に向かった。
食堂を出たところで、廊下の角からこちらに向かってくる船橋さんに出くわした。彼はぼくらの存在を認めると、ぼくよりも二十センチは背の低い体ではしこく動き、こちらへ寄ってきた。煙草のにおいが鼻をついた。
「まったく参っちゃうよ」船橋さんは開口一番そう言った。「あのじいさんのせいで、今日も休憩時間がほとんど残ってないよ。のんびり昼飯も食わせてくれねえ」勢いは止まらない。「何度おんなじことを言っても、おんなじミスばっかりするんだ。それで上の人間に責任を負わされるのはわしなんだ。こんな理不尽なことってあると思うか?」
ぼくは白髪混じりの角刈り頭を見下ろした。少し近すぎると思って、壁際に一歩後退した。そのまま彼の愚痴を五分ほど聞いていた。時々脇に避けて、食堂を出入りする人間のために道を空けた。桧山さんは片足に体重をのせ、適度に相づちを打っていた。彼がなにも言わないときは、ぼくが相づちを打った。
やがて勢いが収まると船橋さんは口をつぐみ、ぼくらの顔を交互に見た。まるで、ぼくらがなにもせずこの場に突っ立っている理由がわからない、とでも言いたげな目だ。船橋さんは言った。「二人とも、昼飯を食べ終わったところ?」
「はい。ついいましがた終えたところです」とぼくは言った。
船橋さんは頷いた。「きみたち二人にはいつも助けられているよ。アルバイトだっていうのに、社員のだれよりもよく働くし、小さなミスにもすぐ気づいてくれる。本来であれば逆でなきゃいけないんだけどね。うちの社員はお世辞にも仕事に熱心とは言えないものな。まったく。こんな場末のホテルじゃ、わしら社員だけでやっていくのは無理なんだ」そこで船橋さんは桧山さんのほうを見た。「たしか桧山くんは、今月いっぱいで契約が切れるんだったかな?」
「はい。あと十日ほど出勤したら、それでおしまいです」と彼はこたえた。
「そうか。できることならきみたち二人には、ずっとここにいてもらいたいと思ってるよ」そう言って船橋さんは桧山さんの顔色をちらっとうかがった。桧山さんはなにも言わずに微笑んだ。船橋さんは言った。「ここを出ていったら、つぎにどこへ行くかは決まっているの?」
「いいえ。それがまだなんですよ」
船橋さんは頷いた。「わしらが若かった頃は、きみたちみたいに数か月単位で仕事を変えて、あちこち渡り歩くなんてことは考えられなかった。会社には一生を添い遂げるつもりで入社したもんだ。少なくとも、この国ではな。羨ましいと思うよ、好きな土地で、好きに仕事を選べるっていうのはな。わしもきみらと同じ時代に生まれていれば、いろんな景色を見てみたかったかもしれん。なんにせよ、若いうちは好きにすればいいんだ。それが若さというもんさ」
「ええ、ほんとうにそうですね」桧山さんは言った。
「だからこそ、いまの時代はきみたちのような若い人材は貴重なんだ。能力のある人間ほど、引き留めておくのが難しくなる。そしてあとに残るのは、どこにも行き場のない、無能な年寄りだけなんだ」
「それは言いすぎだと思いますが」と桧山さん。
ここで船橋さんはぼくへ向き直った。「相沢くんはどうするの? きみも月末で契約が切れるはずだけど」
ぼくは頷いた。小夜が入院することに決まってからは、一か月ずつ、雇用契約を更新しつづけてきたのだ。
「今月もまた、いつものようにお願いします」とぼくは言った。
「わかった」船橋さんは頷いた。「わしのほうから担当者には連絡しておく。きみだけでも残ってくれれば助かるよ」
船橋さんは、ちょっと待っててくれ、とぼくたちを止め、食堂前の自販機に向かった。指先でちょこまかと目当てのものを探ってから、冷たい缶コーヒーを二本買い、ぼくらに一本ずつ手渡した。ひんやりとした感触が、ぼくの手の平を包んだ。船橋さんはぼくらに手を振り、騒々しい音を立てて食堂へ入っていった。
ぼくと桧山さんは並んで歩きだした。窓のない廊下には、修理の必要な扇風機やトイレットペーパーなどの備品が、段ボール箱のなかへ無造作に積み重ねられ、隅っこに寄せられていた。形の崩れたカナブンの死骸が仰向けに転がっている。天井灯が、ところどころ明滅していた。
「それじゃあ、つぎの目的地はまだ決まっていないんですね?」とぼくは歩きながら話しかけた。
「ええ。実際そうなんです」桧山さんは缶コーヒーを振りながら言った。「だから急いでここを出ていく理由もないんですがね。ただ、そういう契約でしたから。ここに残る理由もないんですよ」
ぼくは頷いた。「よくわかります」
ぼくらは喫煙所の前に着いた。天井から吊り下げられたビニールの膜に囲われている。いつもなら桧山さんとはここで別れる。彼は煙草を吸いに行き、ぼくはどこか人目につかない場所で時間を潰す。でもこの日は会話の途中だったこともあって、なんとなく桧山さんにつづいて喫煙所に入った。なかにひとはいなかった。塗装の禿げたテーブルに銀の灰皿がひとつ。椅子が二脚あって、片方はマッチ棒ほどの細い足をした赤い椅子。もう片方はお尻があたる部分だけ黒く変色した木製の椅子だった。ぼくらはいつもそうしている、といった雰囲気で向かいあって座った。
桧山さんは四角い紙を閉じた膝の上に広げ、ポケットから取り出した小さなビニール袋から煙草の葉をひとつまみ、その上に細く並べた。吸い口に当たる部分に白いフィルターをのせ、それらをまとめてくるくると器用に巻き、繋ぎ目を舌で舐めてくっつけ、一本の煙草をつくった。ぼくは缶コーヒーのプルタブを開け、桧山さんが火をつけた煙草をうまそうに吸っているのを眺めながら、苦みの塊みたいな液体を喉に流しこんだ。
桧山さんが口を開いた。「この職場のいいところは、喫煙所が食堂の近くにあることです。ひどい職場は許可された場所で煙草を吸うために、平気で十分ほど歩かされたりしますから」
「それは不便ですね」ぼくは心の底から同情した。桧山さんはほんとうにうまそうに煙草を吸った。
「この街は嫌いではなかったです。穏やかな海がすぐそばにありますし、コンビニやスーパーだって、歩いてもそんなに遠くない。従業員なら食事も温泉も、無料で提供してもらえますしね」
「よくわかります」ぼくは頷いた。「ど田舎の職場じゃ、こうはいきませんよ。ところで、よかったらぼくにも煙草を一本分けてもらえませんか」
桧山さんは少しばかり目を見開いた。「以前は吸っていたんですか?」
「いえ、そういうわけではないんですが。ただ桧山さんがあまりにもおいしそうに吸っているので、ぼくも吸ってみたくなったんです」
桧山さんは先ほどと同じ要領で煙草を巻き、ぼくに手渡してくれた。彼が差し出したライターに顔ごと近づき、火をつけてもらった。ぼくは煙草を躊躇なく、肺の底まで深く吸いこんだ。清涼な空気が血液中を満たす。吸ったのはずいぶん久しぶりだった。
「缶コーヒーといっしょに吸うと、これがまた絶妙なんです」桧山さんは言った。たしかにそのとおりだと、ぼくは煙を吐きながらこたえた。
ぼくらはしばらく黙ったまま、コーヒーと煙草を鼻腔で味わった。心地よい沈黙だった。時折前屈みになり、人差し指で煙草の腹を叩く。灰皿の上に、徐々に灰が積もっていった。やがて桧山さんがぽつりと語りだした。
「さっきは次の目的地はまだ決まってない、なんて言いましたがね。実際そのとおりなんですが、冬が終わって、雪が解けたら、そのときに行く場所はすでに決まっているんです」
ぼくは黙って耳を傾けた。お互いに、今日はいつも以上によくしゃべる日だ。桧山さんは言葉をつづけた。
「自覚もしていますが、これまではさんざん好き勝手をしてきました。ぼくは運よく車を持っているので、行きたいと思った場所に自由に走っていけるんです。山奥で働いていた頃は渓流釣りにのめりこみました。休日は林道に車を乗り入れて、熊に出会いはしないかとびくびく怯えながら、流れ落ちる川に釣り糸を垂らしたもんです。スキー場ではスノーボードを無料で借りて、朝からライトが点灯するほど暗くなるまで滑っていましたし、ここでは休みのたびに湯河原や宇佐美の砂浜まで出かけて、ほかの物好きな連中と肩を並べてサーフィンをしていました。あちこち巡って、その場で適当なものを選択してきて、最近になって、ようやく自分がむかしからほんとうに好きだったものに、手を伸ばしてみようかという気になってきたんです。春になったら、北海道の牧場で、動物たちの世話をすることになってるんですよ」
「北海道」ぼくはその単語を舌の上で転がした。慣れているようで慣れていない、そんな奇妙な味がした。
「はい、北海道です。津軽海峡を越えたその先へ」
「なぜ北なんですか? 桧山さんが好きなものってなんなんですか?」
「ぼくは馬が好きなんですよ」桧山さんは二本目の煙草を吸いはじめた。二人の煙でぼくらの視界が霞んだ。彼は言った。「死んだ親父が競馬好きのろくでなしだったんです。休日は母に黙って、よく近所の競馬場に連れていかれたもんです。もちろん、母には全部ばれていたんでしょうけどね」彼は笑った。「汚えとこですよ、競馬場なんてのは。少なくともうちの近所のはね。道端には焼酎の空き瓶や、雨で濡れて地面にへばりついた段ボールの切れ端やなんかがあって、正体のわからない黒い染みが建物の外壁や床にぽつぽつと、霊の足跡みたいについているんです。だれかが吐いた痰を踏んづけて、何度むかっ腹を立てたことか。敷地内が汚けりゃ訪れる人間も汚いもんです。汗染みのついた野球帽に、何年つかってるかわからない穴だらけのジャンパー。歯が欠けてない人間なんかいやしません。不思議なことに、全員が似たような格好なんです。いつも片方しかレンズのはまっていない眼鏡をかけたおっさんは、親父の顔見知りでした」
ぼくは想像した。レンズが片方しかなかったら、物事はどんな見えかたをするのだろう。
「入口に着くと、決まって親父が五百円玉をくれるんです。ぼくはそれを好きに使っていいことになってました。そこは売店で売っていた唐揚げが名物として有名だったんです。肉汁がたっぷりでね。塩味と醤油味があって、交互にどちらかを選んでました。それに飲みものを加えて四百円。残りの百円は、親父に頼んで馬券を買わせてもらうっていうのが、いつもの流れでした」
ぼくは吸い終えた煙草を灰皿に押しつけた。缶コーヒーを飲みきってしまわないよう、ちびちびと飲んだ。
「馬券のことは母親には内緒でしたけどね。もしもばれていたら、競馬場に行くのも止められていたでしょうから」桧山さんはつづけた。「とはいえ、子供にどんな馬が勝てるかなんて、わかりはしません。知識なんてありませんから。親父はいつも競馬新聞を腋に挟んでましたけど、見せてもらったところで、ちんぷんかんぷんなんです。だからレース前のパドックは必ず確認しました。そこでなんとなく元気そうに見える馬を、親父やまわりのおっさんを真似て批評してみたり、それぞれの馬に対する彼らのアドバイスに耳を傾けたりしたんです。終いには、なにがなんだかわからなくなって、面倒くさくなって、名前の響きがかっこいい馬に賭けてくれって、親父に頼んでましたよ」
「それで、勝てましたか?」とぼくは訊いた。
「勝てるときもありました。はした金ですが、少なくとも親父よりは勝っていたでしょうね。競馬場からの帰りであのひとが機嫌のいいところを、あまり見た記憶がないですから」彼は笑った。「奇妙なもんです。熟慮した大人の予想より、子供の勘のほうが冴えていたんですから。それでも、ぼくが勝ったときの取り分は必ずぼくに渡してくれました。ろくでなしでも、野生の動物的なろくでなしだったんです。悪知恵の働くろくでなしより知能は劣っても、ひとの縁は大事にするひとでした」
「なんとなく想像がつきます。きっと、憎んでも憎みきれないひとだったんでしょうね」
「ええ、まったくそのとおりでした。親父のそういった面に気づいたのは、自分がその一部を彼から受け継いでいると気づいてからでしたけど」
「それじゃあその頃から、子供の頃からずっと馬が好きだったんですか?」
「最近になって、よく思い出すんです」桧山さんは静かにそう言った。缶コーヒーと煙草を、器用に片手で持っていた。「レースの三十分前になると、よく観客席から親父について下までおりていって、爪楊枝に刺した唐揚げを頬ばりながら、パドックの柵に手をのせて頭をのぞかせてました。騎手に連れられてレースに出る馬が目の前を通ると、興奮で胸が震えましたよ。でかいんです、とにかく。見上げるような高さで、まるで崖の前に立っているみたいな圧迫感があるんです。筋肉が岩場みたいにがくがくと盛りあがっていて、毛並みが太陽の光を浴びて、艶やかに光っているんです。年月が過ぎてから、ひとりで旅行先の競馬場を訪れたときも、子供の頃に染みた印象はなかなか変わらないみたいで、忘れられないんです」
「なるほど」ぼくの缶コーヒーは底を尽きかけていた。「だから北海道なんですね。冬の間はどうされるんです?」
「車のなかで寝泊まりしながら適当に過ごそうかと思ってます。この季節なら、毎日風呂に入る必要もありませんしね」
ぼくは大きく缶を傾けてコーヒーを飲み干した。「不思議なものですね」ぼくはぼーっとしていて、頭のなかで考えていた余計なことを口走ってしまった。「半年も共に過ごしてきたというのに、ぼくはあなたのことをろくに知らなかった。共に働いて、共に従業員食堂で飯を食ってきたというのに。いつも決まって、相手のことをいくらかでも知るのは別れ際なんです」
「うーん」桧山さんは眉根を寄せた。しばらくしてから彼は言った。「これは単なるぼくの我儘なんです」
「我儘?」
彼は少し照れたように顔を背けた。「どこへ行っても、数か月も同じ時間を過ごせば、よほどいやな環境じゃない限り、情ってもんが湧いてきてしまうものです。かといって、この放浪生活をやめるわけにもいきません。勢いにのったなにかの軌道を変えるのは、自然の理に反しているような気がしますから。それ自身が力を失うのを待つことが、いまのぼくにできる精いっぱいなんですよ。だからせめて、最後だけは綺麗な終わりを迎えたいんです。汚い終わりかたをすれば、その場所で得たよき思い出は、すべて汚れたものに変わってしまいます。いやな気持は次の場所へ行っても引きずるもんです。要するに、ぼくは終わりさえよければ残りのことはすべて些事だと思ってるような、いい加減な人間なんですよ」
「なるほど」ぼくはつぶやいた。それ以上、言うべきこともなかった。
桧山さんは煙草を吸い終えていた。缶コーヒーを人差し指と親指で傾ける姿はさまになっていた。彼はぼくに尋ねた。「乾さんはお元気ですか?」
「相変わらずですよ。ぼくといっしょにいるときは、退屈だ退屈だ、と日に五千回は言って、ベッドの上でのたうちまわってます」
桧山さんは笑った。「それでは、ここにいた頃とあまり変わりはないようですね。その情景が、容易に目に浮かびますよ」
「ええ。医者いわく、症状も特に悪化はしていないみたいです。よくもなっていないみたいですがね」
「食堂で三人いっしょにまかないを食べていたのが、つい昨日のことのようですよ。相沢さんとのやりとりを見ていると、だれだって笑わずにはいられません」懐かしさに彼は目を細めた。
「社員だというのに、ぼくらのテーブルに居座って、社員の間では浮いた存在になっていましたね」
「寂しかったですよ、乾さんがいなくなったあとは。日常がずいぶんと静かなものになった気がしました」
ぼくはなにも言わずに頷いた。
「最近になって親父のことをよく思い出すのは、きっとそんなお二人を間近で見ていたからです。ぼくのなかにある間隙に、ようやく手を伸ばせるようになったんです。ぼくひとりだったら、永遠にできなかったかもしれません。そしてこれは、ぼくが在るべきぼくになるためには必要なことなんです。彼女がはやいところ完治して、お二人が幸せになることを祈ってます」
「ありがとう」ぼくは頭を下げて礼を言った。「本人に伝えておきます。きっと喜びますよ」
「いくらでも伝えてください。安いものです」
ぼくは笑った。
ぼくは桧山さんを残して、喫煙室をあとにした。長くひとの話を聞いたので少し疲れを感じたけれど、それは悪くない疲れだった。からになった缶を空き缶入れに放って、階段で地上へ向かった。のぼる途中で金井さんに出会った。彼はぼくの姿を認めると、口元に弱々しい笑顔を浮かべて立ち止まった。
「お疲れさまです」とぼくは声をかけた。
「お疲れさま」ひとのいい笑顔だ。「もう休憩は終わり? お昼はゆっくり食べれた?」
「ええ。もう少ししたら、仕事に戻ろうかと」
金井さんは力なく頷いた。その様子は見ていて哀れなほどだった。「すまねえな、おらのせいでみんなに迷惑をかけちまって。自分ではしっかりしようとしてるんだけども、気がつかねえうちにミスばっかしちまってるんだ。そんなはずはねえって、自分の行動を思い返してはみるんだけども、おら以外にそんなミスをするやつは、ここにはひとりもいねえものなぁ」
ぼくは彼を安心させるためにちょっと笑った。「でも、致命的なミスではなかったんでしょう? なら大丈夫ですよ。少なくとも、ぼくと桧山さんは気にしていませんから」
それを聞いて落ちこんだ気分が少しよくなったみたいだった。彼はもう一度ぼくに謝って地下へおりていった。ぼくは彼の薄くなった頭頂部が消えるまで見送ってから、再び階段をのぼった。
ホテルの表玄関の前は、道路一本隔てて海だった。灰色の欄干の向こうにはいくつかの漁船が繋がれていて、もう少し歩いた先には無骨な防波堤が、水平線を視界から遮っていた。ぼくは車がきていないことを確認して道路を渡った。もっとも、この道路の先は宿の駐車場と鉄の車止めが立っている行き止まりがあるだけなので、ホテルの客と釣り人以外の人通りはまずない。
海は静かだった。耳を澄ませば、波が船や消波ブロックと擦れあう音が聞こえる。防波堤には釣り人が群がっていた。彼らを眺めながら、ついさっき桧山さんがぼくに言った言葉を頭のなかで思いかえしていた。
『お二人が幸せになることを祈ってます』
ぼくはポケットからタブレットを取り出し、手を触れて画面を開いた。着信が一件あって、ぼくに気づかれるのを待っていた。こんなふうにぼくに連絡をよこす人間など、この世にひとりしかいない。画面をタップすると、小夜からのメッセージが小さなスクリーンに広がった。
《本日午前十一時頃、母が土産物を携えてお見舞いにきました。彼女が持ってきたのは青森産のりんごで、昼食のあとに自前の果物ナイフで切り分けてくれました。母の手前、わたしはそれに一欠片だけ手をつけました。でも母はそんなわたしの様子をいぶかっていました。わたしがもっと喜んで食べてくれるものと期待していたようです。たしかにわたしは二日前、彼女に言いました。美味しいりんごが食べたいと。あの酸味と砕け散るような食感が好きなのだと言いました。でもそれは二日前のお昼にわたしがりんごを好きだったという単独のお話であって、本日のわたしの好きとはまた別個の事柄なのです。それらは手の平と手の甲のように、互いに独立しあっているのです。きっとそれは説明したところで、母に理解できるものではないので、わたしはなにも言いませんでした。でも今日のわたしはりんごが好きではありませんでした。これから先、また好きになる日はくるでしょうが、とにかく今日ではありませんでした。そういう気分だった、で済ませられるお話ではありません。そのときのわたしは、そのために自分の生活を犠牲にできると思っていたのです。わたしの身を隅から隅まで捧げられるものと信じていたのです。その熱情はわたしの手足をがっちりつかんで放しませんでした。経験から、それはやがて過ぎ去るべきときに消えていってしまうものだとは知っています。それでもそれはわたしの日常ですし、わたしをわたしたらしめているものです。
こんなわたしに期待されても困ってしまいます》
文章はそこで終わっていた。添付の画像は、綺麗に切り分けられ、皿に盛りつけられたりんごの写真だった。みずみずしくておいしそうだった。ぼくは少し考えてから返事を返した。
《余った分は冷蔵庫で冷やしておいてくれ。次に行ったときにぼくが食べるよ》
すぐに返事が返ってきた。
《もう母がすべて食べきってしまいました。それに、切ったりんごはそんなに長持ちしません》
ぼくらはその後も取るに足らないやりとりをつづけた。やがて昼休みが終わり、タブレットをポケットにしまって、ぼくは仕事に戻った。
🌕3
十二月のはじめ。バイクを駐輪場に停め、病室に向かった。正午を少しまわった頃だった。散った紅葉で地面が滑りやすくなっていた。
扉をノックすると、どうぞ、という返事がなかから聞こえた。ぼくが病室に入ると、小夜はベッドの上で、彼女の好きな漫画を読んでいた。彼女は顔を上げ、ぼくに挨拶する。
「こんにちは。お元気ですか?」
これを聞くと、ぼくは瞬時の変態で宇宙人になりきらなくてはならない。そういう決まりなのだ。鞄を肩にかけ、ヘルメットを抱えたまま、その日によって蛸型や植物型や薄い平面型などの地球外生命体になる。
「ワタシハセンケンタイダ。モシモノトキノタメニ、コノホシノイリョウセイドヲ、シサツシニキタ」
体を痛くない程度に捻じ曲げ、はじめてこの星にきたかのように、あたりをきょろきょろと見まわす。漂流物か、あるいはむかで百足のように移動し、その拍子に鞄やヘルメットを壁にぶつける。ベッドをまわりこみ、窓外の景色を小夜の視界から遮り、彼女を見下ろす。
「コノホシノキオンハ、ワレワレノホシトハ、クラベモノニナラナイ、クライタカイ。キヲヌクト、イッシュンデ、ヒカラビテシマイソウダ」
そう言ってぼくは花瓶に活けてあった水仙の花を抜きとり、冷たい縁に口をつけて、なかの薄汚れた水をごくごくと飲む。それを見て小夜はお腹を抱え、くすくすと笑い転げる。まったく、ぼくの悪ふざけで笑うのは、小夜くらいだ。
ぼくは水道の蛇口を捻り、自分が飲んだ分の水を補填した。小夜はまだ笑っていた。花を元通りに花瓶にさし、ベッド脇の机の上に戻した。彼女との距離が縮むと、柑橘系のにおいもまた強くなる。この日はシトラスにラベンダーを混ぜたような香りだった。花瓶を手から離すとき、一瞬だけ、立ち止まってそのにおいを深く吸いこみ、肺のなかを満たしたいという衝動に駆られた。でもぼくは意志の力でそれを抑えこんだ。ぼくの内面を見抜かれる前に、部屋の隅にあるいつもの定位置へと向かった。小夜はぼくに、隣に座ることを許してはくれないのだ。初めてこの病室を訪れたときに、彼女がまっ先に言った言葉がそれだった。
「相沢くんはあっち。あそこに椅子を置いておいたから、つかってね。お願いだから悪く受けとらないでほしいの。ただ、わたしにとって心の距離と肉体の距離は、同じ意味を持つものなのよ」
いつもより重い鞄を床に放り投げ、ヘルメットはパイプ椅子のすぐ脇にある、小型の折り畳みテーブルに置いた。鞄はいつもよりも鈍い音を立てた。小夜もそれに気づいた。
「なあに? 午前中はどこかへお出かけしてたの?」
「うん。今日は朝はやくに起きて、宇佐美のビーチで泳いできたんだ」鞄のなかはゴーグルと、まだ乾ききっていないタオルだった。ぼくは上着を脱いでハンガーにかけ、壁の出っぱりにぶら下げた。
「ふうん」小夜は言った。「どうりで相沢くんから海のにおいがすると思った。頭の上、わかめがへばりついてるわよ」
ぼくは髪の毛に手を伸ばした。コインシャワーで、海水は全部洗い流したはずだった。そんなぼくを見て、小夜はまたくすくすと笑った。
「こんな時期に海水浴だなんて、男の子は丈夫でいいわね。いったいどういう風の吹きまわし?」
「桧山さんだよ」体を投げ出すようにして、椅子に座った。「ここを発つ前に、最後にサーフィンをしに行くから、ぼくもどうかって誘われたんだ」
「そういえば、もうそんな時期だったわね」と小夜は言った。「それでどう? うまく波には乗れた? あなたの口からサーフィンなんて言葉、初めて聞いたような気がするけれど」
「実際、初めてだったからね。帰る間際にようやくコツはつかめたよ。桧山さんいわく、ぼくは下手じゃないらしい」
「そう。それはよかったわね。楽しかった?」
「悪くなかったよ」
「それじゃあようやく趣味と呼べそうなものができたんじゃない?」
「別れるときに、ウェットスーツとサーフボードが買える場所を詳しく教えてもらったよ。それから、乾さんの快復を祈ってます、だってさ」
小夜は口元に静かな笑みを浮かべた。少しの間のあと、「胸が掻きむしられるようね。なにもすることのない人間が、だれかの背中を見送るっていうのは」とだけ言った。
その言葉がゆっくりと床に舞い落ちるまで待った。ぼくは言った。「言葉にするのは時々だったけど、きみのことを気にかけていたよ」
小夜は頷いた。不意に彼女は布団をめくり、いつも履いているスリッパに足を突っこんで立ち上がった。窓際に歩み寄り、窓を開け放つと、その真横にあるソファへと体を沈めた。澱んだ空気が霧散し、外の空気とひとつになった。
「それで、彼はつぎにどこへ行くって言っていたの?」彼女はソファの弾力をたしかめるかのように、体を揺らしながらぼくに訊いた。
「冬の間は特に決めてないらしいよ。でも春になって雪が解けたら、北海道で馬の世話をするんだってさ」
ぼくの言葉を聞いて、小夜の様子が微妙に変わった。体を揺らすのをやめ、やや神妙な顔つきになった。
「どうかしたのかい?」気になってぼくは訊いた。
「桧山くんは、どうして北へ行くか言ってた?」
「ああ。彼は競走馬がむかしから好きだったんだ」
「ふうん、そう」彼女はつぶやいた。「わたし、北海道って行ったことないな。写真は何枚も見せられたことがあるけど。きっといまの季節は雪が積もって大変ね」
「桧山さんもそんなことを言っていたな。彼の車じゃ、とても冬は越せないらしい」ぼくは小夜の横顔を眺めた。「行ってみたいかい?」
「え?」彼女は驚いてぼくを見た。
「北へ行ってみたいかい?」ぼくは質問を繰りかえした。「あれだけ律子さんと旅行の話で盛りあがってたきみが、まだ北海道には上陸していないだなんて、ちょっと意外だな」
小夜はぼくから目を逸らし、虚空を見つめた。口を尖らせ、考え事をしているみたいだ。開いた窓からは、車のエンジン音が聞こえた。それは徐々に遠ざかっていき、終いにはほかの生活音に紛れて消えた。ぼくは小夜の言葉を待った。
「行ってみたくても行けなかったのよ」やがて彼女は、向かいの壁を見ながらしゃべりはじめた。「あそこはわたしがまだ小さかった頃から、ずっと憧れの場所だったから」
ぼくは眉を吊り上げた。そんな話は初耳だった。
「むかし、パパが一度だけ、でも真剣に北海道への移住を計画したことがあったの」小夜はつづけた。「わたしが十歳か、十一歳くらいだったかな」
ぼくは何度か会ったことのある小夜の父を、頭のなかで思い浮かべた。痩せていて顎骨の関節のあたりがどこか緩く、ロックの外れた南京錠みたいな顔をしていた。小夜とはあまり似ていない。
「わたしとママに黙って、けっこう具体的なところまで話が進んでいたくらい。なぜだかは知らないけど、わたしたちが反対するはずない、って思ってたらしいのよね」
「どうして北海道なの?」ぼくは訊いた。「熱海の街じゃ不満だったのかな」
「都会の喧騒に疲れちゃったんだって」小夜は言った。「ママに問い詰められながら、熱っぽくわたしに計画を話してくれたわ。きっとわたしを味方につければママも説得できると考えたのね。パパも桧山くんと同じで、馬が好きだったのよ。街から離れた小さな牧場を買って、馬だか牛だかを育てて暮らしていく夢を描いていたみたい」
「へえ」ぼくは息の塊を吐いた。「お金持ちの考えることは、いちいち規模が大きくて、くらくらしてきちゃうよ」
小夜はくすっと笑った。「わたしもそのとき、気づいたのよ。我が家はまわりより、ちょっと多めにお金を持っているんだなって。それまでは自分の家で温泉に入れることを当たり前だと思ってたんだもの。パパが買おうとしていた、サラブレッドの仔馬の値段を聞いたらびっくりしちゃった。熱海で中くらいの一軒家がひとつ買えるくらいなのよ。それでも海外に比べたらずっと安いって言うんだから、途方もない世界よね」小夜は言葉を切った。部屋の気温が下がりつつあったけど、ぼくも彼女も窓を閉めようとはしなかった。
「何日もの間、パパは移住計画の素晴らしさをわたしの耳元で語りつづけた」小夜は言った。「わたしは妄想するの。大草原のどまん中に、わたしたち家族が暮らすには十分なくらいの小さい家を建てて、三人で静かに生きてゆく。すぐ隣には馬たちを放すための牧場が見渡す限りに広がっていて、畜舎のそばには東京タワーみたいに大きいサイロが建っている。その塔はわたしの家のシンボルでね。遠くからでもひと目見れば、あそこは乾さんとこの家だってわかるの。わたしはいつもパパとママに手を振りながら、そのサイロをぐるっとまわって通学する。学校までは毎日スクールバスが出ていて、通学中には席で揺られながら、朝日を受けてまどろ微睡む。学校は広いけれど、都会とは違って同じ学年に生徒は十人もいないの。みんなが顔見知りで仲よし。粗野な陰口も悪意も、そこは狭すぎて入りこむ余地がないのよ。学校から帰ったらまず宿題をやって、夕飯の時間は家族でのんびりと、テレビでも見ながらおしゃべりする。その日は体育の授業で走り高跳びをやったんだとか、授業中にどこからか野生の鹿が校庭に迷いこんで、だれの目を気にするふうもなくゆったり草を食むのを、先生までいっしょに眺めていたとか、クラスメイトの牧場で、この間、仔牛が生まれたんだとか、そんなことをだらだらとしゃべりつづける。パパとママはじっと耳を傾けてくれるの。眠る時間になると、ベッドでママが本を読んでくれる。毎日毎日読んでくれる。わたしが好きな小説じゃなくて、パパが好きな小説なんだけど、それは赤ん坊の頃に聞いた子守唄みたいにわたしの体をあたためて、次第にわたしもその物語を好きになっているの。そうしてわたしが眠りに落ちるまで、彼らはそばに寄り添って、わたしが決してひとりではないことを教えてくれる。休日は友達を呼んでもいいし、パパとママの手伝いをして過ごしてもいいの。三人でお揃いのオーバーオールを着てね。馬や牛の世話なんてしたことないけど、それは三人ともいっしょだから、なにも不安をおぼえる必要はない。朝がはやくて大変だし、動物たちの菌が移ってお腹を壊しちゃうこともある。でも、これ以上くだらない人間の相手をしなくてもいいんだ、だって。ほんと、あの頃のパパになにがあったのかしらね」
「それで、お父さんの夢が、きみにも乗り移っちゃったのかな」
「そうね。日を経るごとに、パパの話は綺麗な音楽みたいになってくるの。その頃のわたしは毎日、北海道での生活を妄想しながら眠りについたわ。でもなによりわたしが魅せられたのは雪なの。雪は静かで無垢で汚いものが混じってないから。解けないぎりぎりで存在を保っているところも好き。たくさん集まるほど強固になるところも好き。一面の雪景色に囲まれて暮らせたら素敵だなと思うの」
「でも結局、計画は頓挫したんだろう? お母さんが認めなかったのかな」
「違うわ。それもあるけど、わたしがいやだって言ったの」
「へえ?」ぼくは目顔で問いかけた。
「ある日、庭の池に住んでた亀がいなくなっちゃったの」と小夜は言った。「毎日、餌をあげてたから、ペットって言っていいんだと思う。朝いつもの時間に庭におりてみると、姿形も見えないのよ。夕方、学校から帰ってきても、やっぱりいなくてね。パパにいっしょに捜してくれるように頼んだわ。夕飯の時間まで捜しつづけたけど見つかんなかった。わたしはその後も捜したかったんだけど、パパはもう遅いからって、わたしを止めたのよ。それがわたしには許せなくてね。パパには、もうやめるってわたしが言いだすまで付きあってほしかったの。子供の我儘を聞けないなら子供なんて生むべきじゃないって、あのときのわたしは思っていたわ。というより、いまだって思ってる。結局、亀は次の日の朝には帰ってきていたんだけど」
「あたりは暗くなっていたんだろう?」ぼくはちょっと笑ってしまった。「妥当な判断だと思うけどな」
「それでもよ」と小夜は言った。「たとえ無駄だとわかってはいても、望みっていうのはどうしようもなく湧いてくるものなのよ。普段の優しさなんて、ほんとうに困ってるときにくれる優しさに比べたら無に等しい。わたしがほんとうに望んでいるものがなんなのか、ただ知ってほしかっただけなの」
「子供のきみと違って、きみのお父さんは働いていたんだよ。次の日も仕事があったんなら、仕方ないじゃないか。きみたち家族のために、お金を稼がなくちゃならなかったわけだし。当時はいまよりも忙しかったんだろう?」
小夜は身動きもせずに、視線を宙にさまよわせた。少しして、ぼくのほうに向き直って言った。「それならわたし、忙しいひとって嫌い。たとえどんなにお金持ちでも、優しくってもね。積み重ねていればいつか神のもとに辿り着けると信じてる人間なんて、退屈で退屈で仕方ないもの」
ぼくはその部分を聞き流した。「それで、怒ったきみは北海道行きを断ったわけだ。率直に言って、きみのお父さんが不憫だよ」
「ほんとうにそうよね」小夜は肩を揺らして笑った。「こんな娘で、パパもママもかわいそう。でもこれでよかったのよ。わたしたち三人じゃ、絶対うまくいきっこなかったもの。わかるでしょう?」
ぼくはなにもこたえなかった。
「それでも、現実に目にしていないうちは、記憶のなかの憧れって色褪せないものね」小夜はつづけた。「いまでも時々、妄想しちゃうのよ。地平線から滲む朝日で目が覚めて、ほんとうに愛するひとと、他愛もない話をしながら朝食を食べる。寂しくないのよ。たとえ世界に二人っきりでも、好きなひととなら。草原には、いつもわずかながらに風が吹いていてね。わたしの体にまとわりつく汚れを、どこか名前のない場所まで運んでいってくれる。馬たちは従順ではないけれど、みんな元気いっぱいで、わたしの顔を見ると嬉しくて目を輝かせてくれるの。わたしは毎朝、彼らに優しく声をかけながら、たてがみ鬣をくしけず梳ってあげる。出会った当初は、わたしのことを噛み千切ろうとした子たちも、少しずつ心を開いてくれる。そしてある日、わたしは厩舎に敷き詰めてある寝藁に大切なものを落としてしまって、それを拾おうと屈みこんだ瞬間、一番わたしと仲が良かった子が後ろ脚を蹴り上げて、それでわたしの頭はかち割られて、割れた頭蓋骨から脳みそをぽたぽたと垂らしながら、だれにも気づかれずに死んでゆくの」
ぼくは首を振ってため息をついた。
「きみってやつは」
帰り際に小夜から声をかけられた。雲に反射した夕日が、病室を弱々しく照らしていた。
「相沢くんは、熱海の街にきてからどのくらい?」
ぼくは立ち止まり、振りかえって彼女を見た。小夜はベッドの上で手元の漫画に目を落としたまま、ぼくを見てはいなかった。艶のある黒髪が一筋、こめかみから頬を伝って垂れていた。
ぼくは肩にかけた鞄を背負いなおして質問にこたえた。「もうすぐ一年になるかな」ぼくの立っていた場所に、暖房の風が直接吹きかけていた。
「どう? もう熱海の街には慣れた?」
「慣れた?」ぼくは少し驚いた。「ぼくは二週間もあれば、大抵のことには飽きてしまう人間だよ」
「そう。そうだったわね」それっきり、彼女は黙ってしまった。ぼくは彼女のつぎの言葉を待ってその場に立ち尽くしていた。抱えていたヘルメットが邪魔くさかった。
「あの街を出たら」彼女はようやく口を開いた。彼女の声は、いつだって部屋の空気を震わせる。「次にどこへ行くかは決まってる?」
ぼくは彼女を見つめた。表情は逆光と角度のせいでよく見えなかった。ぶかぶかのパジャマを着ているせいで、体の小ささが目立つように思えた。漫画に視線をそそいでいたけれど、ページをめくる手は止まっていた。
「特に決まってはいないよ」とぼくはこたえた。
「いつまであの街にいるつもり?」と小夜は訊いた。
「少なくとも、きみがここにいる間は」とぼくはこたえた。
「そう」声色にはなんの変化もなかった。ぼくの言葉に、わずかに失望したようにも聞こえた。ぼくはふたたび彼女の次の言葉を待った。動かずにその場に突っ立っていると、背中や腕が石のように強張ってきた。暖房の風で目が乾いた。手元に視線を落としたまま、彼女はなにも言わなかった。
「今月末に」ぼくはたまらず口を開いた。「お祭りがあるんだ。海沿いで」
「知っているわ。わたしがどこで生まれ育ったと思ってるの」小夜は言った。
「ぼくらのホテルの近くだよ」
「それも知ってる」
「きみもこないかい? もちろん、病院の許可が得られればだけど」
小夜は音も立てずにページを一枚めくった。「行かない」と彼女はつぶやいた。
「そうか」とぼくは言った。
「知ってる? あのお祭り、観光客の減少で毎年規模が縮小してるの。むかしはいまよりたくさんの花火を打ち上げていたし、出店だって多かったんだから」
「きっときみは見飽きているんだろうな」
ぼくは窓の外を見やった。夕日がまぶしく、目を細めなければならないほどだった。ここにきた当初見えていた城は、いまや頭のてっぺんまで工事用の幌で覆われていた。あたたかさでぼーっとしてきた。外は冬なのに、シャツの下で汗が滲んできた。
小夜がなにか言った。静かな声だったので、ぼーっとしていたぼくは聞き逃した。
「え?」
「行ったことないの。一度も。あのお祭り。行きたいと思ったこともないし」
「そうか」不意に疲れをおぼえた。あの街で過ごした年月が、一度に肩へのしかかってきたみたいだった。ふたたび手の止まっていた小夜に、ぼくは言った。「それなら、気が変わったら連絡をくれ。ぼくはひとりでも行くから」
「気が変わったらね」
ぼくは少し待ってから、彼女の横顔を隠す黒髪を一瞥し、背を向けた。扉の取っ手に手をかけて、彼女に声をかけた。「また土曜日にくるよ」
小夜はなにも言わなかった。ぼくは部屋を出た。
熱海に着き、ホテルの駐車場の、車から少し離れた一画にバイクを停めた。道路を渡ってホテルの脇の狭い階段をのぼった。寮の部屋に戻り、荷物を置いて外に出た。従業員食堂へ行こうと思っていたけれど、夕方のこの時間は仕事終わりの人間と夜勤のひとたちで混みあうのを思い出した。ぼくは街の方向へつま先を向けた。
坂をくだって東へ曲がり、海岸沿いの遊歩道に出た。陽はすっかり山の向こうに沈んでいた。平日だったこともあって、観光客はまばらだった。規則正しい足音が近づいてきたので振りかえると、メッシュの半袖に競技用の短い半ズボン、生地の薄いキャップ、コードレスのイヤホンとデジタルの腕時計を身に着けた若者が、走ってぼくを追い越していった。金の声がする装備から、しばらく目が離せなかった。ぼくは後ろで手を組み、特にこれといったあてもなく、海沿いを歩いた。
歩きながら、波音と街の声に耳を傾けた。車が一台、ぼくの脇を通り過ぎ、信号を曲がって本道へ合流していった。ホテルや旅館の窓から明かりが漏れていて、どこかの宴会場では団体客がカラオケで、聞いたこともない演歌を歌っていた。酒を勧める声や、調理場の喧騒まで聞こえてくる気がした。タブレットを片手に評判の居酒屋を探しまわる、若い二人組の女性がいた。こんなはやい時間に、ほとんどの飲食店がシャッターを閉めているのを見てとまどっているみたいだった。
立ち止まり、海に背中を向け、欄干にもたれかかった。空を見上げても、星の光は街明かりに吸いとられてよく見えなかった。遊歩道にほかの人影はなく、ぼくひとりだった。潮のにおいに混じって、かすかに温泉のにおいが嗅ぎとれた。蒸気と、ひとの生活を全部ひっくるめたような、そんなにおい。
惨めな気分だった。こんな気分になったのは、いつ以来だろう。潮騒のリズムでさえ、いまはうとましい。頭を抱えて叫びだしたかった。だれでもいいから八つ裂きにしたかった。されたかった。
代わりにぼくは振りかえり、背中を丸めて冷たい欄干に頭をのせ、息を潜めた。悪しき熱が体から抜けてゆくのを待った。むかしよりも、この熱が肉体に居座る時間を長く感じるのは気のせいだろうか。だがこのときは去ってくれた。また失わずに済んだ。これでいい。これでいいんだ。
ほんとうに?
そのまま身動きせずに、じっとしていた。体を動かそうと思ってもできなかった。神経を遮断する楔でも打ちこまれたみたいだ。つぎに顔を上げたとき、体はすっかり冷えきっていた。タブレットを見ると、少なくとも三十分はその場にとどまっていたようだった。小夜からの着信はなかった。
ぼくはおぼつかない足取りで街中へと足を向けた。街灯が頭上でぼんやりと光の輪を放っていた。その下で、側溝からぬくい蒸気が噴き出していた。まるで霧のなかに迷いこんだみたいだった。商店街ではすでにほとんどの店がシャッターを閉じていた。まだかろうじて営業していたコンビニに入り、アルコール三パーセントの弱い酒を二本買った。袋を人差し指と中指に引っかけ、ブランコのように揺らしながら遊歩道へと歩いて戻った。背もたれのないベンチに腰をかけ、袋から缶を取り出し、プルタブを開けた。炭酸の抜ける音がした。海を眺めながら、ジュースのような酒を長い時間をかけてちびちびと飲んだ。ぼくはとてもアルコールに弱いので、一本飲み干した頃には足元がふらつくほど酔っぱらっていた。静かなひとときだった。騒がしい酔っぱらいもヤンキーもいない。いたとしてもホテルの一室やスーツを着たコンシェルジュの陰にいる。酔っぱらいは隠されている。本来であれば。
あーあー 自転車置き場に置き忘れた傘
垂れた水滴が パンダみたいな顔を描いてる
乾いたカップにコーヒーがこびりついて
洗い物が全然進まないったらありゃしない
ぴーぴーぴーぴー うずらが鳴けば
たまごは全部 偽物だった
パチロドソから帰還した彼は
めでたくンヴァホ族と 結婚いたしましたとさ
家事は女がやれ 男は働け戦争しろ
ウマ面 ロバ面 カエル面
なにもかも海に沈んでしまえ
二本目を開け、飲みはじめようと思ったけど、こめかみはどくどくと脈打ち、脳が直接温泉に浸かってるみたいに熱かった。ぼくは立ち上がってふらふらと、体を少しずつふたつに分けながら欄干に歩み寄り、缶を逆さまにして中身を波の間にそそいだ。液体どうしがぶつかりあう音が虚ろに響いた。水面がほんの束の間、白く泡立って、波に飲まれた。最後に缶を振り、一滴残らず絞り出した。空き缶を袋に入れ、体の横で振りまわしながら歩くと、缶同士がぶつかりあう高い音が小気味よく耳に届いた。体はゆらゆらと左右にぶれる。足が三本になったような、頭が根元からふたつに分かれたような、そんな感覚だった。この肉体の不気味さも、視界のあいまいさも、いまは心地よい。ぼくは夜を背に、静かに鼻歌を歌いながら物思いに耽った。
ふと立ち止まり、ポケットのなかからタブレットを取り出すと液晶が光り、一時間近く前に小夜からの着信があったことを示した。酔っぱらってからずいぶん長い時間が経っていたらしい。送られていたのは一枚の画像で、ベッドに備えられた卓にのった食事だった。多分、その日の晩ご飯だったのだろう。肉の少ないカレーライスとサラダと味噌汁らしきものだった。病室の照明はつけられていなく、暗闇のなかでカメラのフラッシュだけで照らされていた。ぼくは晩ご飯がまだだったことを思いだした。タブレットをしまい、ふたたび歩きだした。
従業員食堂はすでに閉まっている時間だった。ぼくは海岸沿いを通って南へ戻った。本道と側道が交わる交差点の脇に、観光客は見向きもしない小さな広場があった。石のベンチがひとつあるだけで、遊具もなにもない。そこでは案の定、屋台が一台、軒を広げていた。提灯の仄赤い灯りが闇夜に揺れている。何度か訪れたことがあって、年寄りの主人とは顔見知りだった。彼はぼくの顔を見るとにやっと笑い、虫歯で欠けた歯並びを見せつけた。ほかの客は、制服を着たタクシーの運転手らしきひとがひとりいるだけだった。その頃には冷たい外気が、ぼくの火照った体を冷ましてくれていた。体はふたたびひとつになり、胃袋は正常に脈を打っていた。中心に穴の開いた丸椅子に座って、ラーメンを注文した。むかしながらのオーソドックスな醤油味で、麺は若干伸びていたし、味は薄かったけれども、七百円を支払う価値はあると思えるラーメンだった。主人が丼を運んできた。彼の親指がスープに浸っていた。箸に手をつける前にラーメンの写真をタブレットで撮影し、画像を小夜に送った。すぐに返事が返ってきた。
《今日は従業員食堂で食べないのですか?》
ぼくもすぐに返事を返した。
《帰りに寄り道をしたから閉まっちゃってたんだ》
返事はなかった。ぼくは主人が語る熱海の今昔に、タクシーの運転手と二人で耳を傾けながら、その日の夜を過ごした。
🌕4
桧山さんと入れ替わる形で、新しいアルバイトが二人入った。ひとりは北から、もうひとりは西からやってきた。二人とも男で、二人とも若く、二人とも体毛が薄かった。船橋さんは仕事内容や作法の説明をぼくに一任した。二人の前でぼくの背中をぽんぽんと叩き、「このひとはベテランだから、全部このひとの言うとおりにして」と彼らに言った。
最初の日は一日中三人で行動した。二人ともこういった仕事は初めてらしく、一から説明する必要があった。ベッドシーツの交換、ロビーの清掃、喫煙所の水の補充、大浴場のブラッシングと鏡の水垢落としまで、実際にぼくがやってみせると二人ともすぐに飲みこみ、まもなくぼくが出る幕はなくなった。
昼休みには共に従業員食堂へ繰り出した。まかないをつくるおばちゃんを紹介し、食器の場所やいくつかのルールを教えた。白米とサラダはおかわり自由だと言うと、二人とも目を輝かせて喜んだ。ぼくらは同じテーブルで食事をした。二人はよくしゃべったし、よく冗談を言った。ふざけてぼくのことを〝師匠〟と呼んだ。
「師匠の働きっぷりは、とてもまねできるようなものではありませんね」ご飯を箸で口に運びながら背の高いほうがぼくに言った。「ゆったり動いてるように見えて、ぼくが顔を上げたときには作業を終わらせてるんですから。こういった仕事は長いんですか?」
この街にきて一年になる、とぼくはこたえた。
「どうりで動きがてきぱきしてるわけだ。大学を休学して飛び出してきたぼくとは大違いです」
慣れればだれだってこんなもんです、とぼくは言った。
「どうして休学したんですか?」黒縁眼鏡をかけた、耳のでかいもうひとりが尋ねた。
「恥ずかしい話なんですが、研究室の准教授と喧嘩してしまったんです。あまり東京から出たこともなかったんで、ほとぼりを冷ますついでに離れたところで暮らしてみようかと思って」
「それならせっかく東京を離れるんですし、こんなに近くじゃなくてもよかったんじゃありません? 九州や日本海側でも人手が足りない職場が山ほどあると聞きましたよ」
「まあそれはいいじゃないですか」背の高いほうはぼくに向き直った。「この近くに本屋ってありませんか? 駅前まで行けばなんでもあるのは知っているんですが、なかなか気軽に行ける距離じゃないですし」
近くに本屋はなかった。代わりに図書館の所在と、貸し出しカードのつくりかたを教えると、彼はぼくの言うことを熱心にメモ帳へ記した。
「なるほど。勤務証明書を会社に発行してもらうのと、身分証明書、それと寮の住所が必要になるんですね」
「図書館なんて小学生の頃から通ってませんよ」耳のでかいほうは退屈そうに言った。「興味のないことには指一本触れたくない性質なんです。本を読む時間があったら、パソコンかタブレットをいじってしまいます。漫画は読みますけどね」
「ぼくは小説はあまり読まないんです」背の高いほうはメモ帳を胸ポケットに仕舞って言った。「歴史が好きでしてね。こうしてしばらく住むことになったわけですから、熱海の街について詳しく調べてみたいんですよ。実はここへくる前にも一冊、日本の温泉宿について取りまとめた、分厚い本を読んできました」
「どんなことが書かれてました?」興味をおぼえてぼくは訊いた。
「いまでさえ客足は遠のいてますが、経済が弾けてた頃の熱海はすごかったみたいですよ。シーズンがくれば東京や横浜のほうからひっきりなしに大型バスが流れてきましてね。社員旅行の定番だったんです。いまじゃひとりも見ませんが、当時は着物を着た芸妓さんが街中を歩いてても珍しくありませんでしたし、大きいホテルになると食堂にスケートリンクが設けられていて、プロのスケーターが食事中の客の前で滑っていたんだとか」
「はあ」とぼくはため息を漏らした。
「いまの閑散とした街並みからじゃとても想像がつきませんね」と眼鏡は言った。
「まあ、栄枯盛衰は熱海に限ったことじゃありませんけどね。この国全体に言えることです」
「むかしの日本が異常だったんですよ」眼鏡がしみじみと言った。「なにしろ施設ごとに何億って金が平気で動いてたんですから。田舎へ旅行に行けば、経営難で打ち捨てられた廃墟がごろごろと転がってます」
「廃墟と言えば」背の高いほうが思い出したように言った。「このホテルの隣にももうつかわれてない建物がありましたね。ひと気もなく、鉄骨の上から幌がかけられていて、まるで解体作業をはじめる準備だけしてあるという有様でしたけど」
たしかにぼくが勤めるホテルの隣には廃墟があった。外壁は漆喰がところどころ剥げていて灰色の地肌が露出していた。左右の建物に圧迫され、上の空間に逃げ道を求めたかのような、六階建ての細長いつくりだった。強い風が吹くと幌が音を立ててうねり、漆喰の欠片がぱらぱらとアスファルトの上に零れ落ちた。入口のガラス扉からなかをのぞくとロビーが見えた。埃を被った洋風のソファ。テーブルの上には煤けたクリスタルの灰皿と木材の破片。受付のカウンターには錆びたペン立てや造花の花瓶などが取り残されていて、埃さえなんとかすれば、黒スーツのコンシェルジュが立っていても不思議ではない空気が漂っていた。
ぼくは船橋さんから聞いた話をそのまま彼らに伝えた。その廃墟はむかし、小さいながらも繁盛していたホテルだった。バブル経済の終焉からつづく経営苦の果て、ぼくがこの街を訪れる二年ほど前に営業を断念した。そのときにはすでに財政状況が逼迫していて、従業員の最後の給料も未払いのままグループは解散した。立地が悪く、建物の老朽化も進んでいたので買い手もなかった。地震などの災害が起これば建物はひとたまりもないだろう。周囲の安全と景観のために、本来ならば早急に解体しなければならないのだけど、当然そんなお金はどこにもない。あの規模の作業となると相当な金がかかるらしい。一度は熱海市が費用を捻出しようとしたみたいだが、人通りも少ない街の寂れた一角ということもあって、それもどこかでうやむやになった。責任者はみないずこかへ消えた。追及される人間はどこにもいない。建物を覆う鉄骨や幌は、危ういことが起きたときに通行人に直接打撃が及ばないために備えた、最低限の保険のようなものだった。
二人ともぼくの話を興味深そうに耳を傾けていた。背の高いほうは言った。「ここいらは街のなかでも客を呼ぶのが難しいんでしょう。駅からこれだけ離れていては無理もありません」
耳のでかいほうは首を傾げた。「しかし、もしも崩れた石材が通行人の頭の上に落ちてきた、なんてことが起きたら、いったいだれが責められるんでしょうね」
その後、二人はいまの熱海についてぼくに尋ねた。でもあいにくと、ぼくに話せることはたいして多くもなかった。彼らは美味しい食事がとれる飲食店や、若い女の子と出会える居酒屋がどこか聞きたがった。ところがぼくに話せることといえば、海岸線を横切るうみねこの翼に下から見るとどんな模様が描かれているかとか、毎朝大浴場で見かけるおじいさんが入れ歯を備えつけのボディソープで洗うこととか、熱海図書館の漫画本コーナーに新刊が追加されたとか、近隣の美術館で金箔や螺鈿細工の企画展が開催されてるとか、従業員食堂のおばちゃんが先日の休みに孫と小田原のデパートまで買い物に行ったとか、そんなのばかりだった。訊かれでもしなければそんな話をするはずもない。
でも知っていることはなんでもこたえた。そのほとんどが小夜や船橋さんに聞いた話だったけれど。
二人ともよくしゃべっていたのに、ぼくよりも食べ終わるのがはやかった。ぼくは片づけについて口で説明したけど、二人は空の食器を前に、あたたかい麦茶を飲みながら、ぼくが食べ終わるのを待っていた。
「テキサス、ですか?」と背の高いほうはくつろいだように頬杖をついて問いかけた。
「ええ」耳のでかいほうは大仰に頷いてみせた。「いわゆるポーカーの一種ですね。テキサスで誕生した、比較的新しいルールです」
「すると、プロのプレイヤーなわけですか」背の高いほうはほとんど畏怖の眼差しで耳のでかいほうを見上げた。
「そんなに大層なもんじゃないですがね。オンラインでプレーするので、タブレットとインターネット環境、それに賭けるための資金があれば、だれでも参加できます」
「だれでも参加できると言っても、だれもが勝てるわけではないでしょう? それで食い扶持を稼げるというなら、たいした技術ですよ」
耳のでかいほうは照れたように、それでも表情は崩さないように、眼鏡の鼻あてを親指でずらした。「ほんとうにたいしたことじゃないんですよ。取りかえしのつかないミスをして、結果的に運に救われたことだって何度もあります。ぼくはむかしから、なにかと運がいいみたいなんです」
「世界中の猛者たち相手に勝ちつづけられるほどですか?」
「ええ、実際そうなんですよ」耳のでかいほうは大真面目に頷いた。「もちろん、運だけで勝ってきたともいいませんが」
「まれにいる強運の持ち主というわけですか」背の高いほうがその場の空気に同調した。
「そんな具合で、オンラインカジノでも、なんとか黒字で儲けを出せているんですよ」
「しかし、それならどうしてこんな職場を訪れたんでしょう?」背の高いほうは周囲——古くなった壁、油まみれの換気扇、にぎやかに笑い声をあげている従業員たち——を見まわし、最後にぼくの顔色をちらっとうかがった。「言葉は悪いかもしれませんが、家にいながらお金を稼げるんなら、わざわざこんなところまで働きにこなくてもよさそうなもんですが。余計な肉体労働なんて、だるいだけじゃありません?」
「ぼくはこの仕事、嫌いじゃありませんよ」耳のでかいほうは、なぜだかぼくのほうを向いて言った。「ずっと体を動かしてないと、脳の働きだって停滞してしまいますからね。ほどよい運動をして、夜にはタブレットと向かいあうと、いつだって調子がいいんです。それに・・・」彼は湯飲みに口をつけながら淡々とつづけた。「いまは持ちあわせもあまりないんです。お金が入ってくると同時に、流れるようにつかってしまうんですよ。ネットショッピングでもしてれば、あっというまになくなります」
「お金は大事ですよ」背の高いほうは諭すように言った。「なにをするにせよ、お金はかかってしまいます。飲み食いするにせよ、旅をつづけるにせよ」
「ええ、ほんとうに。お金は大事ですね」耳のでかいほうは頷いた。「はやいところ稼いで、カジノの資金にしなければ」
共に食器を洗っている間も二人はしゃべりつづけていた。ぼく相手にも気軽に冗談を言ってきて笑わされた。ぼくらの後ろで流しに並んでいた、受付の若い女性たちともすぐに打ち解け、声を上げて笑いあっていた。彼女たちは小夜の同僚だったけど、ぼくはほとんど話したことのないひとたちだった。目があうと小夜の容体はどうですかと訊かれたので、当たり障りのない返事をしておいた。それならよかったです、と言って彼女たちは胸をなで下ろした。
翌日からぼくは従業員食堂で昼ご飯を食べなくなった。べつに彼らのことがいやになったわけではない。ただぼくはむかしからしゃべるのや、ひとの話を聞くのが苦手だった。すぐにどうしようもなく疲れて、眠くなってしまうのだ。小夜に誘われるまでは、いつもひとりで食べていた。昼食代はかかってしまったけど、ぼくにはそれが必要だった。あの頃に戻る。ただそれだけのことだ。
昼になると自分のロッカーから、前日にパン屋で買った菓子パンの入ったビニール袋を取り出し、従業員用の出入口からホテルを出て海に向かった。ホテルの制服は着たままだ。駐車場を通って防波堤まで歩き、釣り人たちから少し離れたところに腰かけて、海を眺めながらランチを食べた。タブレットをいじりながら食べることもよくあった。少なくとも二日に一度は、この時間に小夜からのメッセージが届いた。彼女にはぼくの暇な時間帯がわかっていた。ランチはあんパンのこともあれば、ケチャップのたっぷりかかったホットドッグを食べることもあった。飲みものは自販機で買った緑茶かウーロン茶を飲む日が多く、お金がないときは空のペットボトルに水道水を入れて飲んだ。時々は釣り人から、おにぎりやお菓子を分けてもらったりした。しゃべった記憶もないのだが、ぼくの好きな梅干しをタッパーに入れて渡してくれるひともいた。彼らの間でぼくは、ちょっとした有名人だったようだ。
🌕5
十二月も終わりに近づくと、仕事はおおいに忙しくなった。どこの学校も冬休みに入り、子供の宿泊客を見かける機会が増えた。年末はぼくらのホテルでさえも、満室で予約が取れない有様だった。大浴場はひとであふれかえったし、駅前の方の商店街は人いきれで歩くのが困難なほどだった。
ぼくの仕事は朝の十時にはじまり、夕方の四時には終わった。忙しい日は一、二時間ほど残業をすることもあったけど、前日の宿泊客が少なければ、いつもよりはやく帰れる日もあった。空いた時間はよく街中を散歩した。坂の中腹にある古い図書館には頻繁に通ったし、建造物から離れ、もっと内陸へ足を伸ばすこともあった。急な坂をのぼってゆくほどひとはまばらになり、海岸から三十分も歩けば、街では見られなかった雪が木々の根元に積もっていることもあった。少し前まで山肌を染めていた紅葉は残らず散っていたけれど、街中の街路樹の葉は粘り強くしがみついていた。寮の付近を流れる川の上に羽虫が湧いているのをよく見かけた。
クリスマスに近い日だったと思う。昼近く、小夜の病室を訪れるとベッドは空だった。ぼくはいつもの定位置に座り、持ってきた本を膝の上に広げた。古い小説で、図書館の閉架書庫の見学会の際に借りたものだった。昼ご飯をまだ食べていなかったので、鞄からコンビニの袋に入ったサンドイッチを取り出し、それを右手で口元に運びながら、膝の上で本を開いた。鉄色の雲が低く、風のない日だった。レースのカーテンは開け放たれていて、常に視界の隅に映る寒空が、手に触れられそうなほどに近く感じた。
十五分も読んでいると、集中力が切れてきた。ぼくは本を脇に置き、放ってあったサンドイッチの包装を鞄のなかに押しこんだ。立ち上がり、伸びをした。べつに眠くもないのに大きな欠伸が出た。実に暇だったので、流し台の横に立てかけてあったワイパーを拝借し、部屋の掃除をはじめた。掃除は小夜自身がやっていると聞いたけれど、床の隅にはところどころ埃が溜まっていた。彼女にはあれでがさつな面があるのだ。雑巾を流しで濡らし、机や卓や冷蔵庫の上を拭いた。テレビの表面の埃は、もう一枚の雑巾で乾拭きした。花瓶の花を抜いて古くなった水を入れ替えた。ついでにトイレも綺麗にしてしまおうと顔を上げると、律子さんがポケットに手を突っこみ、微妙な表情で音もなく立っていた。
「一体全体、あなたはなにをしているの?」と律子さんは微妙な声色で言った。美人がそんな声色をつかうと、不機嫌そうに聞こえなくもない。
「暇だったから掃除をしているんだ」
「そんなことは見ればわかるわよ」律子さんは濡れた雑巾や、ベッドに立てかけたままのワイパーを一瞥した。「わたしが訊いてるのはそんなことじゃないの」
ぼくだって訊かれていたのはそんなことじゃないとわかっていた。
「どうしてここにいるの?」律子さんは眉間にしわを寄せて言った。「今日は検査の日だから、この部屋は一日中無人になるって、あの子のほうから連絡がきたでしょう?」
たしかにそんなメッセージが昨日の晩にきた。ぼくはちゃんとそれに目を通したし、ちゃんと飲みこんだ。
「習慣っていうのは、そう簡単に変えられないものなんだよ」とぼくはこたえた。
「それにしたって」律子さんはまだなにか言いたそうにしていたけど、諦めたように天を仰いだ。
ぼくは乱れた布団のしわを伸ばし、丁寧に広げた。柑橘系の小夜の香りが舞い上がり、それを胸いっぱいに吸いこんだ。
「これからトイレ掃除をしようと思うんだ」作業をしながら律子さんに話しかけた。「いっしょにやるかい?」
彼女は絶望の表情を浮かべた。「あなた、それ本気で言ってるの? そんなことしたら次にあの子に会ったとき、ひどい目にあうわよ」
「そうなの?」
「一人暮らしの女の子がつかってるトイレを、男が勝手に掃除するなんて」
ぼくは小夜が便座に座っている場面を想像した。「なるほど」電気ケトルを手にとって流しに向かった。「コーヒーを飲む?」
「いらないわ。妙な予感がして、ちょっとの間、様子を見にきただけだから」
ケトルに水をそそぎ、戻ってスイッチを入れた。顔を上げると律子さんは先ほどの場所から動いていなかった。視線は宙に浮いていて、なにかを言いたいわけでも、なにかを訊きたいわけでもわけでもなさそうだった。お湯が沸くまで、ぼくも黙っていた。マグカップを借り、インスタントのコーヒーを淹れると、それが柑橘系の香りをかき消した。
「検査は何時頃に終わるの?」息を吹きかけてコーヒーを冷ましながらぼくは尋ねた。
「夕方まではかかると思う」
ぼくは少し躊躇ってから訊いた。「痛むのかな?」
律子さんは微笑んだ。綺麗な髪が鈴のように揺れた。「心配しなくていいのよ。採血をするときに、注射でちくっとするくらい」
「ふうん」
「小夜と二人でいるとき、そういった話はしないの?」
「病気を想起させるような話はいやがるんだ。彼女自身が語りたくなったときは耳を傾けるけど」
「あの子らしいわね」
ぼくは壁に寄りかかり、コーヒーをすすった。律子さんの視線が肌に刺さる。初めて会ったときから感じていたのだが、彼女には、これ以上このひとを悲しませたくないと思わせるなにかがあった。ぼくはむかしから、ひとの涙を見ても感情に波ひとつ立たない性質だが、おそらく彼女は例外だ。それゆえに、どうしても彼女の視線を避けなければならないときもあった。
「お祭りに、あの子を誘ったらしいわね?」律子さんは言った。
「うん。でも断られちゃったよ」
「ほんとうはあの子も行きたかったのよ。でもなかなか難しいの、わかるでしょう? 出先で体調を崩したりするかもしれないし、懸念材料が多いのよ」
「大丈夫だよ。わかってるから」ぼくは微笑んでみせた。
「この症状の厄介なところは、これっぽっちも予測がつかないことなのよ。最近は比較的安定してるけど、それもいつまでつづくかわからない。口には出さないけど、あなたの誘いを断ったことを気に病んでるみたい」
「口には出さないのに、どうしてわかるの?」
「表情に出てるのよ。とてもわかりやすいの。今度また誘ってあげて。きっと喜ぶわ」
「今日はわざわざそれを言いにきたのかい?」
「偶然よ、偶然。あなたがきてるなんて思わなかったもの」
ぼくは少し考えてから言った。「まったく気にしていないと言えば嘘になるけどね。ただぼくが急ぎすぎたというだけの話なんだ。彼女のペースを乱してしまって、怖がらせちゃったんだよ」
律子さんは首を傾げてこちらを見た。ぼくはコーヒーの表面に映った自分の顔を眺めた。
その後、しばらく雑談してから律子さんは仕事に戻った。トイレ掃除は禁じられてしまったので、ぼくは読書を再開した。夕方になって帰る前、ぼくがきた旨を机の上に手書きのメモで残した。自分の手でなにかを書きたい気分だった。文字を書くのは久しぶりで、ずいぶん下手くそなものになった。だれもいない病室をあとにするのは初めてだったので妙な気分がした。立ち止まって部屋を見渡すと、家主不在のベッドが眼間を覆った。そいつがぐるぐると螺旋を描き、ぼくの肉体は吸いこまれるように、その中心へと落ちていった。不意にパニックに襲われて、足腰に力が入らなくなった。壁にもたれかかり、ずるずると滑って床に尻もちをついた。抱えていたヘルメットが、音を立てて手の届かないところまで転がっていった。どうやらする必要のない、余計なことをしてしまったみたいだ。しばらく立ち上がれず、立てた片膝に頭を休ませ、無為な時間を過ごした。こんなところを律子さんに見られなくてよかった。取りかえしのつかないことになっていただろう。
ぼくは深く息を吸い、吐いた。からっぽのベッドなど、この世からなくなってしまえばいいのに。体に痛みはなかった。その代わり、水のなかにいるみたいに自分の動きが重く鈍く感じる。立ち上がって、あらぬ方向を向いたヘルメットを拾い、「また火曜日にくるよ」とだれにも聞こえない声でつぶやいて部屋を出た。
次に小夜の見舞いに訪れた日、彼女は珍しくぼくに近寄ることを許してくれた。ぼくはパイプ椅子をベッド脇に引きずっていってそこに座り、病院のロビーで借りてきた『ウォーリーをさがせ』を、彼女にもよく見えるように広げた。彼女がやろうと言い出したので、ぼくが下へ行って借りてきたのだ。ぼくらはどちらがよりはやくウォーリーを見つけだせるか競いあった。小夜はぼくが知っているほかのだれよりも、ウォーリーを見つけるのがうまかった。華奢で壊れやすそうな体を幾分こちらに傾け、ぼくがページをめくると視線を稲妻のようなはやさでぎょろぎょろと動かし、星の数ほどもあるダミーのなかから五秒とかからず本物を指さした。彼女にこんな特技があることを知らなかった。二、三ページもめくると、ぼくから熱量は失われてしまった。拗ねてしまったのだ。ぼくは彼女を糾弾した。最初からウォーリーの位置を知ってたんだろう。読んだことがあるんだろう。彼女はこの本を開くのは今日が初めてだと言った。ぼくは彼女が嘘をついてると思ったし、そう言った。彼女は怒って『ウォーリーをさがせ』をぼくの手から奪いとり、部屋の隅に向かって投げつけた。結局、ぼくが彼女のそばにいれた時間は五分もなかった。パイプ椅子を引きずり、すごすごと自分の定位置に引きかえした。
午後になって律子さんが検温に訪れた。彼女はいつものように小夜の隣に椅子を広げ、腰かけた。手を伸ばせば、小夜の太腿に触れられる距離だ。それは先ほどまでぼくがいた場所だ。ぼくの場所のはずだ。小夜の隣に座ることを許されないのはぼくだけだった。二人が笑いあっているのを、世界の端っこから眺めていた。律子さんはぼくらの間に流れる不穏な空気に気づいたみたいだった。なにがあったのかぼくらに尋ね、小夜がそれにこたえた。話すにつれて、ふたたびさっきの怒りが鎌首をもたげてきたらしい。口調は徐々に熱を帯びた。小夜は身振り手振りを交えてぼくを非難した。ぼくに人差し指を突きつけ、「あいつがわたしを嘘つき呼ばわりするのよ!」と叫んだ。ぼくはなにも言いかえさず、彼女の目を静かに見つめ、黙って耐えた。その態度が、ますます彼女の怒りに拍車をかけたようだ。もはや物事は収拾のつかない境界線を越えてしまっていた。やれやれ、と律子さんに向かって肩をすくめてみせ、荷物をまとめて立ち上がった。「また土曜日にくるよ」と小夜に言うと、彼女が枕をこちらに投げつけるような素振りを見せたので、ぼくは小走りにその場から逃げ出した。
「今日はずいぶんと機嫌がいいね?」
金井さんとカラオケボックスの清掃していた。ぼくは雑巾を片手に、灰皿の中身をごみ袋に空けていた。
ぼくは顔を上げて金井さんを見た。「そう見えますか?」
彼はガラス製のテーブルを拭く作業をやめ、こちらに注意を向けた。表情が柔らかい。「うん。なにかいいことでもあった?」
「昨日、友人と喧嘩をしたんです。それが原因かもしれません」
「喧嘩をしたのに機嫌がいいの?」と訝しそうに訊いてくる。
「錆びついて止まっていた歯車がふたたび動き出したような気がしたんです。そういう感覚って、時々ありませんか?」
金井さんはぼくの言った言葉の意味がわからないみたいだった。ぼくは作業に戻った。おそらく口元に、にやにやと笑みを浮かべながら。
あわただしい雑事に追われるようにして、ぼくの年末年始は過ぎていった。忙しさは年が明けても十日ほどはつづいた。少しずつ観光客の数は減っていき、熱海の街はふたたび静かな時間を取り戻した。相変わらず街はあたたかく、外は寒かった。ひとの流れも落ち着いた頃、ぼくは山中に鎮座する神社まで、寮から歩いてお参りに行った。木々に囲まれた敷地に入ると空気はより冷たく、静謐になり、日常から切り離されたような気分を味わった。
特に目的もなく境内を歩いた。社務所に陳列されたお守りを眺め、日傘に覆われた休憩所を通りすぎた。着物を着た初詣らしき観光客が何人か、数えるほどいた。白衣と袴を身に着けた神社の職員が、通路の上の落ち葉を箒で集めていた。
敷きつめられた砂利を踏みしめ、石段を登って賽銭箱に近づき、ポケットから財布を取り出して、なかに入っていた小銭をすべて格子の隙間に投げ入れた。せいぜい六百円程度だったと思う。札の持ちあわせはなかった。次の給料日はいつだっけ? 銀行にはまだ残高があるかな? などと考えながら街まで響き渡れと綱を引っぱって鈴を鳴らし、合掌して慣れない祈りを捧げた。世界中から戦争がなくなれ、と願おうかとも思ったけど、地図で見ただけの外国のことはよくわからなかった。ぼくに自覚できるのは、ぼくの知っている一番小さいものと、一番大きいものくらいだった。その二つの隔たりはあまりにも大きすぎて、ぼくごときには、どうしてもそれらがひと繋がりであるようには思えなかった。街へ帰り温泉に浸かると、日常へ戻ったのだなという実感が湧いた。走り、働き、ひとりで食事をし、メッセージの返事を考え、休日はバイクを駆り、夜はゆうき幽鬼のようにさまよう。繰りかえし、繰りかえし、繰りかえす。この生活は、そう簡単には終わってくれない。
結局、祭りには行かなかった。
🌕6
日照時間が延び、気温が上がっても、温泉目当ての客がいなくなることはなかった。それが日本人の血の深くに刻まれた習慣だとでもいうのだろうか。平日でも一定数の宿泊客がいた。仕事は余裕があったけれど楽すぎるわけでもなく、お金は稼げなくても、ぼくにとってはそれくらいがちょうどよかった。
冬が終わっても、ぼくの生活は相変わらずだった。だが周囲は違う。小夜の同僚だったフロントの女性たちの何人かは、日光にあるという同じ会社が経営するホテルへ異動となった。船橋さんは仕事の内容が変わったわけではないけれど、出世して役職名は変わったらしい。本人は、たいして給料も上がらないのに責任だけが増えていく、とぼやいていた。新人アルバイトのうち背の高いほうはすでにやめていた。ある朝、連絡ひとつなく出勤してこなかったことを不審に思った船橋さんが寮の個室をのぞいてみると、布団は綺麗に畳まれ、荷物は跡形もなく片づけられていた。書置きもなにもなく、窓枠の上に部屋の鍵が置き去りにされているだけだった。船橋さんがそれほど憤慨しなかったのは、渡りのアルバイトがある日突然、言伝もなく姿をくらますのはそれほど珍しいことでもなかったからだ。
でも実はその前日の夜、ぼくは彼と会っていた。誘われて従業員食堂でいっしょに晩ご飯を食べたあと、海沿いを並んで歩いた。街灯に照らされ、ぼくらの影が遊歩道に伸びていた。しばらく他愛もない話をしていた。ビーチに辿り着き、砂浜に足を下ろして海を眺めていると、突然、彼は声を上げて泣きじゃくりはじめた。驚いてなにがあったのか尋ねてみると、仕事をつづけていくのが苦痛で仕方ない、と彼は嗚咽を漏らしながら告白した。たしかに以前から愚痴をこぼしてはいたのだ。問題が起こって船橋さんが金井さんを怒鳴りつけるたびに、彼は身の縮むような想いをしていたらしい。大きな声を出されるのが苦手で、脇で聞いているだけでも、自分が怒鳴りつけられているような気分になってしまうのだ。船橋さんが金井さんを怒鳴りつけるのは、二人が揃って出勤する日ならほとんど毎日のことだった。アルバイトをはじめた当初から、背の高いほうは心を悩ませていた。仕事に通いつづけるうちに心労は積み重なり、先日から腹痛と下痢が止まらなくなった。便器にしがみついたまま一晩を過ごすこともあった。つらいつらい。死にたい死にたい。
ぼくは彼が落ち着くのを待ってから、近くの自販機へ缶の緑茶を買いに行った。精神状態がひどいときはあたたかいお茶に限るという持論があった。戻って一本渡すと、彼は照れたように取り乱したことを詫びた。ぼくらは波打ち際を歩いた。狭いビーチだったのですぐに端っこまで辿り着いた。靴に入るのも構わずに砂を撒き散らしながら歩いていたら、隣の背の高いほうもそれを真似しはじめた。暗闇の向こうにはほかにも何人か観光客の人影があった。折りかえし、半ばまで進んだところでぼくは立ち止まった。
冷たくなった缶を傾けながら、ぼくは彼の望む言葉を言ってやった。彼は表情には出さなかったけれど安堵していた。それで彼にとってぼくの利用価値はなくなったようだった。そろそろ寮へ帰るとぼくが言うと、もう少しひとりで散歩していくと彼は言った。別れ際にぼくに投げた感謝の言葉は本物だったと思う。鍵はわかりやすいところに置いていけばいい、とぼくは言って、きた道を戻った。
変わったのはなにもひとの出入りだけではない。二月から大浴場に備えつけられていたボディソープとシャンプーが、安いものから高いものへと変わった。まったく泡立たない、と客からクレームが入ったのだ。古いボトルと新しいボトルを入れ替える作業で、その日は残業だった。客室には女性用の化粧水が新たに置かれるようになったし、荷物用のエレベーターは故障で三か月ほどつかえなくなった。こうして日々の作業には微々たる変化が訪れ、ぼくのパターン化していた生活に小石を投げ入れてきたけれど、その波紋はじき直に収まる程度のものだった。ひとの出入りは相変わらず流動的だった。知っている人間が減り、見知らぬ人間が増えた。元々ぼくに声をかけてくる人間は、まだ小夜がここに居場所を持っていた頃に知りあったひとたちだった。変わらぬ関係は徐々に減りつつあった。
🌕7
二月の終わり、昼休みになって海へ行こうとロッカーの前で準備をしていると、船橋さんに声をかけられた。
「お昼に行くところで悪いね」
ぼくはまったく問題ないと言った。
「実は、明日からまた新しいアルバイトの子が勤務しはじめるんだよ」と彼は言った。「今日の夕方に着く予定なんだけど、寮を案内をする予定だった人間が急用で早退したんだ。悪いんだけど相沢くん、仕事が終わったらそのひとの案内を頼めないかな? 本来ならわしがやりたいところなんだが、寮住まいでもないから詳しい説明をしてやれないんだよ」
「大丈夫ですよ。ほかに予定もありませんから」
「きっと三十分くらいはかかるだろうね。その分の給料は、ちゃんと払わせてもらうからさ」
「わかりました」ぼくは頷いた。
午後の三時に仕事は終わった。制服から着替え、事務室を訪れると、そこではすでに船橋さんがぼくを待っていた。彼はデスクやパソコンの列の奥からぼくへ手招きし、彼の傍らに立っていた男性を紹介した。
「こちらがお昼にしゃべった新人さんだよ」
よほど目が悪いのだろう。どぎついレンズの眼鏡をかけたひとだった。間の空いた双眸がレンズ越しに拡大して昆虫のように見えた。背丈はぼくと同じくらいで、白髪がごわごわした髪のなかに斑点のように浮いていた。床にこぼした抹茶のような色あいをしたジャケットは、縫い目が解れてまくっていた。肩にかけられたボストンバッグには、着替えや生活用品が詰まっているのだろう。重さで紐がぴんと張っていた。ズボンのポケットには汗で持ち手が変色したせんす扇子が突っこまれていた。
お互いにお辞儀をして、彼はぼくに名前を告げたのだけど、ちょうどそのとき、ぼくの背後で物音がし、気配を感じて注意が逸れた。ぼくのすぐ近くのデスクで、糊のきいたスーツを着た女性が席に着き、パソコンの電源をつけた。向き直って注意を戻したときには遅く、彼の名前は聞きそびれてしまった。かろうじて『シロ』という単語は耳に残ったけど、『シロなんとか』さんなのか、『なんとかシロ』さんなのかわからない。彼はすでにぼくの名前を知っていた。ぼくは船橋さんから個室の鍵を受けとり、彼を連れだって外に向かった。
ぼくの住む寮は車道を挟んでホテルの向かいに建っている。コンクリートの外壁は塗装もなにもされてなく、壁面をよくよく見てみると、おそらく骨組みにつかわれたであろう錆びついた釘がところどころ飛び出していた。だれもがひと目でその古さを見抜けてしまえそうなつくりだ。三叉路の付け根という立地のせいで、上から見下ろせば建物は鋭利な三角形をしていた。寮の入口があるほうの道路は、その奥のドラッグストアに用がある人間でもなければ通らない。
正面のガラス扉を開いて抑え、シロさんを黴くさい屋内へいざな誘った。玄関を入ってすぐ横の壁に、各部屋の郵便受けが取りつけられている。厄介なのは扉と郵便受けの間隔があまりにも狭すぎることだ。外から玄関扉を押して開けば、郵便受けの頑丈な角にガラスの面が平気で激突する。ガラスに走るひび割れを隠すように、粘着力を失いかけたガムテープが縦横にへばりついていた。まだひびの入っていない無事な箇所には、濃いマジックペンで書かれた張り紙が、外側に向けて貼られていた。『引いて開けろ』
足元に散乱していたプラスチックのバケツを足で退かし、奥へと導く。上階へとつづく階段の手前、暗がりの向こうの空間にコインランドリーが三台並んで置かれている。待ち人のためにスポンジの飛び出たパイプ椅子が一脚、角に広げられていた。その横の棚には、いつの時代のものかわからぬふやけた漫画が二冊のみ、倒れた状態で置かれていた。表紙は擦り切れて、タイトルは読めない。たしか釣りを題材にした漫画だったと思う。洗濯の待ち時間にこれを読んでいた人間を、ついぞ見かけたことがない。ぼくだって触れる気にならなかった。
洗濯機を三十分まわすために百円玉が一枚犠牲になった。当然ながら、居住者はできるだけ多くの洗濯物を一度に洗おうとするので、大概の場合、三台のうちの一台には『故障中』の張り紙が貼ってあった。さらには上の棚にのせられていた乾燥機をまわそうものなら、十分でもう一枚の百円玉を奈落の底へ突き落とさなければならない。この寮へ入居する人間がまっ先に用意するもののひとつが、部屋干しをするためのハンガーだった。まったく。従業員であるぼくらから搾りとってどうしようというのだろう。シロさんに諸々を説明していると、彼はぼくから離れて漫画の一冊を手にとり、ぱらぱらとページをめくりだした。その表情はさも興味を抱いてるとか、懐かしいものを見ているといったふうの雰囲気だった。ページをめくっては頷き、レンズの奥の虹彩を小刻みに動かす。聞いているのか聞いていないのかわからなかったけど、ぼくは説明をつづけた。一階の案内はこんなものだったので、彼を二階へ連れていこうとした。
「その漫画は部屋へ持っていっても大丈夫ですよ」いまだページから顔を上げない彼を見てぼくは言った。「どうせここに置いてあったって、だれも読みやしないんですから」
それを聞くとシロさんは漫画本をぱたんと音を立てて閉じ、元の場所に戻した。ポケットから扇子を取り出し、どうしてここはこんなにも暑いのだろう、とでも言いたそうな顔でぱたぱたと扇ぎはじめた。
シロさんの部屋は二階の奥まった廊下の先にあった。同じ階にあるぼくの部屋は、いびつな三角形をしていたけれど、こっちの部屋はまともな形だった。間取り以外は概ねぼくの部屋と変わりなかった。エアコンは建物のつくり上、取りつけられないらしく、おもちゃのような電気ストーブと扇風機で暑さや寒さをしのぐ。内壁は外壁と変わらず、粗忽で味気ない灰色だった。床のカーペットは歴代の居住者がこぼした染みの数々で、凄惨な状況だった。机や椅子はなく、布団が一式、隅に畳まれているのみ。それを二枚も並べて広げれば、部屋中の足元を埋めてしまうほどの広さだった。
「布団のシーツやピローケースは、ホテルのリネン室から自由にとってください。ご自分で洗われても、新たなものを持ってきて交換しても結構です。テレビはありませんので、もし見たければ従業員用の待合室にあるものをご覧になってください。夜の十二時に鍵をかけられるので、電源のオンオフをお忘れにならないことのみ留意していただければ、その時間まで自由に出入り可能です。ぼくの部屋は窓の建てつけが悪く、半分までしか開かないのですが——」ぼくはひとつしかない窓へ歩み寄った。「この部屋は大丈夫みたいですね。気をつけなければならないのは、庇がないので、雨の日に開けると部屋のなかが水浸しになってしまうことです。それから掃除をしたいときには廊下に置いてある掃除機をつかってください。もっとも、二階のはずいぶん前から故障しているので、三階にあるものを持ってきてつかってください。ぼくが以前働いていた職場では、社員の人間が定期的に部屋が汚されすぎていないかチェックしにきましたが、ここではそんなことは起こり得ません。掃除に関してとやかく言われることはないので、神経質になる必要はないです。四、五、六階は女性寮になっているので立ち入りは禁止とされてます。煙草はお吸いになられますか?」
彼は首を振った。
「上階には立ち入れませんが屋上は開放されてます。階段をつかってください。この建物ではそこが唯一、喫煙の許される場所ですので、一応おぼえておいてください。それからご覧のとおり、トイレや流しは各部屋についているわけではないので、扉の外のものを利用してください」
ぼくは彼を部屋から連れ出し、共用トイレの案内をした。便器は和式で、壁際に積み重ねられたトイレットペーパーの芯には、昨年の蜘蛛の巣が張られていた。「説明は以上になります」ぼくはシロさんに彼の部屋の鍵を手渡した。「なにか質問はありますか?」
ここでシロさんは扇子で扇ぐのをやめ、口を開いた。「屋上からの景色は綺麗ですか?」
「ええ。よかったら見に行ってみます?」
階段をのぼって、屋上へとつづく鉄の扉を開いた。空気の塊がぼくらの脇を吹き抜けていく。ここからの眺めは馴染み深い。街の外れに位置しているため、高いところから街中を見下ろす形になる。ぼくらのホテルが若干陰になったけど、その向こうには海が見えた。
開いていた扇を閉じて、シロさんは転落防止の柵へ歩み寄った。ぼくは少し離れたところから彼の背中を見ていた。邪魔になりそうだったら自分の部屋へ戻ろうと思っていたけれど、そういうわけでもなさそうだった。ぼくらはしばらく無言で海を眺めた。シロさんのジャケットの色が、夕方の海の青みとひとつに溶けあわさりそうに見えた。そのときのぼくには、それが限りのない調和に思えた。ああ、この淡い感覚にはおぼえがある。いつか溺れた夢で抱いたものだろうか。
やがてシロさんがこちらへ向き直り、戻ってきた。途中でなにかを踏みつけたみたいで、ぱきんという小気味よい音が響いた。彼は屈みこんで自分の踏んだものをたしかめた。ぼくも近づいた。
それは親指ほどの大きさをした蟹の甲羅だった。手足はなく、色は抜け落ちている。シロさんはそれを指でつまみ上げ、不思議そうに眺めた。
「鳥が食い散らかしたあとに残したものかもしれません」ぼくは前屈みになっていっしょにそれを見つめた。「散歩をしていても時々見かけますよ。鋏だけだったり、脚だけのこともあります」
「蟹が目につくところで歩いているんですか?」
「ええ。海沿いの街ですから。この間は、この寮の二階のトイレで生きているのを見かけましたよ。階段を通ってくるんだか、排水管を泳いでくるんだかわかりませんが」
シロさんはしばらく観察をつづけたあと、立ち上がってそれをジャケットの隙間に突っこんだ。
部屋に帰って一時間ほどのんびりしてから、外の空気を吸いに行こうと思って扉を開けた。目の隅でもぞもぞと動く影があったのでそちらを見ると、トイレの前でシロさんが腰を曲げた姿勢で床を調べていた。ぼくは一瞬だけ迷ったあと、近寄って声をかけた。
「どうかしました?」
シロさんは拡大された目でぼくを見上げた。
「探しているんですが、なかなかみつかりません」と彼は言って、またなにかを探す作業に戻った。
「探しているって、なにを?」思わずぼくは問いかけた。
「蟹ですよ」
ぼくは彼の後頭部をじっと見つめた。ぼくの存在を気にも留めてないようだった。しばらくしてからぼくは言った。
「風邪はひかないでくださいね」
それから二十日ほどが経った。防波堤に座って、空と海の狭間を眺めながらランチを食べていた。雲の多い日で、釣り客はまばらだった。少し古くなったクリームパンにかじりついていると、遠くで防波堤によじのぼって立ち上がる人影を見つけた。シロさんだった。ぼくに気づいてるのかどうかはわからなかった。彼は細い幅の上でバランスをとって歩きながら、ぼくのいるほうへ近づいてきた。
「お疲れさまです」先にぼくから声をかけた。昼休みにこんなところへくる奴はぼくしかいないはずだった。
彼は頷いた。「いつもひとりで食べているのですか? 相沢さんが外へ向かうのを見かけました」
ぼくは目を瞬いた。おかしくはないはずなのだけど、彼がぼくの名前を記憶していることに違和感をおぼえたのだ。
「ええ。ぼくはひとりで食べます」ぼくは言った。「周囲にひとの気配があると落ち着かない性質なんですよ」
「そうだったんですね。食堂でお会いしたことがないので、いつも気にはなっていました」
そう言って彼はぼくの背後を通りすぎ、両手を左右に広げながら歩きつづけた。彼が防波堤の端に建つ、ひとの背丈ほどの灯台まで進み、引きかえしてくるのを、ぼくは手を止めたまま呆けたように見つめた。やがて彼はぼくから少し離れたところで立ち止まった。ぼくは海に向かって座っていたのだけど、彼は反対のホテルや街があるほうを向いていた。ぼくはパンを食べるのを再開した。
「駐車場に停めてあったバイクは相沢さんのものだと聞きました」しばらくの無言のうち、立ったまま彼は言った。
唐突なしゃべりには慣れている。ぼくはそうだと言った。
「カバーがかけてあったのでわかりませんでしたが、中型ですか?」
「はい。二五〇ccです」ついでにメーカーと車種も教えてやった。彼は得心したように頷いた。
「二五〇ccではそれ以上の性能は望めませんよ」と彼は言った。
「ええ。おかげで安くない買いものになりました」
「大丈夫です。法律が変わって四気筒の生産がされなくなりましたから、あと数年もすれば、相沢さんのホーネットの価値もぐんと上がっているはずです」
「ほう」ぼくは自分のバイクのことなど、ろくに知らなかった。摩耗した部品はバイク屋に持っていけば交換してくれたし、ぼくのバイクは滅多に故障しなかった。知識など必要なかったのだ。
「むかしはわたしも毎日のようにバイクを乗りまわしていましてね」彼は淡々とつづけた。「実家のガレージには、いまでもニンジャの七五〇ccが置いてあります。もう弟に譲ってしまったやつですがね。わたしは根っからのカワサキ派だったもので。弟を誘って、そいつでよく山道のワインディングを攻めに行ってましたよ」
ぼくは座ったらどうかと尋ねようとしたけれど、邪魔をするのもどうかと思ったのでやめた。彼はそのままバイクについて語りつづけた。そのほとんどがぼくの知らない、興味もない事柄だったけど、彼はぼくが聞いているかどうかなど、まったく問題にしていない様子だったので、ぼくもたいして注意を払わずにパンを食べつづけた。
「バイク乗りのための安宿が北海道のあちこちにあるんです。畳敷きのボロ部屋に、赤の他人と雑魚寝で眠らなきゃならなかったりしますが、むかしは安ければ五百円硬貨一枚で泊まれる場所もありました。貧乏大学生の頃は重宝しましたよ。宿泊客はみんなわたしと同じように、バイクの荷台に着替えやテントをくくりつけて、何週間もかけて北海道を巡る旅の中途なんです。そこで出会った息のあう人間とは、肩を並べて街まで繰り出して、よくいっしょに夜明けまで飲み明かしたりしてました。それがわたしの青春だったんですよ」
ぼくはパンを食べ終えて水の入ったペットボトルに口をつけた。わずかに元々の中身だった烏龍茶の味がした。シロさんはバイクについてはなんでも知っていそうだったので、ぼくは最近気になっていたことを訊いた。車体の金属部品にぽつぽつと、錆がこびりつくようになってきたのだ。
「それなら歯磨き粉がおすすめですよ」と彼は言った。「タオルに歯磨き粉を垂らして、錆の部分を擦ってみてください。単純な方法ですが、かなり効果的です。粒子の荒いものを使用すると傷がつきやすいですから気をつけてください。特にフロントフォークは一度傷がつくと取りかえしがつかないです。ええ、わたしも失敗したことがあるんですよ。あそこは多少の隙間からオイルが漏れてしまいますから」
「むうん」ぼくは彼の横顔をちらっと見た。相変わらず街やホテルがある方向へ顔を向け、まぶしくもないはずなのに目を細めていた。
「お昼ご飯は食べましたか?」ぼくは尋ねた。
「いえ、それがまだなんです」彼は言った。「わたしも相沢さんといっしょで、どこか静かで落ち着ける場所へ行こうと考えていたんです」
「それなら大浴場前のゲームコーナーなんかがいいですよ」と教えてやった。「この時間に宿泊客はいませんし、筐体の陰に隠れてひとから見られないんです。ぼくも雨の日はよくそこでお昼を過ごします」
シロさんは納得したように頷いた。それから数秒ほどの間、彼は動く気配を見せなかったけれど、やがておもむろに歩きはじめた。
「今日はなにを食べる予定なんですか?」ぼくは彼の背中に向かって声をかけた。
彼は振り向いてこたえた。「これから近くのコンビニへ行って決めようと思ってます」
ぼくはタブレットに表示されている時刻を確認した。貴重な昼休みが半分ほど過ぎていた。「いまからでは遅すぎるでしょうね」ついさっき釣り客からもらったおにぎりを袋から取り出し、彼の方へ山なりに放った。彼は一瞬それを取り落としそうになったけど、新人のピエロみたいなステップを踏んでなんとかキャッチした。「もう一個」そう言ってもう一度アルミホイルに包まれた塊を投げた。今度は落下点に素早く移動し、器用につかんだ。「従業員用の待合室に麦茶の入ったジャーが置いてあります」ぼくは言った。「好きに飲んでしまってください。どうせいつも余った分は捨ててるんです」
シロさんはぼくから受けとったものをしばらくひっくりかえしたりして観察した。やがて顔を上げると、ぼくを見て、ゆっくりと右手を掲げた。ぼくも同じように右手を掲げた。ぼくは彼の背中が小さくなってゆくのを見送った。
午後になると、遊戯室の清掃をするようにとの指令がくだった。作業は船橋さんと二人きりだった。彼は自分の作業の手伝いに、よくぼくを指名した。きっと、女性やあれこれしゃべる男より、ぼくのような人間といるほうが楽なのだろう。
電動の麻雀卓の調子が悪いというので、船橋さんはそれをいじくっていた。コンセントを引っこ抜いたり、屈んで卓の裏をのぞいたりしていた。ぼくはその間、ホースがガムテープで継ぎ接ぎにされている掃除機で、床の埃を吸いとっていた。
掃除機のスイッチを切り、騒々しい駆動音がやんだ合間に船橋さんが話しかけてきた。
「あいつ、今日は従業員食堂に顔を見せなかったみたいだな」
〝あいつ〟というのがだれを指してるかわからなかったけど、適当な相づちを打っておいた。
「何人もの人間から苦情が入ってるんだ。ところがいくら言っても聞かねえもんだから、とうとう追い出されちまったんだな」
「そんなことがあったんですね」
ふたたびスイッチを入れ、清掃に戻る。椅子をずらし、卓の下までノズルを潜りこませる。積まれた麻雀牌に謎のテープが貼られているのを見つけたため、スイッチを切って、それを剥がす作業にしばらく没頭した。
「まったくよう、呆れてしまうよな」船橋さんは卓の電源を入れ、牌が自動でシャッフル、整列されるのを見守った。「もういい歳した大人なんだ。学生じゃねえんだからな。人様の迷惑になるようなことをするんじゃねえって話だ」
ぼくは手持ちの雑巾で牌を綺麗に拭き、元の位置に戻した。ついでにリーチ棒を四つの場所へ、ほとんど均等な数になるよう配り直した。偏りがあれば、どこに座っていた人間が、どのくらい勝っていたのかよくわかる。
「みんながつかう場所には、ちゃんとその場所ごとにルールが定められているものなんだ。でなけりゃみんなが気分よく過ごせねえじゃねえか。それなのにあいつは、くちゃくちゃとでかい音を立てて飯を食ったり、ご飯の上に直接、味噌汁をぶっかけてずるずるとすすったりするんだ。何度注意しても、わかりましたって生返事するだけだ。終いにはあの温厚な食堂のばあちゃんを怒らしちまった。どういう教育を受けてきたのか知らねえが、当たり前の行儀や作法っちゅうもんがなってねえ」
「うーん、それはまた・・・」
「挙句の果てに、職場に酒のにおいをぷんぷんさせて出勤してくるしな。酔っぱらった状態でまともに働ける奴がいるものか。いったいあいつは仕事をなんだと思ってるんだ? お客さんから苦情が入ったら、あんな下っ端がどうやって責任をとるっていうんだよ」彼はしゃべりながらも手を動かしつづけていた。「知っているか? あいつ、元警察官だってよ。白バイに乗って、交通違反者を取り締まってたらしいんだ。ところが休みの日に事故に巻きこまれて視力が悪くなっちまった。だから前の職場はやめざるを得なかったんだとよ。はっ。警察にあんなやつを採用するなんて、わしらの国は頭がいかれちまったのかね? あんなやつに速度超過で切符を切られたら、だれだって納得いかねえって面をするだろうさ」
「たしかにそのとおりですね」ぼくはリーチ棒を整理し終えると、船橋さんを真似て卓の電源を押し、ちゃんと動くかたしかめた。じゃらじゃらと牌がぶつかりあう気持ちの良い音が卓のなかで響き、綺麗に整列した山が四つの穴からせりあがってきた。再び掃除機を手にとりスイッチを入れる前、船橋さんがつぶやくように言ったのが聞こえた。
「短期のアルバイトは、実際に働いてもらうまでどんな人間かわからねえのが難点だ。みんながみんな、相沢くんみたいに真面目で勤勉なひとだったら、なにひとつ文句はねえんだがなあ・・・・」
その日は朝から、しばらく使用されていなかった体育室の清掃を頼まれた。夜に泊まる団体客が社交ダンスの同好会らしく、夕方には踊りはじめられるように準備せよ、とフロントから急遽連絡があったのだ。船橋さんは休みだったので、ぼくとシロさんが駆り出された。ぼくはこの手の雑用を任されることが多い。船橋さんの頼みをほいほいと引き受けていたら、ほかのひとたちまでぼくに頼みごとをするようになった。断る理由もなかったので、いつのまにかこのホテルの裏方作業は大抵こなせるようになっていた。
「ではまず掃除機をかけてから、軽く濡らしたモップで水拭きしていきましょう」ぼくは隣に立っていたシロさんに話しかけた。いつものように彼の目は充血していたし、顔は熱っぽく赤みが浮き出ていて、全身からアルコールのにおいを発散させていた。彼はぼくの言葉に頷いた。
作業は滞りなく進んだ。部屋の両端からそれぞれスタートし、まん中あたりで落ちあう。ぼくは同僚たちよりもはやく仕事を終わらせることが多かったけれど、シロさんはぼくとほとんど同時に作業を終えた。
「思ったよりはやめに終わってしまいましたね。少し休憩していきましょうか」
モップに体重を預け、他愛もない世間話をして時間を潰した。それから部屋を囲うように並べられた椅子を綺麗に整え、お互いの作業した箇所を確認のために見まわり、ぼくらは体育室をあとにした。
問題が起こったのは夕食前、大浴場が宿泊客で混みあう時間帯らしかった。又聞きなので詳しい話は知らない。そのつぎの日、ぼくは船橋さんから報告を受けた。
「お偉いさんを怒らせちまった。あいつは三月いっぱいでクビになることが決まったよ」
船橋さんも詳しいことは知らなかったみたいだけど、ヒステリック気味だった食堂のおばちゃんや、ほかの人間から聞いた話を総合すると、ある程度あらましがはっきりしてきた。どうやら彼はべろんべろんに酔っぱらった酩酊状態で大浴場へ向かったらしい。入口の付近にはコーヒー牛乳が売られている自販機やゲームコーナーがある。宿泊客はマッサージチェアに座っていたり、クレーンゲームに興じて賑わっていた。そんなひとの川のまっ只中にシロさんは飛びこみ、白い半袖シャツにメッシュの半ズボンという格好で、有名なアニメソングを大声で歌いながらタップダンスをはじめた。噂によればそのタップダンスは、酔っぱらいの千鳥足にしてはなかなかのものだったらしいが、何人かの客からフロントへすぐに苦情がいった。フロントの人間ははじめ、酔っぱらった客が騒ぎを起こしているものと考えたらしいのだけど、現場についてみると、それは短期アルバイトのひとりだった。しかも以前から白い目でみられていた輩だ。シロさんはほとんど引きずられながら、ホテルの事務室まで連れていかれた。そこでは専務だか支配人だかが憤怒の形相で待ち受けていた。言い逃れる術などあるはずもない。その場で派遣会社に連絡がいき、シロさんは解雇を宣告された。
それからの日々は穏やかに過ぎた。彼はホテルを去るまで揉め事を起こさなかったし、飲酒の量も控えめになった。仕事は素早く、なにに対しても文句や愚痴をこぼさなかった。昼休みはぼくが教えたゲームコーナーの陰で、ひとり静かに過ごしていたらしい。共に作業をするときに多少言葉を交わすことはあったけど、ぼくらの関わりはその程度だった。
彼の最後の出勤日の翌日。午前中の仕事に手間取ってしまい、昼休憩をとる時間がいつもより遅れてしまった。パンの入った袋を片手に外へ出ると、霧のように細かい雨が天地を覆っていた。見上げれば、空から羽虫のような水滴がぼくの瞳に迫ってくる。視線を海に向けると、繋がれた漁船の向こう、防波堤の先端に建つ灯台の横に人影があった。海を向いていた。暗い緑のジャケットを着て、左の肩に紐の張ったボストンバッグを背負っていた。冷たい雨のなかに、彼ひとりしかいなかった。
ぼくは防波堤の付け根から三分の一のあたり、いつもの場所に腰をかけた。パンを袋から取り出し、それが雨に濡れないよう体を丸めて食べた。その日のメニューは、期限切れが迫って安く売られていたロールケーキだった。生クリームは少し酸味が増していて、スポンジ部分からは水分が抜けてパサパサしていた。体を傘にしていたけれど、それだけではどうしようもなく、ロールケーキからは雨の味がした。
一本食べ終わっただけでお腹がいっぱいになった。ペットボトルから水を口に含み、軽くゆすいでから飲みこんだ。その水は雨の味がしなかった。雨は先ほどの強さで降りつづけていた。段々とあたたかくなってきたとはいえ、この日は冷えた。ホテルの制服が少しずつ水分を吸収し、冷たく重くなっていった。用済みの包装をしまい、丸めていた体を伸ばして、後ろについた手に体重を預けた。
ぼくらはほかにだれもいない海岸で、煙雨のなかに漂う水滴のひとつひとつを目で追いかけ、それぞれが巨大なとぐろを巻く水面に溶けていくのを見守った。彼の着ているジャケットは雨に濡れ、肩から背中にかけて黒く変色していた。白髪混じりの髪の先端に引っかかった雨粒は、露から雫に、雫から流れに変わり、顔の表面を伝い落ちていった。
やがて彼は灯台に背中を向けて歩きだした。ぼくの脇を静かに通りすぎるときも、歩くペースはそのままだった。ぼくは霧雨の向こうを見つづけた。別れの挨拶は、質素なものだったけれど、昨日のうちに済ませていた。だからぼくらに交わせる言葉などあるはずもなく、その必要もないはずだった。それでも一瞬だけ、振りかえって彼の目を見つめ、なにか声をかけたいという衝動に襲われた。この場にふさわしい言葉などどこにもなかったし、その衝動に抗うのは濡れた紙を引き裂くのと同じくらい容易だった。ぼくは昼休みが終わるぎりぎりの時間までその場から身動きせず、ずぶ濡れになり、ぼくの生活が属すると周囲が見当違いを起こしている世界から背中を向け、ただ海を眺めつづけた。
次の休みの日、ぼくは朝から近くのスーパーマーケットを訪れ、粒の細かい歯磨き粉と洗車用のファイバータオルを買った。賑やかな朝だった。冬の間、姿をいずこかへ消していた鳥たちが街に戻ってきて、けたたましい鳴き声をあげながら黒い電線の上にずらりと並んでいた。一羽が飛び立つと群れもつづけて舞いあがり、空の一面を翼の影で覆った。あちらこちらの木々に成っていた赤い木の実は彼らの好物らしく、開けた道路にはピンク色の糞が音を立てて落ちた。
ホテルの駐車場に戻り、隅に停めていたぼくのバイクのカバーを剥がした。その横には寮から借りてきた、水の張ったプラスチックのバケツ。ぼくの手には歯磨き粉のチューブと洗車用のタオル。昼ご飯の時間までには一区切りつけたい。
チューブを圧迫して、ほんの少量をタオルの上に垂らす。ブレーキレバーやハンドルの錆びた部分を擦ると、思った以上に錆が落ちた。ある程度、作業を進めてから軽く水拭きをし、その上から乾拭きした。すぐに夢中になって、時間を忘れた。手先に集中する作業をはじめるといつもこうだ。
ふと顔を上げ、ぼくが昼休みに過ごす場所や、灯台のある方向を見た。防波堤は乾き、釣り人たちが戻ってきていた。それは日常であって、あるべき姿のはずだった。けれどもそこにはぼくが欠けていた。ついでに霧のように細かい雨も。ほかにも欠けているものがあるような気がした。それがなにかはよくわからないし、わからないことがとても悲しい。この日以降、昼休みや休日の朝にこの景色が視界に入るたび、ぼくの目は防波堤の付け根から灯台の建つ先端まで、その欠けたなにかを求めてさまようことになる。それはぼくを構成するパーツのひとつでもあって、埋めこまれた深い喪失感と引きかえに、その場所のどこかに、いまでも置き去りにされたままでいる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

