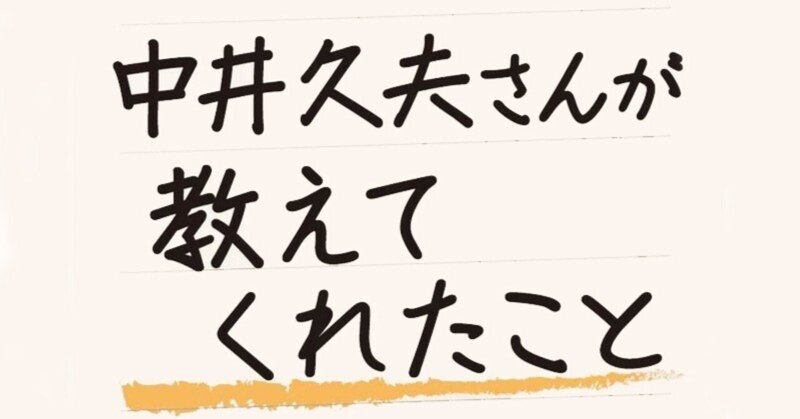
連載「中井久夫さんが教えてくれたこと」⑴⑵
重苦しい年明けとなりました。能登半島地震の被災地は、発生1週間を過ぎても被害の全容が見えず、道路の寸断や悪天候で救助が難航しています。食事や物資は不足し、避難所の衛生環境も悪化しています。
お亡くなりになった方々のご冥福をお祈りし、ご遺族に心からお悔やみを申し上げます。被災された方々の安全と一刻も早い復旧を願うばかりです。
今回と同じ1月に起きた阪神・淡路大震災では、避難先などでの「災害関連死」が921人に上りました。「阪神・淡路大震災の反省、教訓は生かせているか」。1月17日で発生29年となるのを前に、神戸新聞では検証報道が本格化する矢先でした。
被災地からのニュースを目にすると、阪神・淡路大震災と態様に違いはあれど、かつての反省、教訓が十分に生かされているとは言い難いと感じます。被害拡大を防ぐ手だてが急がれます。食事や寒さ対策、衛生環境の改善は無論のこと、29年前の教訓の一つに「心のケア」があります。
今では大きな災害や事件・事故が起きたとき、「心のケア」の重要性は必ず指摘されるようになりました。今回、兵庫県や県内自治体から被災地に派遣された支援チームにも、精神医療の医師らが含まれています。
そうした「心のケア」が広がるきっかけとなった1人の医師の足跡を、数回に分けてご紹介します(※神戸新聞で2023年1月に掲載した連載記事「中井久夫さんが教えてくれたこと」を一部再構成し、再録しています)。
(1)プロローグ
心のケア まなざし優しく

今年の「1・17」に、その人はいない。
中井久夫さん。精神科医で神戸大名誉教授。1995年の阪神・淡路大震災では、全国から駆けつけた精神科医とともに傷ついた被災者を支え続けた。「兵庫県こころのケアセンター」(神戸市中央区)の初代センター長も務めた。
2022年8月、肺炎のため、88年の生涯を閉じる。
でも、日々の世界には今も中井さんが教えてくれたことが息づいている。
23年1月初旬。神戸大学医学部付属病院(同市中央区楠町)を訪ねた。精神科病棟「清明寮」の外庭で、オリーブの木が黒い実を付けていた。
小豆島から苗木が運ばれ、中井さんが成長を喜んだというオリーブ。2階の窓まで届くほど伸び、鳥たちがさえずっている。
1994年に完成した2階建ての清明寮は、教授だった中井さんが細部までこだわった建物だ。
「病棟とその庭は精神科においては唯一で最大の治療用具」。中井さんはそう言って、患者の居心地の良さを大切にした。
当時の精神科病棟で多用されていた鉄格子は使わなかった。大きな窓、明るく広い廊下や病室。光を取り入れる中庭もある。
外庭にはオリーブやクスノキ。春にはサクラやコブシが花をつける。

▼まず、被災者の傍にいることである―「災害がほんとうに襲った時」(みすず書房)
あの震災。清明寮は、全国からボランティアとして駆けつけた精神科医たちの「基地」になった。そこは指揮所、仮眠室、食堂。彼らは夜は寝袋に潜り込み、朝になると避難所へ。被災者の声に耳を傾け続けた。
「まず、被災者の傍にいることである。それが恐怖と不安と喪失の悲哀とを安心な空気で包むのである」。年長だった中井さんの考えは一貫していた。
以降、災害の被災地に精神科医の姿は珍しくなくなった。いち早く心のケアに取り組む「災害派遣精神医療チーム(DPAT)」の仕組みもできた。その源流をたどれば、やはり28年前の神戸の活動に行き着く。
▼だれも病人でありうる、たまたま何かの恵みによっていまは病気でないのだ―「看護のための精神医学」(医学書院)
中井さんの文章にある。
「『だれも病人でありうる、たまたま何かの恵みによっていまは病気でないのだ』という謙虚さが、病人とともに生きる社会の人間の常識であると思う」
例えば「こころのケアセンター」の相談室。部屋にはいすがあるが、「目線を対等に」という中井さんの考えから、医師用と患者用は全く同じものを使っている。医師のいすには背もたれがあり、患者は簡易ないす―そんな見慣れた風景はここにはない。
相談室の壁も「黄色は落ち着くから」と、ほんのりと黄色い壁紙が選ばれた。患者を見つめる優しいまなざしがそこにある。
もしも、中井さんが神戸にいなかったら―。心のケアは今のように広がっていなかったかもしれない。巡り来る季節に、中井さんが残したメッセージを見つめたい。

なかい・ひさお 1934年奈良県生まれ。甲南中・高、京都大卒。東京大や名古屋市立大を経て、1980年から神戸大医学部教授。統合失調症研究の第一人者で、「風景構成法」と呼ぶ絵画療法に取り組んだ。文筆家としても多くの業績を残した。阪神・淡路大震災では、いち早く被災者の心のケアの必要性を説いた。97年から神戸大名誉教授、甲南大教授。2004年には「兵庫県こころのケアセンター」の初代センター長に。13年に文化功労者。
(2)人として
「こころのうぶ毛」を大事に

精神科医の中井久夫さんは白衣を着なかった。医師というより、人として患者に向き合おうとした。
錯乱している患者の脈を取り、聴診器を当て、何度もささやいた。
「きみは、いまとてもそう思えないだろうけれども、ほんとうは大丈夫なんだよ」
17年勤務した神戸大学医学部付属病院(神戸市中央区楠町)の外来では、患者の語りに耳を傾け、本人と家族の「年表」を手作りした。これまでの人生が今の症状にどうつながっているのか、思いを巡らせた。
患者が黙り込んだ時は、カルテの記録もその分だけ空白。沈黙の長さにも、きっと意味があると思ったから。
大学教授の肩書に縛られず、患者の自宅まで往診に出かけた。生活の場を見てこそ、相手のことを理解できると考えた。
▼回復の道で患者を一人孤独に歩かせてはいけません―「統合失調症は癒える」(ラグーナ出版)
そんな仕事ぶりを助手として間近に見てきた兵庫教育大大学院教授の岩井圭司さん(61)は言う。「異例ずくめで、パッションの人だった」と。
中井さんが神戸大に着任したのは、今から40年ほど前。「患者の言うことは当てにならないと、平気で言う教授がいた」(岩井さん)時代に、中井さんは若い医師に伝えていたという。
「パイプいすを患者さんのベッドサイドに持っていって、20~30分座っていなさい」「患者さんが入院した初日には、一晩一緒に過ごしなさい」
自ら神戸市内にある自宅の電話番号を患者に伝えることもあった中井さんは、こう書いている。
「治療者は患者と山頂で出会い、どこに次の一歩を踏み出せばよいかをともに探りながら、安全に麓まで寄り添う役割だと思います。回復の道で患者を一人孤独に歩かせてはいけません」

中井さんの歩みをたどれば、決して平たんな一本道ではない。京都大法学部に入ったものの、結核で休学し、医学部へ。その後、ウイルス学の研究者から32歳で精神科医に転向した。
患者が胸に持っている繊細さ、優しさ、敏感さ。それらを「こころのうぶ毛」と呼び、傷つけないようにしながら、回復まで伴走していくスタイルは、東京の勤務医だった頃から次第に練り上げられ、一つの考えに行き着く。
「治療とは、症状とよばれる霧の奥にあるその人自身と向き合い、人としての尊厳を再建する作業である」
1995年1月。中井さんが神戸に暮らし、15年ほどがたっていた。振り替え休日の16日は、中井さんの61歳の誕生日でもあった。
長年取り組んできたフランス人詩集の全訳作業を終え、インフルエンザで伏せっていた体も回復し、自宅でくつろいでいた夜―。
「さて明日から働けるだろうか」。かすかな不安を胸に抱きつつ、職場の仲間と久しぶりに会えるのを楽しみにしていた。
