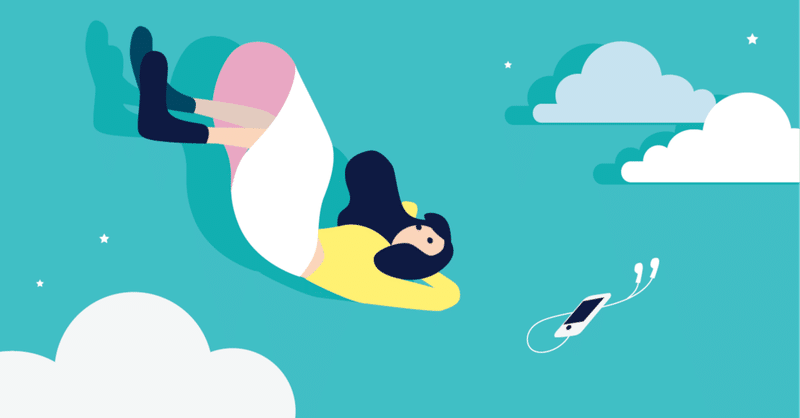
一億総表現社会に花束を【未来を生きる文章術017】
2002年4月29日のコラム。
コラムの背景に、掲示板の書き込みを出版物に掲載した事案に関し、掲示板の投稿にも著作権があると認める判決が出された日本初の判決があります(「ネット掲示板書き込みにも著作権!)!)東京地裁が初判断」参照)。インターネットにおける知的財産権に関する扱いが成熟途中のできごと。
ブログの登場で個人が表現する敷居が低くなったのが2005年。週刊誌『TIME』が毎年選んでいる「PERSON OF THE YEAR」に始めて「You.」と個人名でない人が登場し、表紙には鏡があしらわれたのが、それをうけた2006年号。
日本でもその頃、Web2.0という言葉が流行し、「一億層表現社会」と呼ばれもしました。
このコラムは2002年のことですから、その前夜の話。しかし「ホームページ」作成を通して、誰もが「自分の手で表現する」可能性を感じてはいました。
当時のインターネットのとらえ方については、コラムの中で紹介している内閣府による「IT革命による21世紀経済社会の姿に関する調査・研究」、経団連による「知的財産権を核にした産業競争力の強化に関する考え方について」とも、ネット上にアーカイブが残っていますから、参照してください。
今読み返すと一カ所、誤読しそうな箇所があります。文中で「二次利用」について論じているところです。
当時の意図としては、掲示板の書き込みのようなネット上の著作物を、出版物等で二次利用する際の自覚について論じています。ネット上の著作物は固定されないため、二次利用にあたっての引用元表示が難しいといった当時の議論を紹介しているわけです。
しかしいま「二次利用」というと、むしろ著作物をネット上で利用する場合のことをイメージするのではないでしょうか。たとえば「踊ってみた」動画のように音楽著作物をネット上で利用するような事例です。
ですから、注意して読まないと「二次利用」を誤読する可能性があります。時代の文脈によって言葉の持つニュアンスが変わってくる事例ですね。
東浩紀氏が『動物化するポストモダン』でオタク文化を論じつつ「物語からデータベースへ」と指摘したのが2001年のこと。その後、インターネット上の文化は、まさにデータベースを消費する方向に向かいました。
ゲーム実況やTikTokを見ていると、先行する文化というデータベースの活用方法に自己を表現している様子。
この時代の特徴については、あらためてゆっくり考えてみる価値を感じます。
■ ■ ■
掲示板の匿名書き込みにも著作権、自らの「知価」が問われる時代へ
日経ビジネスExpress2002年4月29日掲載
インターネット上の掲示板に匿名で書き込んだ文章に著作権を認める判決が、東京地裁で下されました。この問題をとりあげるウェブサイトでも活発に情報が交換され、注目を集めています。
この裁判は、インターネット上の掲示板で行った発言を書籍に無断で掲載されたとして、投稿者たちが原告となり、ウェブサイトの運営者や出版社などに対し、販売の差し止めや損害賠償を求めていたものです。
今回の判決は、ふたつの側面で著作物のあり方に影響をもたらすと考えていますが、現在までのところは、そのうち一方の視点での報道が多いようです。
その一方というのは、今回の判決がネット上の著作物の二次利用のあり方に一石を投じるとする、いわば作家、出版側の視点に立ったものです。
ネット上の情報は、一時的な掲載や匿名での発表も多いだけに、引用や参考文献としての紹介に難しさが伴います。信頼性の判断も含め、確かに作家側の自覚が求められるところではあります。ただ、一般に作品というのは、多くの資料にあたりつつ創造されるものであり、この問題は、いれものこそ新しいですが、引用や参考文献の範囲や扱い方という、古くからの課題といえるのではないでしょうか。
気になるのはもう一方の視点、掲示板の投稿者側が迫られる意識変革です。今回の判決は、掲示板の投稿に著作権を認めたわけですが、このことは単に権利が認められたと喜ばしく思うだけの問題ではなく、むしろ自らの発言が著作物にあたるという自覚を、投稿者が持つ必要性を照らし出していないでしょうか。
インターネットの登場により、われわれはより多く日本語に接するようになりました。電子メールやチャット、掲示板と、日本語を書く機会はインターネット以前より増えたように思います。ところが、それらひとつひとつが自身の著作物であるという自覚は、紙に鉛筆で記していた時代の方が高かったのではないか。気軽に文章を相手に伝えられるゆえ、自らの著作物への自覚、自らの「知的財産」への関心が薄れていないでしょうか。
内閣府の「IT革命による21世紀経済社会の姿に関する調査・研究」では、21世紀を「知的影響力を持った世界市民の時代」と定義しています。経済的価値より知的価値が重視される時代になるというわけです。
ことは個人に限らないでしょう。経済団体連合会が発表している「知的財産を核にした産業競争力の強化に関する考え方について」でも触れられているように、企業にとっても知的財産の取り扱いは大きな課題です。
われわれは、言葉によって「知」を伝えます。自らの言葉と相手の言葉が切り結び積み重なる、つまりはコミュニケーションによって、社会全体の知は高まっていきます。言葉を書きとめ、伝えるとき、あなた自身も「作家」として社会に参加しているのです。
今回の判決を機に、自らの言葉の持つ力とそれゆえの責任について、振り返っておきたいものです。
ゼロ年代に『日経ビジネス』系のウェブメディアに連載していた文章を、15年後に振り返りつつ、現代へのヒントを探ります。歴史が未来を作る。過去の文章に突っ込むという異色の文章指南としてもお楽しみください。
