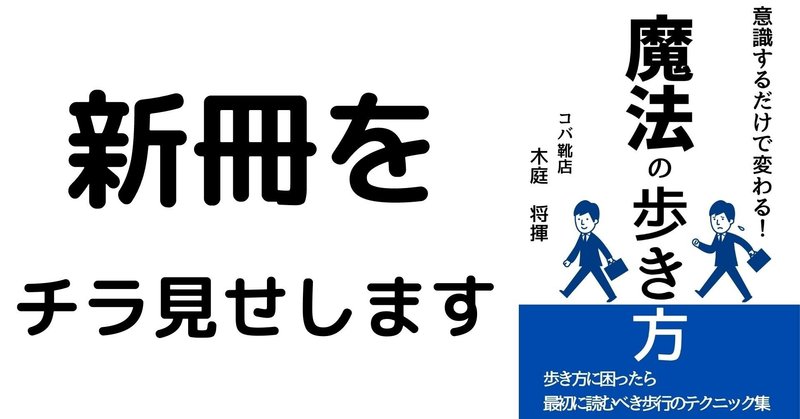
意識するだけで変わる!魔法の歩き方をチラ見せ
こばです!
4冊目の本は【意識するだけで変わる!魔法の歩き方】です。
来週の土曜日(2/20)まではワンコインセールを実施しているこの本です
が
中身が気になる!
というお声を幾つか頂きました。
大層なタイトルをつけているのでそりゃそうですよね。
それにお応えする意味でも今回は冒頭から始まる
全体の約15%程度を公開したいと思います!
解説パートですが少しでも参考にして頂けたら幸いです。
では、スタート

まえがき
本書を手に取ったということは、あなたは「歩き方でお悩み」ですよね?でも、どう歩いたら良いのか分からない・・・とも思っているでしょう。
それもそのはず。そもそも「歩き方」は習ったり学習をした事のない人が大半ですからね。
わたしは今まで、人の歩き方を変えることで収入を得てきました。元々は義肢装具士という病院で靴やインソールを作る国家資格を持つプロで、今は歩き方の指導であったり「靴」、「インソール」といった道具を使って、足のトラブルを改善する専門の靴屋として活動をしております。
わたしが歩き方や立ち方など姿勢の改善に興味をもったのは当時、小学生だった頃。重度のねこ背でずっと悩んでいました。
大人になっても様々なトレーニングやストレッチなどをたくさんやり続けました。鍛え上がった腹筋や背筋は得られたのですが、ねこ背の解決には至りませんでした。
しかし、とある欧米の足病学の文献がわたしの悩みを呆気なく解消してくれたのです。これが、歩き方の大切さを身に染みて気づけたキッカケでした。
義肢装具士から靴屋へと転身しておりますが「足元や歩き方からカラダを改善する」という考え方はずっと共通して持っております。そう考えると、ようやく10年選手になれたでしょうか。
そんなわたしの強みは義肢装具士の知識と欧米の足病学の知識にあります。足病学と言っていますが、実は日本にはまだ浸透していない学科です。しかし、欧米では一般的な足専門の外来です。
わたしのねこ背を一瞬で解決してくれた事もあり、ドップリと崇拝しています。本書では、それらの知識も交えて「歩き方の解説」をしていきます。
本書の内容をざざっとお伝えすると、次の通りです。
・なぜ歩き方が必要なのか
・なぜ歩くのか
・なぜ姿勢が大切なのか
・どのように歩くべきなのか
・靴、インソールの必要性と考え方
理論だけでなく、実際に歩く時のコツやアドバイスなども幅広く解説していきます。
今回わたしがお伝えするのは、わたしだからできることではなく、皆さんにもできることです。ぜひ今回お話する内容を習得して、皆さんも良い歩き方でどんどん健康になりつつお悩みも解決していきましょう!
一度読んで理解できなければ、何度も読んでみてください。歩き方の講義だと思って、何度も読み返して実践して頂ければ幸いです。
また、この本では様々なウォーキングテクニックを述べていますが、全てを行う必要はありません。色々と試して頂き、自分にあった方法と組み合わせを見つけて自分だけの歩行術としてください。
※ 電子書籍で読みやすいように改行を多用しております。
大事
最後に読者プレゼントがございます。
目次

なぜ歩き方が必要なのか
まずは、なぜ歩き方を知る必要があるの?という話をしていきます。これには大きく分けて3つの要因が関係しています。
1 足にトラブルが起こりやすい環境
2 歩かされ方の変異
3 歩き方を知らないので最善な歩きができない。
何だかちょっと難しそうな話ですよね。でも、全然そんな事はありません。セミナーでも何度か話をしたのですが、「確かにそうだ!」というお声をよく頂きますのでご安心ください!という所で早速解説に入ります。
足にトラブルが起こりやすい環境
現代人は足のトラブルが非常に起こりやすい環境にあります。 それは
・運動不足による足の弱体化
・アスファルトという土よりも硬い地面で生活している事
・靴を履くようになってからまだ日が浅い事
これらが影響していると言われています。
特に、運動不足は思い当たる節のある方が多いのかと思います。
通勤手段の発達やデスクワーカーが増えたこと、カラダを動かさない娯楽が増えたこと、今回のコロナ騒動でも拍車がかかったという声もあります。
※ WHO(世界保健機関)の発表でも世界の若者の5人に4人が運動不足である。と警鐘を鳴らしています。世界規模で発生している悩みなのです。

また、運動不足が続くと筋力や足のセンサー機能が低下します。歩くための力が弱くなるだけでなく、ケガもしやすくなるのです。
足裏のセンサーは本当に大切で、ざっくり言うとバランス感覚の話になります。
最近なんだかつまづきやすい、こけやすい。
これらはバランス感覚の低下に多い自覚症状だと言われています。バランスが悪いと転倒につながることが多く、頭部外傷やその他の身体障害を引き起こす可能性があります。
特に股関節骨折は、深刻な健康上の合併症を引き起こし、自立を脅かす可能性があるので、年齢が高い方ほど気をつけたいですね。
運動不足によって歩く力が弱くなるので、歩みが遅く、つまづいたりケガに繋がりやすくなります。
さらに、追い打ちをかけているのが

アスファルトという土よりも硬い地面
一般的に、歩行時に足には体重の約1.2倍の力がかかると言われています。体重が50kgなら約60kgの力がかかる計算です。
また、ここ最近は土や草の地面がめっきりと減りました。土よりも硬いアスファルトに変わったのです。国土交通省の道路統計年報によると、日本では90%を超える割合でアスファルトが利用されているそうです。
公園や田舎の奥地などに行かないとアスファルトからは逃れられません。アスファルトは土や草の地面よりも硬いので足や膝、腰などへの負担が大きくなります。
運動不足によって足が弱体化し、さらに地面が硬くなった。
だから、現代人の足にトラブルが起きやすくなっている・・・・だけではないのです!これは、進化学的な話にもなるのですが、
日本人が日常的に靴を履くようになって、まだ70年
実は、日本人が今のように欧米式の靴を日常的に履き始めて、まだたったの70年しか経っていません。それまではゾウリやワラジ、下駄のような「踵のない物」を履いていたのです。
70年前となると、今の高齢者が欧米式の靴を日常的に履き始めた第一世代で、中高年の方が第二世代といったところでしょうか。今では当たり前のように履いている欧米式の靴ですが、日本人は踵のある「欧米式の靴」を履き慣れていない人種です。
そして、今まで先祖代々履いてきた
踵のない履物にはある特徴があります。
・ 足の指を使って履物が脱げないようにする
・ 踵から着地をせずに、足の指のつけ根から着地をする
つまり、ずっと長い間わたし達日本人は、前足部から着地をする歩き方がメインの前重心傾向が強かったのです。
※ ゾウリやワラジの感覚はビーチサンダルを思い出してください。踵から着地をするのは脱げやすいしちょっと大変でしたよね ※
一般的に生物学的な進化、変化は長い時間をかけて行われてきました。それが、たったの70年前に靴を履くようになった事で今までの
【前重心+前足部着地】から【後ろ重心+かかと着地】になりました。
また、前述の通り 柔らかかった土や草の地面が一気に硬いアスファルトに変わり、運動不足によって足が弱体化してきた。
カラダの進化よりも早く、環境が進化してしまった事でカラダが対応できず、結果として足にトラブルが起こっても仕方のない環境に変わっていると思いませんか?
※ 履物自体は弥生時代から出土した記録があるそうです。
諸説ありますが、一般的に履かれたのはもう少し先の時代だそうです。

歩かされ方の変異
履物の変化によって歩かされ方も変わりました。
最近では厚底スニーカーやハイヒールなど足裏の形状と大きく異なる底の靴を使用している人が非常に多くなったように思います。
これによって足にかかる重心のバランスや力のかかり方が変わり、足や膝、腰の負担として訴える方が増えてきました。
また、日常生活だけでなくマラソン界隈でも厚底スニーカーが話題になったのは記憶にも新しいですね。驚異的なタイムをどんどんと叩き出して様々なメディアでも話題になりました。
このように最近の靴は様々な目的と効果が想定されて作られています。しかし、足には元々様々な機能が存在します。その機能を使うために足は片足で約26個、両足で約52個の骨で構成されていると言われています。
多くの骨が連動する事で
・力の分散
・力の集中
ができるようになります。
これによって楽に速く効率的に歩けるのです!
世紀の天才として知られるレオナルド・ダ・ヴィンチは
「足は人間工学上の傑作であり、最高の芸術作品である」と述べています。

人間工学の傑作を有効活用するには靴底の形が大切です。靴底が厚くなりすぎたり、靴底の傾斜が大きくなると足本来の機能を活かした歩行が難しくなります。重心のバランスや力のかかり方が変わるのです。
それに合わせた歩き方になります。今まで履いてきたような柔軟で薄い靴底ですと歩き方もそこまで大きく変わりません。しかし、クセの強い靴底によって歩き方が変わります。
特殊な靴底によって、強いクセで歩かされてしまうのです。
本来の機能を活かせないとカラダに負担がかかってしまっても不思議ではありませんよね?
※2/20(土)までワンコインです!
お見逃しなく!
こばでした!
カラダに関する情報を国内外問わず分かりやすい形に直してどんどん発信していきます。頂いたサポートは次の文献購入費用に宛てております。 もし、よろしければ文献購入費用のお手伝いをして頂きますと幸いです。よろしくお願い致します。
