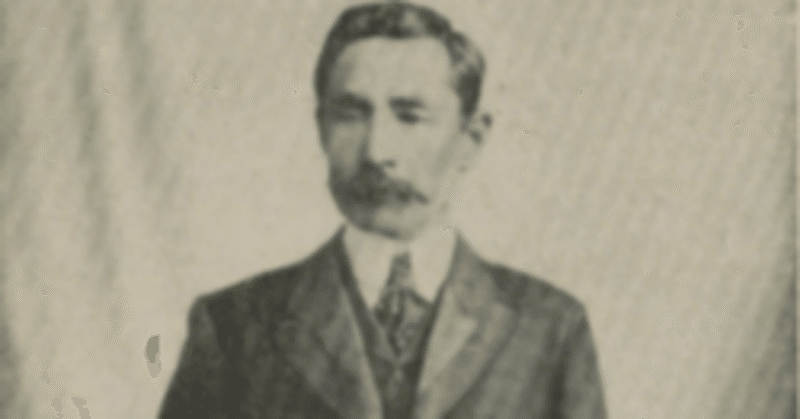
夏目漱石の「おはなし」をどう読むか 贔屓の理由
夏目漱石や芥川龍之介については何か書いているのに、正宗白鳥や牧野信一についてはなぜ何も書かないかと云えば、
①夏目漱石や芥川龍之介作品には誤解されている点が多いから、何かを書く意味が大いにあるから。
②正宗白鳥について何も書かないのは島崎藤村同様、そんなに作品が面白いとは思わないから。
③牧野信一ほか面白い作家はたくさんいて、本当なら三島由紀夫についても書きたいのだが、ざっとスケール感で捉えたとき、私の残された人生において、芥川作品に関する話でもどうも時間的に間に合いそうもないから。
④太宰治に関しては訂正すべき点はそんな多くないので簡単に済ませたが、芥川、三島由紀夫に関しては訂正すべきところが山ほどあるから。
……ということになる。それは一言でいえば特定の作家に対する贔屓ということにもなろうか。夏目漱石はこの贔屓ということについて、講演でこう語っている。
文芸は law によって govern されてはいけない。personal である。free である。しからばまるで、無茶なものかというと、決してさようではない。かようにあなた方の出発点と、吾々文芸家の出発点とは違っている。
そのものの性質よりいえば、吾々の方のものは personal のもので、作物を見て、作った人に思い及ぶ、電車の軌道きどうは誰が引いたかと考うる必要はないが、芸術家のものであるとき、誰が作ったということがじき問題になる。したがって製作品に対する情緒がこれにうつって行って作物に対する好厭の念が、作家にうつって行く。なおひろがって作家自身の好厭となり結局道徳的の問題となる。それゆえ作物から当然得べき感情が作家に及ぼして、しまいには justice という事がなくなって贔負というものができる。芸人にはこの贔負が特にはなはだしい。相撲なんかそれです。私の友人に相撲のすきな人がある、この人は勝った方がすきだと申します。この人なんか正義な人で、公平で、決して贔負ではない。贔負になるとこんな事ができない。かく芸を離れて当人になってくるのは角力か役者に多い。作物になるとさほどでもないようにも見える。
これほどまでに芸術とか文芸とかいうものは personal である。personal であるから自己に重きを置く。主がなくなったら personal のなくなるのはあたり前だけれども、自己がなくなれば、芸術はだめである。
そんなに大したことは言っていない。誰が作ったということがじき問題になるというのは必ずしも厳密な法則性ではなく、飯田蛇笏は芥川の句をそれと知らず絶賛して後で芥川の句と知り、知った後でも良い句を誉め、悪い句は批判した。
そういう意味で確かに私は夏目漱石や芥川を贔屓しているのかもしれないが、村上春樹を読み、川上未映子を読むのには共通した理由がある。あるいはどこの誰でもない誰か、つまり名無しの権兵衛の作品であれ、それがあれば私はその作品を読むのだろうがそれがあるかないかが解らないので、とりあえず村上春樹を読み、川上未映子を読むのだ。
それとはオープンにされているのにほとんどの読者が気が付かないでいる重要なポイントということになる。たとえば、
そして多分ほとんどの読者は忘れたことに気づかないくらい、完璧に忘れている。目を閉じてこそ見える景色が人生の向こう側なのに、「僕」は目を見開いてこの美しい世界を見つめてしまうという落ちを。
それに第一、これはだれにだつてできることだ。
目を閉じさえすればよい。
すると人生の向こう側だ。
—— セリーヌ『世の果てへの旅』
エピグラフにはこうあったのに、多分みんな忘れている。
川上未映子はこういうことをやってくる。
その「オープンにされているのにほとんどの読者が気が付かないでいる重要なポイント」に気が付いてみて、はじめて私は『ヘヴン』という作品と川上未映子という作家の価値にたどり着いた感じがした。勿論それは一度きりたまたま現れたものではない。
みんなストレスすごくって。旦那の愚痴ばっかりで。そういう記事とか本とか多くないですか? ママ作家とかもそんなのばっかりでしょう?出産本とか育児本とか、苦労と共感系っていうか。産まれてきてくれてありがとう——とかね。作家がそんな凡庸な感情を書いていったい何になるんですか。わたしからすれば、ああいう身辺雑記を書いたら小説家なんてそこで終わりですよね。
こんな振りがなされていたのに、結果として「夏目夏子という作家が子供を産む話」である『夏物語』は「身辺雑記」どころか川上未映子の最高傑作になってしまった。
そのことに気が付けば、吉田精一はもっと勉強しろよと思ってしまう。
おそらく花ちゃんは処女だ。
谷崎潤一郎は「民草」という言葉をあえて用いなかった。
しかしそれはまた「あざむき」だけではない。村上春樹や三島由紀夫の魅力は、解りにくい解りやすさでもある。
「ルュツク・ザック」はドイツ語、「無答責」「頒たれる」は法律用語、「星あかりに霧ふ空」「月は望に近く」は古式な表現、「鷄初鳴咸」は『小学』、そこに「新しいタオルのやうに汚れのない権力」だの「汚い身なりの子供に菓子パンをあたえるやうに」だとの書いて来れば、この男はドイツ語に堪能で法科出身で、古典のしつかりと身についた、そして大岡昇平に「あなたのは、凄いものを持って来て、並列して特別なものを出そうとしておられますね」と言われるような男なのではなかろうか。
そうこんな作家はほかにいない。平安時代の言葉を平気で使ってくる。あざむくつもりもなかろうが、決してわかりやすくはない。読み込む価値のある作家である。
今更ながら村上春樹さんの『納屋を焼く』とウィリアム・フォークナーの『納屋は燃える』の関係を調べなきゃと焦る。というか冷汗ものだ。しかし『納屋を焼く』にはいくつものバージョンがあり、どこからどう手を付けたものやら。
クロポトキンの『パンの略取』と『パン屋再襲撃』の間には洒落程度の関係があるとして、やはりそういう本歌取りのようなところには気が付いておきたいものだ。
つまり吉田精一はこの「わんわん」の関係に気が付いていたのか、いなかったのか?
大どんでん返しでなくともよい。作家のpersonalとはその人ならではの特別なもので、誰しもが理解し得るものではないもの、ある特定の贔屓筋がどうしても期待してしまうもの、そういうものを持っている作家はそう多くはない。
その中でも梅は植え替えられても無意味という夏目漱石の書きっぷりの鮮やかさは格別なものだ。
こんなことが書ける作家がほかにいれば贔屓にしたいが、なんかこう見え見えの分かりやすさに安住している人が多いんだよね、という話。
これなんかちんぷんかんぷんだったんじゃないの?
https://twitter.com/i/bookmarks?post_id=1745274914670788773
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
