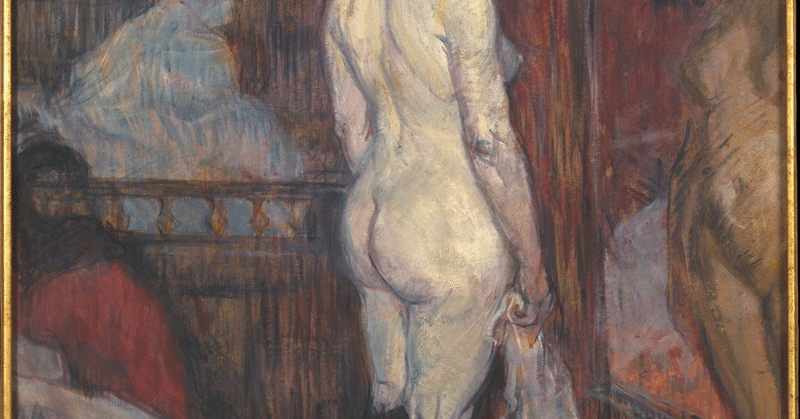
川上未映子の『ヘブン』をどう読むか⑨ みんな忘れてしまう
羆に突然襲われなければ、人は何十年かは生きられる。戦争のない国に生まれたのだから、もしもアンゴルモアの大王がやって来ないとすれば1991年の中学生はやがて高校生になり、2023年にはもう44歳か45歳のおじさんになっている。
しかしおそらく『ヘブン』の「僕」は『ノストラダムスの大予言』通りに1999年7の月に人類と共に亡びるべきなんだろう。その先の未来は彼には必要ない。
まるで何もかも片が付いてしまったかのように、「僕」は母親にこれまでのいじめのことを話してしまう。おそらくそこに間違いなくあったはずのコジマに対する複雑な感情の記憶をすっかり失ってしまったかのように。肝腎なことはそこじゃないかという感傷は一切受け付けませんというきっぱりとした態度だ。八章の最後でコジマのことにはもう蹴りが付いていたのだ。
話は斜視の手術に移る。
そこで母親に告げられた三つの障壁は、
①斜視を手術をすることで二宮たちに屈することになるんじゃないか
②この目が僕を僕たらしめているんだとコジマが言ってくれた
③本当の母親が斜視だったので、斜視は絆でもある
……いやいやいや、コジマが「僕」の目を好きだと言ってくれていて、「僕」は一日に二回もマスターベーションをして、コジマをおかずにしていて、斜視であることでコジマと仲間だったことを何故言わないのか?
まあ、おかずのことは言わなくてもいい。
実際「僕」の中ではコジマとの「再会」や「回復」の可能性を一ミリも期待していないのだろう。村上春樹の小説のように消え去った女は二度と戻らないということか。
ただし『騎士団長殺し』では秋川まりえは戻ってきた。『1Q84』のつばさちゃんは消えたままだ。
それでも「僕」は斜視が自分のアイデンティティであるだけではなく、コジマの歪んだ愛情の起点であり、絆だったことは忘れてはならないのではなかろうか。斜視を手術をするということは、汚れた運動靴やコジマのにおいを否定すること、本当の父親とのつながりに固執して箱男のようになっていくコジマを切り捨ててしまうことになるのだ。
しかし「僕」はあっさりと手術を受ける決心をする。
そこには葛藤も苦悩もない。
既に何もかも片が付いてしまったのだ。「僕」は石を使わず、コジマが自ら全裸になって「僕」を守ってくれたのに。
「君はまだとても若くて、この先何十年も生きる。手術が成功すれば、新しい目にあっというまに慣れてしまうさ。そしてそのうち自分が斜視だったことも思いだせないくらいになるよ」と言って笑った。
「そうですか」と僕は言った。
「忘れるんですか」
「忘れるさ」と医者は言った。
「忘れたことに気づかないくらい、完璧に忘れると思うよ」
彼らはまだ青春が何時までも続かないことを知らない。それは残酷なことでもなんでもなく、ただ覚えていられないだけだという当たり前の事実が八章と九章の空気で証明されている。二宮を警戒するうっとうしさは消え、コジマに会いたくて会いたくてたまらないという気持ちも消えている。あのおさえきれないなにかが消えている。
斜視の手術を終え、「僕」が見た世界は美しかった。
ただそんな美しさも忘れてしまうのだということを彼は知らない。「僕」はその美しい世界をおかずにマスターベーションすることもなく、まだヘヴンを見ていないことさえ思いださない。食事をとらず、風呂に入らないコジマがあれからどうなったかということなど考えない方がいいだろう。二宮や百瀬がどんな人生を歩むのかということも。そこにはひたすら胸糞悪いものだけが詰まっているかもしれない。
二十一世紀のある日、原宿の裏通りで「僕」とコジマは『4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて』みたいに出会わない。それはもう終わったことであり、忘れられるべき事なのだ。
そして多分ほとんどの読者は忘れたことに気づかないくらい、完璧に忘れている。目を閉じてこそ見える景色が人生の向こう側なのに、「僕」は目を見開いてこの美しい世界を見つめてしまうという落ちを。
それに第一、これはだれにだつてできることだ。
目を閉じさえすればよい。
すると人生の向こう側だ。
—— セリーヌ『世の果てへの旅』
エピグラフにはこうあったのに、多分みんな忘れている。
川上未映子はこういうことをやってくる。
[余談]
芥川龍之介の『あばばばば』ではこんな話を書いた。
ただ「あばばばばばば、ばあ!」にフォーカスしてみると、この赤ん坊が遺伝性の斜視であるという、普通は、まあ、常識的に書かれるべきではない落ちも見えないではない。
つまり単に赤ん坊をあやしているのではなく、赤ん坊の目の異常を確かめているのだと。
本当の母親がもつと早く手術の可能性について調べることがなかったというところからして「僕」の人生はスタートしている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
