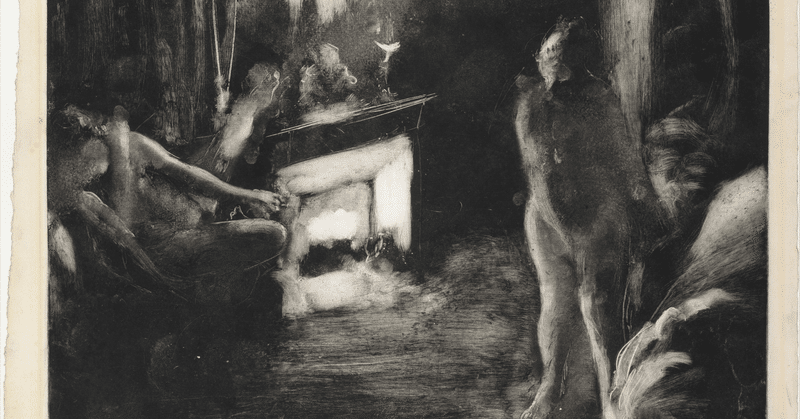
江藤淳の漱石論について⑳ 登世という嫂と夏目漱石はセックスをしたのか? というどうでもいい問い
江藤淳のライフワークともいえる『漱石とその時代』は平たく言えば確かに小説家夏目漱石の実像に迫ろうという試みであり、作品を読み解きながらその関心はあくまで漱石にあった。いや、もう少し正確に言えば、漱石自身よりも漱石が存在した時代に焦点が当てられていたと言ってよいだろう。私はその真逆で、時代も漱石も漱石作品を理解するための資料に過ぎないと考えていて、これまでその方向性で夏目漱石作品を論じてきた。江藤が作家論者であれば、私は作品論者であり、その求めるところが明確に異なる。
文芸批評の目的が文学作品から時代性を切り取ることだと頑なに信じている人はやはりまた、文芸批評の目的は作品から文豪飯を切り取ることだと信じている人と同じ程度に悪意はなかろう。むしろ何の戦略もなく、わざとらしさもなく、ただ自然にそう振舞っているだけに違いない。だからゼロ年代に現れた「セカイ系」なる一連の映像作品、文学作品はポスト・モダンなり、ポップカルチャーなりと呼ばれ、新しい時代の枠組みで持て囃された。しかしそもそもさしたる現実的な手立てなく、直接世界や宇宙とつながってしまうことは古今東西普遍的な、いわばごく当たり前のことではなかっただろうか。
例えば『世界の中心で愛を叫ぶ』という小説・映画があったが、三四郎だって現実世界の激烈な活動の中心に立っている。なら夏目漱石も「セカイ系」である。それは当たり前のことではなかろうか。つまり「セカイ系」なるアイデアにはさして意味がない。あるいは全く意味がない。その程度のさして深みのない理屈で、私はこれまでに江藤淳の漱石論を様々に批判してきた。それは最終的には夏目漱石作品の読みに関する過ちを指摘する形になった。
今回は少し違う形で、江藤淳の漱石論について考えてみたい。
江藤淳の年譜を見れば、1975年、博士論文『漱石とアーサー王伝説』により博士号を取得、漱石と嫂登世との恋愛関係と『薤露行』の解釈を巡って大岡昇平と論争になったことになる。このこと自体はまだいくらか真面なことだ。その前年1974年、江藤は『決定版 夏目漱石』に収められた「登世という嫂」の中で、
つまり漱石は兄嫁を密かに恋していたのであり、嫂もまたおそらくこの義弟に「親愛の念」以上のものを感じていたのである。
と書いて話題になっている。ここまでも何とか許せる話だ。しかしこれはどうだろう。
そして、そのすぐれて特権的な問題をめぐって『漱石とアーサー王伝説』と題された上質のメロドラマが書かれたことは誰でもが知っているとおりだ。兄の嫁と情を通じることは、世間ではよくないこととされている。ところが夏目漱石は、嫂の登世と深い関係に陥ってしまった。だから漱石文学は、「罪」という過失の問題をめぐって書きつがれる必然性がある。たとえば初期作品の一つ『漾虚集』におさめられた『薤露行』を読んでみるがよい。そこには、西洋の中世伝説の一挿話をかりて、嫂の登世との不幸な過失の体験をめぐる漱石の記憶が生なましく息づいているではないか。(蓮實重彦「健康という名の幻想」『表層批評宣言』所収/ちくま文庫/1985年)
この『表層批評宣言』の単行本は1979年に出版されている。この部分を書いた蓮實重彦はとんでもない知ったかぶりっ子ではないかと言いたいのではない。私にはむしろ夏目漱石が、嫂の登世と深い関係に陥ってしまったかどうかはどうでもいい。しかし『薤露行』に嫂の登世との不幸な過失の体験をめぐる漱石の記憶が生なましく息づいていると書かれてしまうこと、それを江藤淳ではなく蓮實重彦が書いてしまうことにこそ大きな問題があると考えている。それは「恣意的に『薤露行』を罪と死と破局の物語と読む誤りを犯している」という大岡昇平の指摘とは全く次元の違うレベルの過ちである。あるいはフェイクニュースと言ってもいい。
信じがたいのは蓮實重彦が「たとえば初期作品の一つ『漾虚集』におさめられた『薤露行』を読んでみるがよい」とあたかも江藤淳の博士論文の手柄を無きものにするかのごとき傲慢な、そして厚かましい台詞を選んだことである。段取りを踏んで確認していけば、ここで蓮實重彦はどういう了見かわざわざ『薤露行』をたとえばと挙げているが、『薤露行』に嫂との関係を見出したのは蓮實重彦ではなく、江藤淳なのである。身もふたもない話にしてしまえば「嫂の登世との不幸な過失の体験をめぐる漱石の記憶が生なましく息づいている」という蓮實重彦の感想は江藤淳の漱石論によってミスリードされたものである。私も『薤露行』は何度となく読んだが、蓮實重彦が言うような気配はまるで感じない。
そして「たとえば」といって、夏目漱石作品のうちに別の「嫂の登世との不幸な過失の体験をめぐる漱石の記憶が生なましく息づいている」といった作品を挙げることもできない。江藤淳は『一夜』も「嫂の登世との不幸な過失の体験をめぐる漱石の記憶が生なましく息づいている」作品だと主張するかもしれないが、決め手に欠くように私には感じられる。
それでも敢えて言えば『行人』の直と二郎の関係が生なましいが、深い関係に陥ってはいない。深い関係に陥ってしまったのは『門』の御米と宗助くらいなものではなかろうか。代助と三千代ですらその手前であり、先生と静にはセックスレスが仄めかされる。『坊ちゃん』の「おれ」は「本当の本当のって僕あ、嫁が貰いたくって仕方がないんだ」といいながらその気配すらない。三四郎は風呂場から逃げ出すし、吾輩もさかりがつかない。そう思ってみれば蓮實重彦の「たとえば」とは如何にも見え透いたはったりなのである。
目が覚めると先までのことは綺麗さっぱり忘れてしまった。何か長く陰鬱な夢をみていたような気もするが、それも一瞬の間に終わったとも思える。布団の上に出していた筈の手が、いつの間にか布団の中に忍び込んでいて、臍の胡麻を取っている。人間の無意識というものは不思議なものだ。
私は枕元に用意されている水を飲もうとうつ伏せになった。その瞬間隣でううんという声がした。私は電気刺激を受けた蛙の太もものように跳び起きて布団を捲った。浴衣をはだけ、殆ど腰紐だけになりながら私の隣に眠っていた者は嫂だった。すっかり化粧が落ちているので人相が変わってはいたが、私にはその素顔に近い顔が、やつれているとも年寄り臭いとも思えなかった。腫れぼったい顔は染みや出来物がある訳ではなく、飽くまで艶やかに透明で、ふっくらとした少女の顔と言っても良い位だった。眉が落ちた所為か、顔全体がぼんやりしている。それは不断の少し尖った印象からすると、可愛らしくも思える。なんでも好い方に解釈しなおすことは可能だ。彼女の乳房は仰向けになりながらもきちんと存在した。ややなだらかながら、霊峰の曲線を模して天を衝いている。ぷっくりと盛り上がった下腹部には、薄い陰毛が下向きに生えそろっていた。余った肉が左右から寄り添おうとしている。
私はそんな幸福な観察を終えて青くなった。実際私は化粧道具の並べられた鏡台に映った自分の顔を確かめた。その端には半裸の嫂が寝そべっている。私は部屋を見回し、柱時計の時刻を見た。私には最初それがどんな時刻を示しているのか分からなかった。それは左右が反転した"く"の字に似ていた。要するに…… もうすぐお昼である。
一体私と嫂はこんな時間までここで何をしていたのだろうか。
いや、それを誰よりも知りたがるのは兄であることは間違いない。しかし今度という今度は、それこそどんな言い訳も用をなさないように思えた。我々は布団を並べて寝た訳ではなく、一つの布団で寝たのだ。同衾したのだ。私は社会道徳を無視し、倫理を撥ね除け、利己的遺伝子の働きにより、嫂を遺伝子の乗り物にしたのだ。
ううん、とまた嫂は唸った。私は振り返って直に彼女を見下ろした。未だ完全ではないが、目が開いてこちらを見ている。それは生まれて間もない子猫の目で、黒く濡れ、見ているものになかなか焦点が合わせられずにいた。
「義姉さん」
私はそう呼びかけた。一刻も早く混乱から解放して貰おうとして、この状況の認識を共にしたかったのである。だが彼女は、返事の代わりに甘えた声でううんと唸り、くるりと向こうへ寝返りを打ってしまった。こちらには大きなお尻が向けられただけである。
背中にはなんとか浴衣が巻き付いてはいたが、お尻は半分見えていた。自分の存在に気がついていながら、そんな格好のままでいる嫂が急に腹立たしく思えて来た。私は障子を明け放ち、昼の光で直に嫂を照らした。それでも丸まっただけの彼女が胸に抱えた掛け布団を奪い取ると、私は彼女の正面に座って直談判を始めた。
「ちょっと義姉さん、起きてください。寝ている場合ではありません」
「なあに」
「なあに、ではありません。これは一体どういうことなんです。何故お義姉さんがここにいらっしゃるんですか?」
「何を怒っていらっしゃるの?」
「何も怒ってやしません」
「でも、怖い顔をしていらっしゃる」
「してません」
そこで嫂はようやく起き上がり、さして急ぐ素振りもなく浴衣の胸を合わせ、裾の乱れを直した。
「お義姉さん。私はあなたの義弟でしょう」
「はいはい」
「つまりあなたは私の義姉です。私の兄さんの妻ではありませんか。おまけに私の両親から見れば娘同然です」
「そりゃそうに決まっているわ。やっぱり兄弟だけあって、あなたも蟹太郎さんそっくりのおっしゃり方をするのね」
「私は真面目にお話しているのです」
「一体何のお話?」
「どうしてこんなことになったんです? 昨夜私たちに一体何が起こったんです?」
嫂はじいっと私を睨んでいたが、堪え切れなくなった様子で吹き出した。
「あなた昨夜のこと、全然覚えていらっしゃらないの?」
そう問われてみると、部屋の中でも見回してみようかという気にもなる。ここはどうやら母屋ではなく、兄夫婦が暮らしている離れの二階で、日当たりの良い和室だった。離れは兄夫婦が両親と同居することが決まって、兄の意向で庭の一部を掘り返して建て増しをしたもので、畳もまだ新しい。私はこの部屋に足を踏み入れた記憶が殆ど一、二度しかなかった。しかもそれは兄夫婦が本格的な新婚生活を始める以前のことで、布団が敷かれた状態を見るのは初めての経験である。嫁入り道具の三面鏡がここに置かれていることも知らなかった。いかにも生活を匂わせる配置でそこに並べられているコールドクリームや化粧水や脱脂綿やブラシの類いの一つ一つが、私にはある種の驚きを与えていた。
どうやら私は彼女の寝室に泊まったらしい。それは間違いない。ただしそれ以上の推測は、どんな記憶とも結び付かなかった。私は鈍器で後頭部を殴られ、担がれてここへ運び込まれたのではないかと勘ぐった。
「本当に何も覚えていらっしゃらないみたいね」
嫂は立ち上がり、折角直した浴衣を脱ぎ始めた。私は慌てて横を向いたが、それは余りにも堂々としている彼女に対して、弾かれたように真後ろを向くのが癪で、あなたの着替えになどまるで興味がありませんと無視する為に横を向いたのであって、目の玉を端に寄せれば、視界の隅には何かが見えそうな向きではあった。だが改めてそれ以上体を捩るのも癪なので、私はそのまま質問に答えた。
「何も覚えていない訳ではありません。しかし私はどうしてもあなたの口から釈明をお聞きしたいんです」
「釈明って、何の釈明?」
「こういう事情になった一切の釈明です」
「何かまるで万引きの常習犯でも捕まえたようなおっしゃり方ですのね」
「万引きとは申しません。しかしあなたは罪だ」
「何故妾が罪なんですの?」
「罪だから罪だと言うんです」
「それじゃ少しも分かりません。妾、あなたやあなたのお兄様みたいに頭が高級にはできていないのよ」
「じゃあ、申し上げます。あなたは卑怯だ」
「卑怯?」
「あなたは卑怯だ。そ、その…… 人生の物事の筋道の上で、あなたはまるで卑怯だ」
「六ずかしくて分からないわ。妾があなたに一体何をしたとおっしゃるの?」
「あなたは私に…… その恋愛的暴力を振るったのです」
「恋愛的暴力?」
「そうです。あなたは私を撥ね除けなかった。それが恋愛的暴力です」
日が暮れる程の沈黙の途中で、私にはもうどんな言葉も残されてはいなかった。私の舌と喉は浅草海苔のように乾き、さらに炭火で炙られるのをじっと待つよりなかった。すっかり着替えを終わった嫂は、私が正座した膝に涙を落としているのを気がついた。だが、そんなことなどどうでも良いとばかりに布団の始末を始めた。部屋がすっかり片付いてみると、着替え終わった嫂と、寝崩した浴衣姿の私の間には、囚人と面会人程の身分の隔たりが感じられた。嫂の言葉でようやく沈黙が終焉を迎える寸前には、私はすっかり死を覚悟していた。
「基地次郎さんったら、」嫂はそう呟くと、私の髪をくしゃくしゃに掻き混ぜ、頬の肉を抓って左右に引っ張った。「あなたって余程意気地が無い人ね」
それはまるで江角マキ子が軟弱な男を窘める演技のようであった。そして結局私は義姉の口から事の顛末を聞きそびれた。記憶も戻らない。食堂に降りて、下女に怪しまれながら二人で麺麭とバタとウーロン茶の朝食を食べながら、終始無言であった。両親が共に出掛けていたことが幸いして、下女には弁解の代わりにお小遣いを渡して済ませた。朝食を終えると、私は久しぶりに犬を散歩に連れて行った。犬はすっかり私を忘れていて、首に引き綱をつけている最中からあちこち噛み付いたが、腹を蹴上げると観念して口から泡を吹いた。それからはおとなしく道を引きずられていくばかりである。そして丁度どこかの西洋館からお昼を告げる鐘が打ち鳴らされたのを聞きながら、しまった、会社をさぼってしまったと気がついたのだった。(村雨春陽『シベリア 第一部第一章』)
これは村雨春陽の小説の一部で、漱石とは関係ない。いや勿論、夏目漱石作品の特徴として兄との不仲や嫂への思慕、恋愛をめぐる屁理屈や、意気地のない男や案外度胸の据わった女が現れることは間違いない。こんな「冗談」はその夏目漱石作品の特徴をことさら作り物めいた形で誇張したものだ。そうしたものを書いてみればこそ、こんなことは罪の意識があっては到底書けるものではないことが解る。だからこそ変人・漱石なのだ、と譲らない人がいても仕方ないが、仮にも「たとえば」というのであれば、こんな「冗談」を漱石作品の中にもう一つは見出さねばならないのではなかろうか。
私には蓮實重彦が小説家夏目漱石の実像に迫ろうとした江藤淳の手柄を最悪な形で横取りし、あたかも事実の上に証拠立てられたものとして「夏目漱石は、嫂の登世と深い関係に陥ってしまった」と書いたことは間違いだとしか思えない。江藤は「つまり漱石は兄嫁を密かに恋していたのであり、嫂もまたおそらくこの義弟に「親愛の念」以上のものを感じていたのである」と書いたのだ。繰り返すが私にとって作家の私生活など基本的にどうでもいい。つまり作家夏目漱石が嫂の登世と深い関係に陥ってしまったとしてもそうではなかったとしてもどちらでもいい。
しかしこんな最悪の伝搬が批評であり文学だと考えられていることが残念と言えば残念、おかしいと云えばおかしいのである。それもこれも作品ではなく作者を論じようというズレに問題があったからではないかと私は考えている。作品に書かれている内容を作者自身に引き付けすぎる傾向は、作品には必ず作者の実像が現れるという誤解から生じる。そういうこともあり、そうでない場合もあり、いずれも程度問題だ、とは誰も考えないものであろうか。そうであればまだ文豪飯から半歩も踏み出していない。
この僧都、ある法師を見て、しろうるりといふ名をつけたりけり。「とは、何物ぞ」と、人の問ひければ、「さる物を我も知らず。若しあらましかば、この僧の顔に似てん」とぞ言ひける
『徒然草』には「しろうるり」なる語義不詳の言葉が出て来る。(『竹取物語』の「うかんるり」も諸説あるも語義不詳と言ってよいだろう。)作家は訳の分からないもの、自分でも捉えきれないものも書くことができる。そこに実像を当て嵌められても剣呑だ。
【余談】
蓮實重彦のだらしなさを確認するためには、「しろうるり」よりも「チー牛」の例えの方が適切かもしれない。私の電子書籍を購入する金もない程度の人にはむしろ説明する必要もないことばかも知れないが、ネットスラングにチーズ牛丼を訳して「チー牛」というものがある。これはいかにもすき家でチーズ牛丼を頼みそうなオタクの事で、なんJ、なんでも実況する板の住民の近種である。
しかし「いかにもすき家でチーズ牛丼を頼みそうなオタク」というラベリングそのものはさして画期的なアイデアでもない。むしろそのように「なんでもないこと」を膨らまして面白がるネット文化の中で「チー牛」という言葉が定着してしまったのだと見るべきだろう。
蓮實重彦がやったことは江藤淳のアイデアを掠め取り、膨らませただけであり、そこには何の工夫もなく、だらしがないと言わざるを得ない。「生なましく息づいている」などという感想は、「いかにもすき家でチーズ牛丼を頼みそうなオタク」という思い付きに対して、枯渇した想像力で「そうそう、いるよな」と同調してしまう中高生レベルのものである。こんなものを有難がる人は基本的に可笑しい。
そもそもオタクがクーポンを利用することなく、チーズ牛丼に半熟卵をトッピングするものだろうか? 果たして牛丼屋の全メニューの中でチーズ牛丼がいかにもオタクが注文しそうなメニューと云えるのだろうか? データはあるのか?
実は蓮實重彦の本の購買層こそがチー牛なのではないのか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
