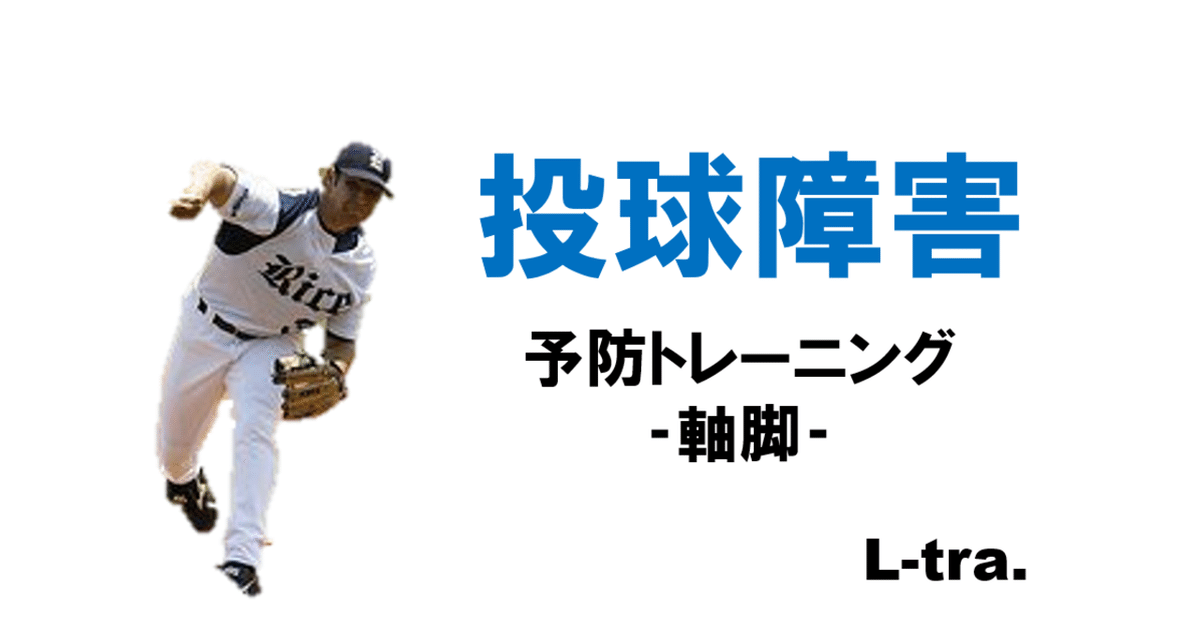
投球障害予防のための軸脚機能-柔軟性-
L-tra.投球障害予防シリーズ!
第3弾「軸脚機能」についてご紹介します。
前回までは上半身を中心に
投球障害につながる要因について紹介してきました。
これまで配信してきた内容を踏まえ
今回からは「下半身」を中心に紹介していきます。
投球障害が起こりやすい原因として、
痛みのある上半身、特に肩・肘に着目することが多いと思います。
上半身の問題がみられないけど、
肩・肘の痛みが続いてしまうという選手もいるのではないでしょうか?
そういう選手に必要になってくるのが
「下半身の機能」になります。

よく『下半身をうまく使えていない』
という言葉を聞くことがあると思います。
今回は
・『下半身をうまく使えていない』という状態がどういう状態なのか?
・それに必要な柔軟性とは何か?
を軸脚に絞って、ご紹介していきます!
軸脚に必要な柔軟性をチェックして、
自分に足りない部分を取り組んでみましょう!
■投球動作とは
まず、投球動作の考え方についておさらいしていきます。
投球動作とは全身の動きを伴う運動になります。
そのため、上半身だけでなく、下半身の動きも必要になってきます。
上半身を支えているのは下半身です。
下半身が不安定であるとその上の上半身も不安定になります。
投げて肩や肘を痛めてしまう選手の多くに、
下半身の問題によって投球フォームを崩してしまっていることがあります。

下半身にも上半身同様、柔軟性-筋力-連動性が動きの土台となります。
『下半身をうまく使う』ためには、
上記の中でも前提条件として柔軟性が必要になります。
柔軟性を獲得して『下半身を使いやすい』環境を作ることが重要です。
■軸脚が使えていない!その投球フォームとは?
ここでの投球フォームというのは、
肩の柔軟性・連動性編でも紹介した
・体幹の早く開いてしまう
・手投げ
など投球障害につながる不良フォームになります。
これらの投球フォームは結果的に起きてしまっているものであるため、そのフォームに至った要因となる下半身の改善を図っていく必要があります。

以下に、投球動作に必要な「軸脚の役割」を挙げます。

■軸脚の役割-3つのポイント-

軸脚の働きが不十分となり、負担のかかりやすいフォームになってしまわないように、軸脚が十分に機能する環境を整えてあげなければなりません。
そこで必要になるのが「柔軟性」です!
軸脚に必要な柔軟性について3つのポイントを紹介します。
ーーーーーーーー
<①投球動作のスタートとなる「片脚立ち」>
投球開始となる場面(ワインドアップ)では、
「片脚立ち」から投球方向に進む、並進運動にスムーズに移っていく必要があります。

片脚立ちから並進運動にうまく移れないと、下半身でパワーを十分に発揮できなくなり、上半身で”かばった動き”が大きくなってしまいます。
そのためには、
片脚立ちを行った際にお尻が垂れるような姿勢にならないようにする必要があります。
お尻が垂れないようにするためには、
軸脚と反対の股関節がしっかり曲げられることが重要になります。
図のBadパターンのように、脚を上げた時に軸脚の股関節も曲がってしまう場合は反対の股関節の動きに問題があることも考えられます。
<②軸脚での重心移動>
ここでは、並進運動といわれる動きが必要になります。
この並進運動によって、
次動作に移るための準備する時間を稼がないといけません。

軸脚での重心移動が早まってしまうと、準備時間が少なくなるため、内側にステップした動作(インステップ)などが生じ、”肘下がり”や”体の開いた投球フォーム”につながってしまいます。
そのため、
いわゆる「ため」と呼ばれる
軸脚でのコントロールが必要となります。
軸脚の膝が内に向いてしまうと
重心をコントロールする力が働きにくい状態になってしまいます。
軸脚で重心をコントロールするためには、
膝を外に開くことができる柔軟性が必要になります。
<③軸脚での蹴り上げ>
軸脚から踏み込み脚に重心を移していく際に
軸脚での最後の蹴り上げが必要になってきます。

ここでの重心移動が不十分になると下半身での重心移動が十分に行えなくなってしまいます。そのため、上半身の力に頼った”手投げ”や”前への突っ込んだ投球フォーム”につながってしまいます。
そのため、軸脚にて地面をしっかり蹴った、
踏み込み脚への十分な重心移動が必要となります。
蹴り上げを十分に行えるようにするためには、
股関節の柔軟性が必要になります。
Goodパターンのように股関節が後ろに伸ばせることで、
下半身のパワーをしっかり投げる方向に伝えることができます。
■軸脚柔軟性セルフチェック
ここまでお伝えしてきました軸脚に必要な柔軟性の内容を踏まえ、
「ひとりでチェックできる方法」をお伝えしていきます。

①反対側の股関節を曲げることができるか

方法|脚を抱えるように胸に近づけていく
Check point|太ももがお腹につくまで曲げられるか
②膝を外に開くことができるか

方法|仰向けで両脚を立てた状態から両側を開いていく
Check point|開いた膝の高さが床から10cm以内であるか
③股関節を後ろへ伸ばすことができるか

方法|うつ伏せでお尻を浮かせないように膝を曲げていく
Check point|踵がお尻までどのくらい近づくか
みなさんはすべてできましたか?
■改善ストレッチ
それでは①②③のセルフチェックの結果をもとに
それぞれの改善エクササイズをご紹介していきます。
①臀部のストレッチ
方法|
①伸ばしたい側と反対側の脚を斜め後ろへのばす
②伸ばした脚を滑らせながら、伸ばす方のお尻を斜め後ろへ突き出す
②内もも・裏もものストレッチ
方法|
①四つ這いになり、真横に脚を伸ばす
②つま先を上に向けたまま、お尻を後ろへ引いていく
方法|
①肩幅の2倍の幅に足を開いて、腰を落とす
②膝についた手で膝を外に開くように押しながら肩を入れる
③股関節の付け根・前もものストレッチ
方法|
①脚を前後に開いて、体を起こす
②骨盤を前に進めながら、身体を伸ばす方とは反対に倒していく
■さいごに
自分自身のカラダがどういう状態なのか把握して、今回の軸脚に関わる部分の柔軟性がない場合はストレッチしてケガの予防をしてみましょう!
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
ライター

|Twitter
https://twitter.com/hrkw031yk?s=20

|Twitter
https://twitter.com/ko_bmk
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
