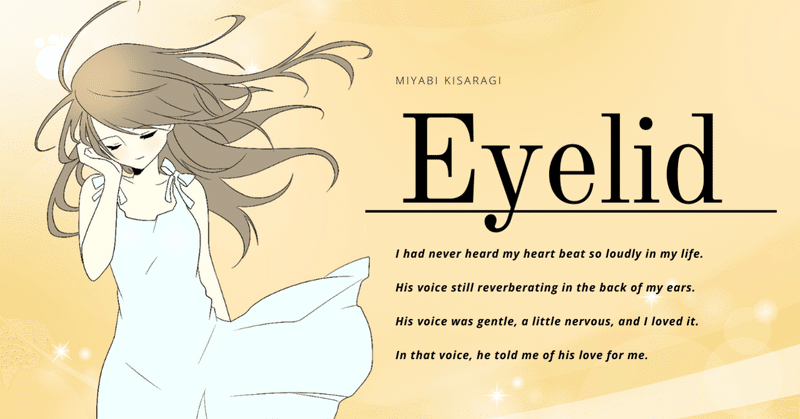
【掌編小説】Eyelid
どうしよう、まだどきどきしている。
自分の心臓の音がこんなにも大きく聞こえるなんて、生まれて初めての経験だった。
彼の声がまだ耳の奥で反響している。
優しい声、少し緊張した声、大好きな声。
その声で、わたしに向かって愛を告げてくれた。
場所はいつもの夜の公園。
ブランコに彼と二人、並んで腰掛ける。キイキイと少し軋むブランコをそっと前後に揺らしながら、とりとめのないお喋りをする。まるで世界に二人きりになったかのような、かけがえのない時間。
でもいつもは饒舌な彼が、今日に限っては妙に無口で、視線をあちこちに彷徨わせていた。私が不思議に思っていると、ふいに今まで見せたことのないような真剣な目でこちらを見つめてくる。
突然の展開に戸惑うわたしに向けて、彼が愛の言葉を囁いた。
彼の顔が耳まで真っ赤になっていたのが、街灯の薄暗い明かりの下でもはっきりと分かった。それはいまでもまぶたの裏にくっきりと焼き付いていて、いつまででも思い出せそうな気がする。
私は彼の言葉に小さく頷くと、彼の愛を受け入れる。
ふわふわとした気持ちのままで家に帰ってきたのは覚えているけれど、途中の道のりが思い出せないくらいわたしは舞い上がっていた。
ねえ聞いて! わたし今日男の子に告白されたんだよ。
わたしは母にそう告げる。
何かあったときは、わたしはいつも母に報告していた。
中学校でひどいいじめに遭ったときも、高校でこれからの進路に悩んだときも、まっさきにそのことを告げる相手は母だったように思う。
目の前の母は穏やかな微笑みを絶やさないまま、静かにわたしの話を受け止めてくれる。
「そっか、あなたも誰かに愛されるようになったのね」
うん。19歳って遅いのかな?
「誰かに好きになってもらうのに、早いも遅いもないと思うわ」
そうだね。うん。そうだと思う。
「それよりあなたの気持ちはどうなの」
わたし? わたしも彼のことが好き。大好き。
「それなら良いけど、あまり熱を入れすぎないようにね」
うん、わかってる。
「本当に? あなたは思い込みが強いところがあるから、お母さんは心配」
大丈夫だって。
「ほら、小学校のころに隣のおうちのタカシくんと喧嘩して大泣きしたじゃない」
もう。それは子供の時の話でしょ。わたしももう19歳なんだから。成人だってしているんだし、子供じゃないんだよ。
「世の中からみたらそうかもしれないけれどね。でも、わたしからみればいつまでだってあなたは子供なのよ」
……もう。それは、そうだけどさ。
わたしにとっても、お母さんはずーっとお母さんだしね。
たとえこの先わたしが何歳になったとしても。
「ふふ。そう言ってくれると嬉しいわ。ありがとう」
母は、いつでも私の傍にいてくれる。
何かあったときに私がまっさきに相談するのは、いつも母だった。
……ねえ、お母さん。……本当はね。
「なに? どうしたの」
本当はね。
わたし、お母さんとお父さんとのなれそめも聞きたかったんだけどね。
二人がどこでどうやって出会って、どうやって愛し合うようになって、わたしが生まれたのか。それに、わたしが生まれてどう思ったのか。
「……そっか。ごめんね。あなたもまだ小さかったし、本音でいうとわたしも恥ずかしかったからそういう話はあまりできなかったものね」
うん。
「そうね、でももうあなたも19歳かぁ。月日が経つのは早いものなのね」
このままだとすぐに追いついちゃうかも。
「そうねぇ。そうしたら今度はわたしが相談する番かもね」
それは、なんか恥ずかしいなぁ。いつまでも相談するのはわたしからでいたいかな。
「ふふふ。ごめんごめん。そうよね、安心して。いつまでだって、わたしはあなたの傍にいるわ。それはあのとき約束したでしょ?」
そうだね。うん。よく覚えてる。いまでもわたしを優しく撫でてくれた、あの手の温もりを覚えているよ。だからわたし、こうやっていつまでもお母さんに向けて、心の中でお話しすることができるんだもの。
わたしを生んでくれて、ありがとうね、お母さん。
「いえいえ、どういたしまして」
そうして、わたしはゆっくりと目を開ける。
目の前で優しく微笑む母の遺影を見つめ、それからもう一度小さく「ありがとね」とお礼を告げた。
更なる活動のためにサポートをお願いします。 より楽しんでいただける物が書けるようになるため、頂いたサポートは書籍費に充てさせていただきます。
