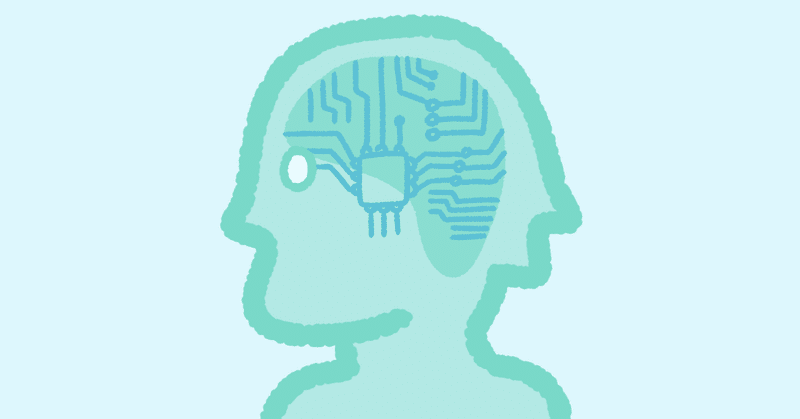
脳炎とは 【今日の医療知識 vol.18】
1.脳炎とは
脳炎とは、脳内に白血球が入り炎症を起こし、脳が障害される病気。
多くの場合は、脳自体だけでなく、脳を覆っている髄膜にも炎症が及んでおり、髄膜炎のような症状も併発する。
2.原因
(1)感染性脳炎
ウイルス、細菌、真菌(カビ)、寄生虫が病原体。
ほとんどのウイルス感染は急性の経過を辿るが、
麻疹ウイルスは長い時間脳に感染することで亜急性の経過を辿る。
JCウイルスは、免疫不全状態の患者さんが感染すると、
慢性的に進行する多発的な脱髄病変を引き起こす。
〈主なウイルス〉
・単純ヘルペスウイルス
→急性脳炎の約60%
死亡率10%
過半数が記憶障害や高次脳機能障害などの後遺症が残る。
・日本脳炎ウイルス
・コクサッキーウイルス
・エコーウイルス
細菌感染では脳炎よりも髄膜炎が主体となる。
(2)自己免疫性脳炎
病原体がいないのに白血球が脳組織を破壊してしまう脳炎。
ウイルス感染やワクチン接種、癌に伴う免疫反応などによる。
抗NMDA抗体と抗VGKC抗体が有名。
肺小細胞がんや乳がん、卵巣奇形種の患者さんは、
これらの自己抗体を産生しやすいといわれている。
さらに、橋本病や全身性エリマトーデスなどの自己免疫性疾患は、
その原因となっている自己抗体が脳炎を引き起こすことがある。
3.症状
急性脳炎は、一般的に発熱や意識障害が生じ、
炎症部位に依存する痙攣発作が生じる。
また、幻覚や人格変化、異常行動などの精神症状も現れる。
亜急性期脳炎は、感染後6~8年の潜伏期間を経て、
学業成績の低下や人格変化が起こる。
症状が進行すると、痙攣発作や視覚障害、末期には意識障害が生じる。
慢性脳炎は、視覚障害や認知機能障害、人格障害が生じる。
亜急性期と慢性期脳炎は、ウイルス性急性脳炎に典型的な発熱や頭痛が生じないことが特徴。
4.検査・診断
脳炎は1つの検査のみで診断できるものではなく、
いくつかの検査を行い、複合的に確定診断を行う。
脳髄液検査
ウイルス感染症による脳炎では、髄液のリンパ球増加とタンパク質軽度上昇がみられる。また、髄液のPCR法培養を行うことで、原因ウイルスの特定が可能。
画像検査
病変部位の特定し、脳腫瘍や脳膿瘍などとの鑑別を行うことが可能。
CTよりもMRIのほうが早期に病変を発見できる。
単純ヘルペスウイルスによる脳炎では、MRIで側頭葉に限局した病変が特徴的。
自己免疫性脳炎の原因となる腫瘍などの病変がないか調べることも可能。
脳波検査
脳炎では、脳全体に異常が見られることが多い。
ヘルペス脳炎は、側頭葉に限局して異常が認められる。
MRIと合わせて、早期病変発見に役立つ診断方法。
自己抗体
画像検査や脳波検査で脳炎が疑われたにも関わらず、
髄液検査で感染症を示唆する所見がない場合には、自己免疫性脳炎を疑う。
自己免疫性脳炎の確定診断には、自己抗体の特定が必要。
これには、血液検査や髄液検査を行う必要があり、
検査できる期間は限られているので、専門的な医療機関への入院が必要となるケースも。
5.治療
ウイルス性の場合
原因ウイルスにピンポイントで作用する抗ウイルス療法を行う。
アシクロビルやビダラビン。
脳圧が亢進している場合や痙攣発作を起こしている場合は、
それぞれに応じた治療が必要。
痙攣が生じていない患者さんにも予防で抗痙攣薬が投与されることがある。
亜急性期や慢性脳炎では根本的な治療はなく、諸症状に対応した治療を行う。
自己免疫性脳炎の場合
ステロイド投薬が効果的。
ステロイド投薬で改善しない場合や重度な副作用がある場合は、
免疫抑制剤や血漿交換、大量免疫グロブリン静注が行われることがある。
腫瘍による自己免疫性脳炎が疑われる場合、
全身状態が落ち着いてから外科的な腫瘍全摘出や抗がん剤、
放射線治療が行われることもあるが、
神経学的な後遺症に効果は期待できない。
6.参考
https://medicalnote.jp/diseases/%E8%84%B3%E7%82%8E
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
