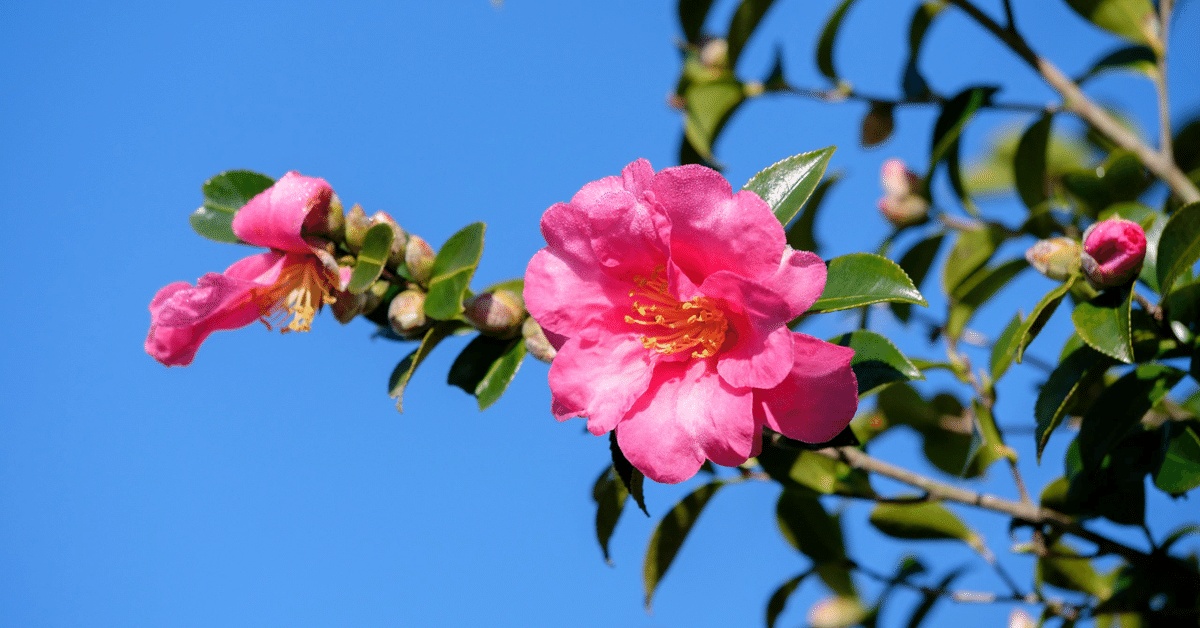
わからなかったら質問してね。に潜む罠
「わからなかったら質問してね」と教える側が教わる側に言います。
でもこれ、実際に質問すると「ちゃんと答えてもらえなくて傷ついて、もう質問をしなくなる」というパターンになることがよくあります。
そのような体験をされている方は、とても多いのではないでしょうか。
すると、質問者は質問をすることを諦めただけなのに、「質問がないから説明は出来ている。OK」と思う教え手が益々増えていきます。
学校で生徒が先生に、素直にわからないことを聞いたのに、「どうしてそんなこともわからないの」「ふざけているのか」「そういうものだと覚えておけばいい」などと言って匙を投げられてしまうことや、責められてしまうこともあるでしょう。
親子関係でも、上司と部下でも、こういうことはとても多いでしょう。
私は高校時代、化学が苦手でした。予備校で講師の先生に思い切って基本的なことを質問しに行ったことがありました。
確か、原子や電子の仕組みについてだったと思うのですが、どうしても自分では理解できなかったため、勇気を出して講師の先生に質問しに行ってみました。
授業後の講師控室に出向き、色々と尋ねました。でも疑問は解消されずに、「おまえがわからないって言っていることの意味がわからねえ」(べらんめえ口調の講師だった記憶)と最後は言われてしまい、とても嫌でした。
そういうものだと思え。そこに疑問は持たなくていい。というメッセージを受け取りました。そのあとその先生には一度も質問に行くことはありませんでした。化学も好きにはなれませんでした。
もしその先生が、私の「わからない」にとことん付き合ってくれて、「わかった」体験が出来たら、あるいは「わからない」という態度を、肯定的に評価するか、少なくとも面白がってくれたら、もしかしたら化学が好きになって、今とは違う仕事をしていたかもしれません。
つくばのカウンセリングルームではなく、産総研やJAXAで働く未来も、もしかしたら、あったかもしれないなあ(笑)
わからないのは自分がおかしいのかもしれない。そこに疑問を持つのは受験には必要がないことなのだろうな。これ以上質問にいくと迷惑だろうな。わかったふりをして問題を解けばそれでいいのだろうな。でも、嫌だな。いろんな気持ちになったのを覚えています。
疑問を持ち続けることや、とことんディスカッションをする文化は日本には乏しいように思います。その講師の先生は「聞きに来いよ」とよく言っていたので、この人なら話を聞いてくれるかも。と期待したのですが・・・。
「そこはそういうものだと思っておくこと」、「まあそこは触れないでおくこと」・・・こういった態度が「大人な態度だよね」とされる場面が特に日本では多い気がします。
こういう疑問を持ったことが、私が心理学の道に進んだきっかけのひとつかもしれません。
日本の学校では、校則問題でも、疑問を解消できない生徒はたくさんいます。なぜツーブロックはだめなんだ?とか。
政治状況でも「財源はない?裏金はどうなんだ」・・・・といったことまで。
我々支援者も、「困ったら相談してね」と言いつつ、相談しにくい構造を作っている可能性もあります。つまり、「勇気を出して相談したら、うやむやにされたり、迷惑そうにされた」などの体験を相談者にさせてはいないか。
相談してね、相談するな。の相反するメッセージをダブルバインドメッセージと言います。ダブルバインド=二重拘束です。2つのメッセージに縛られて動けなくなります。
ダブルバインドメッセージは、こころを混乱させ、支配するためにも使われます。
とても怖いものです。
カウンセリングでは、わかったふりをしない、わからない違和感は小さなものでも取り上げて、とことん話し合います。これがカウンセリングの魅力です。
でもこういう活動は、確実にマイノリティですので、自己理解が深まるにつれて集団での居心地は悪くなるかもしれません。
それでも。とことん話し合いたい。わかるまで考えたい。ごまかしや嘘は好きじゃない。ちゃんと聞いてほしい。
このようなニーズがおありの方には、とても合う取り組みだと思います。終了の期限を設けず、納得がいったら終了。という目標設定も可能です。
こころのメカニズムについて、コミュニケーションについて、親子関係について、性格について、器質について、わからないことを話していきたい、そういう場が欲しいという方は、ぜひ一度お問合せください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
