
【読書会】第13回レバレッジリーディング読書会(2020年4月)レポート
こんにちは!
4/18(土)の夜に、定例で行なっているオンライン読書会(レバレッジリーディング読書会)を開催いたしましたので、その内容をレポートしたいと思います!
参加者の読んだ本のリストもこのレポートの中で紹介しますので、もしよければご覧ください。
概要
まず、今回開催した読書会の概要を解説します。
この読書会は知識や知恵を得るための本をよく読んでいる方が集う、ボイスチャット形式のオンライン読書会です。 具体的には月に10冊以上の本を読むというのを一つの目安とし、コンセプトは「圧倒的な量のインプットとアウトプットができる読書会」!
読書会用のホームページも準備しているので、詳細が気になる方はそちらもご確認ください。
全体の流れとしては、まず順番に自己紹介を行い、その後に読書会のメインイベントとして①月間ベスト本の紹介と、②読んだ本リストを見ながらのQ&A形式のフリートークです。
読んだ本リスト
事前に参加者の方から3月に読んだ本のリストを頂き、主催である私がそれを一つの表にまとめて参加者の方々に配布しました。実際の読書会ではそれを見ながらの進行になります。↓が実際に使ったリストです。
個人利用の範囲で閲覧・ダウンロードは自由にしていただいて問題ありませんが、二次使用・無断転載等はご遠慮願います。

ベスト本紹介
リスト内の黄色塗りのセルは各参加者の月間ベスト本です。ここでは、それぞれの本について簡単に説明します。
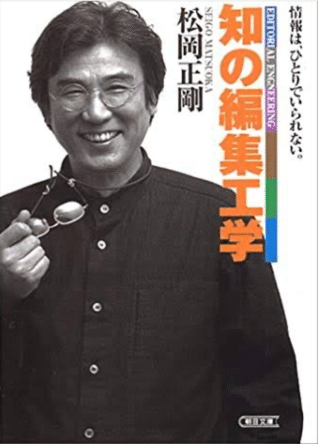
知の編集工学 / 松岡正剛(朝日文庫)
こちらは私が紹介させていただいた一冊。内容としては、一般的には雑誌や本などの出版の業界で使われるイメージのある「編集」という概念を拡張し、その本質に迫るというものです。この本における「編集」とは、膨大な情報の中からいくつかを選択し、なんらかの関係をつけていく行為であるとのことです。
面白かったポイントは、計算工学や脳科学、熱力学、歴史、社会や哲学など多様な分野を「編集」という構造で統合してところです。この本自体が「編集」についての「編集」をしていると言えるのかもしれません(ややこしいw)。とにかく知的好奇心を大いにかき立てられる一冊でした。
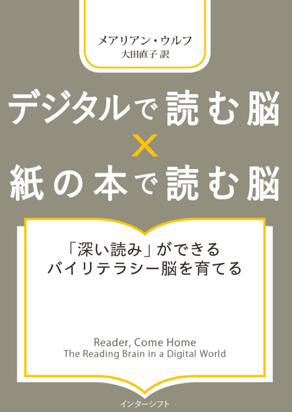
デジタルで読む脳 x 紙の本で読む脳 / メアリアン・ウルフ(インターシフト(合同出版))
こちらは、前回「未来をつくる図書館」を紹介していただいた方の紹介本です。人間が文字を読むとき、紙の本とデジタルデバイスでどのような違いがあるのかを心理学的に考察した本であるとのこと。色々な要素はあるようですが、全体的に見ると紙の本の方が深い理解には向いているようです。
私は電子書籍と紙の本の両方を読んでいるので、非常に気になる一冊です。斜め読みに向いているデジタルデバイスと、深い読みに向いている紙の本をどのように使い分けていくのは、これからますます重要になってくるのかもしれません。上手に使い分けていきたいですね!
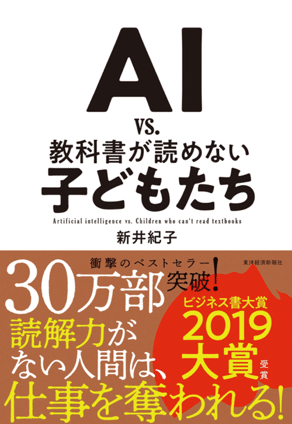
AI vs. 教科書が読めない子どもたち / 新井紀子(東洋経済新報社)
こちらは今回初参加の方の紹介本です。何年か前に話題になった本なので、ご存じの方も多いかもしれません。書かれているのは、AIが読解力を苦手としていること、そして、一般的に想像されている以上に中高生は読解力が不足しており、そう言った子どもたちがAIに仕事を奪われるのではないか、という懸念です。
私も一度読みましたが、冷静な視点からAIを考察し、それを教育論として昇華している良書だと思いました。特に先進技術に関する言説は、実態を伴わず過剰に装飾した「バズワード」的な扱いをされている傾向が多い中、専門家の視点から書いている本は説得力があります。なかなか難しい問題ですね。
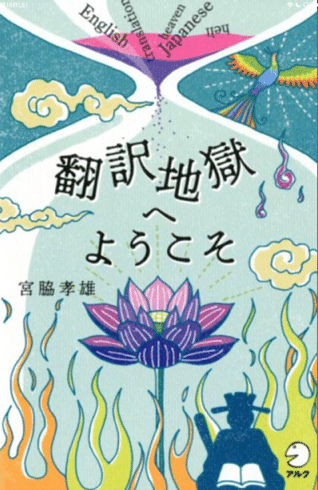
翻訳地獄へようこそ / 宮脇孝雄(アルク)
こちらは前回「怒りの葡萄」を紹介してくださった方の3月ベスト本です。筆者は翻訳の業界で一線を張っている方らしく、翻訳に対する心構えや翻訳や難しさについて語っている一冊だそうです。海外との文化的背景の違いや、言葉のニュアンスの違いからくる難しさなど、翻訳家ならでは視点が面白そうですね。
紹介された方は、最近話題になっている「Social Distance」を例に出しながら説明をしてくれました。「Social」のように、わかっているつもりの言葉こそ誤解をしやすいのではないかという指摘があり、妙に納得してしまいました。最近は外来語が多く使われているからこそ、考える必要があるのかも知れません。

日本のフェミニズム / 北原みのり(河出書房新社)
こちらは今回が初参加の方に紹介いただいた一冊。その方は「フェミニズム」についてあまり知らなかったので、3月にはその分野について色々と本を読んでみたとのこと。日本のフェミニズム運動の歴史について、知るきっかけになってよかったというコメントがありました。
正直言って私自身も完全の守備範囲外のテーマだったので、未知の分野について関心を持つ良い機会になりました。日本のフェミニズム運動が、一時期、各方面から批判されて下火になったことや、海外の動きとの関係など、興味をひかれる話を聞けたので、自分でも積極的に調べてみようという気になりました。
Q&Aタイム
今回もこれまでと同様に、Q&Aタイムとして、リストを見ながら1人1回づつ他の参加者に自由に質問ができるという時間を設けました。今回は人数が多く、すべての質問をキャッチアップすることは難しいので、個人的に印象に残ったところだけ紹介したいと思います。
私が質問させていただいたのは、「最後の秘境・東京藝大」という本について。タイトルの通り、一般にはあまり知られていない東京藝大の学生の実態について書いた一冊であるとのこと。私はあまり知らなかったのですが、数年前に話題になった本のようで、なんでもマンガ化もしているらしいですw。藝大生たちのカオスな感じがとても面白いとのことでした。やはり、新しいものを生み出すためには、少しくらいは尖っている部分が必要なのだなぁと改めて思い知らされます。
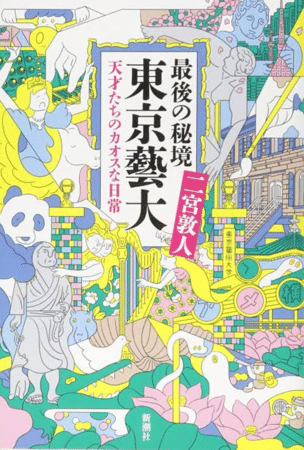
また、この時間に話題になったのが「レンタルなんもしない人のなんもしなかった話」。ご存じの方も多いかも知れませんが、筆者は「なんもしない」を提供している人です。こう書いてもよくわからないかも知れませんが、気になるかたはご本人のTwitterを見ていただくのがいいかなと。私も名前くらいしか知らなかったので、色々と詳しい話を聞くことができて、非常に興味深かったです。

最後に、アーシュラ・K・ル・グィンの「闇の左手」についての話題。この作品はゲド戦記で有名な筆者によるフェミニズムSF小説。「男女のない惑星」が舞台の小説で、「男女のある世界」から訪れた主人公が「男女のない惑星」の住人と、いかにして人間関係を築いているかを描いている小説です。3月にこの本を読んだ方は、そんな中で描かれる人間関係の美しさについて語ってくれました。
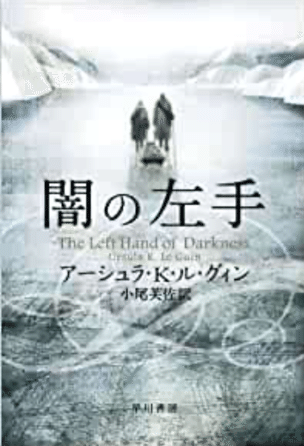
そんなこんなで気がつけば終了時間になったので、挨拶をしてお開きに。やはり人数が多いと色々な話が聞けて得られるものが多いと強く実感した90分でした。
まとめ
今回は先日行ったオンライン読書会のレポートを書きました。
今回もジャンルにとらわれず、様々な話が出来る会になったのではないかと思います。最近はオンラインでの読書会が増えてきたこともあり、わりと皆さんリラックスして話していたような印象です。緊張がほぐれてくると、お互いのやりとりが活性化されて、新たな気づきも増えてくるように思いました。この会としても継続してやっていく開催していくことで、お互いに良い学びの場にできればいいですね。
次回は5月16日の夜に開催予定です。すでに募集は開始しており、HPか読書メーターより参加申し込みが可能です。興味のある方は是非お申込みください!
ホームページからの申し込みはこちら
読書メーターからの申し込みはこちら
https://bookmeter.com/events/7418
それでは、また!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
