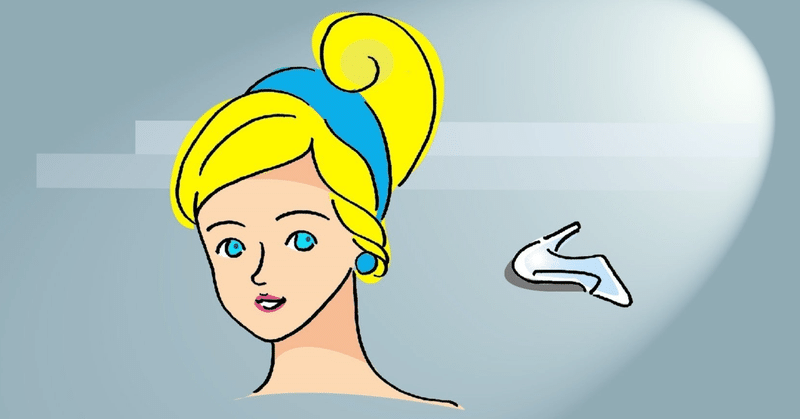
改変部 the1st- シンデレラ
☆約2万字。読了目安30分程度。
是非気になる見出しからお読みください!あなたの知っているシンデレラかもしれない。違うかもしれない。
改変部―それは、地球に存在する「物語」を改変する仕事。
あらゆる人間が学び、楽しみ、時に怒り、時に涙する、「物語」は計り知れない力を持っている。
私はセレーン。
改変部のメンバーは他に二人。ジャックとレビン。
我々が何者なのか、何の目的で物語を改変するのか、それは私の口から語ることではないだろう。
私自身、本部の命令には文句を言わず黙って従う、コマの一つに過ぎない。
ーま、根気よく読んでりゃそのうちわかることだ。
どうやって改変するかって?それは簡単。物語の世界に入り込んで直接干渉するんだ。タイムマシンで過去を変えるあれと一緒。
事実なんて意外と簡単に変わるものだ。
一言話しかけるだけ、
「お嬢さん、歯にキャベツ挟まってますよ」
たったこれだけで、着飾った娘は化粧室に行くし、その間に麗しの貴公子は別の娘とお知り合いになる。話が弾んで、キャベツ娘が戻ってくる頃には恋のチャンスは通り過ぎてしまっている。そんなもんだ。
あんまり前置きが長いのはつまらない。私はそういうタイプの本は読まない。
ので……、
改変部へようこそ!いざ、私たちのハチャメチャな世界に放り込まれたし!
「ジャック!セレーン!仕事だ仕事」
レビンは端末を片手に、大股でキャビンに乗り込んできた。扉が横開きの自動ドアで、バンッと音を立てて押し開くタイプではないのが惜しい。
ミッションはいつも、レビンの一声から始まる。
同じ事を二回言うのは彼の癖だ。
「こいつはでかいぜ!今までやったことないタイプだ。ほら、だって考えてみろよ。俺たちの今までの案件ってガキが夏休み最終日に慌ててでっち上げる絵日記とか、代わり映えしない日々に飽き飽きした独身サラリーマンが夜な夜な記す上司愚痴物語くらいだろ?」
無駄が多いのもレビンの癖だ。
「いいから早く本題に入れよ」
溜息と共にジャックが漏らした。
「ちぇっ、こっちを見もしない」
レビンは呟きにしては大きすぎる声量で吐き捨てる。意気揚々と乗り込んできたレビンは、メンバーの冷めた歓迎を受けながらも、素早く室内を見回し、颯爽と中央のソファにやってきてドカッと腰を下ろした。
解析装置を修理していたセレーンとジャックも手を止めてその両脇に寄る。
セレーンが腰を下ろすとレビンはニカッと歯を見せて笑いかけてくる。
ひょろっとしたレビンの身体の向こうからその様子を覗き込んだジャックは些かムッとしてレビンの膝をつついた。
そんなジャックをレビンは同じ顔のまま見遣ると、ようやく持ってきた端末に手を掛ける。
そして、開けてビックリ玉手箱とでも言いたそうな顔で彼はその内容を明かした。
「シンデレラだ!」
「シンデレラ?」
「それってあのシンデレラか?迂闊にも王子のところに靴忘れて帰ってくるあの?」
残念なことにジャックにはロマンどころか夢の欠片もない。巨体の堅物。熊みたいな彼は眉間に皺を寄せ、レビンが投影したスクリーン上のデータを遠目に見ている。
レビンはジャックの反応に笑みを漏らしつつ、目の前のローテーブルに乗ったビスケットを口に詰め込んだ。
「良いか?よく聞け?上が言うにはこうだ」
―王子とシンデレラが結ばれないようにしろ。
こぼれ落ちるビスケットのカスと任務内容。ジャックは青いモンスターがクッキーをむさぼるのを見てしまったような目で顔をしかめ、ティッシュを差し出した。
王子とシンデレラが結ばれないようにする?
『シンデレラ』とは、母親を失い、父親を失い、継母と姉たちにはいじめられながらも、何もなかった女の子が幸せをつかみ取るお話。
「こりゃまた大きく出たな」
ジャックが率直な感想を述べた。
「だろ?女の子は誰でもプリンセスになりたいんだよな。その中でも『シンデレラ』ってったら王道だ。だからよ、地球の子どもたちの夢と希望なのに。なんか可哀想だよなぁ」
「シンデレラが可哀想とか、地球の子ども達の夢を壊すとか、そういうのは蛇足。私たちは確実に任務を遂行する。それが改変部」
「さすが!セレーンちゃんはシンデレラ相手でも容赦ないねぇ」
レビンはおー怖い怖いと言ってこれ見よがしに肩を震わせる。そして人差し指を立て、ぶんぶん振り回して二人しかいないオーディエンスの注意を引き、言った。
「シンデレラをブスに仕立てるってのはどうだ?不細工過ぎワロタってやつ」
レビンはひょうきん顔を更に崩し、自分の発言に自分で笑う。
「お前ふざけてるのか?」
冗談の通じない男は真剣に文句を言う。
「ここはちゃちゃっと、ガラスの靴を入れ替えるってのは?」
セレーンの提案。
レビンは頷きビスケットに手を伸ばした。それを見たジャックはすかさずティッシュケースに手を伸ばす。
「シンデレラが落とした靴をぶん取って、姉二人のどっちかにサイズを合わせた靴とすり替える」
「無難で安全。これ一択だな」
そうと決まれば早速出発。三人は立ち上がり、それぞれこめかみに埋め込まれた本部との通信機に手を当てる。
「x5dセレーン」
「6ifジャック」
「re4レビン」
「改変部、エントリを確認しました」
キーンと鳴る起動音に続いて耳の奥にビリビリと伝わってくる機械音声。ミッション開始が本部に通達される。
「なぁ、俺向こうで白い馬買って良い?」
「何に使うのよ?」
「王子様になれるかなって!」
口許をニィっと曲げたその顔を見ると、レビンは結構本気で言っているようだ。
「あぁ、また女か」
ジャックはまさに苦虫を噛みつぶしたとしか思えない渋い顔を見せる。
そんなジャックにレビンはふんと鼻を鳴らしてビスケットをつかみ取ると端末のアイコンに触れた。食い意地に呆れるジャックの顔が見えたのは一瞬で、直ぐに目の前が真っ黒になり、真っ白になる。
改変部の極秘システム。名前も仕組みもセレーンは知らない。エントリが確認されると、物語へのワープホールが開かれ、セレーンたち三人はその都度、話に相応しいモブキャラに設定される。
持って行けるのはワープホールを開く端末一つとこめかみの通信機だけ。その他のチートは一切禁止。己のボディだけが頼りだ。
白く霞んでいた目の前が段々とはっきりしてきた。喧噪に包まれ、人々が通り過ぎていく気配が鮮明になる。
頭の奥を突かれたような衝撃の後、何度か瞬きをすると浮ついていた身体があるべき所に収まったような感覚を得られる。
人が行き交う道の真ん中、セレーン、ジャック、レビンの三人は突っ立っていた。両サイドには店が並び、店主と客の大きすぎる会話音、笑い声、砂を踏む雑踏それら全てが視覚情報と共に脳内に流入する。
「うわぉ、セレーン、良いドレスだぁ!だろぉジャック?」
「う、あぁ」
所変われど通常運転のレビンと突然話を振られて口ごもるジャック。
それをまじまじと観察したセレーンは危うく吹き出すところだった。
赤毛でひょろ長いレビンとガッシリで金髪大男のジャック。
二人の男はピッタリとした細身のズボンに緩いチュニック姿で、びっくり箱から飛び出してきた道化か、序盤でやられるくせに無駄にイキっている海賊みたいだ。しかも、正直なところ仕上がりの対比はかなりウケる。
セレーンは勝手に上がってしまう口角を抑えつつ自らの服装に視線を落とした。柔らかい生地のスカートが目に入る。シンプルな仕立ての薄いブルーのワンピースを着ている。
「あ、あれ見ろよ、あれ!めっちゃ旨そう!」
レビンが叫ぶと町民の何人かが振り返り、二人の男を認め、顔をしかめる。
「あの人たち見ない顔ね。怖いわぁ」
「近づかない方が良いわよ。この前の盗賊団の残党じゃないの?あのマルタンさんのお宅に入ったって言う」
「あぁ、あのマルタンさんね……」
「見てよ!噂をすれば影だわ」
顔を見合わせて何やら話していたと思えば、人だかりをかき分けて、小太りのご婦人がツカツカとこちらへやって来る。そしてレビンの前で止まると声を張り上げた。
「ちょっと!チキン野郎!この前は散々びびり散らかしてたくせに、また戻ってくるなんて、あんた良い根性してんじゃねぇか!今度は何が欲しいんだい?豚足かい?」
「はぁ?チキン野郎?俺はチキンじゃねぇよ!誰よりも強い色男さ!」
「あ?色男だって?よく言うよ!前は小麦粉の大袋に突っ込んで今にも泣き出しそうだったってのにさぁ!さあ来なよ!今日は肥溜めに突っ込んでやる!」
ご婦人は大きな腹を揺らしてガハハハと笑う。多分肝っ玉母ちゃんってこういう人のことを言う。
断じて自分の母親にはしたくない。
「ん?どうしたね?チキってんのかい?」
煽るご婦人。そして困ったことに、ここで大人しく引き下がるレビンではないのだ。
「はぁ? 俺はそんなことでチキったりしねーよ!」
道の真ん中で突如始まった罵り合いに続々と野次馬が集まってくる。
「なんだか知らないけど、喧嘩上等!かかってこいやぁ!」
まずい。目立ちすぎだ。誰かに通報されるのは時間の問題。牢にぶち込まれて汚い水を飲むなんてごめんだ。
「ねぇレビン……」
すると隣のジャックからはこれ見よがしな大きな溜息。
真顔で二人の間に割っては入るとご婦人に向き直る。胸ぐらを掴む勢いで女性を見下ろすと、片腕でレビンを指さして言った。
「おい!奥さん!目が悪いのか?こいつはどっからどう見ても人間だよ、鶏じゃねぇ!この赤いのはトサカじゃなくて髪の毛だ!」
ご婦人は豆鉄砲を食らった鳩の如く、ポカンと口を開けてジャックを見つめる。
ジャック、違う。そういうことじゃない。
するとご婦人は見る間に口許を歪め、叫んだ。
「こんのぉ!チキン泥棒がぁ!ウチの鶏を返しやがれぇ!」
ご婦人の叫びを待っていたかのように、野次馬が三人を襲う。
「痛っ!石は反則だろ!やるなら拳でかかってこいやぁ!」
レビンが言ってしまったものだから、民衆は躊躇うことなく飛びかかってくる。
「やべぇ!逃げるぞお前ら!」
「おいレビン、お前がそこにいると何も見えない。お前自分がデカい自覚あるか?」
「お前に言われたかねぇな、ジャック。俺ら三人で一番体積デカいのはお前だろ?」
「ちょっと静かにっ。見つかる!また騒がれたいの?」
開始そうそう鶏泥棒の一味と勘違いされ、半ば逃げるように繁華街を抜け出して町外れまでやってきた三人はシンデレラの屋敷にいる。
庭の茂みにデカい図体を屈めて息を潜めていた。
逃げてくる途中で、「まずはターゲットを見ておかないと」と言い出したのはレビンだ。
しかし、そんな彼が任務よりもむしろ彼女の美貌に見とれているのは疑いようのない事実。
「頭巾からはみ出た金髪は日の光を反射して遺憾なくその輝きを発揮し、薄く憂いを滲ませた整った顔はまさに守ってあげたくなる女の子そのもの。王子が惚れるのも頷けるぜ」
感嘆混じりにレビンは実況する。
ジャックはというと、さして興味なさげに掃き掃除をする女の子に視線を投げている。
自分は、デカとノッポのせいでほとんど見えない。
ジャックの横ににじり寄る。すると驚いたジャックがバランスを崩し後ろにひっくり返った。
「あーヤバい」
言ってる間にジャックは背後の枝をメキメキバキバキと虐待している。
「誰かそこにいるの?」
すると鈴の鳴るような高い声が上がった。どちらかと言えばかすれ声の自分とは違う、可愛らしい声だ。
あー、まずい。ここで見つかるのは計画外。
「シンデレラー!?庭の掃き掃除が終わったら次は大広間よ。わかった?」
「はい、お母様」
セーフ。
めいいっぱい首を伸ばすと屋敷の窓から身を乗り出している中年のおばさんが見えた。遠目でもよく映える盛り立てたヘアセットは彼女の顔を余計に大きく見せる。
シンデレラは返事をし、三人の視界の向こうに姿を消した。
レビンは背中についた残骸を落とすジャックをやれやれと肩をすくめて見遣る。
「助かったぜぇ。気をつけてくれよジャック。前にガキの日記に潜り込んだときも、お前が音を立てたせいでトリケラトプスに気づかれただろう?」
「あの時もセレーンが俺を押したから……」
「ちょっと、私のせい?」
「いや、それはその……」
しかし言い争っている暇は無かった。背後から足音がすると思った時にはもう手遅れ。
「見つけたわ!侵入者さん!」
振り返るとそこにいたのは、箒を片手に僅かに首を傾げて微笑む華奢な女の子だ。
―侵入者、さん?
「やぁ!脅かして悪いね。俺たちはぁその、靴屋なんだ!ちょっと入り口がわからなくて迷っちゃって……」
レビンは器用に体を反転させると、その達者な口で弁解をはじめる。
「レビン、靴屋って……」
セレーンが耳打ちするとレビンもコソコソと答える。
「そう言っとけば後で足のサイズ測らせてもらえるだろ?」
口から出任せ。こういう悪知恵は良く働く男だ。
女の子はキョトンとして眉を持ち上げ、そして直ぐに破顔してクスクス笑った。
「正面の門がわからなかったの?おかしな人」
「俺たち遠い田舎で靴屋をやってたんだけど、ほら飢饉でその村潰れちゃって。仕事がないかと思ってずーっと向こうから来たのよ」
いや、流石にそれは無理が過ぎないか?飢饉で村が潰れたなら少なからず噂は立つし。そんなことが起きればここにも影響しているはず。それに放浪の靴屋が突然屋敷に忍び込む意味がわからない。
チキン泥棒じゃあるまいし。しかし―
「あらそうなの?どうりでそんなにボロボロなのね。そうしたら今晩のお宿がないのではなくて?」
シンデレラは不審者の適当過ぎる作り話を何の疑問も示さずに受け入れた。
この娘、能天気なのだ。
「そーなんだよぉ!宿無しの可哀想な流離い者なんだ」
レビンがたたみかけるように訴える。
「お屋敷のお部屋は貸してあげられないけれど、物置小屋なら一角が空いているの。あまり居心地は良くないかも知れませんけど、良ければ一晩泊まって下さいな」
育ちの良さそうなお嬢さんは満面の笑みでそう言った。
「それじゃあ、甘えさせてもらうよ。ありがとう」
早速シンデレラが案内すると言うので、三人は彼女に続く。
目の前のプリンセスは綺麗な金髪を揺らし、水辺の白鳥を連想させる滑らかな所作でゆったりと歩く。その姿を見ていると、彼女が箒を持っていることに違和感を覚えた。やっぱりヒロインのオーラは隠せない。
「間近で見る後ろ姿も綺麗だねぇ。生のプリンセスは違うよ」
レビンが耳打ちするとジャックは鼻に皺を寄せる。
「お前キモいぞ。鶏のくせに」
「俺は鶏じゃねぇ!」
「さっき鶏に間違えられてたじゃねぇか」
「お前本気でそう思ってるのか?脳みそまで熊かよ!」
「なんだと?」
「ちょっと男子!静かにしなさいよ!」
黙って先を歩いていたシンデレラはチラリと振り返ってクスクス笑う。
「大丈夫よ。お母様もお姉様も外には出てこないし、屋敷は壁が厚いから庭の音はほとんど聞こえないもの」
そして小屋の前で足を止めると扉を背にして三人に向き直った。
「自己紹介をしていなかったわね。私はシンデレラ。この屋敷の娘の一人よ」
「自分で名乗るときもシンデレラなのか?俺はてっきり本名はエラなんだと思ってたよ」
何の気無しに言うジャック。途端表情を変えるシンデレラ。
まずい。多分それは言ったらダメなやつだよ、ジャック。
「いやぁごめんねぇ!ほら、シンデレラって珍しい名前だからさ。ちょっと捻ったあだ名なのかなぁって思っちゃうわけよ。シンデレラ、シンデレラ、シンダー・エラ、みたいな?あはは」
レビンがまくし立てるが、全く耳に入らない様子で、シンデレラは俯いた。そしてか細く言う。
「どこで私の名前をお知りになったの?」
つい先程までニコニコしていたシンデレラは瞳に涙を溜めて食い入るようにジャックを見つめる。
ここでようやく、ジャックはしまったと思ったようだ。そりゃ、初めて会った他人が本名を知っていたら怪しい以外の何でもない。
さっきまでチキン泥棒に間違われてたし、恐怖に涙も出るはずだ。
物語を知ってしまっているが故の過ち!
シンデレラは涙を拭うと下唇を噛んだ。箒を握る指の関節は白くなっている。
殴ってやろうか迷っているのかもしれない。
ジャックの巨体を彷徨う彼女の視線は、どこを突くのが一番効くかのか考えているのかもしれない。
「あぁ、本当の名前で呼んでくださる人なんてお父様が最後だったわ。ずっと呼ばれていなかったもの。そうよ、私はエラ」
シンデレラはレビンとセレーンが見ている前で箒を落とし、熱っぽくジャックの手を取った。
―え……うわー……
戸惑い、助けを求めるようにこちらを見るジャック。
そんな目で私を見ないでよ。自分が撒いた種でしょ!
「どうかあなたの名前を教えて!運命の方!」
「う、運命?」
ジャックはカラカラの喉から絞り出したような情けない声を発した。
シンデレラはドラマチックに涙ぐみ、一層強くジャックの手を握る。
「そうよ。どんなに辛くても夢と希望を忘れないでいれば、きっと素敵な方がやってきて私を連れ出してくれるって、毎日そうお祈りしていたもの」
「そうなんだよエラちゃん!ウチのジャックは運命の人がいる気がするって言って、俺たちが止めるのも聞かずにここまで来たんだから!」
レビンはここぞとばかりに、しゃあしゃあと言ってのける。ジャックの双眼から飛び出す、射殺すようなビームには気づいていない。
ピンチはチャンス!
これはレビンの数多ある座右の銘のうちの一つであるが、この男の吐くセリフでこれほど恐ろしいものはない。
シンデレラは目に浮かべた涙を美しくこぼしながら微笑み、ジャックに身を寄せた。
「あなたはジャックさんと言うのね。綺麗なお顔、逞しいお身体で、とっても素敵だわ」
確かに彼はブスではないが―。
大袈裟でくるくる変わる表情、多分なボディタッチ。
そりゃそうだ。一度踊っただけの王子にわざわざ靴の主を探させるほどのしたたかさと、男たらしの才能。それら無しではシンデレラは務まらない。
『おい!どういうつもりなんだよレビン!』
『いいから合わせろって』
口をパクパクさせてレビンに噛みつくジャックと涼しい顔でウィンクをかますレビン。
「でも、近々お城で舞踏会が開かれるんだろ!?王子が結婚相手を探すって」
悪魔に手を掴まれたとでも思っているのか、その手を振り払うこともできないまま、ジャックは真っ青になって苦悶に顔を歪めていた。シンデレラ、彼の苦手なタイプだ。
「王子様?」
シンデレラの目の色が変わる。
あー、合コンで目の前の男をさっさとロックオンして「私の彼よ!」みたいに振る舞っていたと思ったら、あとから合流してきた優良株にけろっと乗り換えようとする感じの女の子か。嫌いだ。
「シンデレラー!?ちょっと来なさいよー!洗濯して欲しいんだけど!!!」
もはや収拾不能とも言えるカオスな展開に、突如舞い降りた救いの神は二人の姉のどちらかの声だった。
「私、もう行かないといけないわ。お夕飯の時間になったら、お料理をお持ちするから。それまでバレないようにしてくださいね」
シンデレラは可愛らしい声でそう言うと、すっとジャックの頬にキスを落として去って行く。三人はその背中をあんぐりと口を開けて見送る。
「私、あの女嫌い」
「女の勘ってやつですか?セレーン先輩。
―って痛って!ど突くことないだろ?」
レビンに食い込んだ拳の余韻を感じながらセレーンはレビンを睨み付けた。
「ジャックとシンデレラがくっつく。そうしたらシンデレラは王子には興味を示さないし二人が結ばれることはないだろう?完璧じゃないか!」
確かに、否定する理由は無い。
「ちょっと待てって、俺には無理だよ!俺はぁ―」
「やるしかないよ、ジャック」
何はともあれ、結局のところミッション成功が第一優先事項だ。
頬にキスされて蒸気したままの顔をセレーンに向けるとジャックは諦めたように俯いた。
シンデレラはなんかいけ好かないが、よく考えれば彼女がどんな娘であっても自分には関係ない。
その日の晩、
シンデレラが持ってきたなけなしの残飯を囲い四人は輪になって食事をした。
メニューはパンとシチューの残りカス。
そうは言ってもパンがあるだけ豪華だろう。
誰のために持ってきたのかは、ここでは考えないものとする。
そして言うまでもなく、シンデレラはジャックの隣を陣取った。可愛い女の子の隣に行きたいレビンはその横に座り、セレーンはレビンとジャックに挟まれる。
ジャックの体が何となく自分に傾いているのは許してやろう。彼も不器用ながら頑張っているのだ。
「それにしても、エラちゃん!顔だけじゃなくて声もイイネ!可愛いよ」
パンを片手にレビンはだらしなく頬を下げた。
「本当? 嬉しいわ」
するとシンデレラは照れ笑いというのは名ばかりの、煌びやかな微笑を、少し顎を引いてレビンに向ける。
こんなに描写と実際がちぐはぐな行動があって良いのか?
シンデレラ恐るべし。これまた顔が良いから許されるのだ。
「セレーンさんも素敵な声だと思うわ。ほらちょっと低めで、なんだか……強そう」
褒めているのだろうか?けなしているのだろうか?
「そうそう、セレーンは強いんだよ!男に生まれるべきだったと俺は思うね!」
「ああ、セレーンは強い。声も、その……似合ってる」
「それってどういう意味よ!?」
散々に言われているセレーンを見て、うふふと笑うシンデレラ。
「仲良しなんですねぇ」と呟く。
そりゃ、小さな動物のお友達と歌いながら着替えるのが日課のお嬢様に比べたら、私の声は枯れてて低くて、可愛くないですよ。
口許に手を当ててクスクスと笑い、ジャックの肩に頭をもたせるシンデレラ。セレーンはパンにかぶりつこうとして開きかけた大口をさりげなく閉じ、小さくちぎった。
そうしているとセレーンを見て何かを思い出したのか、シンデレラは居住まいを正す。
「あの、これを見てくださらない?」
そう言ってエプロンのポケットから取り出されるのは例の招待状だ。
「先程届いたのよ。ジャックさんの言うとおりだったわ。舞踏会の招待状。年頃の娘は全員出席するようにって」
「もちろん、セレーンさんも明日出席するわよね?」と、シンデレラはそう尋ねた。
ああ、エラ、あなたも出席する気満々なのね。
「私、ドレスなんてもってない」
「それならお母様が昔着ていたのを着れば良いわ。きっと探せば二着くらいあるもの」
あなたは用意する必要ありませんけどね。
しかし、ここで思いがけず異論を唱えるのはレビンだ。
「え、でもエラちゃん、君にはジャックがいるじゃないか!」
ジャックはギョッとしてレビンを見るが、文句を言いたくなるのをぐっと堪える。顔には任務のため任務のためと書いてある。
「でも王命には従わないといけませんわ」
眉をハの字にしてそう言うシンデレラのなんたる破壊力。ズキュンと胸を打たれてしまったレビンはあははと乾いた笑いを漏らすしかなかった。
「それでジャックさん、私の付き人になってくださる?」
「え、それって、君の飼い犬の仕事だろ?」
「ジャック!」
レビンがたしなめる。口を滑らせすぎだ。魔法のおばさんはまだ登場していない。
シンデレラの怪訝そうな顔にジャックは慌て取り消しを試みた。
「ああ、あぁ何でもない」
結局シンデレラは、それじゃあ約束したからと言い残して小屋を出て行った。
レビンが言う。
「おいジャック!お前何とかしろよ!エラちゃんと王子がくっつかないようにさ。城に行くまでにブチュっとやっちまえよブチュっと!」
「無茶言うなよ!俺がそういうの苦手だって知ってるだろ?大体俺には理解不能だぜ。名前呼ばれたくらいであんなに熱上げられてさ」
「一夜で本物の愛見つけたって信じ込むくらいお花畑じゃないとシンデレラなんてやってられないのよ」
中央に置いた蝋燭がお互いの顔を照らし出す。
オレンジの光が浮かび上がらせるのはすっかり疲れた様子のジャックと、
それとは正反対に、「まだまだこれから!こっからが面白いんだよぉ!」とでも言い出しそうなレビン。
淡い光の中、レビンは咳払いをした。もったいぶって顔を見合わせ、口を開く。
「ジャック。キスができないならこうだ。明日、舞踏会の前にお前は彼女にこう言うんだ。『エラ、今夜は僕と二人きりで過ごしませんか?』ってな」
蝋燭に照らされたレビンの実演は見事なものだった。
最高に気取った表情で優しい目をする様は自分が見るとぞっとするが、客観的に見れば上出来だ。もうお前がやれよ!
レビンの話はまだ続く。
「それだけで良い。後は何もいらない。お前のチャーミングな金髪と青い目があれば何とかなる!」
「青い目はお前もだろ」というジャックのコメントは無視される。
「それでだ。もちろん俺とセレーンは城に行って王子が他の娘と結ばれるように図る」
息を詰めて聞いていたジャックは長い溜息をつき、おもむろに横になった。
「お前ほんと溜息多いな。幸せ逃げるぞ?」
「うるせぇ。俺はもう寝る。明日は長いんだ」
言い捨てると寝返りを打ってそっぽを向いてしまう。
「んじゃ、俺も寝るよ。狭いけど我慢してくれよな、セレーン」
レビンにはウィンクのない人生は耐えられないようだ。ここでも鮮やかに決めてきた。
「変なことするなよ?レビン」
「しねーよ!てかお前が心配することなのか?ジャック」
返事はない。と思ったが―
「何となく妹を思い出すのさ」
ジャックはボソッと口に出すと、チラリと顔をセレーンに向けてまた黙った。
そうして三人は眠りに落ちていく。
ジャックは前に言っていた。「俺には妹がいたと思う」と。
自分には家族はいない、と思う。
というのも、三人とも改変部に入る前の記憶はほとんど持っていないのだ。僅かに残っているのも、おぼろげでハッキリしない。
家族。セレーンはそれを知らない。曖昧な記憶でもこれだけは確かである気がする。
シンデレラには両親がいて、今も一応家族がいる。どんなものなのだろう。自分がジャックとレビンに感じている仲間意識、それとは違うものなのだろうか?
「私にはあんた達二人しかいないもの」
思わず言葉を漏らすと、ジャックが小さく呻いて寝返りを打った。
翌日。
事はシンデレラ物語の筋書き通り、順調に進んでいた。
天然男たらしの娘さんは、大量の仕事を押しつけられながらも器用にこなす。
そして母親のドレスをリメイクして着るも、姉たちにズタズタにされる。
で、彼女は今ここにいる。
「ジャックさん!どうしましょう。私、舞踏会に行けないわ」
いざ目の前にすると想像以上に悲惨な格好のシンデレラはボロボロと涙を流した。
破れたり裂けたりして、色々とギリギリを攻めているシンデレラを前に、オロオロとセレーンを振り返るジャック。
「まぁまぁ、そんなに泣かないでエラちゃん。なんとかなるよ!それに、仮に舞踏会に行けなくても大丈夫!俺たち四人集まれば楽しい事があるって!」
できるだけ楽に済ませよう。
舞踏会に行かなければ良い。
下心がちらついているとは言え、ここでフォローを入れるのはレビンの仕事だ。
「ダメです!舞踏会には行かなければならないわ!」
しかし、そこはやはりシンデレラとしての本能が訴えかけるのだろうか?シンデレラはキッと口許を結ぶと、止まらない涙に顔を伏せることもなく、より一層激しく泣きはじめた。
泣きじゃくる女の子なんてみっともないと思うだろうか?
これがまた不思議なことに、シンデレラがやると結構様になるのだ。
サファイアのような瞳から溢れる雫はセレーンから見ても美しいと思える。
しかしイライラしないかと言われればそれはまた別の問題だった。
泣いても何にもならないでしょうが!
「エラ……」
できるだけ腹の内の黒い感情を悟られないように、一応宥めるつもりで声を掛ける。
シンデレラはつと顔を上げてセレーンを見ると、しゃくり上げながらも語りはじめた。
「小さい頃ね、よくお父様と踊ったの。お母様はご病気であまり動けなかったけれど、私が踊るのを椅子に座って嬉しそうに見ていてくれたわ。それで約束したのよ。いつかお城の舞踏会に行って、素敵な方と踊るんだって。そうしたらお母様は私に言ったわ。強く願って、強く生きなさいって」
シンデレラは一拍おいて、肩をふるわせながら息を吸い込む。
「それなのに、お母様のドレス、こんなになっちゃった。私、この一着しか持っていないのに」
そう言ってシンデレラは数十分前までドレスだった物に触れた。途端、胸元がはだけて下着が露わになる。
レビンが物置にあったぼろ布を差し出すが見向きもせず、またしゃくり上げはじめた。
めんどくさ。
そう思うと、霧がかかったような昔の記憶が少し鮮明になる。
何にもない自分には、他人に語れるような思い出も無ければ、壊されたことを嘆く大切なモノだって持ち合わせていない。
それでも、何にもなくても、意地と根性で、時に汚いこともやりながら生きている。それがセレーンという人格だ。
あんたはおとぎの国の住人で、綺麗でいられるんだから、みんなに夢と希望を与えられる存在なんだから……
「しっかりしてよ!あなたシンデレラでしょ?灰にまみれた人生逆転して幸せになるんでしょ?諸事情あって、あんたが王子と結ばれることはないけど、泣いてないで夢を追い続けなさいよ!」
「セレーンさん……」
「これはぁ、舞踏会出ないといけないやつだなぁ……」
「おばはーん!魔法使いのおばはーん!もう出てきて良いんだぜ!」
寒空の下、レビンは天を仰いで叫ぶ。その声は夜闇に溶けて聞こえなくなる。
静寂。何も起きない。
「まずいよぉ。これじゃあ本当にエラちゃん舞踏会に行けない」
そんなのは杞憂だった。
「おばはんですって!?」
艶っぽい声と、ボンっと音を立てて何も無いところから突然現れたのは、ちゃんとフェアリー・ゴッドマザーだ。
「おばはんですって!?」
魔法の杖を持った白髪の女性はレビンに詰め寄る。
「え、えっとぉ、お姉さん! そう、お姉さん!」
いや、流石にお姉さんと言うにはちょっと年が行き過ぎだ。
「よろしい」
よろしい、のか?
フェアリー・ゴッドマザーは艶やかに微笑むとレビンにウィンクした。
レビンは片眉をつり上げる。反応を見るに、多分彼女は守備範囲外だ。
「さて、舞踏会に行くのはどなた?」
ゴッドマザーはくるりと四人を見回した。
「あなた?」
いや、私ではありません。
シンデレラはというと、おそらく目の前で繰り広げられている事件に全くついてこられていない。
今やすっかり涙は止まり、ゴッドマザーを穴のあくほど見つめているが、怪訝そうな顔を崩さないまま固まっている。
ジャックが優しく背中を押すと、シンデレラは一歩前に出た。
列を成して跳ねるキョンシーを思わせるぎこちなさで。
「あなたね?」
「えぇ。あの、あなた本物なの?本当にフェアリー・ゴッドマザー?」
「あらぁ、そうよエラ!私はあなたのフェアリー・ゴッドマザー」
ゴッドマザーは軽く杖を振る。するとフェアリーダストが結晶となって、シンデレラの眼前を舞った。煌びやかな結晶は暗闇に良く映える。
ようやく笑みを浮かべるシンデレラ。
「さぁさ、ぼさっとしてないでカボチャを持ってきて!」
「カボチャ?」
「それに、あなたの小さなお友達も必要よ!」
ビビディ・バビディ・ブー!
あれよあれよと準備は整い、我らがエラはすっかりガラスの靴のプリンセスに姿を変えた。
「エラちゃん、メチャクチャ綺麗だ!」
レビンは良い物見た!とご満悦。
「それに、男前だな!ジャック!お前じゃないみたいだ」
付き人ということで漏れなく魔法にかけられた熊さんはレビンにはやし立てられ、ムスッとしてそっぽを向いた。そんな顔の熊いそう。
フェアリー・ゴッドマザーはおほほと笑う。
「楽しんでらっしゃい!一二時までに帰ってこないとだめよ」
「それじゃ、俺たちも行きますか!」
先にジャックとシンデレラが馬車に乗り込むと、セレーンはレビンに続いて馬車に乗ろうとする。
内装までちゃんとできてる。やっぱりカボチャの筋が見えたりはしないのねぇ……とか思っていると、思いがけず腕を掴まれた。
「まさか、あなたたち二人も行くの?そんな格好で?」
「まさかまさか、そんなはず無いわよね?」とゴッドマザーは眉間に皺をよせ、口をへの字にして無言で訴えた。
もちろんそのまさかだ。
「別に良いだろ? 俺たちは踊るわけじゃないし」
「ちゃんと見つからないように忍び込むからさ」と、レビンはけろっとして言う。しかしゴッドマザーには聞き入れてもらえなかった。
「ダメダメダメダメ!」
セレーンを引き戻す腕力は相当なものだ。魔法で強化していたりして。
「そんな汚い服で舞踏会に行くですって?とんでもない!」
ビビディ・バビディ・ブー!
見るもまばゆいスミレ色のドレスを着たプリンセス・セレーンの誕生だ。
横を見るとゴテゴテに飾られたレビンがいる。
割と似合っているから笑える。
「セレーンさん!とっても綺麗!」
馬車の中から顔をのぞかせたシンデレラはついさっきまで泣きじゃくっていた女の子とは思えない、美麗な微笑を湛えていた。
「これでよし!さ、いってらっしゃい!遅刻する前に!」
杖を一振り、猛スピードで走り出す馬車。
「似合ってる」
小窓から吹き込む風に吹かれながら、隣に座るジャックがボソッと言った。
人の波に揉まれながらセレーンはできないダンスを試みる。
こんなことなら練習してくれば良かったと割と本気で後悔している。
セレーンが右足を出そうとすると、
「違う!左っ!」と上から声が飛んでくるし、
「次の三拍でターンだぞ!」とか、
「もっと俺を信じて体を預けろよ!」とか
―なんでレビンは踊れるのよ?
「モテる男はダンスが上手いんだ!俺はワルツは得意だぜ!」
顔に出ていたのかもしれない。レビンはすまし顔でセレーンが抱いた今世紀最大の謎に答えた。そしてその内容は案の定くだらない。
気の毒なのはジャックの方だった。
可愛らしいパートナーのドレス踏んづけては謝り、シンデレラに引っ張られるまま懸命にステップを踏む。
「ジャックさん、力を抜いて。ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー」
「こ、これで良いのか?」
シンデレラは困っているジャックを見つめ、花が咲いたような明るい笑顔で、クスクス笑っている。
「やきもちですか?セレーンお嬢様」
「はぁ?」
「痛っ!!!踏むことないだろ?しかもわざわざ踵で―」
そうして二人がターンすると、向こうの波にいる王子と目が合った。
「おいセレーン!王子がこっちを見てるぞ!」
レビンは器用にセレーンをリードし、ジャックとシンデレラに近づいていく。
「王子が見てる。ちょっと離れろ」
耳打ちすると、ジャックは顔をこちらに向けようとする。
「―うわぁ、ごめん」
「大丈夫よ。上手になってきたと思うわ、ジャックさん!」
「あ、あの、ちょっと中庭見に行かない?」
離れろと言われ、ジャックなりに考えたんだろうが―
「おいっ!下手くそ!」
レビンの合格を得るにはお粗末すぎた。
「あぁ、あのぉ。疲れちゃって」
シンデレラは僅かに首を傾げてジャックの顔を覗き込んだ。そして柔らかく微笑み、鮮やかなステップで上手に群衆から遠のきはじめた。
セレーンとレビンはハラハラしながら彼らの背中を見送る。ちょうど彼らが姿を消したタイミングで音楽が止まった。
周りで踊っていたカップルたちはお互いに頭を下げ挨拶をしている。パートナー替えだ。
「あの、お嬢さん。次のダンスは僕と踊っていただけますか?」
「はい?」
ジャックとシンデレラにばかり気を取られていた二人は慌てて声の主を振り返った。
「ジャックさん、本当は別の方のことが好きなんでしょ?」
中庭の噴水に腰掛けたシンデレラはジャックを見上げている。
鼓動が激しいのは踊っていたからだ。断じて彼女の言葉に焦っているからではない。
「え? 俺は別に好きな人なんかいないよ」
「あら、いつもセレーンさんのことを見ているから、てっきりセレーンさんのことが好きなんじゃないかって思ってたのよ?」
シンデレラは微笑する。
「セレーンのことは別に好きとかそんなんじゃ。妹というか、家族みたいなもので」
シンデレラは「あらそう?」と小さく言うと噴水の水に目を落とした。
「私、あなたのことが好きよ。あなたのこと、何にも知らないけれど、レビンさんを見る表情とか、セレーンさんの横で見せる仕草とか、素直で優しい人なのは良くわかるわ」
そう言って、花びらが浮く水面に映るのは可愛らしい女の子だ。鈴の鳴るような高い声で、守ってあげたくなる女の子の典型。確かに可愛いのは認める。
ジャックが何も言わないでいると、シンデレラは再び顔を上げた。
「今夜は舞踏会に付き合ってくれてありがとう。とっても楽しい」
そう言う彼女の様子はいじらしくて、セレーンとは違うなとジャックは思う。
苦手だ。とにかくこういう女の子は苦手だ。気を遣うし、今だって、なんて返したらいいか本当に困る。下手なこと言うとまた泣きそうだし。
そんな悩めるジャックを救ってくれたのはやっぱりレビンだった。
「おーいっ!ジャック!走れぇー!」
「え?」
凄い勢いで走ってくる赤毛ひょろノッポと、艶っぽい黒髪を振り乱す美女。
後に続くのはこの国の王子様だ。当然、王子を追いかけるお嬢たちの黄色い声も飛んでくる。
「待ってくれ!スミレ色のドレスのお嬢さん!せめて名前だけでも!」
一体何がどうなってこんなことになったのか……?
レビンは何やら喚いている。「やっぱ名作って半端ねぇ!」とか何とか。
何が何だかあまりよくわからないまま、ジャックとシンデレラは門に向かって走る。そうしていると、鐘が鳴り出した。まさに原作のシンデレラと同じタイミング。ちょうど逃げ出すときに。
ジャックは無意識に天を仰いだ。確かに名作は半端ねぇかも知れない。
要はプロットの強度が桁違いなのだ。
想像してみてほしい。ペラペラ下敷きをしならせて指を離すと、ビヨーンと元に戻るだろう?弾かれた下敷きの先端は戻ろうとする勢いでビヨンビヨンする。
改変も同じだ。
話を曲げると少なからず元の筋書きに戻ろうとする力が生じるわけだ。まぁでも、ガキの日記なら紙ペラと同じだ。少しの力で内容は簡単に曲がるし、その反動も大したことない。
ところが、シンデレラ級の名作となると、その材質は鉄板並だ。手を加えて曲げた部分がもとの筋書きに戻ろうとする力、そのエネルギーはガキの日記とはまるで違う。
今回の場合、シンデレラと王子が結ばれないように我々が改変しても、結局その他の部分は筋書き通りに進行しようとする。プロットの強度が高ければ高いほど、強引にでも敷かれたレールに戻ろうとする。
階段に差し掛かるとセレーンが躓いた。靴が片方脱げる。
セレーンは咄嗟に振り返るが、取りに戻るのは愚策と判断したようで止まらずに走り抜ける。
すると王子と共に追いかけてきた使用人が拾い上げようと指を掛けた。
すかさずひったくるレビン。
「これだけは絶対回収!てか、シンデレラガールのセレーンか!悪くないぞ!」
ダッシュで城を抜け出した四人は、
帰路の途中で元の姿に戻った。
二人の女の子はそれぞれ己のガラスの靴を抱えている。
確かにシンデレラの靴は小さかった。セレーンの足が特別大きいわけではないのに、二回りくらい小さい。
ジャックは自らの腕に視線を落とす。そこには、シンデレラの、自分をしっかりと捕まえて離さない女の子の手がある。
「あのさ、俺たち本当は違う世界から来たんだ。だから―」
「シーっ」
ぴったり隣を歩いて、腕を離してくれないのに、何を話すでもない沈黙に耐えられなくなったジャックは話はじめたが、シンデレラに止められてしまった。
そして急に立ち止まるので危うく転びかける。
驚いて彼女を見ると、シンデレラは靴を片方差し出した。
「これをお持ちになって。それから、どうか私を忘れないで―」
ジャックが顔を手元に向けて靴を見ていると、その腕に体重がかかり―
驚いた時にはもう真っ白。
思考停止。早鐘を打つ心臓。刺さるセレーンの視線。
背後から聞こえるレビンの「ワーオ、エラちゃんやるねぇ!」と言う声を聞いて、ようやっと半分くらい我に返る。
キスされたのか?キスされたのか?しかも今回はほっぺじゃない!本当に?嘘だろ?マジかよ?
「エ、ェエ、え、エラ?」
「夢を叶えてくれてありがとう。素敵な妖精さん」
あぁなるほど。別世界の住人=妖精だと勘違いされているわけか。
キスされた恥ずかしさと気まずさに死にかけているジャックと、妙に冷静なもう一人のジャックは脳内でせめぎ合っている。
「あのさ、俺たちはエラちゃんの夢の中でしか生きられないんだ。だから俺たちを忘れないでいてくれるかな?もしだよ?もし、王子が君を探しに来ても、間違っても王子と結婚したりしないで」
レビンが言うとシンデレラは頷いた。
「うふふ、わかったわ。約束する」
愛嬌のある爽やかな表情だ。これが吹っ切れたってやつなのかもしれない。一方的にキスしてさ。
三人とも舞踏会の余韻に浸っていたのだ。
そうに違いない。
そうじゃなければ、さっさとワープホールを開いて帰ってたし、シンデレラと一緒に屋敷まで戻ってくることはなかった。
だからここでピンチに陥ることもなかった。
セレーンは屋敷の門にいるその人物がもしかしたら亡霊なのではないかと思ってしまう。
「あなたは、娘さんたちと舞踏会に行ったんじゃ……」
セレーンたち四人を待ち構えていた巨大タマネギみたいな髪型の中年の貴婦人は口を開いた。
「昨日の夜、キッチンを通りかかったら、まだ沢山あったはずのパンが無くなっていたわ。シチューの残りも、いつもなら少し残っているのに、昨晩の分は一滴も残っていなかった。思い返せば、昼間、シンデレラが庭掃除をしていたときから何となく怪しいと思っていたけれど、まさかシンデレラ、あなたが賊を連れ込むような娘だとは、流石のわたくしでも思っていませんでしたわよ」
「賊だと!?」
喧嘩早いレビンは直ぐに食いつく。シチューを一滴残らず平らげたのはこの男だ。
タマネギ頭は魔女顔負けのギラつかせた目をレビンに向けた。その刹那、おもむろに持ち上がった杖が火を噴き、何やら光線が飛んでくる。
「ちょっ! あの杖は歩行用じゃねぇのかよ?」
レビンが華麗にかわしながらみんなの疑問を代表して口に出した。
魔法。魔法!?シンデレラのストーリーは何回も読んでしっかり頭に叩き込んだはずだ。継母って魔法使えたっけ?いや、使えないよな。
ああ。改変の反動か。やっぱり名作は半端ない。今までの案件みたいに、犬のはずが猫で登場するとかそんな甘っちょろいもんではないのだ。
―とか納得している間にも光線はびゅんびゅん飛んでくる。当たるとどうなるのかなんて考えたくないが、一つ重要なことは、物語の中での死はすなわち実存の自分も死すること。それだけは何としてでも避けたい。
「早くおばはんから杖取り上げないと、止まらないぜ?俺はとびきり的がデカいんだよ!」
ノッポ・レビンの悲痛な叫びに継母は声を上げて笑う。
「すばしっこいね。鶏みたいだよ」
「だから俺は鶏じゃねぇって!!!」
「俺とレビンが距離を詰める。気を引いている隙にセレーンは杖を奪い取れ!」
門の手前に鎮座している天使の像に身を隠したジャックはセレーンを引き寄せて言った。
「ダメ!私が先に出る!あんたたちが前じゃデカすぎてバックアップできない!」
「それはダメだ!危険過ぎる!」
セレーンが出て行こうとするとジャックが手を引いた。ダメだと言って譲ろうとしない。
「ジャック!このままじゃ埒が明かない!」
視界の端には集中砲火を受けているレビンがいる。
「私が行くわ!」
―え?
「ジャックさん、セレーンさん、私はあなた方二人を信じているから!」
言うが早いか隠れていたシンデレラは飛び出した。慌ててセレーンも後を追う。
「おいっ!ダメだって!……あーくそっ、俺の苦手なタイプだ!」
シンデレラが飛び出すと的はすぐに彼女に変わった。
「シンデレラ、ずっと目障りだった。お前ばっかり美人で、愛されて、わたくしと娘たちが可哀想だわ」
「みんな私が悪いって言うの?そんなのおかしいわ!あなたが美しくないのは、心が美しくないからよ!」
怒鳴り返す傍らのシンデレラ。散々泣いていたあの女の子は一体誰だったのか。
あんた結構言うじゃん!
しかし余計なことを言うもんだから、継母はますますいきり立って執拗にシンデレラを追い回した。
チラリと後ろを振り返るとジャックとレビンは合図を交わしている。
「シンデレラ!お前なんか消えてしまえぇ!!!」
―危ない!
反射的にシンデレラを突き飛ばすセレーン。
その勢いで体勢が崩れ、顔面から倒れ込む自分に、緑に光る怪しい光線は飛んでくる。
―ヤバっ!
自分は撃たれて死ぬのだ。
―え?
前に転ぶはずだった自分の体が強い力で後ろに引っ張られる。
光は左手前すれすれを通り過ぎ、
後ろに倒れ込むとそこは冷えた土ではない。
温かくて、何故か心地良い。
「ギリギリだったな。大丈夫か?」
「う、うん。ありがと」
ジャックの体にもたれたまま、半ば呆然と前方を見るとちょうどレビンが後方から杖をはたき落とすところだ。
走り寄ったシンデレラは杖を拾い上げ、真っ直ぐに継母に向ける。
次の瞬間、緑の光線がタマネギ頭の真ん中を貫き、消し飛ぶ。
うわぁ……容赦ない……。
レビンが素っ頓狂な声を上げて飛び退いた。
「うぎゃあ!おばはん蛙になったぞ!」
シンデレラの手に乗せられた蛙を三人は寄り集まって眺める。
「小さくなったら意外と可愛いじゃない」
優しく微笑んでそう言うシンデレラ。
え、マジ……?
シンデレラは指の腹で蛙の頭を撫でる。蛙はゲコッと鳴く。
するとシンデレラはクククッと笑った。
「肝の座った強そうな鳴き声ね。やっぱりお母様だわ」
「セレーンも蛙になってたとしたら、似たような鳴き声だな、きっと」
レビンは悪そうな顔で笑う。ムカつく。
しかしセレーンが言い返すよりも前にジャックが言った。
「こんな汚い鳴き声じゃない。もっとその……ハスキーボイスで良い感じに鳴くんだよ」
町外れの屋敷では四人の笑い声が響く。星の綺麗な澄み渡った夜だった。
セレーン、ジャック、レビンの三人はソファに座り、スクリーンを眺める。
―自らの手で継母を懲らしめたシンデレラは、屋敷の女主人となりました。困った時はその屋敷を訪ねてみなさい。魔法の杖を使って、きっとあなたの夢を叶えるお手伝いをしてくれますよ。めでたしめでたし。
「良い話だ!」
レビンはまた一つビスケットを口に放り込む。
そんなに食べたら口の中が干からびるのではないかと、セレーンは常々思っている。
「そういえば、なんであのとき追いかけられてたんだ?」
ジャックはレビンの身体越しにセレーンを見る。
「それはだな」
レビンは深刻そうに目を細めてジャック、セレーンを交互に見た。
「早く言えよ」
大きく息を吸う音が隣から聞こえる。
「エラちゃんとジャックが中庭に行ったあと、王子が来てセレーンに言ったんだよ。一緒に踊ってくれませんか?って。そしたら、セレーン、君ったら断らないからさ、王子と一曲踊っちゃったわけ。それで二人きりになりたいって言われて慌てて逃げ出して来たんだよな?」
レビンが言い終わると、すぐジャックの低い声が続く。
「セレーン、王子と踊ったのか?」
「悪い?あなただってシンデレラと仲良くしてたじゃない!キスまでしちゃって!」
「どう考えても、あれは不可抗力だろ!?」
レビンを挟んでジャックとセレーンは睨み合う。
「はいはーい!二人とも!痴話喧嘩しないの!」
―レビン!あんたは黙ってて!
―レビン!お前は黙ってろ!
―エピソード1 完
☆シンデレラのストーリーはディズニーバージョンを元にしています!
ジャックとセレーン、恋の予感?
エピソード2はそのうち発表!彼らが次に飛び込むのは一体どこなんでしょう!?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
