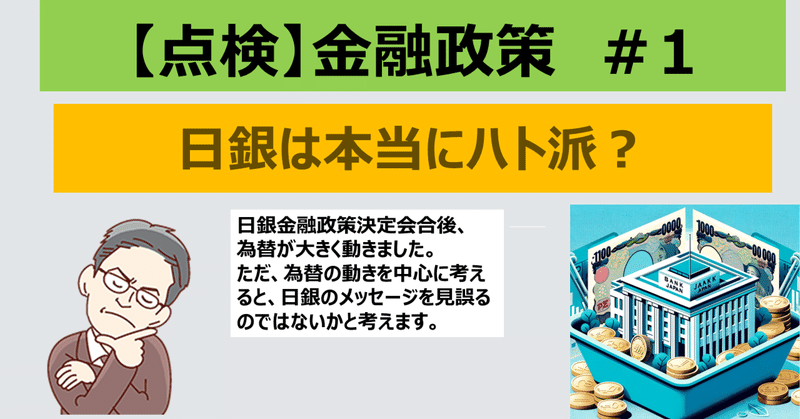
日銀金融政策決定会合は本当にハト派だったのか?
日銀金融政策決定会合の結果が据え置きかつ公表文も短く、QT(量的金融引き締め)や利上げの示唆といった、市場期待への「ゼロ回答」の印象が強かったので、早期利上げ観測が後退した。とマーケットでは説明されている。
市場では、事前に国債購入額を減額する方法検討と時事通信が報じていたことから 、注目されていたが、減額を強く示唆する内容ではなかった。
「6 兆円」という数字はなくなったが、「2024 年 3 月」の決定という文言があるため、タカ派とは捉えられていない。今後の金融政策についての言及もなくなり、超シンプルな声明文だった。
植田総裁はフォワードガイダンスで、先行きの政策パスを明示的に示すことによって、不確実性を低下させ、市場経済からリスクを取り除く(リスクプレミアムを低下させる)ことを重視してきた。
今回、国債購入額や利上げパスについてまったく指針を示さないということは、市場に対して不確実性が高いということを示したいという意味で、政策の自由度を確保したいという考えがあると考えられる。
円安が進んでいることに対して日銀がタカ派方向に動く可能性をマーケットは期待していたが、このような「催促」から日銀は距離を取った。
つまり、日銀は「為替」によって政策を変更すると市場に捉えられることも避け、円安の進行は財務省による為替介入によって抑制していくことになる。
一方、日銀が判断する「利上げ」に関しては景気や物価の指標を確認しながらゆっくりかつ淡々と利上げを進めていく。
記者会見での質問が、円安が金融政策に与える影響に集中しており、植田総裁は現時点で円安に対応して金融政策を変更する可能性を事実上否定しているため円安容認の部分が強調された。
また、国債買入額の変更を金融政策調節手段として用いる意思がないとしたことも、QTに否定的なイメージで捉えられたのかもしれない。
しかし、私が重要と思ったのは、「安定的な物価目標が実現する段階で、政策金利は概ね名目中立金利に接近している」との見通しを示した部分だ。
展望レポートでは、2026年度末までの見通し期間の後半に「安定的な物価目標」が実現する、との見通しを示している。つまり、今後3年間で政策金利が名目中立金利に近づくことになる。
植田総裁は名目中立金利の水準については言及していないが、3月決定会合後の記者会見で、現在の政策金利は名目中立金利をかなり下回っていると発言している。
安定的な物価目標の実現は名目中立金利の一段の上昇につながるため、1~1.5%になると考えて良いのではないか。
おそらくマーケットでは、0.5~0.75%がコンセンサスであるので、短期金利が市場の想定上に引き上げられる可能性を示唆していると考える。
植田総裁は、今後基調的な物価上昇率が日銀の見通しに沿って上昇すれば、政策金利を引き上げてゆくとも発言している。
つまり、日銀が追加利上げ、それも複数回の利上げを視野に入れていることは明らかだ。仮に自然利子率を小幅なマイナスとみても、見通しのインフレ率の水準を踏まえると、中立金利の水準が1%割れとなることは考えづらい。
展望レポートや植田総裁の発言を額面通り受け取れば、見通し期間後半、すなわち25年度後半にも政策金利が1%以上になる可能性がある。
ただ不思議なのは、政策金利に関してはタカ派的な色彩を帯びているのに対して、なぜ、為替とQTの部分ではその様な姿勢が見れなかったのかということだ。
2022年12月、2023年7月、2023年10月、2024年3月の政策変更は全て、通貨防衛の色彩を帯びていた。特に2023年7月は、通貨防衛にも触れている。にも拘らず、なぜここで日銀は為替から距離を置いたのか?
そこで取沙汰されているのが、「新藤大臣は何をしに金融政策決定会合に参加したのか?」という点だ。現役大臣の参加は何か重要なメッセージがあると考えるが基本だ。

今回の出席の意図は不明であるが、QTや利上げ示唆を自粛させた可能性も考えられる。
政府と日銀の駆け引きは今後金融政策を考える上での不確定要因になるのかもしれない。
ただ、政策変更のスピードはともかくとして、現在の環境が続けば、利上げ・国債買い入れ額の減額の方向には進んでいくと考えられる。
私は日銀ウォッチャーではないので、時期や幅に対しては特に意見はない。ただ、株式投資家として押さえておきたいのは、日本経済が着実に金利のない世界から金利のある世界に動き出している事と、デフレからインフレへの転換。また、このことは意識はされつつも、まだ十分に予想に反映されていない様に感じる。
掲載されている記事は、個人の見解であり、執筆者が所属する企業の見解などを示すものではなく、証券投資や商品申込み等の勧誘目的で作成したものではありません。
記事の情報は信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その確実性を保証したものではありません。最終的な投資決定は、読者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。
当コラムの閲覧は、読者の自己責任でなされるものであり、本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。
なお、記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
いただいたサポートは主に資産運用や経済統計などの情報収集費用に使わせていただきます。
