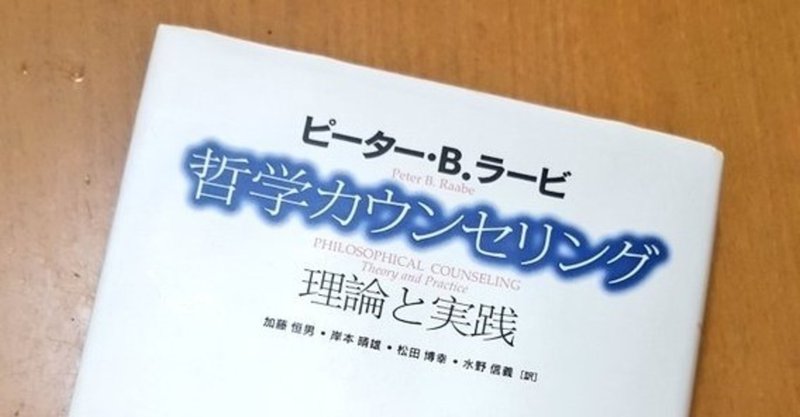
ピーター・B.ラービ『哲学カウンセリング』
ピーター・B.ラービ『哲学カウンセリング』を読んだので、そのメモなどを3-4回に分けて紹介します。Ⅰ-Ⅲは一度Facebookで紹介したものです。
メモⅠ 「哲学カウンセリング」の四段階
ラービは「哲学カウンセリング」を四つの段階からなるものと考えることによって、「哲学カウンセリング」についての従来の錯綜した状況を、整合的/包括的に理解できると述べます。このラービの理解の仕方は、ただ先行研究の定義を否定するのではなく、それらを統合し包括するという意味で、優れた整理であると思われます。以下、簡単に概括し、考察していきます。
①自由浮遊
・共感しながら傾聴する段階。なるべく自由率直に話してもらえる促し、クライアントの要望、悩み、問題を理解する段階。
②当面する問題の解決
・①で明らかになった、クライアントの問題の結ぼれをほどき、分類整理することで、攪乱された均衡を回復する段階。
・カウンセラーが一方的に問題を解決するのではなく、カウンセラーとクライエントの間の話し合いの中から生まれ育つ知識によって、問題は解決される。
・クライエントのパラダイムまでは問わずに、パラダイムや信念体系の内で議論すべき(神への信仰を持っている人に対して、「そもそも神はいるのか?」とは問わない、ということ)
・カウンセラーは問題を明確にするための質問をしたり、異議をさしはさむことで、クライエントの思考パターンを明らかにし、クライエントが問題を客観的に吟味できるようにする。
③意図的行為としての教育
・②で生じた洞察を活用し、クライエントの自律性を高め、カウンセラーの助けがなくても、自身の人生やそこで生じる問題についての批判的吟味と再構築を可能とする段階。
・多くの哲学カウンセラーは、カウンセリング行為そのものが教えるということでもある、つまり意図的な教育をしなくても教育はなされていると考えているが、ラービはそれは間違っているとする。
・哲学探究の方法を身につけるためには、クライアントの側に、或る気構え、特定の精神的態度が必要であるが、それは自分の心配事や恐れに巻き込まれ、それを解決しようとしている②の段階では難しい。
哲学カウンセリングにおける教育についての三つの基準
(1)意図的であること(カウンセラーは教えるという明確な意思を持って、クライエントに臨なければならないし、クライエントもそれらを学ぼうという意思を持っていなければならない)
(2)主題が明確に提示されていること(カウンセラーは、哲学的推論技術について、それらをたんに応用するだけではなく、それらを説明、実証など、それらと積極的に関わっていかなければならない)
(3)クライエントが、知的にも感情的にも自分の当面する問題の議論を(少なくとも一時的にであれ)超え出る用意ができており、その注意をカウンセラーが教えようとするものに集中することができなければならない。
・カウンセラーは、クライアントの推論における未確認の虚偽を穏やかに訂正することからはじめ、それらが虚偽であることを指摘し、それらを分類しラベルを貼って確定し、将来にわたってそれらを処理し回避する方法を提案することへと進む。
~「自己診断」の能力、批判的創造的思考の能力の涵養
「批判的創造的思考による哲学的探求はまた、議論の感情的側面、すなわち、話し手と聞き手双方の態度と感情とを、承認し理解しようとするものである。…哲学カウンセリングにおける哲学的探求は、孤独な、独立した認識努力ではなく、むしろある種の「心の出会い」なのであって、そこにおいてクライエントとカウンセラーの一対の相互依存こそが、自己自身について単独の思索者として成し遂げるよりも、より意義深い認識の場を形成するのである。」(229頁)
・ただ物事を違った風に見るのを援助するということ(②)と、その自律を高める哲学的推論過程の理解といったところに到達させるということ(③)とは、異なる。③をなすためには、どのようにして物事を違った風に見るようになり、それを可能にしたのは何かを理解しなければならない。
④超越
・思考技術を学んだうえで、問題の確認や明確化や解決にはるかに熟達した主たる探求者として、いわゆる「自己診断」を行う者として、以前の問題に立ち返る段階。
・自己自身を改善進歩させ「より深く、より豊かで、よりよい生活」、他の人びととの関係でも「より意義深い生活」を送るために、自己自身のより洞察力のある理解へと至る道。
・何がなすべき正しいことなのか、という倫理的問題への実践的答えを見つけようとすることをやめて、そうした答えの基礎にあるメタ倫理的基礎を考慮検討する。
・この道は、「孤独なもの」ではなく、クライエントとカウンセラーの協力によって構築される。
・②では、問題解決は、短期的なものであり、狭い範囲の偶発的出来事に限られていたのに対して、④では、より長期のもの、より大きな状況へと広がり、全体としての人生が吟味される。
・クライエントは、問題をばらばらな出来事として捉えるのではなく、全体的に捉えようとし、すべての出来事を貫く「糸」、共通性を認識し、それは自分が何者であり、どこにいるのかに深く関連していることを知る。
・自分自身に対しても「本格的に向き合う」こと、自分自身に耳を傾けることになる。
------------------------------------------
メモⅡ 若干の覚書(Ⅰの続きです)
①と②は、二人で行う哲学対話といってよい形式といえます。しかし、二人で行うことと、一方が専門家であることによって、多数で行う哲学対話と比べて、内容にも変化が生ずるだろうことが予想されます。第一に、ラービが繰り返し指摘するように、精神医療との重複があり、そういった状態のクライエントとの対話となりやすいこと、第二に、二人で行うことにより、内容がプライベートなものになりやすいこと、です。また、両者の親密性が高まることで、問題に対する客観的な視座を確保することの難しさにつながるということもありそうです。
③および④が、ラービの哲学カウンセリングの最も特徴的な点であり、現在の日本の哲学対話(哲学カフェ)文化において、あまり重視されていない点といえるでしょう(多分)。つまり、哲学カフェに参加して、これまでの考えの偏狭さに気づき、より自由になるという体験を得ることはあっても、それがいかなる仕組みでなされ、次にそのような自由を独力で得ようとした場合に、どうすればよいのかが体系化されていないように思われます。(無論、意図的な教育など必要ないという立場もありますので、するべきかどうか/必要かどうかは議論が必要です。)
ラービによれば、哲学的な思考能力(「批判的創造的思考」)は、②では身につかないわけです。これは、哲学カフェや哲学対話にただ参加するだけでは、哲学的な思考能力は身につかないという主張と、ある程度読み換え可能といえるでしょう。それを身につけるためには、③まで進まなければなりません。具体的には、クライエントとカウンセラーが②での対話を振り返り、そこでの対話の流れを再考し、クライエントが用いた手法を意識させることを行うことです。
このような③を経ることで、ラービによれば、④の「超越」に進むことになります。これは、私の理解では、③の「教育」を経たうえで転回し、再度②で検討したような自分の問題について向き直ることといえます。②では、その問題に囚われており、ただその個別的な問題の解決をするしかなかったのに対して、③の「教育」を踏まえることで、その他の問題との関係や、また自分の人生というより大きな文脈でその問題を考察することができるようになるといえます。そうすることではじめて、今後の人生で起こる問題を先取的に予防したり、問題に巻き込まれた場合でも、以前とは異なった仕方で対処することが可能となります。
--------------------------------------------------
メモⅢ 「哲学カウンセリング」の限界
ラービ『哲学カウンセリング』のよいところ・妥当な点は、哲学の危険性および哲学カウンセリングの限界について、適切に指摘している点です。
まず、哲学の中にある危険とは、人がすでに持っている有害な偏見や不埒な道徳的立場を正当化するために、哲学的推論技術が用いられることです。たとえば、「殺人は正しい」という観念を否定できず、補強してしまうというようなことがあげられます。
それに対してラービは、これまでのセラピストや心理カウンセラーらの議論を踏まえながら、カウンセラーは、クライエントや社会一般に対して、特定の状況においては、非中立的であるべき道徳的義務を持つべきであり、どんな内容であってもクライエントが自分の結論に到達するのを助ければよい、とするだけでは不十分だと結論します。つまり、哲学カウンセラーは、クライエントの推論における適切さと道徳的受容性について価値判断をすべきであり、そこでは中立的でなくてもよいとします。
「哲学カウンセラーは、クライエントがただ道徳的にみて差し支えのない道理にかなった目的を達成するのを援助することを当然選ぶであろうが、そのような哲学カウンセラーは中立的であるべきだと要求することはできない。絶対的中立性は、クライエントに間違ったシグナルを送るだけでなく、劇的な逆効果を及ぼすことさえありうるのである。」(285頁)
また、哲学カウンセリングの「限界」については、薬理学的あるいは外科的介入が必要である場合や、心的外傷後ストレス症候群などの場合には、他の手法を用いるべき、あるいは協働するべきであるとします。また、クライエントが家族の愛情をカウンセラーに求めているという場合なども、対応できないとしています。
「身体的、性的、あるいは精神的虐待に起因する苦しみの或るものは、哲学カウンセリングによって軽減され得るが、クライエントの複雑なニーズに完全に対応するためには、心理学、医学といった他領域の専門家と協働することが必要となるかもしれない。」(286頁)
-------------------------------------------
メモⅣ さらなるメモ
A
ラービが哲学カウンセリングの目的を、(1)問題と解決、(2)自律的な思考能力の涵養と定めていることは妥当なのか、ということを問う必要があるでしょう。また、個人的には、この(1)と(2)は相反する側面があるようにも思われます。
たとえば、(1)の問題が、自己の存在が肯定されていないと感じていることなどであった場合、哲学カウンセリング②~④は、経験の解釈の不整合性を指摘したり、「自己」や「存在」、「肯定される」とは何かについて問いを深め、当初の問いを相対化する視座をもたらすことはできたりしますが、実際に肯定感を与えるという仕方で解決することはできないといえます。つまり、哲学カウンセリングによって構成されるのは、そのような悩みをもっている自分を客観化し、他者からの評価にとらわれていることを問いただすような自己といえますが、しかし、それがクライエントが当初求めていたものではないということです。別の言い方をすれば、そのような自己を形成することや、問題を批判的創造的に思考することができるようになることは望ましいことだとしても、当初の自己の肯定感を確保したうえで、それらの問いに着手したほうが、より良いのではないか、ということです。
そもそもラービは「近代的な自己」・「自立的/自律的な自己」(偏見や先入見に囚われない自己)を自明とし、それを確立することが哲学カウンセリングの目的(そこでなされる教育によって達成されるべきこと)としているといえますが、そのような方針は、(1)問題を解決せず、非問題化しているだけではないのか、(2)そのような仕方で確立された自己であることは、ニーチェの超人がそうであるような、過大な要求をクライエントに強いるのではないか、という点で疑問があります。
「自己の存在」についての問題は、「自己の意味」において何らかの問題が発生しているために生ずる場合が多いとすれば、また意味とはそもそも他者との関係性において形成され、習得されるとすれば、この問題はクライエントとカウンセラーの二者の関係だけでは解決され得ず、クライエントの身近な他者の協力が必要となるかもしれません。
B
哲学カウンセリングを日本に導入することを考えた際にすぐに思いつく課題としては、①制度化がされておらず、それによって国家による定義や承認、資格化などによる最低限の質の確保、責任の所在の明確化と分散がされていないこと、②求められる個人的な問題の解決に対する、哲学カウンセリングという手法の適切性、つまり、深刻な問題を相談された際に哲学カウンセリングでは解決しえないケース(ラービが「哲学カウンセリングの限界」として指摘したようなケース)が多くなるのではないかということ、③哲学カウンセリングが対応すべき問題の解決や教育にとって、現状の哲学カウンセリングのシステムが最適かどうか、特にカウンセラーとクライエントの一対一関係においてカウンセリングを行うことが適切かどうか、などがあります。
①については、重要ですが、手法についてコンセンサスが形成できておらず、効果についてもエビデンスが出ていない現状では、具体的な検討はまだできないと思われます。そのため、②③についてのほうが、現状で議論する価値があるでしょう。
そこでの提案ですが、クライエントの問題によっては、オープンダイアローグの考え方を取り入れてはいかがかと構想しています。オープンダイアローグとは、(私もまだ勉強中ですが、)
①複数で行うカウンセリングであり、そこには専門家も複数参加し、さらにクライエントの身近な他者(家族・友人)も参加するということ、
②ダイアローグは、事実確認的なものというよりも、象徴的・物語的なものであること、
③ダイアローグの外側での打ち合わせは存在せず、すべての方針はダイアローグの中で決定されること、
④ダイアローグのなかで、専門家同士の意見交換(リフレクティング)が行われること、
などが特徴といえます(斎藤環著・訳『オープンダイアローグとは何か』参照)。
これが効果的なのは、前述のとおり、「自己の存在」についての問題は、その「意味」において何らかの問題が発生しているために生ずる場合が多く、また意味とはそもそも他者との関係性において形成され、習得されるとすれば、この問題の解決のためには、自己の意味の再構築が必要といえるためです。しかしながら、一対一の対話では、その物語を再構築するための素材が足りていない点に問題があります。
たとえば、「ある人が自分を嫌っている」と思い込んで、それを悩んでいる人に対して、哲学カウンセリングでは、出来事の不整合性を指摘することで、そのような思い込みが事実に反していること(たとえば、その人の言動は、別様にも解釈することができること)を示すこと、あるいは「そもそも嫌われているとは何か」「嫌われることがなぜ嫌なのか」と問うことによって、当初の思い込みを非問題化することもできるでしょう。しかしながら、その思い込みを棄却するためには、その対象となる知人当人から「そんなことはない」「あの時の嫌われていると思いこまれた言動は、……という理由があったんだ」などと語ってもらえたほうが、より効果的でしょう。
また、せっかく知人から「そんなことはない」と言ってもらっても、その新しい情報を基に、新たに自己の意味を再構築できなければ意味がないでしょう。そのためには、自分の人生を俯瞰してみることが必要ですが、専門家同士のリフレクティングは、そのような視座を提供するといえます。
つまり、オープンダイアローグの手法は、①クライエントとカウンセラーの二者の関係だけでは不十分な自己の存在の意味を再構築するための素材を、身近な他者から提供してもらうことができること、②提供してもらった素材を、これまでの自分の物語に接続し、再構築するための自分の人生を俯瞰する視座を、専門家同士のリフレクティングが提供しうること、という点で優れたものといえます。
以上のオープンダイアローグのシステムを哲学カウンセリングにも導入することによって、メモⅡで指摘した、哲学カウンセリングの困難についてのある程度の解決策となるだろうと期待できます。まず、深刻な精神的問題を解決する力が増強され、また問題を非問題とすることなく、解決したうえで、哲学的な問いとして深めることができます。さらに複数での対話となることで、一対一であることによるデメリットも軽減されるでしょう。
しかしながら、哲学カウンセリングにオープンダイアローグを導入することについては、そのハードルが高いこと(専門家が複数必要ということでコストの増大、ダイアローグに身内が参加してもらうことの難しさ、など)が考えられます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
